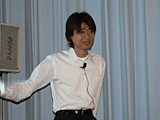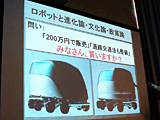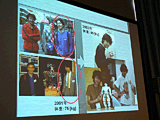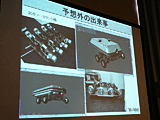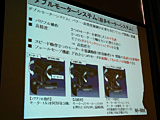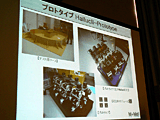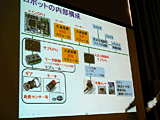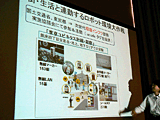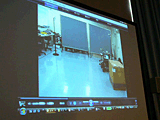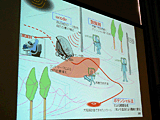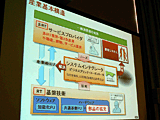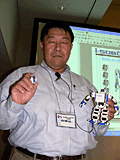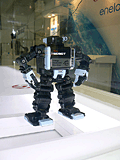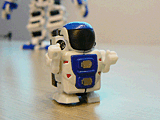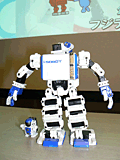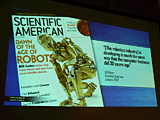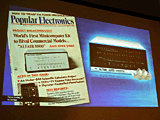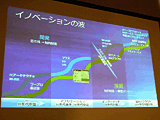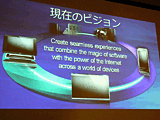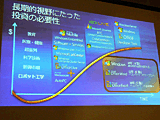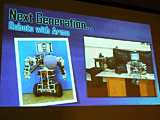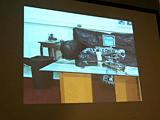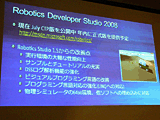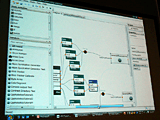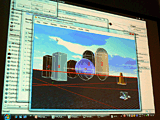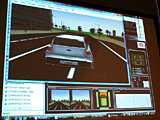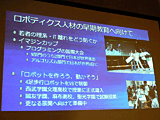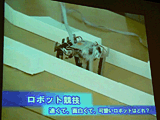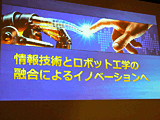|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ITとRTを使いこなしてロボットを作る次世代の育成が急務 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
タカラトミーの渡部氏は実物初公開となる教材用「i-SOBOT」の試作品をセミナー受講者だけに特別公開。簡単にコピーできない、日本の高度な技術あってのi-SOBOTと、それを使った次世代技術者育成や、他社との今後の事業の可能性について来場者たちに呼びかけた。今回のセミナー中でもっともセミナーらしいセミナーだった。 マイクロソフトの加治佐氏もMicrosoft Robotics Studioの話と、マイクロソフトが現在試験的に行なっている学生向けのロボット作り教室とその大会化の可能性を述べた。会場からの質問にも答えた。それによれば当面、マイクロソフトとしてはロボットに適したリアルタイム性を持ったOSの開発といった方向ではなく、クラウドコンピューティングをからめたサービスなど、上位のアプリケーション・レイヤーでのロボット関連ソフトウェアの可能性を探っていく方向のようだ。 ● 君のスキルはこう活かせ!?
まずはじめに「このロボットは意外と大好きなんです」と米国Boston Dynamicsのロボット「BigDog」の動画と、ハンソンロボティクスが作ったアインシュタインヘッドを載せた韓国KAISTのヒューマノイド「Alberto HUBO」の動画を見せたりしながら、「最近のロボットはよく動く」と紹介した。 前ふりのあと、古田氏は「まず最初に謎解きです」と講演を始めた。古田氏の問いとは「ハルキゲニアが道路交通法が整備され、200万円で販売されたら、皆さん乗りますか?」というもの。古田氏は「私の妻にも絶対にいやだと言われました」と述べた。「いろいろなロボット技術がある。でも普及するためには機能や『できること』もさることながら、『これに乗って走って恥ずかしくないか』ということが大事なんです」と続けた。普及のためには先端技術かどうかは関係ない。経済的な部分や文化が重要。先端技術と「未来の技術」は違う、とよく言っている 古田氏はラジコンメーカーの双葉電子工業と共同開発した二足歩行ロボット「G-ROBOTS」の基礎設計、レスキューロボットやそこから派生した床下点検ロボットの開発などfuRoとしての活動も紹介した。古田氏が過去に開発した「mk」シリーズは現代用語の基礎知識の表紙になり、「morph3」は切手にもなった。ロボットのデザインは山中俊治氏が担当している。morph3は無駄を削ったアスリートロボットというキャッチフレーズがあったが、開発のため徹夜をつづけることで、古田氏自身の体重も80kg程度から46kgへと激減。「ロボットの無駄をなくすと私の無駄もなくなった」と会場の笑いをを誘った。 日本科学未来館にも納入されている「Halluc II」はビークルモード、アニマルモード、インセクトモードの3つに変形したり、いろいろな動きができるクルマロボットである。アニマルモードは設計している最中に古田氏がちょっと思いついて実装したモードだという。インセクトモードも初めから狙ったのではなく「しょうがなくなっちゃった」ものだという。合計56個のモーターを使い、ダブルモーターで、高精度&ハイパワーを歌っているのは、たくさんのモーターとセンサーを使ったロボットの作り方を学ぼうとしたものだという。だがこれは全部「大人の事情」で、「全部後付け」ですとぶっちゃけた。
Halluc IIのプロジェクトはもともとは動くロボットのほうが中心ではなく、コックピットを作るプロジェクトだったという。だから最初はちょっとしたロボットで十分だと考え、ロボットを外注にした。関節用モーターは1個3万円超の150個が先に納品された。だが設計を見ると、パワーがまったく足らず動かないと考えられた。でもモーターは無駄にできないし、数カ月後には納品しないといけない。そこで設計をやりなおし。パワーが足らないのでダブルモーターにすることにした。 そのときの話が「ピンチをチャンスに」である。ダブルモーターにすることで片方で片方のモーターを締め付けてバックラッシュ(ガタ)をなくし、速度とパワーを出すことを考えた。2カ月ほとんど寝ずに試作機を作ったという。それをさらに山中氏の設計デザインとマッチさせるために設計をやりなおした。このときにトルクリミッターをつけたり、ケーブルカバーやコネクターハッチの配置を考えて製作していったという。
だが「Halluc II」は一品モノである。やるべきことは、技術者ならば誰でも簡単にロボットシステムを作れるようにパーツを整備することであり、将来的にはモジュール化している各ユニットをネットワーク配線で繋ぐだけでロボットを作れるようにしていきたいという。 またこれから重要になるのはアプリケーションであり、街を賢くすること、その街で動く1人乗りのスマートビークルの研究開発をしていると現在の研究の一端を紹介した。国土交通省のプロジェクト「東京ユビキタス計画・銀座」でもシステム開発を行なっているという。街中のインフラと連動して事前情報がなくても賢く動くロボットができるといいなあと思っていると語った。古田氏は「いろんな技術が出てくるが、これからはサービスプロバイダにRTやITを紹介するシステムインテグレータが重要になってくる」と述べた。講演終了後も多くの人たちがHalluc IIに群がり写真を撮ったりちょっと触ってみたりしていた。
■ 関連記事 ・ 「最先端ロボットフォーラム」レポート ~最先端科学と最新のロボット開発の講演(2008/07/04) ・ fuRoとL.E.D.、多関節ロボット用没入型コックピット「Hull」を未来館に導入 ~一般体験可能、多自由度ロボットの直感的操縦を目指す(2007/08/01) ・ fuRoとL.E.D.、8本の脚・車輪を持った移動ロボット「Halluc II」を発表(2007/07/26) ● タカラトミーが目指すロボットの今後の展望
特徴は、17自由度ある多関節ロボットであるにも関わらず完全組み立て済みであること、操作が簡単であること。スイッチを入れるとすぐに遊べる。完全組み立て済みの製品を量産するということは、サーボモーターや各種センサーなど部品のばらつきをなくして一定の精度を出さなければならないということだ。 昨年6月には世界最小二足歩行ロボットとしてギネスに認定された。ただ定義にもよるだろうが二足歩行というだけなら発表されたばかりの34.5mmの「ロボQ」のほうが最小だという。なお台湾メーカーが15cmの二足歩行ロボットを販売しているが、それはキットであるため、完成された状態で販売されているものとしてはやはりi-SOBOTが最小だそうだ。昨年12月には福田首相からアブダビ首長国ムハンマド皇太子にプレゼントされている。さらに「インターナショナルギフトショー」でグランプリ受賞。2008年には「G8エネルギー大臣会議」の要人ギフトに選定され、「グッドデザイン賞」の金賞も受賞した。ちなみにタカラトミーでは「リカちゃん」は広報に属していて、社内報はリカちゃんから送られてくるといったユニークな話題も紹介された。
さてロボットには、見せるためのプロトタイプロボット、あまり販売はされていないホームロボット、研究や教育に使う学習ロボット、二足歩行ホビーロボットなどがある。ではi-SOBOTはどういう位置づけかというと、高性能の音声認識チップを使うなど機能的には高いが安価であるというものを目指したという。 渡辺氏はタカラトミーの歴史を振り返った。タカラトミーはタカラとトミーが合併してできた会社だ。トミーはオムニボットなどロボット開発の歴史がある。いっぽう、「ウォーキービッツ」のような小さいトイなども作ってきた。そのなかに「アームトロン」という144枚の歯車をモーター1つで動かすアームロボットがあった。これを本当に偉大な商品だと渡辺氏は紹介した。 おもちゃメーカーにとって、ミニカーやドールなど、小さいものは永遠のテーマだ。渡辺氏が開発した「マイクロペット」も2002年当時は世界最小のロボットとして登録され、1年間で1,000万個くらい売ったそうだ。その当時から将来的にはマイクロヘリや二足歩行ロボットを作って行きたいという構想はあった。同社では「ヘリQ」も昨年10月から発売しており、なかなか順調とのこと。今回発表された「ロボQ」は電池が入って3,500円程度で販売予定である。 さて「i-SOBOT」の具体的なプロジェクトスタートは2004年11月20日。第一次試作完了が12月27日。短期間で一次試作が完了してしまった背景には渡辺氏曰く「日本の玩具ロボット業界ではダントツでナンバーワン」という同社社員の米田氏の個人的能力に負うところが大きいそうだ。同氏らはその動きに感動したが、未完成だったため、営業側の反応はあまり良くなかった。そのため2005年に開発は一時保留となる。 2006年3月30日、再スタート。6月28日、第3次試作完了、そして5月30日、IRIにて発表された。本誌が取材に出かけたのはこの発表を聞きつけたあとである。またこの直後、すぐに香港、中国でニュースになった。今や世界のおもちゃの8割が中国広東省で作られている。コピー製品が出回るかとも思われたが、実際にはそれはなかった。なぜなら、そんなに簡単にコピーできる製品ではなかったからである。 同社でも、開発途中で何回か挫折があったという。といっても制御などはほとんど苦労がなかったそうだ。苦労したのはモーターである。i-SOBOTは90cmからの落下テストなどを繰り返し安全性を確認している。これはオモチャの基準だ。タカラトミーから発売される以上、ロボットだろうがおもちゃとして販売するよ、と社内の品質管理部から言われ、歯車が割れないように作りこんでいくところに非常に苦戦したという。 中でも一番重要な部品は金属歯車と精密部品だった。おもちゃでいうクラッチ、一般的にはトルクリミッターにあたる部品だった。タカラトミーではそれを全部自前で作り、日本国内で製造し、中国で組み立てた。日本で作った理由は、日本でしか作れなかったからだ。これがコピー製品が出回らなかった理由だ。 おもちゃとしては非常に高価なi-SOBOTだが、ロボットとして見ると安価だ。この価格を実現した背景には、サーボモーターを自前で開発していることが大きいという。量産して広く売るためにコストを下げるためには、自社でモーターを作ることが必須だと渡辺氏は語った。 また、世界で販売することにより、日本市場の5倍を販売している。大量生産によるコストダウン効果も大きい。購入部材のコストダウンも非常に重要だ。使われているICは「缶コーヒー1本分くらいの値段」だ。ロボQのICはもっと安い。非常に安価な部品を使って作っているそうで、同梱されている部品のなかで一番高いのは三洋電機のエネループだという。今後は、わざわざ同梱していれなくても家にエネループがある家庭も増えてくると考えられることから、見かけの値段を下げることができるかもしれない。次は村田製作所のジャイロ、そして音声認識用チップという順番で、それ以外の部品は本当に安い、仕様を満足する最低限度の部品を選別して組み立てられているそうだ。 いろいろなイベントに参加しているi-SOBOTだが、渡辺氏は三洋電機と一緒に参加している「環境授業」の例をいくつか紹介した。多くの子供たちは驚きを持ってi-SOBOTを見ているという。さらに今後の展開として、教育用教材としてのi-SOBOTの可能性について渡辺氏は紹介した。実際に実物も、セミナーでは紹介された。 また、エンターテイメントとしてのロボットの可能性は大きい。初日のセミナーで産総研の比留川氏が紹介したように、ヒューマノイドは5億円で頭うちになると言われている。だが「ロボQ」は順調に行くと、全世界で200万個くらい販売できるのではないかという。おおざっぱに計算すると予価3,500円×200万個はおおよそ70億円となる。渡辺氏が開発した「マイクロペット」も年間128億円の売上を達成したという。 そのほか「QFO」や「ホバーQ」なども紹介しつつ、エンターテイメント、玩具としてのロボット用途の大きさを具体的な数字で示した。オモチャの場合は「驚きと感動を、買っていただいたお客に味わってもらうことが一番重要だ」と強調。たとえば、i-SOBOTは何にもできない。だが、見た瞬間、「わー、すごい、ほしいなあ」と思ってもらうものを作ることが何より重要だという。 今回の講演で分かるように、i-SOBOTは日本の高度な技術力の産物である。いっぽう、日本のGDPを支える製造業が落ち込んでいくと、日本経済がシュリンクしていく。理工系離れも進んでいると言われている。そういうところにi-SOBOTを安価に提供して、若者にいろんなことを勉強してもらうことができるのではないかという。 ロボットの仕組み、サーボ制御、構造、強度、エネルギー効率、デザイン、マーケティングなどだ。制御や構造設計がロボットのすべてではない。採算検討ができなければ販売できないし、製造技術も必要だ。もともと優れた企画開発も重要だ。マーケティングもいる。ロボット1つとってもさまざまなことが学べる、という。今後は、i-SOBOTを使って大学や高専で勉強していってもらいたいという。渡辺氏は、現状のままでは、将来本当に実用になるロボットを作ることになるのは、中国の優秀な技術者・研究者たちではないかと危惧を述べた。 さて紹介された試作モデルは、i-SOBOTに使っているサーボモータをそのまま使い、通常商品では3.6Vの電圧を少し上げてモーターパワーをあげたもの。通常バージョンのi-SOBOTは、量産商品の確実性を維持するため、ゆっくりゆっくりと着実に動くように作られている。だがビデオで紹介されたそのロボットの動きは、ROBO-ONEに出場しているロボットなみの速度だった。もっとパワフルなi-SOBOTサイズのロボットを作ることもできるという。 渡辺氏は出身大学である同志社大学で教鞭をとっており、そこではおもちゃの企画を教えている。玩具メーカーでは、外部企画開発会社から提案を受けて、それを中国の工場で生産するという形をとっている。開発会社はおもちゃメーカーをやめて独立した人が設立しているケースが多く、なかには中国の工場の情報まで詳しく把握した企画を持ち込んでくる開発会社も少なくないという。 渡辺氏は、大学、企業のなかでロボットのプロジェクトなどを進めていた人で、何らかの事情でそれができなくなった人も、外部の開発会社のような立場で渡辺氏らのところに提案してもらえれば何かができるのかなと思っている、と呼びかけた。渡辺氏は「埋もれたアイデアを実現化していきたい。もし今日のセミナーで興味を持った人は私のほうに来ていただきたい」と述べた。
■ 関連記事 ・ 「第11回かわさきロボット技術交流会」レポート ~タカラトミー「i-SOBOT」キット化案も(2008/03/18) ・ タカラトミー「Omnibot 17μ i-SOBOT」分解・解析レポート(2007/11/08) ● 技術者が拓く新しいロボット産業 ~情報技術(IT)とロボット技術(RT)の融合~
1970年代のコンピュータは非常に大きく、しかも低速なデバイスを使っていた。そこに初めて個人が使える画期的なコンピュータとして「ALTAIR 8800」が登場した。いま振り返ると何ができるのか分からないようなスペックだったが、個人が手を出せる最初のコンピュータだったため、マニアの間では人気を呼んだのである。そのマニアの1人がビル・ゲイツであり、その後のマイクロソフトを生むことになる。 その後、さまざまな個性を持ったパーソナルコンピュータが登場した。その中から最終的に大きなシェアを占めたのがIBM/PCである。これがデファクトスタンダードとなり、さまざまなものを結びつけて業界を発展させていくことになる。
イノベーションには4つの波があったという。ワープロ、表計算といったキラーアプリケーションの登場、さらにマウスやGUI、LANの登場が第2の波。この時期にさまざまなアプリケーションが登場した。第3の波がネットワークの発達に伴う、電子メールやウェブブラウザの登場である。ここでまた大きな飛躍があった。そして今はCPUのメニーコア化、ウェブサービスの登場、クラウドコンピューティングなどが発展しつつある。まだまだわくわくする状況が続いていくと思っていると述べた。 昔のマイクロソフトのビジョンは、すべての家庭のすべての机上にPCをといったものだったが、最近のビジョンは、ネットワークを使いながらさまざまなデバイスを繋いでいく、というものに変わっているそうだ。 マイクロソフトの各種製品は一夜にしてできたものではなく、「稼ぎ頭」になるためには10年ほどかかっているという。ロボットはまだまだこれから投資していくことで将来伸びると思われているという。
ロボットは既に製造業のなかでは大いに使われており生産性を上げることで完全に実用段階に入っている。だが家庭ではまだまだだ。加治佐氏は売れているロボットとして、iRobot社の「Roomba」、ワーウィー社の「ロボサピエン」と、レゴ社の「マインドストームNXT」をあげ、まだまだロボットは成功できると述べた。 ではマイクロソフトはロボットにどのように関わるのか。加治佐氏は「Microsoft Robotics Studio」を紹介した。ロボットを協調して動かすための並行協調環境(CCR)、分散システムサービス(DSS)などを機能として持つ。また物理的にロボットを動かす前にソフトウェアのなかで物理シミュレーションを行なうことができる。その開発もビジュアル開発言語を使って行なえる。また非常にたくさんのサンプルプログラムを入れている点もウリだという。 加治佐氏はロボットの応用例として、韓国のホームロボットの例や、火星ローバーやPackbotなどの遠隔操縦の例、そしてマサチューセッツAmherst大学との共同研究を見せた。Robotics Studioは現在、「Robotics Developer Studio 2008」として、地道にアップデートを重ねている。年内に正式版を供給予定だという。
楠氏は、Robotics Developer Studioを使って、自律型のソフトウェアを開発していってもらいたいと思っていると述べた。そうすると、たとえばロボット相撲のプログラムをシミュレーション環境で開発することもできる。強いプログラムを世界中から応募してもらって、互いに競い合わせるという取り組みもはじめているという。 また、「ROBO CHAMP」では、自律ロボットを街中で走らせる「DARPA Urban Challenge」をシミュレーションで行なうような競技も募集が始まっている。カメラからの画像や距離情報など、各種センサー情報などを与えられた車をコントロールするプログラムを書いてゴールまでたどり着くことを目指すというものだ。実機がなくても自律型ロボットのプログラムを組むことができ、試験して、他の人と競うことができるようにしたことで、ハードウェアを得意とする人たちだけではなく、もっとたくさんのソフトウェア技術者がロボットの世界に入ってきてもらいやすいようにしていきたいという。
そのほかマイクロソフトでは「Windows Embedded」など組み込み機器関連の取り組みを行なうほか、早期教育にも取り組んでいる。IT業界ではいま若者が情報技術、理系から離れていくことが問題視されているという。それを防ぐために「イマジンカップ」という取り組みを行なっている。 それ以外に昨年12月から試験的に行なっているのがロボットを作るコンテスト。ベネッセが主催し、マイクロソフトが支援している。コンピュータの歴史などを教えたあとに、四足歩行ロボットを組み立て、プログラムを組み、最終的にプレゼンをしてもらうというものだ。多くの学生が興味を持ってくれているという。ロボットを動かすためにはVisual Basicを使ってプログラムを組む。何よりも、ロボットのハードウェア・ソフトウェアを自分たちの手で作り、動かしてもらって、その感動を味わってもらうことを狙いとしているという。 現在は10校程度で行なっており、うち1校で授業として採用された段階だが、将来的には全国の学校に広めていき、大会を主催することも狙っているという。 最後に加治佐氏は、マイクロソフトはPCそのものではなく、そのなかで動くソフトウェア部品を提供し、そこでいろいろなものを結びつけて価値を作ってきた。ロボットでもソフトウェアを提供しながら、さまざまなものを結び付けていくことでイノベーションを起こしたいと講演をまとめた。今はまだバラバラに開発されているソフトウェア・ハードウェアだが、やがてそれらを繋げるようなイノベーションを起こすプロダクトが登場する都考えているという。
■ 関連記事 ・ マイクロソフトとZMP、Robotics Studio活用で協力開始 ~「イノベーション・ジャパン2007」内で発表、デモ(2007/09/13) ・ テムザックとマイクロソフトが協業 ~Microsoft Robotics Studioを使ってソフトウェア部品を共通化(2007/09/07) ・ Microsoft、ロボット開発プラットフォーム「Robotics Studio」CTP版を公開(2006/06/21) ■URL ROBO_JAPAN 2008 http://www.robo-japan.jp/robo/ ■ 関連記事 ・ 「ROBO_JAPAN 2008」開幕レポート 【会場展示編】(2008/10/11) ・ 「ROBO_JAPAN 2008」開幕レポート 【オープニングステージ編】(2008/10/10)
( 森山和道 )
- ページの先頭へ-
|