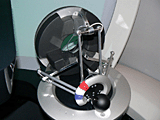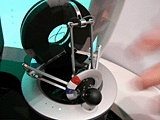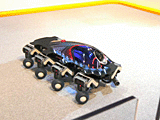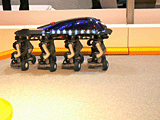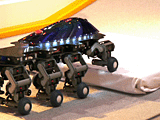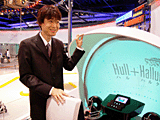|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
fuRoとL.E.D.、多関節ロボット用没入型コックピット「Hull」を未来館に導入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「Hull」は全高170cm、全幅230cm。直径150cmの半球型のスクリーンと、操作デバイスとして3軸ハプティックデバイスを2つ備えたロボット操縦システム。正面のディスプレイにはロボット正面に搭載されたカメラ映像が投影され、操縦桿であるハプティックデバイスではロボットからのセンサー情報を力覚に変換して、反力としてオペレータにフォースフィードバックすることができる。ハプティックデバイスはForce Dimension社の製品を一部改造したものが用いられている。「Hull」という名前は殻という意味の英語に由来する。
操縦はハプティックデバイス握りのスイッチを押しながら行なう。両手をそれぞれ前に押し出すと前進、後ろに下げるとバック、それぞれの操縦桿を前後逆に動かすと旋回する。たとえば左を前、右を後ろに引くと、右旋回する。斜め前に進ませたいときには、ゆっくり前進させたあとに斜めにスティックを倒す。するとロボットが滑るように斜めに移動する。各関節の角度を個別に指定する必要はない。 またロボットが移動しているうちに壁が近づくと、操縦桿が固くなり、そちらには進みにくい/進めないことをオペレーターに提示する。当日行なわれた体験デモにおける実際の操縦感覚では、前進では確かにだんだんスティックの操作感が固くなり、動きにくくなる感覚に近かったが、後進の場合は、むしろスティックが引き戻されるような感覚だった。 「Halluc II(ハルク・ツー)」は、ビークル、インセクト、アニマルと3つの移動形態を持つため、手元にはそれぞれのモードへの変形スイッチも装備されている。操縦席正面のプロジェクター部上には液晶タッチディスプレイによるサブディスプレイのほか、有機ELディスプレイを使ったモード切替スイッチもあしらわれている。
「Hull」は「Haluc II」専用ではなく、多自由度のロボット全般に使える汎用の操縦システムだという。今後は、テレイグシステンスを利用したロボット操作システムとしてだけではなく、多自由度の乗り物のコックピットや、知能化された車椅子操作部の研究に応用していく。fuRo所長の古田貴之氏は、通信速度の遅れやダイナミクスの違いによるモデル化誤差によるズレを吸収できるような操縦システムの開発を目指していくと語った。 また実際に人間が搭乗できるロボットの開発を視野に入れた大容量モータードライバやバッテリの開発、システム全体で安全性を確保するためにロボットシステム全体のモジュール化や、下位システム内でのローカルな自律制御システムの開発を行なっていく。下位のシステムがあたかも反射神経系のように、ほぼ自動で自律制御を行ないつつ、上位の人間による操縦系から指令を与えるといった操作系が目標で、それは次世代の車椅子やビークルにも応用可能だという。
古田氏によれば、日本科学未来館に今回のシステムを導入した理由は2つ。1つ目はシステムそのものの運用実証テスト。たとえば「Hull」のフォースフィードバックもテスト中であり、どの程度の力をオペレーターに送り返すかといった細かいチューニングも随時調節していく予定だ。2つ目は、一般の幅広い年齢の老若男女に実際にロボット操作を体験してもらうことだという。L.E.D.代表でデザイナーの山中俊治氏は、「未来を少しでも体験してもらえれば。新しいアトラクションを楽しんでもらいながら、僕たちも学べれば最高です」と語った。
なお、日本科学未来館では「Hull」と「Halluc II」導入にあわせて、3F「技術革新と未来」フロアーのロボットコーナーをリニューアルした。未来館のロボットコーナー担当者である科学コミュニケーター 佐藤雅一氏は「眺めて見るだけではなく、実際に触れられて体験できるようなコーナーにしていきたい。ロボット技術の未来を感じてもらいたい」と語った。 また、8月13日~17日の5日間は、「サマーナイト・ミュージアム」として未来館の開館時間を午後8時まで延長。このなかでは裸眼で360度パノラマ立体映像を映し出せるコミュニケーションシステム「TWISTER」の公開実験も行なわれる。各回10名以上がこのテレイグシスタンス・システムを体験できるという。こちらもインターフェイス技術に興味があれば必見である。 ■URL 日本科学未来館 http://www.miraikan.jst.go.jp/ Halluc II展示について http://www.miraikan.jst.go.jp/j/info/2007/if_0731_01.html 千葉工業大学未来ロボット技術研究センター http://www.furo.org/ リーディング・エッジ・デザイン http://www.lleedd.com/ ■ 関連記事 ・ fuRoとL.E.D.、8本の脚・車輪を持った移動ロボット「Halluc II」を発表(2007/07/26)
( 森山和道 )
- ページの先頭へ-
|