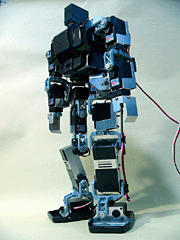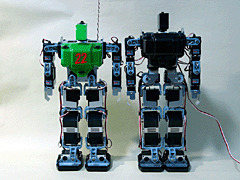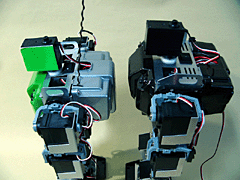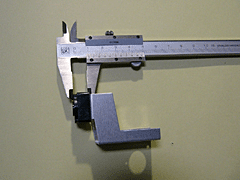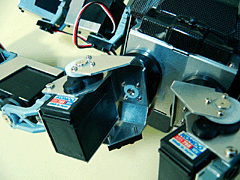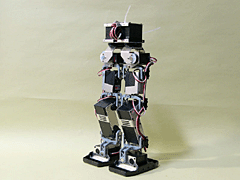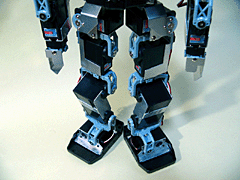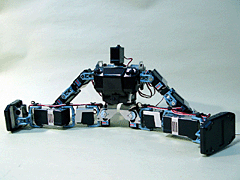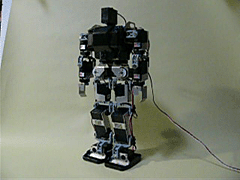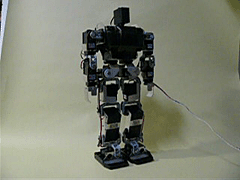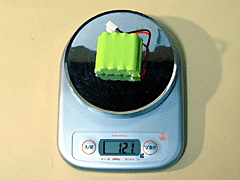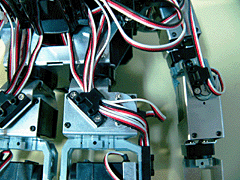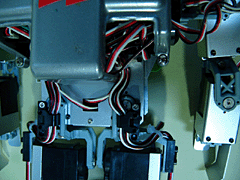|
記事検索 |
バックナンバー |
【 2009/04/17 】 |
||
| ||
【 2009/04/15 】 |
||
| ||
【 2009/04/09 】 |
||
| ||
【 2009/04/06 】 |
||
| ||
【 2009/04/03 】 |
||
| ||
【 2009/03/27 】 |
||
| ||
【 2009/03/24 】 |
||
| ||
【 2009/03/18 】 |
||
| ||
【 2009/03/11 】 |
||
| ||
【 2009/03/06 】 |
||
| ||
【 2009/03/04 】 |
||
| ||
【 2009/02/27 】 |
||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KONDO最強ロボットキット「KHR-1HV」レビュー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
~純正オプションがふんだんに盛り込まれた機能強化版
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reported by
梓みきお
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
だが、人間の片足をおおまかに自由度で表現すると、じつは「6軸」となる。初代や2HVは、つま先を開く軸(ヨー軸)を省略していたのだ。多くの二足歩行ロボットキットが発売されているが、「片足5軸」であれば大抵この「ヨー軸」が省略されていると思っていいだろう。 この軸がないロボットが苦手とするのが「方向転換」だ。人間でも「つま先を開かずに右に向いて」と言われたらまごついてしまうだろう。実際上は不可能というわけではなく、キット付属のサンプルモーションでは足裏を滑らせることでこなしているのだが、それゆえに足元の状況に大きく影響されてしまうので、方向転換をした後に「意外と回っちゃった」とか「意外に回らなかった」とか、まちまちになってしまうことも少なくない。 それを解決するために、初代では「拡張4自由度ユニット(足の裏にもう1枚板を追加し、それをヨー軸サーボで動かすもの。腕に2軸も追加するキットだった)」や「旋回軸ユニット(股関節に足全体をひねるヨー軸サーボを追加)」などのオプションパーツを発売して、2軸を追加した「19軸」の機体にバージョンアップさせることができるようになっていた。 しかし、今回ついにKONDO初の「ヨー軸を標準装備したキット」として「KHR-1HV」がリリースされた。――誤植ではない。「KHR-1」が2代目になったのだ(ちなみに「KHR-1」という名前を旧モデルから引き継いだのは、KONDOのフラッグシップモデルは常に「1」を引き継いでいく、という慣例からのようだ。歌舞伎で“市川団十郎”を受け継いでいくようなものかも)。 キットを買って、オプションを買って……となるとどうしてもお金がかかってしまうので(このあたり、趣味でロボットをやっている人にはとても切実)、初めから「ヨー軸がほしい」と思っている人にとっては期待が大きい製品だろう。 ● 肩を40xx系サーボに換装し、一回り大きくなったボディ まずは全体の構成から見ていこう。今回は発売前の実機でレビューするので、細かい部分が発売までに変更される可能性もある。その点はご了承願いたい。全高は377mm。2HVが353mmだったので、24mm伸びている。一方、幅は189mmだったものが179mmに狭められているので、正面から見ると微妙に細長くなったような印象を受ける。 しかし、奥行き(=機体の厚み)を見てみると、2HVの約100mmに対して125mmと、1HVのほうが分厚い。背面のボードカバーや前面のバッテリカバーは色こそ違うが2HVと共通の形状なので、ボディフレーム自体の厚みが増していることになる。 サイズ的な変更はもうひとつ。腕の長さが20mm延長されている。これは背が高くなったことで、元の腕の長さでは起き上がりなどに無理が出てくるためだと思われる。その副次的効果として、リーチが長くなったことは、格闘系の競技でメリットを生むだろう。
追加された旋回軸を含め、主なサーボは2HVと同じ「KRS-788HV」を使用し、肩を回す軸にのみ「KRS-4024S HV」が採用されている。この2種類のサーボは、一部が金属ギヤであったり、トルクやスピードがほぼ同じなど共通点が多いが、動作角度だけが大きく異なる。約180度の788HVに対し、4024S HVは約270度もあるのだ。 肩を回す軸は可動範囲が大きいほうが起き上がりなどの際に有利だし、人間はぐるりと360度動くので、“らしい”動きをするためにはぜひとも広くしたい軸。ファインチューニングと言っていいだろう。それに伴ってボディフレームと腕の間に挟まるサポーターは新型の「アームサポーター4000A」に切り替えられている。
モーション作成ソフトは「HeartToHeart3」で、2HVの「HeartToHeart3“J”」とは微妙に異なる。といってもボード自体の機能追加に伴ってコントロールできる項目が増えるだけなので、基本的な使い方やGUIでサクサクとモーションを作ることができるインターフェイスは変わらない。 ● お待ちかねの旋回軸部分 ぱっと見た目でわかるように、「足」の構造そのものは2HVとまったく同じだ。アルミ製だった足裏がオプション発売されている「バスタブソール」になっているのが、唯一の変更点である。足裏の面積そのものはほとんど変わらないが、2HVの板金による足裏と異なり、エッジが立っていないぶんモーションの誤差で躓くような場面が少なくなるだろう。旋回軸が付いたことで異なっているのは、足の付け根のロール軸(左右に振る軸)のサーボからだ。2HVの場合、この軸がボディフレーム内に固定されているので、つま先(つまり足全体)を“開く”ことができなかった。 そこで2HVは、このロール軸サーボを横に寝かせたうえでアルミ製のブラケットを組み付け、そのうえでヨー軸サーボによって足全体をひねる動きを可能にしている。ブラケットパーツ自体も他のアルミ板金パーツ(1mm)より厚い1.2mmを採用して強化してあるし、ボディへの取り付け部分はアームサポーターが支えているので、強度的な不安はない。
今回は動作サンプルモーションとして「柔軟体操」と「旋回」があるので、その2つの動画をお届けしよう。
見てもらえば一目瞭然だが、どちらもヨー軸がない機体には不可能な動きだ。旋回は特に説明も要らないだろう。非常にスムーズに旋回している。 一方、柔軟体操では両足のヨー軸やひざ下を柔らかく使うことで、手を大きく前に振り出している。これがただの体操だと思う人は、前に振り出している手を「パンチ」だと思って見て欲しい。 KHRシリーズで格闘をしている人を見ると、横向きのパンチが多数派で、正面のパンチを出す人は少ない。というのも、胴体部分を「ひねる」ことができないので、正面に出すとリーチが腕のぶんしかないからだ(しかも胴体の幅はマイナス)。しかしこのヨー軸があれば、肩幅をリーチに含められるのである。KHR-1HVの目玉となる「旋回軸」は下半身のパーツだが、その効果は下半身のみならず、上半身の動きにも幅を出すのである。 ● 旧旋回軸ユニットよりも格段に組み立てやすく 初代モデルのオプションだった「旋回軸ユニット」はコンバージョンキットという性格もあり、パーツの組み合わせが複雑だったり、組み立てにコツが必要だった(ついでに言えば元のボディパーツなどが無駄に余ってしまうのももったいなかった)。しかし、KHR-1HVはキットなので、2軸が追加されたのをほとんど感じないくらいに組み立ては簡単。もちろんパーツも余らない。難点があるとすれば、2HVの1,270gに対して、1,510gとなった重量増に見合うサーボのパワーアップがない点と、若干トップヘビーになった機体バランスだ。ただ、元になった2HVがパワーに余裕があった(近藤科学によると、頭に200gのおもりを乗せても平気で歩くそうだ)こともあり、無理をしているわけではないようだ。 どうしても気になる人は、稼働時間が短くなることを覚悟のうえで、バッテリを「Cタイプ(2HV標準の10.8V-300mAh)」に交換すれば約50gダイエットできるので、試してみてもいいだろう。 また、自由度が増えたぶん、コントロールしなければならない軸が増えるので、モーション作成時にひと手間増えるのは仕方がないところ。特に2HVの組み立てやすさに貢献していたホームポジションのめやすとなる「ガイド」が一部省略されているので、そこを自分でしっかりと設定できる人でないと、まっすぐ歩かせることすら苦労してしまうかもしれない。
2HVの上位機種として発売されたKHR-1HVだが、「上位機種だからコレ」ではなく、まず自分のロボットに「何が必要か」を考え、そのうえで必要な能力を持つ機体をチョイスするのが正解だろう。 もっとも、得られるメリットは上記のようにかなり大きいので、旋回軸が欲しいと思っているなら、最初からKHR-1HVを手に入れたほうがいい(ベストなのは、2HVからステップアップできるように「旋回軸追加パッケージ」を発売してもらうことなのだが……)。同社のユーザーサポートスペース「KONDO ROBOSPOT」でも近々展示が始まるようなので、ぜひ実機を見て、確かめてほしい。 ■URL 近藤科学 http://www.kondo-robot.com/ ■ 関連記事 ・ 近藤科学、旋回軸が追加された二足歩行ロボットキット「KHR-1HV」を発売(2006/11/28) ・ 石井英男のロボットキットレビュー ~近藤科学「KHR-2HV」(第2回)(2006/12/08) ・ 石井英男のロボットキットレビュー~近藤科学「KHR-2HV」(第1回)(2006/10/10) ・ ロボットキット「KHR-2HV」最速レビュー(2006/05/30) ・ 近藤科学、実売9万円のホビーロボット「KHR-2HV」(2006/05/29) 2006/12/12 00:30 - ページの先頭へ-
|