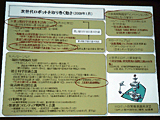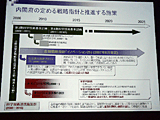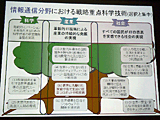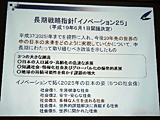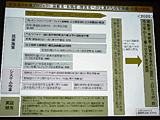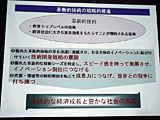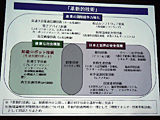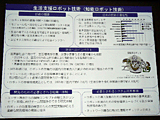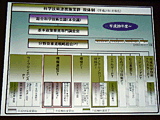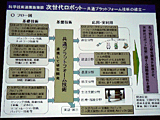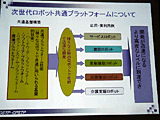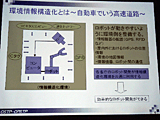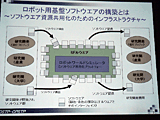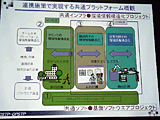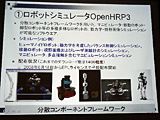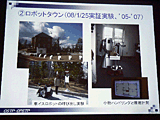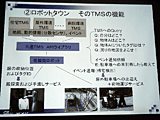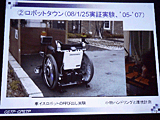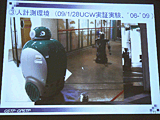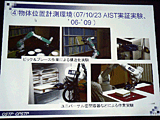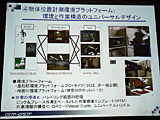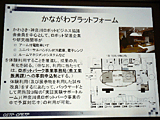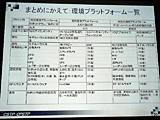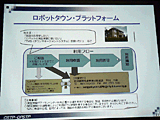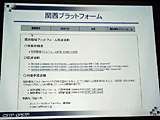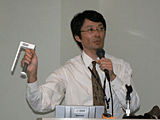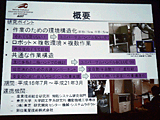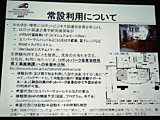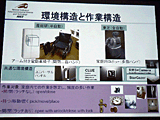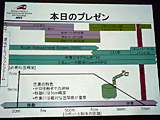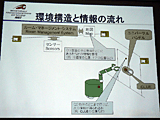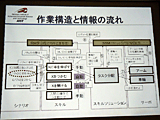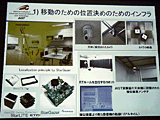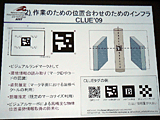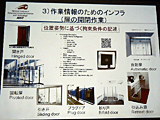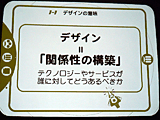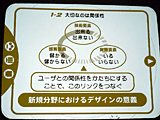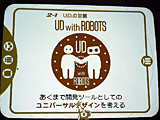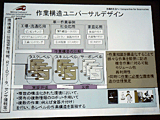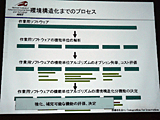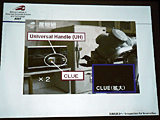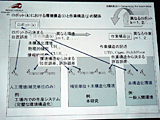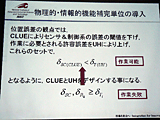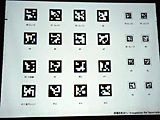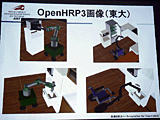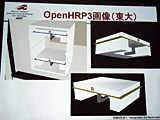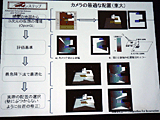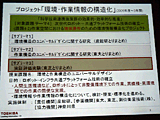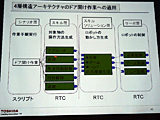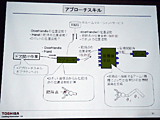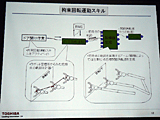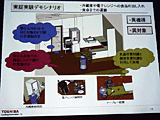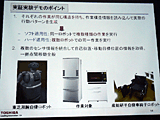|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「ユニバーサルデザイン・ウィズ・ロボット」とは? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2月5日、次世代ロボット連携群「平成20年度第4回講演会/見学会 次世代ロボット共通プラットフォーム技術神奈川環境プラットフォーム」が開催された。この記事では、先にレポートした「神奈川環境プラットフォーム」見学会の前に行なわれた講演会をレポートする。デモンストレーションの記事と合わせてお読み頂きたい。 ● 内閣府の推進するロボット施策 ~政府からロボットに向けられる期待とは
「科学技術連携施策群」は第3期科学技術基本計画以前から始まっていたもので、ロボットは情報通信分野のなかに位置づけられている。「イノベーション25」は先にも述べたように2025年までを視野に入れて、今後20年先の未来社会を展望したものだが、ロボットは「多様な人生を送れる社会」の実現に寄与することが期待されている。「社会還元加速プロジェクト」ではさまざまな技術を社会還元することで「高齢者、有病者、障害者を含めた国民一人一人が、自宅で安心して暮らせる社会の実現」が目標として掲げられている。世界トップレベルの技術を推進する「革新的技術戦略」においては、知能ロボット技術は「健康な社会構築」を目標にしている。これは生活支援ロボットを社会に送り出すことで国民の生活環境改善を目指そうというものだ。 平成17年度から実施されている科学技術連携施策群は、全部で14施策ある。そのなかの1つが次世代ロボットだ。基礎から応用に繋げる上で、互いに利用できる部分は利用できるようにする「共通プラットフォーム技術」を確立することで、技術開発を加速していこうというのが狙いだ。堀氏は「ロボット技術は重要な研究開発目標の1つに上げられており、将来の日本の姿に不可欠な存在となっている」と述べ「第3期科学技術基本計画に基づくロボット技術への重点的な投資が将来の日本の姿に大きく貢献することを期待している」とまとめた。
● 次世代共通プラットフォーム
共通プラットフォームのうち、ワールドシミュレータ(OpenHRP3)、ロボットタウン(街の環境構造化)は昨年度終了している。今年度終了し、それぞれいま成果が公開されているのは関西環境プラットフォーム(ユニバーサル・シティウォーク大阪)で行なわれていた人の行動を計測し判断、施設内での案内などをロボットにさせるというものと、神奈川環境プラットフォームの作業のためのプラットフォームだ。ユニバーサル・シティウォーク大阪での実証実験の模様や神奈川環境プラットフォームの公開の模様についても本誌でそれぞれ既にレポート済みである。ご覧頂きたい。 OpenHRP3はもともとヒューマノイド用のシミュレータだったものを一般用に拡張したもの。これまでのダウンロード数は1,400本以上だという。ロボットタウンでの実証実験では、無人車椅子ロボットの実験などが公開された。この環境では分散カメラやタグを使い、データ・マネージメントシステムを経由して環境情報をロボットに伝達できる。ユーザーがロボットを持ち込めば実験検証できる環境を構築した。 ユニバーサル・シティウォーク大阪では、人計測環境のプラットフォームを構築した。レーザーレンジファインダーや天井のカメラなどを使って最大20人くらいの人の動きを5cmの精度で計測し、その人が何をしようとしているのか判断してロボットに教えるシステムだ。環境を通じて、すぐに複数台のロボット連携ができるのが特徴だ。実証実験では人の行動を把握して案内するというアプリケーションが行なわれたが、これからどう活かすかはアプリケーション次第だという。
今回公開された神奈川環境プラットフォームは産総研の大場氏が中心になってシステム構築・実験を行なったもので、違う環境、違うロボットであっても同じ作業を行なえるようにすることを目標とした。これからは開発した環境の共有化やシミュレータの普及などを行なっていく。プロジェクト自体は今年度で終了するが、一部は経産省の次世代ロボット知能化技術開発プロジェクトに引き継がれる予定だという。また、2月26日には、秋葉原のアキバホールにて全体を報告するシンポジウムが行なわれる。各プラットフォームは研究者であれば申し込めば使用できる。是非利用してもらいたいという。
● 環境と作業構造のユニバーサルデザイン
もともと作業のために必要な精度として移動で5cm、作業で5mmの精度があれば十分ではないかと大場氏らは考えていた。だが実際にロボットに作業をやらせるとそれでも精度が足らなかった。そこで接触精度誤差を補い、位置決めをより容易にするために考えられたのが、ロボットのエンドエフェクタとワークの間の位置誤差を吸収して作業の信頼性を上げるための「ユニバーサルハンドル」と、絶対座標と相対座標のずれを吸収し、さまざまな作業情報を環境側から与えるための二次元コード「CLUE(Coded Landmark for Ubiquitous Environment)」だ。 2007年にそれらを開発した後、さらに多指ハンドと2指ハンドの両方で使えるように検討を加えて改良を行なった。そして位置決めのための共通コンポーネントとして、半自動/全自動モードの切換を考えた。大ざっぱな操作を人間が行ない、対象の近くまで持っていったらあとはロボットが自動で位置決めを行なうという考え方だ。またロボットが生活環境に入ってくるとなると力が強いものだと危険だ。いっぽう、非力なロボットでは位置精度を出しにくい。それは「CLUE」を使うことで安定して行なえるようにした。
このプロジェクトで行なったことは、「環境」と「作業」の構造化だ。そのためにセンサーを使って環境構造を整え、シミュレータを使って作業構造を整えた。まず環境構造から見ていくと、環境には「RMS(ルームマネージメントシステム)」というサーバーがあり、物品やロボットの位置情報管理を行なっている。環境側には作業や位置のための手がかりである「CLUE」や、位置決めタグ(神奈川環境プラットフォームでは「StarGazer」を使用)、実際に作業対象となるユニバーサルハンドルが貼り付けられているが、物体のどこに行けば次の情報が得られるかといったこともRMSが管理している。 作業構造は、「4層構造アーキテクチャ」をとっている。シナリオ層、スキル層、スキルソリューション層、サーボ層の4段階に作業を分けており、うちシナリオ層とスキル層が部屋の物体位置管理を行なうRMS内で処理され、スキルソリューション層とサーボ層がロボット内のSSM(センターセルフマネージャー)で処理される。シナリオ層では、仕事の内容が記述されている。ノブAに手を伸ばし、ノブAを掴み、ドアを開ける、といった具合だ。いっぽうスキル層では、それらがXに手を伸ばす、Xを掴むといった形で記述されている。スキルソリューション層はそれを実際に実行するために各ロボットのアクチュエーターに合わせてタスク分配を行ない、サーボ層はそれを実際に実行する、という仕組みになっている。この仕組みでは各スキルはコンポーネント化されている。だから逆に特定部分を手動にしたり、自動にしたり比較的容易に切り替えることができる。 こうして構築された神奈川環境プラットフォームはロボットパーク事業事務局県工業振興課に事前申し込みすれば使える。なお、統合シミュレーション環境である「OpenHRP3」を使うことで、神奈川県まで来なくてもシミュレータ上で環境プラットフォームでロボットを動かした状態をシミュレーションできるように現在準備中だという。
● ユニバーサルデザイン・ウィズ・ロボット ~ロボットも含めたユニバーサルデザインとは
たとえば掃除機のように関係性が明確になっているもの、既に普及して久しいものにおいては、かっこよさや親しみを持たせるための見かけのデザインも付加価値として重要になってくる。「売るためのデザイン」だ。だが、ロボットのように、まだどのように使えばいいのかよく分かってないものに対しては、その前段階のデザインが必要だという。関係性の構築、すなわち普及させるためのデザインである。 さて「ユニバーサルデザイン」とは一般的には、誰でも使えるデザインのことだ。だが園山氏は「ロボットも仲間に入れたUD」が必要だという。また行為よりも結果を重視したという。たとえば、ドアを閉めるという行為一つとっても、戸締りをするためにドアを閉めるのか、向こうに行きたいのかで関係性は変わるからだ。そのために、ツールと環境の両面からアプローチしていくことを考えたという。足りないものは環境で補い、それでも補えないものはツールで補う。そうして環境をしつらえることが、日常生活空間にロボットを入れるためには必要になる。 このプロジェクトのロボットの活躍フィールドは日常生活空間であり、そこは快不快といった人間の価値観が優先される場所だ。いっぽう、導入においては費用対効果が重要になるが、家庭における費用対効果、すなわち「くらし費用対効果」は、工場やオフィスのような合理性だけの空間のそれとは別物の価値観であり、理論性と情緒性が混在した価値観だと園山氏は強調した。「くらし費用対効果的には万能選手的なロボットはない」という。 園山氏は「リフォームする感覚で家にロボットを1つ入れる、ちょっと未来のあたりまえを構築したい」と述べた。壁紙を張り替えたり風呂場をリフォームするような感覚で入れられるようなものでなければ、つまり日常生活空間のなかにあって違和感のないデザインモデルでなければロボットの家庭への普及はない。園山氏はデザインモックアップなどを示しながら講演した。トライ&エラーによる精度向上、生活空間で違和感のないスタイリング、発展、展開性の高い形状を意識してデザイン作業を行なっているという。
● 産総研 音田弘氏 独立行政法人産業技術総合研究所 音田弘氏は「神奈川プラットフォームにおける環境構造化のための作業構造化 環境と作業のためのユニバーサルデザイン」と題して「裏方」としての講演を行なった。すなわち、作業知識の構造化や、環境にセンサーを配置したり、それをうまく使う仕組みを構築することで、作業のための環境構造化におけるインフラ整備などだ。作業知識を構造化して分解、ブレイクダウンすることで、さまざまな作業をロボット(計算機)が扱えるような形式にして記述することができ、また各スキルをモジュール化することで再利用できるようにもなる。同時に作業に必要な環境構造の仕様を決めていった。その過程で「物理的・情報的機能補完単位」として生まれたのが「ユニバーサルハンドル」と二次元コード「CLUE」である。「ユニバーサルハンドル」は物理的な保管、「CLUE」は情報的な機能保管を行なうものとして捉えることができる。物理的な機能保管を行なうユニバーサルハンドルをロボットと対象との間に入れることで、対象との物理的インターフェイスを限定できる。それによって作業構造そのものを限定できる。「CLUE」は、位置精度が出ないロボットにビジュアルサーボをかける位置決めの手がかりとしても使われる。 「OpenHRP3」を使ったロボットの立ち位置シミュレーションの様子も示された。遺伝的アルゴリズムを使って最適な位置を見出したそうだ。「iARM」の完全なシミュレーションは一部がブラックボックスになっていることもあり難しかったが、それでもシミュレーションできるようになっているという。またカメラの位置などもシミュレーションされている。
● 環境・作業情報構造化を利用したロボット作業
実証評価を行なう場所になった「神奈川県実証実験プラットフォーム」は、住宅展示場の一角に手を加えて整備したもの。使用されたロボットは、「iARM」付き電動車椅子ロボットと、東芝の双腕ロボットだ。「高齢者の1人暮らし世帯」をイメージした食事シーンで、お弁当を冷蔵庫から取り出して電子レンジで温める作業を補助する、という仕事が想定された。 前述のようにこのプラットフォームの作業構造は、ロボットに依存・非依存を考慮した4層構造アーキテクチャで構築されている。ロボットに依存しない「シナリオ層」と「スキル層」、動作を実現するため実際のロボットに依存する「スキルソリューション」「サーボ層」である。ロボットに依存した部分と依存しない部分を分けていることがポイントで、それぞれのコンポーネントは「RTミドルウェア」のRTコンポーネントで書かれているので流用も可能だ。 なおこの環境・作業情報構造化を利用したロボット作業技術全般についてはネット上でもPDFで読める「東芝レビュー」2009年1月号「特集:ロバスト性を向上するロボット技術」でも詳述されている。本誌読者には興味深い内容だと思うので併読をおすすめしたい。
なお「次世代ロボット連携群」によるシンポジウム「次世代ロボット共通プラットフォーム技術の確立」が2月26日(木)10:00~17:40の日程で予定されている。会場は、アキバプラザ アキバホール5階(東京都千代田区神田練塀町3)。「次世代ロボット連携群」の研究紹介のほか、特別講演として早稲田大学理工学部教授の菅野重樹氏による「WABOTHOUSEと次世代ロボット」、トヨタ自動車株式会社理事の高木宗谷氏による「パートナーロボット」に関する講演も予定されている。詳細はシンポジウムのホームページを参照してほしい。 ■URL 科学技術連携施策群 http://www.jst.go.jp/renkei/ ユニバーサルデザイン・ウィズ・ロボット http://www.is.aist.go.jp/udgn/indexUDGN.html ■ 関連記事 ・ 次世代ロボット連携群「神奈川環境プラットフォーム」見学会を開催 ~東芝ロボットと産総研ロボットがキッチンで作業(2009/02/06) ・ ユニバーサル・シティウォーク大阪で4社7体のロボットを連携して実証実験 ~ネットワークサーバーで情報を共有し、サービスを提供するロボット達(2008/12/05) ・ 次世代ロボット連携群、環境情報構造化プラットフォームの実証実験を公開(2008/01/24) ・ 産総研、ロボットのためのユニバーサルデザインを開発(2007/10/24) ・ 次世代ロボット共通プラットフォーム技術の現状は? ~「次世代ロボット連携群」講演会レポート(2007/09/20) ・ 「次世代ロボット共通プラットフォーム技術」平成18年度成果報告会レポート(2007/02/23)
( 森山和道 )
- ページの先頭へ-
|