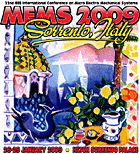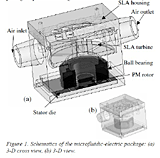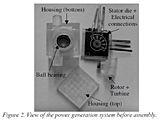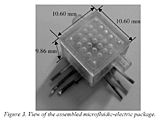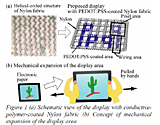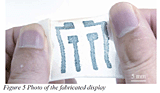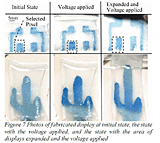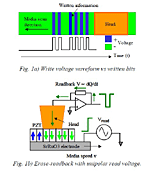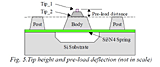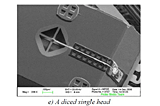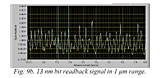|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEMS 2008レポート |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
会場:米国アリゾナ州ツーソン市 JW Marriott Starr Pass Resort & Spa MEMS(メムス)の研究開発に関する国際学会「MEMS 2008(21st IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems)」の現地レポートを、さらにお届けする。今回はカンファレンス3日目である16日の発表から、注目の研究成果をご報告する。 ● 1cm角の発電タービン 午前のセッション7「パッケージングとアセンブリ」では、MEMS技術による小型発電モジュールの発表が興味深かった。米Geogia Institute of Technologyの研究成果である(F. Herraultほか)。高圧の空気を取り込んでタービンを高速に回転させ、タービンに取り付けた永久磁石を回して発電する仕組みのモジュールである。空気取り入れ機構を含めたモジュールの大きさは約1cm角と小さい。試作したモジュールは、電気出力用リード線付きの固定子電気回路、タービンおよび永久磁石(回転子)、ボールベアリングと空気流路を備えたハウジング、それからフタで構成される。液体の樹脂をレーザーで高速に硬化させる3次元ラピッドプロトタイピング技術を駆使してタービンとハウジング、フタを製作した。永久磁石の材料にはネオジウム鉄ホウ素(NeFeB)合金を使用した。回転子の直径は2mm、タービンの直径は6.35mmである。 動作実験では、高圧の空気をモジュールに送り込んで発電させた。言い換えると、開発したモジュールは高圧の空気に耐える構造になっている。およそ25kPaの空気圧でタービンが回り始める。回転速度は空気圧が25kPaのときに毎分10万回転、75kPaのときに毎分20万回転である。商用の小型タービンとほぼ変わらない値を得ているという。電気出力は極めてきれいな3相交流出力である。 試作したモジュールの容積は約1.1立方cm、重量は約1.5gである。発生電力の密度は1立方cm当たり0.7mWだった。なお、このモジュールを第一世代品とする、改良版の第二世代品も試作した。第二世代品の容積は約0.75立方cm、重量は約1.2gと小さく軽くなっている。発生電力の密度は1立方cm当たり46mWとなり、第一世代品に比べて大幅に向上した。
● 手で引っ張ると伸びる小型ディスプレイ 午前の後半であるセッション8「光MEMS」では、機械的に伸縮する小型ディスプレイの発表が目を引いた。東京大学の下山・松本研究室による研究成果である(S. Takamatsuほか)。ディスプレイの両端を両手で持って引っ張ると、画像を表示したままディスプレイが伸びる。手を離すか、あるいは手の力を抜けば、ディスプレイは縮んで元の大きさに戻る。ディスプレイの構造材料は、らせん状に巻いたナイロン繊維である。このらせん状ナイロン繊維で、将棋盤や碁盤の目のような平面状の構造を作る。これがディスプレイの基板となる。エレクトロクロミック効果(電気を加えると酸化還元反応によって色が変化する効果)を有する導電性高分子材料をこの基板(繊維)に含ませれば、ディスプレイとして動作するようになる。そしてナイロン繊維と導電性高分子材料が、ともに伸び縮みする。 下山・松本研究室は、4×4画素(16画素)のディスプレイを試作し、動作する(色が変化する)ことを確かめた。またMEMS 2008の開催場所であるツーソン市を代表する植物、すなわちサボテンを表示したディスプレイを試作し、手でサボテンの高さを伸ばしたところを撮影したビデオを会場で再生してみせた。ビデオを拝見したところでは、サボテンの背丈は3割ほど高くなっていた。なお導電性高分子材料にはPEDOT(poly(3.4-ethylenedioxythiophene):PSS(polystyrenesulfornate)を使用した。
● 強誘電体で大容量の外部記憶装置を作る 午後のセッション9「NEMS」では、強誘電体材料を使った大容量外部記憶装置の研究開発に関する発表が非常に面白かった。ハードディスクドライブ(HDD)の大手ベンダーである米Seagate Technology Inc.が、研究内容の一部を公表した(Y. Zhaoほか)。講演の始めに、強誘電体材料を利用した外部記憶媒体は、HDD媒体よりも1桁高い、1平方インチ当たり10テラビットの記憶密度(面密度)を実現できる可能性があると説明した。ここで強誘電体材料とは、電界を加えると分極が発生し、電界をゼロにしても分極が残る性質を備えた材料のことである。強誘電体材料の薄膜(薄いフィルム)で分極の向きを上下のどちらにするかで記憶情報の「1」と「0」に対応させる。分極の区切りをどんどん短くしていけば、記憶密度が高まる。 ただし、高密度な記憶情報の読み出しと書き込みには、極めて小さくてしかも記憶媒体と安定に接触するヘッドが必要である。そこでシリコン基板を使い、半導体微細加工技術を駆使してヘッドを試作した。 試作したヘッドと記憶媒体(PZT)を実験用の精密な移動ステージに取り付け、データの読み書き性能を評価した。書き込み電圧が8Vのときに、トラック幅51nm×ビット幅22nmと小さなビット列を観測できた。記憶密度(面密度)では1平方インチ当たり450Gビットに相当するという。また13nm幅とさらに小さいビットで信号を読み出せることも示した。
■URL MEMS 2008 http://www.mems2008.org/ ■ 関連記事 ・ MEMS 2008レポート 医療分野で活躍するMEMSデバイス(2008/01/17) ・ MEMS 2008レポート ジャイロや燃料電池などのデバイスに注目(2008/01/16) ・ MEMS 2008 前日レポート 微小な機械システムの最新研究成果が集結(2008/01/15)
( 福田 昭 )
- ページの先頭へ-
|