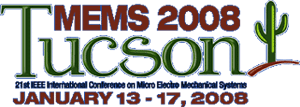|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
|||||||||
|
MEMS 2008 前日レポート |
|||||||||
|
|
|||||||||
会期:1月14~17日(現地時間) 会場:米国アリゾナ州ツーソン市 JW Marriott Starr Pass Resort & Spa MEMS(Micro Electro Mechanical Systems、「メムス」と読む)の研究開発に関する国際学会「MEMS 2008(21st IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems)が米国アリゾナ州ツーソン市で始まった。 MEMSとは、電気信号で動く微小な機械システムを指す。シリコンやガラス、有機材料などをベース(基板)にしており、大きさは数ミリ角程度しかない。マイクロプロセッサやメモリなどと同様の半導体微細加工技術のほか、MEMS独自の加工技術を使って製造する。 これまでに商品化された代表的なMEMSデバイスは、米Texas Instruments(TI)が開発した投射型ディスプレイ(プロジェクタ)用のミラーアレイ「DMD(Digital Mirror Device)」である。シリコンチップ状にディスプレイの画素数と同じ数の微小なミラーアレイを並べたデバイスで、電気信号によってミラーの傾きを高速に変える。DMDを組み込んだ投射型ディスプレイ用光学エンジン技術「DLP(Digital Light Processing)」をTIは開発、販売しており、数多くの採用実績を有する。 最近になって注目を浴びているのが、シリコンマイクロホン(シリコンマイク)である。シリコン基板に振動板を形成して音声(大気の振動)を電気信号に変えるデバイスで、既存のマイクロホンに比べて軽く小さいことと、プリント基板へのはんだ付け工程をほかの電子部品と同時にできることから、携帯電話機での採用が急速に進んでいる。Siマイクの代表的なメーカーは米国のKnowles Acousticsである。このほか、圧力センサーや加速度センサー、角速度センサーなどが複数の企業によって製品化されている。 研究開発段階のデバイスには、各種のセンサーやアクチュエータ、モーター、ポンプ、シリンジ、燃料電池セルなどがある。応用分野は非常に広く、研究テーマとしては相当に面白い。アイデア次第でさまざまなデバイスを作れるからだ。MEMS 2008は研究開発の成果が集結する会議であり、MEMS技術を利用した楽しいアイデアを観賞できる場でもある。 それでは14日~17日に予定されている技術講演(カンファレンス)の概要を紹介しよう。 ● 1月14日(月):室温で1個の電子を測る 14日~16日の3日間はいずれも、午前の最初に招待講演が予定されている。初日の14日は、CMOSベースのセンサーに関してスイスSensirion AGのFelix Mayer氏が招待講演する。続いて一般講演のセッションとなる。「集積マイクロシステム」と「マイクロ流体デバイス/システム」のセッションが午前には予定されている。昼食休憩を挟んで午後の前半は、ポスターセッションとなる。ポスターセッションとは、研究成果(発表論文)の概要を記述してあるポスターを衝立に貼り、発表者がポスターの前に立って参加者の質問を直接受ける発表形式である。同じ時間帯に数多くの研究成果を公表できるという利点がある一方で、参加者がすべての発表を十分に閲覧することは難しいという問題がある。 プログラムを見ると、初日のポスターセッションにはいくつかの興味深い発表がある。例えば、室温で電子1個と極めて高い分解能を備えたエレクトロメーターである。英University of Cambridgeが発表する。このほか、軟らかくて使い捨てできる免疫センサーを米University of Minnesotaが発表する。MEMS技術を利用して有毒ガスの検出感度を高める試みを米University of Illinoisが明らかにする。 午後の後半には、「マイクロアクチュエータ(微小なアクチュエータ)」のセッションが予定されている。 ● 1月15日(火):生体内のセンサーが外部とワイヤレスでやり取り 2日目の15日も、招待講演でカンファレンスが始まる。医療用に細胞を操作する微小なシステムについて、米Massachusetts General HospitalのMehmet Toner氏が解説する。続いて午前の前半パートとなる。「バイオメディカル応用」のセッションである。ワイヤレスで外部と信号をやりとりする生体埋め込み型の圧力センサー(米Callifornia Institute of Technologyらの共同研究グループ)や、可変インダクタを使ったワイヤレスセンサー(カナダUniversity of British Columbia)などの講演が予定されている。 休憩を挟んで午前の後半は、「マイクロ共振器(微小な共振器)」のセッションと「物理センサー/システム」のセッションが続けて実施される。MEMS技術を利用した4軸のジョイスティックをドイツのUniversity of FreiburgとデンマークのTechnical University of Denmarkが共同で発表する。 昼食の後は前日と同様に、ポスターセッションとなる。慢性的な痛みの緩和を狙って2種類の薬液を供給するシステムを、米University of Michiganが発表する。 ● 1月16日(水):外部記憶装置用のMEMSプローブ 3日目の16日も、招待講演でカンファレンスが始まる。光ファイバを使って痛みを感じる神経システムを構築する研究について、東京大学の保立和夫教授が招待講演する。招待講演に続いて午前の一般講演となる。「パッケージングとアセンブリ」のセッションと、「光MEMS」のセッションが午前に予定されている。ここでは分子層レベルの高い分解能で画像を表示することを狙った単原子層の発光ダイオード(LED)を米University of Texas at Austinが発表する。 昼食休憩の後は前日と同様にポスターセッションとなる。この日のポスターセッションは、注目の発表が少なくない。バクテリアを濃縮するチップ(香港のThe Hong Kong Polytechnic University)、高感度の質量センサー(産業技術総合研究所とオリンパスの共同研究)、燃料電池セル向けの燃料と炭酸ガスの自動交換システム(シャープ)、自己発電型の無線送信器(米Cornell Universityなど)といった発表がある。 その後は「NEMS」のセッションが予定されている。NEMSとはNano-Electro Mechanical Systemsの略で、ナノ技術を駆使したMEMSよりも微小な機械システムを指す。「ネムス」とも呼ぶ。このセッションでは、外部記憶装置の読み書き用MEMSプローブ技術を米Seagate Technology Inc.が発表する。 ● 1月17日(木):昆虫の飛行を制御する 最終日の17日は招待講演がなく、ポスターセッションでカンファレンスが始まる。再構成可能なICに向けたCMOS MEMSプローブ(米Carnegie Mellon University)、リストバンド型の液体滴下システム(台湾National Chiao Tung University)、タバコモザイクウイルスをテンプレート電極に使った超小型電池(米University of Maryland)などの発表がある。ポスターセッションの後は、「埋め込みマイクロデバイス」と「RF MEMS」のセッションが予定されている。昆虫の飛行を制御するインターフェイス技術を米Cornell Universityが解説するほか、カブトムシの飛行を制御するシステムを米University of Michiganが発表する。 このほかにも注目すべき講演が少なくない。随時、レポート記事を掲載していくので期待されたい。 ■URL MEMS 2008 http://www.mems2008.org/ ■ 関連記事 ・ Transducers 2007レポート 医療の進歩に貢献するマイクロマシン技術(2007/06/21)
( 福田 昭 )
- ページの先頭へ-
|