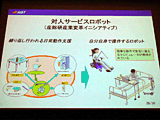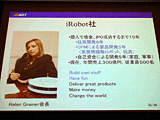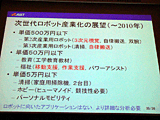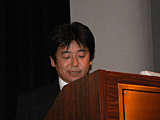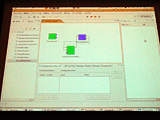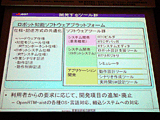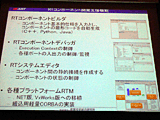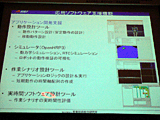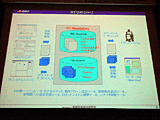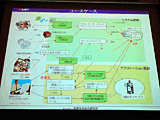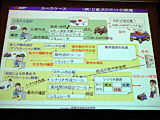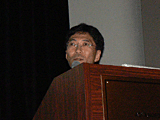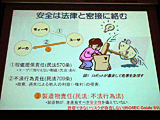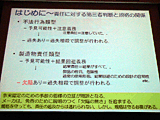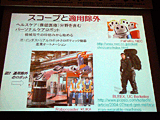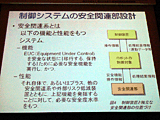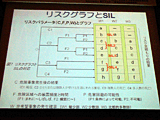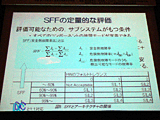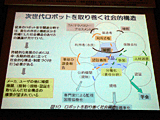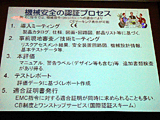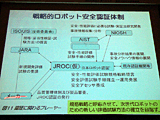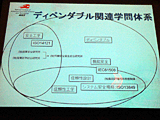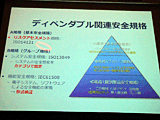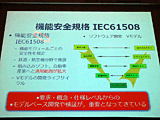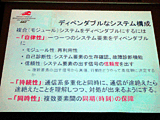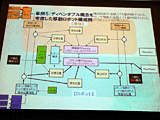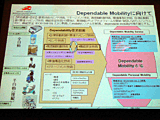|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
産総研知能システム研究部門技術講演会レポート |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10月20日、21日の日程で独立行政法人 産業技術総合研究所のオープンハウスが行なわれた。21日にはロボット技術関連の研究開発を行なっている知能システム研究部門から技術講演会「次世代ロボット産業化基盤技術」が行なわれた。4名の講演者から、現在の次世代ロボットの研究開発を取り巻く環境と課題、それを改善していくためのソフトウェア技術・ハードウェア技術・共有化技術の現状、そして産業化のために必要な安全認証への取り組み、ロボット技術をより安定性と信頼性を高めた技術とするための考え方に関する講演が行なわれた。 ● 次世代ロボット研究開発最前線
まず比留川氏は「次世代ロボットのビジネス化阻害要因」について概説した。以下の4つである。 1) 単一製品あたりの市場規模が小さい 2) 共通基盤技術が未整備で開発コストが大きい 3) 規模の小さい市場を立ち上げる主体が少ない 4) 安全規格等の社会制度が未整備 これらの阻害要因によって次世代ロボット市場はせいぜい100億円規模にとどまっているのが現状である。現状の技術では単一製品あたりの市場規模を大きくすることはいかんともしがたい。そのため比留川氏は2番目の要因、共通基盤技術の整備による開発コスト縮小について重きを置いて述べた。すなわち、ソフトウェア技術・ハードウェア技術の共有化による、ロボット開発コストの低減である。 「RTミドルウェアプロジェクト」(2002-2004)は、各ロボットに実装されているソフトウェアをモジュール化することで共有し、他のロボット開発にも転用できるようにしようというものである。現在も開発は継続中だ。「共通基盤プロジェクト」(2004-2007)は画像認識、音声認識、運動制御のモジュールを作って複数ロボットで共有しようとしたもの。それぞれロボットに実装して有効性が検証されている。 現在はさらに「次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト」(2007-2011)が走っている段階だ。今度は、RTミドルウェアや共通デバイスを搭載したロボットの「知能ソフトウェア」を共有化しようというのがプロジェクトの目的である。現在はロボットのハードウェア・ソフトウェアを開発するツールチェーンを開発中である。 4番目の安全規格や認証機関の問題については次世代ロボットについては安全性確保ガイドラインというものがあり、また工業用ロボットについては労働安全衛生規則があるが、まだ整備は不十分であり、ISO等で規格検討が行なわれている段階だ。後に「安全」についての考え方ともども、詳細が講演で解説された。また、安定なシステムを作る上での「ディペンダプル」という考え方に関しても同様に後に講演が行なわれたのでここでは省く。 さて、では実際に産総研では何をしているのか。あるいは、いま日本国内ではどんなロボットがあるのか。比留川氏は次世代の第2次産業用のロボット、第3次産業用ロボット、そして家庭用ロボットについて概説した。 まず次世代第2次産業ロボット。産業用ロボットは少品種大量生産に対応することを求められており、溶接や塗装、電子部品実装、検査などに使われている。市場の状況そのものは好調だが、なかなか用途が広がっていない。その理由としては、3次元視覚や高度マニピュレーション技術が未成熟であること、そして現場で扱うための工夫が足らない(分かりにくい、難しすぎる)ことがロボット利用の拡大を阻んでいるという。 比留川氏はうまく行った例としてデンソーの高速高信頼性検査ロボット、安川電機の大型液晶ガラス基板搬送ロボットを挙げ、実用化のキーポイントは人間の能力を超えることだと述べた。ただし売れている産業用ロボットであっても、新しい製品の初年度売り上げは数億円にとどまる点には留意が必要だ。 第3次産業においては、人間に勝てる領分で勝負している富士重工の掃除ロボットのほか、産総研の恐竜ロボットやパロなどをあげた。 家庭用ロボットについては、ピーク時に年間100億円を超える売り上げをあげたAIBOとRoombaの例を出し、家庭用ロボットは当たると大きいが、失敗する可能性も高い、そのためいきなり年間100億円を狙うにはリスクが高すぎるので、もうちょっと低いところを目指すべきだとした。 比留川氏は先日のROBO_JAPANで同席したiRobot ヘレン・グレイナー氏のトーク内容を紹介した。iRobotはまず技術開発に8年をかけ、その後多くのファンドから断られながらも何とか獲得した他人の金、つまり投資を受けてさらに5年、そして自己資金による開発を5年続けて今日に至っている。技術開発だけで15年かかるとすると、日本企業はまだまだロボットで儲かる前の技術開発段階にあると考えられる。 ヘレン・グレイナー氏は当日、iRobot社の方針として5つを挙げた。Build cool stuff、Deliver great products、Make money、Have fun、Change the worldである。比留川氏はこの順番を変えて提示し、日本の企業はせいぜい、いかしたモノをつくる、楽しむまでのレベルにとどまっており、偉大な製品を作ったり、金儲けしたり、ましてや世界を変えるところまで行っていないと述べた。 比留川氏の分類によれば次世代ロボット産業化には単価500万円コース、単価50万円コース、単価5万円コースの3つがあり、それぞれ狙うべきところが違う。そしてロボットに向いたアプリケーションというものはない、そうではなく「1つのアプリケーションのなかに、ロボットに向いたフィールドがあるだけ」であり、より詳細な分析が必要だという。
● ロボットソフトウェアプラットフォームの研究開発
最終的にはRTコンポーネントのモジュール化に基づくロボットシステムの開発支援ツール群の開発を目指す。ユーザーインターフェイスを統一し、システム開発やアプリケーション開発などの検証機能をユーザーに提供することで、RTCの再利用を促していく。 現在は再利用性を高めるための仕様策定、どれが必要でどれが必要ないのかの検討、そして記述の形式などを決めている段階だという。ソフトウェアツールに関しては要素機能開発ツール、ロボット設計に直接関わる部分の支援ツール、シミュレータ、アプリケーション開発支援のための動作設計、シナリオ作成ツールなどを開発している。利用者からの要求に応じて、開発項目の追加・廃止のほか、OpenRTM-aistの各種OS、言語への対応、組み込み機器用軽量CORBAへの対応を行なっているところだという。 RTミドルウェアではハードウェア、システム、動作記述をそれぞれ仕様に合わせて記述し、それを動作設計ツール、作業シナリオ作成ツールを使って実際の作業動作を記述していく。このときに単に仕様を作るだけではなく、ロボットの安全性を、実際のシステムを動かす前に判断できるようなものを作っていかなければならないという。
続けて原氏はRTコンポーネント開発支援機能としてRTコンポーネントビルダ、RTコンポーネントデバッガ、RTシステムエディタ、そして各種プラットフォーム版のRTミドルウェアについて説明した。RTコンポーネントビルダは基本的仕様を入力するとコンポーネントの雛形コードを自動生成してくれる。デバッガは各種ポートの入出力の制御/監視を行なう。システムエディタはコンポーネント間の接続を作成し、RTCの状態の制御を行なう。他のプラットフォームとしては.NET版、VxWorks版を開発中のほか、組込み用に軽量化したCORBAへの実装を行なっているという。 応用ソフトウェア支援機能としては、アプリケーション開発支援とロボットシステム開発支援の2つの機能がある。まずアプリケーション開発支援としては、安定した動作を検討可能な「動作設計ツール」、「OpenHRP3」を統合化することで動力学ならびにRTCのシミュレーション、動きの可視化を行なう「シミュレータ」「作業シナリオ設計ツール」実時間性評価を行なう「実時間ソフトウェア設計ツール」などがある。 ロボットシステム開発支援ツールとしては、仕様記述やRTC格納する分散型データベースである「RTリポジトリ」をWebサービス版(通信はHTTPとSOAP)と、通信しないローカル版の2種類で提供。「ロボットシステム構築ツール」ではRTリポジトリに蓄積されたRTCを使ってシミュレーション可能なロボットシステム構築のサポートや、アクチュエータと自由度の配置、必要なセンサーの有無の検証を行なうことができるという。
ユースケースとしては、まずハードウェアメーカーや研究者がハードウェアや知能モジュールをRTC仕様に準拠して記述して分散データベースに蓄える。それを使ってロボットサービスプロバイダなどからなるシステムインテグレーターが、各種設計支援ツールやシミュレータ、作業シナリオ作成ツールを使いながらアイデアを具体化、知能ロボットサービスのアプリケーション設計を行なっていくことになる。原氏は介助犬ロボットによる物体拾い上げ動作の開発という例を示した。 現在、今年度中の「OpenRTM-aist-1.0」対応版の開発及び公開を目指しているところだという。
■URL OpenRT Platform Official Site http://www.openrtp.jp/ ● ロボット安全 ―「規格・認証」の現状と課題―
安全は法律と密接に関係している。たとえばロボットが暴走して怪我をさせたケースを考える。ユーザーに知りえない瑕疵があったら民法570条が問われることになるが、ユーザーとメーカーのあいだには通常、契約はない。そのため責任をこの法律で問うことはできない。同様に、民法709条の不法行為責任はユーザーが立証しなければならないのでこれまた非常に難しい。では野放しでいいのかというとそんなことはないわけで、そこで最近出てきたのが「製造物責任」という考え方である。製造物が本来有すべき安全性を結果において保障しなければならないとするものだ。 製造物責任類型においては、予見可能性に加えて「結果回避義務」が生じる。結果としての安全をメーカーは守らなければならない。たとえば安全規格を守っていたからといって、免責されることはないのである。規格を守っていても、責任の追及からは逃れられない。が、規格は守る必要がある。これは、運転免許を持っていたからといって事故を起こしたときに免責されるわけではないし、運転免許は取らなければならないのと同じようなことだという。
また、安全部のレベルを定量的に評価しようという動きも非常に広い範囲で広がりつつあるという。たとえば不具合がある場合に、不安定な状況を起こすのかどうか、ロボットは自分では分からない。そこで自分を監視する安全関連部を作って、不安定にならないような方策を行なうわけだが、その安全関連部に対する技術的要求を「SIL(Safety Integrity Level)」という尺度で定量的に評価するのである。 まずリスクアセスメントをすることで、リスクと危害がどのくらいの特性を持つのか明らかにする。リスクにはもう1つ頻度というパラメータがある。最終的にそのようなリスクが人間に襲いかかってきたときに人間は回避できるのか。そのなかで、対象となる危害がどのくらいの人数に影響を及ぼすのか。そういった過程でSILを決めていく。SILの技術を使うことで、自分が作っているものがどの程度の安全レベルにあるのか製作者側は把握することが出来る。 SILは主に「SFF(安全側故障比率)」によって決まる。SFFとは要するに安全側に故障するか、危険側に故障してもシステム自身がそれを把握できるかを表したもので、1に近づくほど安全ということになる。これらの技術を使うことで、たとえばSIL2が必要だとなった場合、回路だけではその安全レベルを満足させることができないとなればアーキテクチャからそれを補おう、といったことが判断できるという。このように技術の安全設計を定量化していくのが今日の流れだという。ソフトウェアに関しても同じように安全性達成が求められる。
では次世代ロボットに関してはどうか。社会的には利用者、製造者、保険会社の3者関係だけではすまない。持続可能な技術としてロボットが残っていくためには、安全性の問題が重要になる。それを下支えするのが認証機関だという。日本にはそのような機関がない。ロボットのように新技術が含まれたものから、日本に認証機関を設立させることを狙うのが必要なのではないかと山田氏は述べ、日本独自の認証機関の必要性を訴えた。今は新技術が導入されているためある意味では良いチャンスだとし、今後は安全規格戦略と呼応させて次世代ロボットのための新しい評価試験方法の確立を目指すという。
● ディペンダブルなシステムデザイン
ロボットを実用化するには安全認証が必要であり、またハードウェアやソフトウェアを共通モジュール化することで、ある意味で技術を枯れさせて、安定性を高め、再利用性を高めていくことが重要であり、産総研ではシステムの安全性、信頼性を考慮した設計手法と評価手法の体系化を行なおうとしているという。 なお「ディペンダブル」という概念はいま広がっている途上であり、安全工学や信頼性工学などを包含するものだという。ロボットを使用するには信頼性と安全性、そして市場性が必要になるが、それらは個別で議論できるものではない。
では、ディペンダブルなシステム構成を目指すにはどうすればいいのか。大場氏は「持論」として複合システムをディペンダブルにするには、1つ1つの要素の自律性、通信ほかの持続性、同時性が必要になると述べた。 まず自律性においては、再利用性を高めること、システム要素の機能を明確化して入出力を決めることでリスクマネージメントを行なうなどモジュール姓を高める必要がある。システム要素の生存確認を行なう自己診断性、システム要素の出す信号の信頼度を出すことによる信頼性の確保なども必要だ。持続性においては、たとえばコネクタが切れたらちゃんとそれが分かるようにする必要があるし、接続が切れたとしても、個々の自律性で機能することが求められている。またロボットのような複数モジュールをスケジュールどおり動かすためには、時刻補償も必要である。現在はセンサデータにタイムスタンプをつけることで同期を取ろうとしているという。 事例としてレーザーレンジファインダーの例を出し、センサーが本来出している情報の意味をきちんと考えることが重要だと強調した。また、移動ロボット側のタスクプランナと、インフラ側のタスクプランナによる二重系を使った移動ロボット構成の例を示した。現在はディペンダブル・モビリティ、つまり移動を高信頼に行なうロボットの実現を目指して基礎技術の開発や、共通記述言語としてSysMLを採用し、それによるリスクの記述を行なおうとしているという。 最後に大場氏は複数の移動ロボットを4時間連続稼動させた実験ビデオを見せながら「このような馬鹿みたいな実験もちゃんとやらないと何が起こるかわからないのが現在のロボットなのかもしれない」と述べた。
■URL 産総研オープンラボ2008 http://www.aist-openlab.jp/index.html ■ 関連記事 ・ 産総研ほか、「OpenHRP3」をオープンソースで配布開始 ~ソフトウェア再利用によって開発コスト低減を目指す(2008/06/19) ・ 次世代ロボット共通プラットフォーム技術の現状は? ~「次世代ロボット連携群」講演会レポート(2007/09/20) ・ 第2回安全工学フォーラムレポート(2007/02/02) ・ 産総研、知能システム研究部門 研究成果展示会「オープンハウス2006」を開催(2006/11/16) ・ 産総研、ロボット産業活性化を狙うオープンアーキテクチャの開発を開始(2006/06/28)
( 森山和道 )
- ページの先頭へ-
|