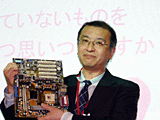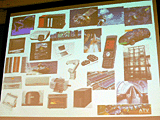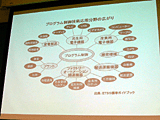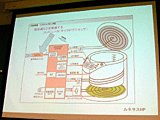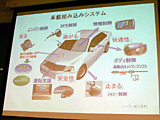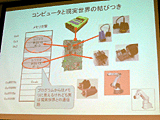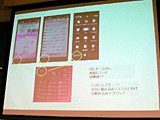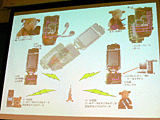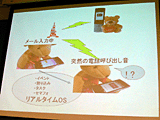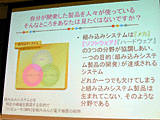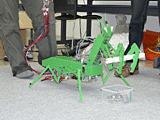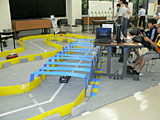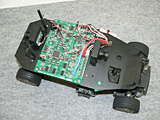|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「ET×ロボット2008」レポート |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6月21日(土)~22日(日)に、大阪電気通信大学四條畷キャンパスにおいて、ET(Embedded Technology:組み込みコンピュータ技術)とロボットをテーマにした体験・展示の複合イベント「ET×ロボット2008」が開催された。主催はET×ロボット実行委員会、共催は大阪電気通信大学。 ● ET入門講演会「誰にでもわかる組み込みシステム」
南角准教授は、「身の回りの家電製品で、コンピュータが使われていないものを上げてください」という質問から、講演を始めた。自宅にある家電製品を思い浮かべながら、答えを見つけられずにいると、南角准教授は「業界では、蛍光灯が最後のアナログ家電と言われていました」と言った。“最後の”と但し書きがつくのは、蛍光灯もいまではインバーター制御になり、コンピュータ搭載されている製品が珍しくないからだ。 組み込システムというのは、特定目的の機能を実現するために開発された、メカ、ソフトウェア、ハードウェアから構成されるシステムのことを言う。工場で作業をする産業用ロボットや工作機械はもとより、家電製品も商品に新機能を追加し付加価値をつけるために、コンピュータを搭載し組み込みシステムの対象とされるようになった。 今では、我々の身の回りにあるものはほとんど全てと言って差し支えないほど、コンピュータを搭載している。
南角准教授は、身近な例として、携帯電話を取り上げて組み込みシステムの解説をした。携帯電話はひとつのボタンでも、表示される画面によって異なる機能が割り当てられる。メニューボタンは、Webブラウザを使っている時には「メニュー」キーだが、設定画面では、「カスタマイズ」キーになっている、という感じだ。これもコンピュータが組み込まれていて、プログラム上で画面を判定して、ボタンの機能をプログラム的に振り分けているから実現している。 音声というのは、入力も出力もアナログだが、携帯電話はアナログ信号をデジタルデータに変換して通信する技術を駆使している。 初期の携帯は、音声というアナログデータだけで処理されていたが、携帯電話の普及と、高機能化に伴ってデジタル化せざるを得なかったという。まず周波数の問題がある。携帯電話で使用できる周波数は法律で定められているため、同じ周波数の電波を複数送ることは、アナログでは不可能だ。デジタルなら、同じ周波数に10人分の電波を乗せることも可能になる。それ以外にも、ノイズの除去などデジタルだから解決できることはいろいろとあるという。 例えば、メールを入力している最中に電話が掛かってきた時、会話をした後にメールの続きを入力できる。このような複雑な割り込み処理に対応できる仕組みは、全て組み込みシステムの成せる技である。組み込みシステムは、ユーザーに意識されないくらい自然に身の回りにあるのだ。
つまり、組み込みシステムは前述の携帯電話のように、いつどのような条件で割り込み処理が入るのか分からない。その点が、実行ボタンを押せばその結果を表示する会計管理ソフトや出退勤管理ソフトなどと違う点だ。 組み込みシステムは、「メカ」「ハード」「ソフトウェア」の3つの分野が協調し、1つの目的を達成するシステムだ。どれかひとつでも不備があれば、システムは稼働できない。携帯電話業界などで顕著なように、新製品投入サイクルは短くなるのに、機能は複雑になり開発するソフトウェア量は増大している。このような背景があって、組み込みシステム技術者の需要は高まっているという。 南角准教授は「組み込みシステムに興味を持ち、将来、自分が開発した製品を多くの人の役に立つ喜びを感じてほしい」と語った。
● ET&ロボット体験、製作・プログラミング教室 会場では、来場した小中高校生向けに、レゴを使った「ETロボット製作&プログラミング教室」や、大阪日本橋でんでんタウン協力の「触覚センサーで自律移動するオリジナルロボット工作教室」「ETプログラミング教室」「ET&ロボット体験教室」などが開催された。初級者~上級者まで多くの参加者が、ロボット工作とプログラミングを楽しんだ。
ET&ロボット体験教室では、大阪電気通信大学の自由工房による人型ロボット操縦体験コーナーが大人気。午後には、ミニ・バトルトーナメントも開催された。他にも、ロボカップ小型リーグのデモンストレーションや、大阪府立工業高等専門学校のブースでロボットの展示があった。同校の学生が製作したアニマトロニクスは、エアシリンダーでジャンプするカンガルーロボットや、カマキリロボットが人気を集めていた。
サンリツオートメーションは、レスキューロボットコンテストのプラットホームに採用されている遠隔操作IPシステムを活用し、ラジコンカーにカメラを搭載しゲーム感覚で楽しめる展示をしていた。遠隔IPシステムは、キャプチャと画像圧縮を並行処理しながら、無線LAN経由で100ms以下の遅延時間を実現している。人はわずか0.1秒の遅延でも違和感があるため、車速と操舵角度情報から、伝送遅延分の予測画像を算出して加工し、遅延が生じていない画像を補整して、リアルな操作を可能にしている。 今年の8月には、デジタル入出力8ch、オーディオ入出力、CANなどを追加したボードを新発売するという。 アールティは、新製品のハーフサイズマウス「Pi:Co」で子ども達に迷路ロボットのデモンストレーションを行なった。子どもに迷路を作ってもらい、マウスがスタートからゴールまで自走する。ゴールした後も迷路の探索をしてからスタート地点に戻り、第二走行は今、探索した走路の中から最短距離を選んで走るマウスの賢さに子どもも保護者も感心していた。
■URL ET×ロボット2008 http://et-x-robot.jp/ ■ 関連記事 ・ アールティ、ハーフサイズマイクロマウス「Pi:Co」を発売開始 ~技術力向上のための新競技に対応(2008/06/04) ・ 「ET×ロボット2007 パート2」レポート ~WRO Japan 2007 関西地区予選会同時開催(2007/08/27) ・ 「ET×ロボット2007 パート1」レポート(2007/06/14)
( 三月兎 )
- ページの先頭へ-
|