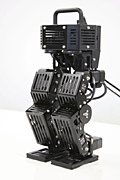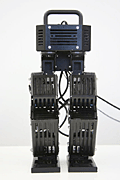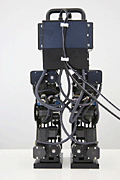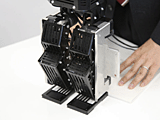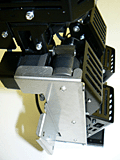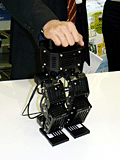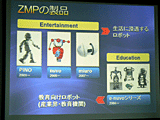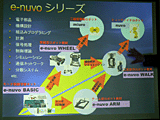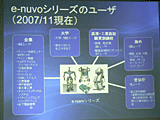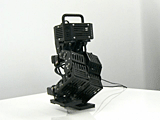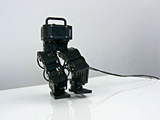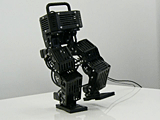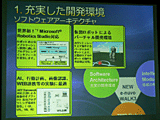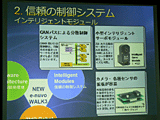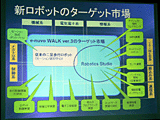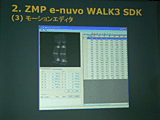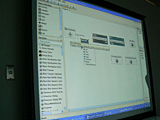|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZMP、情報系研究室をターゲットとした2足歩行ロボット教材「e-nuvo WALK ver.3」製品版を披露 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「e-nuvo WALK ver.3」は高さ35.3cm、重量2.5kg、片足6×2で全12自由度を持った、足だけの2足歩行ロボット教材。体内LANには自動車に用いられることの多いCAN、アクチュエーターには双葉電子工業と新規に共同開発した「インテリジェント・アクチュエータ・モジュール」を採用。ホストPCのOSはWIndows XP/Vista、ロボットとの通信インターフェイスはUSB 2.0。価格は588,000円。 今回の出荷版は、2007年11月に発表されたプロトタイプよりも全体を軽量化。関節構造やハーネス配置を変更し、より教材として適したものとなったという。一定以上の外力が加わると脱力する機能も備えており、安全性にも配慮されている。また、各関節のキャリブレーションを簡単に行なうためのアルミ製治具も付属する。
ZMPはiPodのスピーカーとして機能する音楽ロボット「miuro」のほか、産業界・教育機関向けに「e-nuvoシリーズ」を2004年から展開している。e-nuvoシリーズはモータ制御やソフトウェアの基本を学ぶ「e-nuvo BASIC」、倒立二輪型ロボットを使って制御を学ぶ「e-nuvo WHEEL」、機構解析を学ぶ「e-nuvo ARM」そしてそれらを応用し運動解析やシミュレーションを学ぶ二足歩行ロボット教材「e-nuvo WALK」から構成されている。基礎をいろいろ学んだ上で二足歩行ロボット、というのが基本プランだが、実際のユーザーは別れているそうだ。 現在、「e-nuvo」全体は主に組み込み系と自動車系の企業を中心に広がりつつあるが、今回の二足歩行ロボット教材「WALK ver.3」は、もう一度大学や高専、研究者向けに提供していきたいと考えて作ったとZMP技術戦略室室長 坂井亮介氏は語る。 特にメカ設計は「これまでの経験をいかして、教材として組み立てやすく、かつ壊れにくくなっている。他のロボットとはぜんぜん違うレベルに達している」と自負しているそうだが、今回の教材はむしろメカとしてのロボットの歩行や機構だけではなく、上位のソフトウェアを開発するためのプラットフォーム環境としてのロボットを主に情報系の研究室に提供していきたいという。ハードウェアの知識がなくても上位のアプリケーションを構築できる環境を提供することで、ロボットそのものだけではなく、ロボットを使って、あるいは情報家電などとロボットを連携させて、何をするのかといった部分にアプローチしていく予定だ。
「e-nuvo WALK ver.3」は、ハードウェアとソフトウェアを繋ぐミドルウェア/開発環境として「Microsoft Robotics Studio」を採用している。「Microsoft Robotics Studio」の機能を使ったバーチャルロボットと実機の連携がスムーズに行なえる2足歩行ロボット教材は他にはないという。また、カメラや各種センサー類も、これから1年かけて準備していく予定で、最初はカメラから始める。「メカトロ寄りだったロボットを、コンピュータサイエンス系のほうに引っ張っていきたい」と坂井氏は語る。 「Microsoft Robotics Studio」は、汎用インターフェイスをもったソフトウェア単位としての「サービス」の集合として、システム全体を構築する「サービス・オリエンテッドアーキテクチャー(SOA)」ベースで構成されている。非同期通信をベースにしているため、多種多様なセンサ入力への応答処理を多用するロボットに適しているという。ロボットをコントロールするソフトウェアはVPL (Visual Programming Language)を使ってドラッグアンドドロップで書いていくことができる。 ZMP技術開発部の落合亮吉氏によれば、「e-nuvo WALK ver.3」ではシミュレータと実機を表現するサービスがあり、それを抽象化する「Generic Biped Walker」というインターフェイスがあるという構造になっている。ユーザーは、制御対象がシミュレータ上のバーチャルロボットであろうが実機であろうが、「Generic Biped Walker」に対してプログラミングをすればいい。 ユーザーアプリケーションからは非同期でキーフレームを使ったモーションを送り、ロボットサービス側が補完処理を行なうことでリアルタイム性を保証する。ロボットの体内通信にはCANが用いられている。ロボットはCANとUSBを変換するボードを搭載しているので、PCとの接続はUSBで行なう。 モーションの作成は専用のエディターを使って行なう。順運動学、逆運動学それぞれの手法でGUIを使ってモーションが作成できる。サンプルモーションなどはウェブを通じて配布を行なう予定だ。
「e-nuvo Walk ver.3」は海外販売も予定されており、既に台湾に20台出荷されることが決まっているそうだ。またシンガポール、韓国、メキシコなどにも出荷の予定があるそうだ。特に海外ではコンピュータサイエンスの研究者から「ロボットを使いたい」という要望が多いという。 ロボット教材には他社のロボット教材もいろいろあり、現場で用いられている。ZMPではエンジニア育成を目的とした資格認定・検定会社である株式会社ロボテストを2007年11月にFRI、パソナテックと共同設立しており、そこではZMP社のロボット以外も扱っている。今後、ユーザーである先生たちの反応を見つつ、教材だけではなく、テキストとカリキュラムを充実させていく予定だ。 ZMP教育市場開発リーダーの金子康行氏は「ただ単にモノを売るだけではない」という。「ZMPのリソースでできることをやりながら、ロボテストのほうで世の中のニーズをうまくひろっていく」とのことである。 他の教材と比較した強みの一つとして、ZMP技術開発部の瀬川正樹氏は、「おそらくこの教材を使っていると自然にVPL(Visual Programming Language)ベースのサービスを開発したくなり、結果として.NETサービスを作れるプログラマーになれる」という点をあげる。「e-nuvo WALK ver.3」を使って簡単にプログラムしてコントロールしていくことで、インターネットのほかのシステムとも協調させながら、プログラムを作れるようになることが望ましいという。 なおZMPで「Microsoft Robotics Studio」を実際に使って今回の開発を行なったところ、最初は非同期通信環境と同期が必要なモーション実行環境との作りこみがなかなか難しい面もあったそうだ。 今後同社ではハードウェア開発会社としての強みをいかしながら、マイクロソフトの技術も取り込みつつ開発を続けていくという。 たとえば「e-nuvoアーム」は、WALKと同じサーボユニットや通信基板を用い、ソフトウェアも「Microsoft Robotics Studio」に対応している。流用した部分もあるそうだ。ソフトウェアの流用により開発スピードが大幅に上がったという。今後も、自社でのロボット開発にもMSRSを使える部分は大いに活用していくという。 また、国内だけではなく広く海外にも通じるブランドでもあるマイクロソフトのプラットフォームを用いていることにより、互いに効果的に情報共有しながら海外展開も積極的にはかっていくという。ものづくりに強いアジアだけではなく、ロボットを使ったサービス開発に興味を持っている人がより多い、アメリカやヨーロッパの研究者/技術者に効果的にアピールしていく方法も模索中だ。 なお「e-nuvo WALK ver.3」は3月末時点で既に100台近い引き合いがあり「初年度200台はいける数字だと思っている」とのことである。特に台湾、韓国、シンガポールなどが見込みのある市場だという。 なお「Microsoft Robotics Studio」そのものは、現在は無料で配布されている。「e-nuov WALK ver.3 SDK」を使えば、実機のロボットがなくてもロボット開発が行なえるが、「e-nuov WALK ver.3 SDK」そのものは、購入したところの同一法人内では自由に使ってもらえるようにする方針だそうだ。また現在は16個程度のサンプルモーションしかないが、今後、ユーザーがモーションエディターで作成したデータをお互いにウェブサイトを使って共有するといったことも検討しているという。 上位のアプリケーション開発だけ行ないたい、ロボットのモーション作成や制御技術開発そのものには興味がないというユーザーをターゲットにするのならば、「Microsoft Robotics Studio」をプラットフォームとした各種サービスの共有なども必要となってくるだろう。それらは「ZMP一社でできることではない」ので、ある程度、ユーザーの動向を見ながら進めていくとのことだ。 ■URL ZMP http://www.zmp.co.jp/ e-nuvo http://www.zmp.co.jp/e-nuvo ■ 関連記事 ・ ZMP、MS、双葉電子工業3社がロボット教材「e-nuvo WALK ver.3」を開発 ~共同記者会見で発表(2007/11/30) ・ ZMP、エンジニア教育カリキュラム「e-nuvo」シリーズを強化(2006/07/12)
( 森山和道 )
- ページの先頭へ-
|