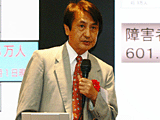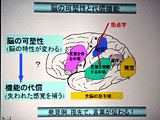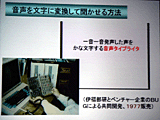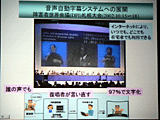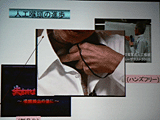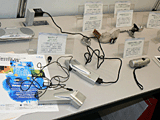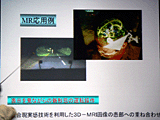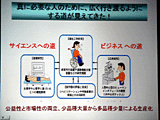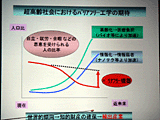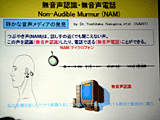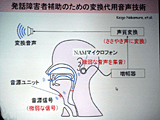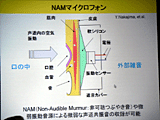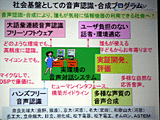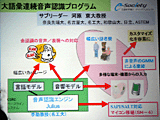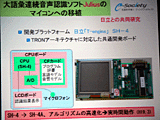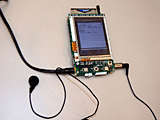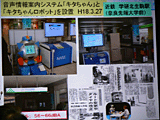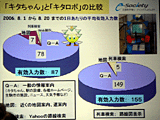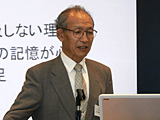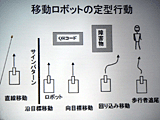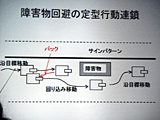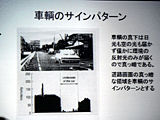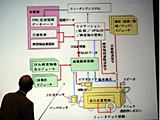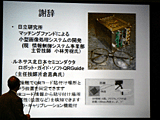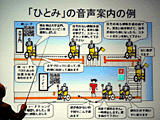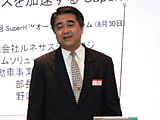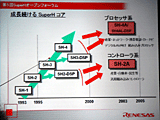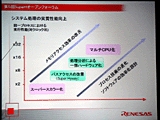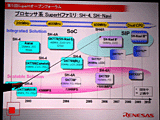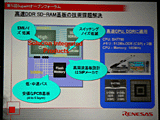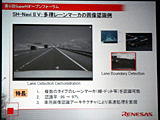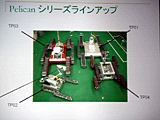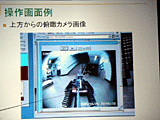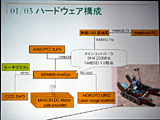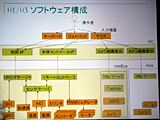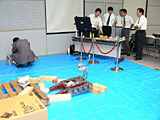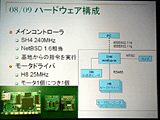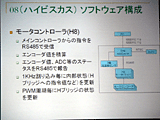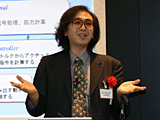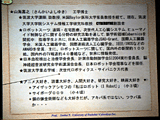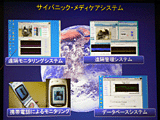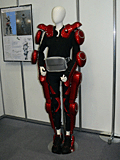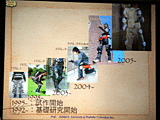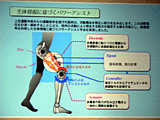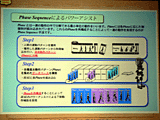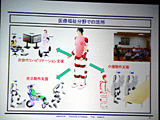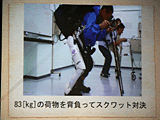|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「第5回 SuperHオープンフォーラム」レポート |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
~ロボット産業で活用されるSuperHファミリ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8月30日、「第5回 SuperHオープンフォーラム」が開催された。主催は株式会社ルネサステクノロジと株式会社日立製作所 研究開発本部。 SuperHフォーラムとは、大学等の研究機関に対して、日立製作所が開発し、現在はルネサステクノロジに移管されている32bit RISCマイコンである「SuperH」を活用した研究を支援することを目的として、'98年に設立されたもの。また、大学研究者からのアプリケーションを探索することも目標の1つだという。 オープンフォーラムそのものは2002年から開催されており、ルネサステクノロジ、株式会社日立製作所中央研究所、日立研究所、システム開発研究所など研究開発本部が推進している。 SuperHファミリは「SHマイコン」の名前でよく知られており、さまざまな組込み機器等に用いられている。会場では大学の研究者によるSuperH関連研究の講演だけではなく、ルネサステクノロジと日立製作所によるSuperHの開発・展開計画や技術紹介のポスター展示やデモが行なわれた。
福祉は、以前はなかなか企業が手を出しにくい分野だったが、平均寿命の伸びもあり、徐々に注目を集め始めている。伊福部教授は、東大助教授の福島智氏と共同で、身体機能支援の研究を行なっている。福島氏は視覚と聴覚を幼いころから青年にかけて失ったが、自ら開発した「指点字」という手法でコミュニケーションを行なっている。いっぽう伊福部氏は、'70年代に、音声を触覚で提示するための触覚ディスプレイを開発していた。現在では脳科学の知見もとりいれて改良を続け、盲ろうの人に歌の練習をしてもらうまでになっている。 また音声を文字に変換する試みも、伊福部教授は'70年代からZ80を使って試みていた。いわゆる音声ワープロである。しかしながら音声認識は未だに非常に困難だ。 「機械でできることと人間しかできないことをうまくすりあわせられないだろうか」。この考え方をベースに2002年に開発したのが「音声自動字幕システム」である。講演の様子を字幕で出すのだが、いったん決まった人間が復唱することで、テキスト化を正確に行なうシステムだ。現在は、インターネット経由で復唱することで、復唱者がどこにいても使えるシステムへと改良しているという。 伊福部教授は、声帯を失った人に対して声を出すのを助ける技術も開発している。もとのアイデアは九官鳥の発声だった。九官鳥は声帯がない。だが人間の声真似ができるのは2つの音源を使って抑揚までもまねしているからだという。だから波形を見ると人間の声とは違う。しかしながら「おはよう」という声を聞くことができる。それをまねて人工喉頭を作った。最近は首のバンドに装置をすべて埋め込んでハンズフリーとする方向に改良しているそうだ。 なお、質疑応答で明らかにされたところによると、もともと人工喉頭を作ろうと思って九官鳥の研究をしはじめたのではなく、九官鳥の鳴き方そのものに興味を持ったことから始まった研究だったという。 そのほか、腹話術師の「いっこく堂」氏の協力も得て、生まれつき口が閉じない人に発声訓練をさせたり、タッチパッドを使った発声障害者のための音声楽器の研究開発なども行なっている。
読むことを助ける研究も行なっている。人間の脳が持っている隠れた能力を利用して、認知を助けようというものだ。たとえば、最近はGUIによって、画像が多くなったが、これは視覚障害者にとってはハンディキャップになる。そのため、画面情報を指先で感じ取りながらテキストを好みの速さの音声で聴くというものである。 また、これらのような技術を、バーチャルリアリティやロボティクスへと応用しようという試みも行なっている。コウモリは超音波を使って空間を知る。伊福部教授は長年コウモリの研究をしているが、盲学校の生徒たちが気配によって障害物を知覚できることに気づき、その研究も行なった。その能力は空間のどこに何があるかという空間定位どころか、衣服の材料や壁の向こうの様子までわかるほどだという。これは、人間が何らかの「気配」を感じ取っていることを意味する。それらの知見をVRやMRへと応用しようとしているのだ。 さらに伊福部教授は、そのほか水素吸蔵合金を使った補助器具開発など、幅広く多種多様な分野で研究開発を行なっている。「これからは高齢化社会が来ることもあってビジネスの道も見えてきたし、サイエンスも福祉工学のなかに見えてきつつある」と講演をまとめた。
まず鹿野教授は、他人には聞こえないが自分には聞こえる非可聴つぶやきと呼ばれる声を音声認識させてささやき声に変換することで、声を出さなくても電話ができる、「無音声電話」の研究開発について述べた。 「NAMマイク」と呼ぶ特殊なマイクをつけることで、わずかな声を認識させるのだ。さらにこれを同じく鹿野教授らが開発していた「固有声に基づいた声質変換」技術と組み合わせて応用することで、発達障害者補助のための変換代用音声技術へと展開しているという。つまり静かな場所でも電話できるし、声が出しにくい人でも電話できるといったことに応用できる技術である。
いっぽう、ノイズが多い場所での音声認識技術、音源分離も研究している。ロボットへの命令などに応用できる技術だ。また携帯電話へのハンズフリー入力もターゲットだという。 また、音声認識を広く普及させることが目的だと強調する鹿野教授は、屋外での道案内など、音声認識合成技術への応用にも力を入れている。講演では現状が技術と実証実験の様子を含めて紹介された。
音声認識システムを動かすと大人は恥ずかしいのか、むしろ子供が多く使うそうだ。しかし子どもの呼びかけを認識することはさまざまな問題があって難しいのだが、それもなんとかクリアし、外部雑音も、種々の雑音や笑い、咳払いなどの認識モデルにより音声と区別できるレベルに到達している。もっとも企業が音声認識システムを設置してくれることはまだ少なく、主に大学などで使っているそうだ。鹿野教授は「徐々に性能はあがっているのが現状だ」と語った。 特に、「たけまる君」という音声認識システムを生駒市の北コミュニティセンターに設置し運用しているという。笑い声や咳払いなども認識することができ、それは棄却している。対話は1万例くらいの質問応答を用意しておき、それを候補の上から順に出しているだけだが、それでもかなりのコミュニケーションが成立するという。 また近鉄からの依頼で、学研北生駒駅に音声情報案内システム「キタちゃん」と「キタちゃんロボット」を設置し、運用している。やはりロボットは子供たちに大人気だが、あまり実用的なやりとりには使われていないようだ。
今後は、現状ではPCを使っているところをSHなどのマイコンに置き換えて、音声情報案内システムの低コスト化を狙うという。ソフトウェア開発のコストを下げることも課題だという。 普及についても駅での案内用途では限界があるので、やはりカーナビや携帯電話などへの搭載が目標だという。会場からは、LSIへの期待についての質問が集中し、鹿野氏は「マイコンそのものはかなりいいところまで来ている。企業が使う道筋ができれば」と期待を語った。
現在も画像認識を使ったインテリジェント車椅子の開発を行なっている。車椅子という名前だが、実際には後ろのハンドルにつかまって歩行補助具として使うこともできる。「ロボット」という名前にしなかったのは、現在の道路交通法では、ロボットはだめだから、ということだそうだ。現在は、歩道を動くものでモーターをつけていいのは車椅子だけで、乳母車にもモーターはつけられないのだという。 道路交通法14条では「目が見えない者(目が見えない者にじゅんずる者を含む)が道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない」となっている。 白杖は歩行支援と、周囲の人に視覚障害者であることを知らせるために使用されるが、白杖の他に××を持ってはいけないとは何処にも書かれていない。そこで、白杖を携えれば視覚障害者が「ひとみ」を道路で利用しても問題ないと考え、実用化に踏み切ったという。 「ひとみ」の利用者は、次のような場面で白杖による歩行をする。視覚障害者が歩道の工事区間に来ると「ひとみ」は経路を先へ進めなくなり、誘導を中止する。そこで、視覚障害者は作業員に誘導してもらい、白杖を携えて先頭を歩行。「ひとみ」は視覚障害者の後から付いて行く。工事区間を通り過ぎたら、「ひとみ」は元の経路に戻り視覚障害者の誘導を続ける。視覚障害者は背中にQRコードをつけているので、工事現場の作業員とは区別される。 インテリジェント車椅子の移動戦略は、3次元認識を行なうのではなく、より単純なものとすべきだと考えているという。特定のパターンを認識すると、ある特定のアクションを行なう。昆虫や魚の行動のような、単純な生き物行動を真似た、いわゆる「定型行動」を行なうのである。 たとえば歩行者の脚部分の画像明度は周期一秒程度でリズミカルに変化する。それを「サインパターン」として認識する、すなわち歩行者だと判断する。そうすると、取りあえず定型的な回避行動を行なう、といった仕組みだ。どういう障害物を検出したときにどんなアクションをとるかはXMLで記述しておく。画像処理でロボットが認識して動くといっても、通常の道路にある縁石や横断歩道のデータだけを持っていればいい、というのが森氏のアプローチだ。
インテリジェント車いす「ひとみ」を開発する上で一番苦労したのはビデオカメラの位置だったそうだ。搭乗者の影となってしまう場所にはつけられないからである。特徴は折り畳みができること。そのおかげで壊れないという利点もあるが、たえず車体そのものが2ヘルツくらいで揺らぎ続ける。さらにより高い位置にあるビデオカメラそのものは5ヘルツくらいで絶えず揺らいでしまう。そのなかで精度を出さなければならないことが課題の1つだ。 インテリジェント車椅子の実際の使い方としては、まず環境側に貼られたQRコードを使って位置方位を合わせて、点字ブロックにあわせて移動していくイメージ。途中のルートにもQRコードを張り、ルートを間違っていないか絶えずチェックを行なう。横断歩道など危険な場所での前進決定は手動で行なう。 2006年度から198万円で受注生産されており、現状で、2台売れているそうだ。内訳は、部品代が130万円で、残りは人件費だそうだ。数が出るものでもないので、価格はなかなか下がりそうにない。 森氏は、「道路交通法では視覚障害者は盲導犬または白い杖をついて歩けということになっているが、これを改正しなければならない」と語った。そのためには視覚障害者団体などが主体となって要望を出していく必要がある。技術的な課題は、画像認識のスピードアップと、ビデオカメラのゆらぎ解消。今後はハイビジョン対応のカメラと高速なビデオ処理システムがほしいという。現状では、昆虫や魚のようなレベルにも達していないと述べた。
野口氏は、モバイル機器、自動車、家電などの領域で、「革命的な変化」が起きているという。製品サイクルは短くなり、開発コストは増えている。しかし一方で、アプリケーションの融合も進んでいる。たとえばモバイル機器、車載機器などでそれぞれ同じ音声技術が使われるようになっている。 SHファミリは、'93年に始まり、コントローラ系とプロセッサ系、主に2つの方向で開発が進められている。開発の上では、ソフトウェア継承性を重要視しているという。これまで、スーパースカラー化、バスアクセスの改善、処理の一部のハードウェア化によって処理性能をあげてきた。現在はマルチCPU化を目指して開発を進めているという。
マイコン製品展開と、開発環境の提供などシステムソリューション展開を行なっているSHだが、コントローラー系では、不揮発性メモリを微細化によって1チップのなかで大容量搭載することで高速化を進めている。いっぽうプロセッサ系では、携帯電話多機能化に伴って画像・音声処理に活用されている「SH-Mobile」が目立つ。現在では携帯電話キャリア、メーカーと共同開発を進めるようになっているという。 また、SH-4などでは高速化するとノイズの問題が発生するが、ルネサスでは全体をSiP化することでこの問題を解決し、まもなくSH7780をCPUに、512MB DDRを2個組み合わせてSiP化したものを量産する予定だという。 またカーナビなどに使われるSH-Naviは、画像処理技術を向上化させ地図描画や、まるでゲームのような3Dグラフィックス描画を可能にする方向に性能を向上化させている。また、車線の認識など車の安全技術向上にも使われている。 ルネサスではこのような技術をシステムとして提供していくことで開発速度向上やユビキタス化を加速していく、と述べた。
現在のレスキューロボットは、人間を直接助けるロボットではない。救助するレスキュー隊員よりも先に入って情報を収集するロボットだ。画像を中心にセンサー情報を集めて取ってきて、実際にあとから現場に入る隊員に役立てることがタスクだ。小柳教授は長岡での災害復旧支援活動や、ロボカップレスキューでの様子、アメリカやドイツでの訓練参加についてもふれながら、レスキューロボットの現状について述べた。 小柳教授は、不整地を突破するためのフリッパーアームをつけた「ペリカン(Pelican)」という一連のレスキューロボットを開発している。ロボットを雨水管のなかで実際に活動させた経験から、レスキューロボットは災害救助だけではなく、復旧にも役立つと考え、防水されている05号や、完全に倒壊した家屋で活躍する07号を作った。
NBCテロ対策用に実用化を目指して開発され、今年5月に記者発表された「ハイビスカス」は08号機だ。「世界ナンバー1のモビリティを持っている」と小柳教授は語った。最新型の09号機「アイリス」は08号機の小型版。子犬くらいの大きさで、動きもどことなく犬を思わせる。 これまではメインボード上にモータドライバがのっていたが、08号機と09号機は、モータードライバを独立分散化させることで、ロバスト性を向上させた。モーター制御はH8で、メインボードにはSH-4が搭載されている。それぞれの制御コンポーネントはできるだけ小さくコンパクトにモジュール化されていて、それぞれの完成度を上げるという形で開発を行なっているそうだ。
将来的には被災現場に到着して10分以内にすべて準備ができて、数時間活動できるような体制を実現することを目指しているそうだ。 最後に小柳教授は、レスキューロボットに用いられる機器は本質的に信頼性の高いシステムが要求される。同時に、ヒューマンインターフェイス(操作性)、小型化(対地適応能力)、軽量化(耐久性と運用)、低消費電力(長時間稼動と低発熱量)が求められるという。現在は25kg程度ある重量を少なくとも20kgくらいまで軽量化し、どういう不整地でどんな姿勢が最適か判断するくらいのインテリジェンスはロボットが持つべきだと述べた。 また、広い範囲を見ることができるマルチビジョンを実現する画像処理と通信技術のハードウェアがほしいと語った。
いまはすっかりHALでお馴染みの山海教授はロボティクスだけではなく、血栓や人工心臓、遠隔モニタリングシステムなど医療系の研究も行なっている。「中途半端は好きではない。やはり1つ何かを研ぎ澄ましていくことが重要」、「自分はアニメやSFも好きだがアキバ系ではなくツクバ系」と、硬軟取り混ぜた調子で講演を行なった。
基本的に「未来ビジョン」が重要だと語る山海教授は、医療系のバックグラウンドを語ったあとに、ロボットスーツの話を述べた。 '92年に基礎研究をはじめたロボットスーツ「HAL」は、その後試作開発を繰り返し、現在に至っている。HALは、脳から筋肉に送られる運動指令の信号(生体電気信号)をセンサーで読み取って、解析。実際に筋肉が出すだろう筋力を推定する。そして筋肉が動き出すよりも少し早くモーターを動かして、人間の動きを補助する。 オペレーションは人間の身体そのものに依存しているが、間の動きについていくのではなく、ロボットのほうが先に動き出してアシストするように動く点が特徴だ。また、ロボット的な自律制御も組み込まれている。
HALは、装着しているだけで人間の状態を記録することもできるので「次世代リハビリテーション支援」、また車椅子と組み合わせた「自立動作支援」、重いものを持つ「介護動作支援」などさまざまな分野でも使えるという。 また、80kg以上のものを背負ってスクワット競争する様子など、先日テレビでもオンエアされた(日本テレビ ドキュメント'06「今しかない君と あの峰へ ロボット・友情・アルプス 」、8月27日放送)雪山登山仕様のロボットスーツ開発の模様もビデオを交えて紹介された。現在、40kgのものを片腕で持てるようにもなっているという。
■URL ルネサステクノロジ http://japan.renesas.com/homepage.jsp SuperHフォーラム http://resource.renesas.com/lib/jpn/superh/forum/index.html
( 森山和道 )
- ページの先頭へ-
|