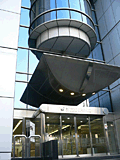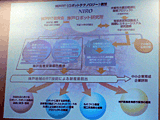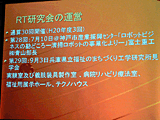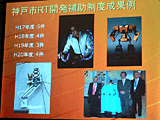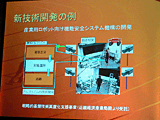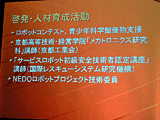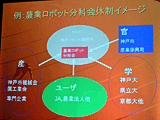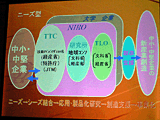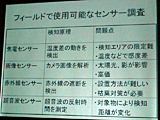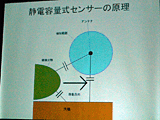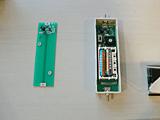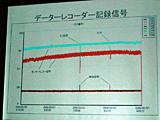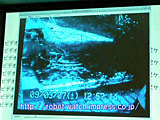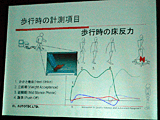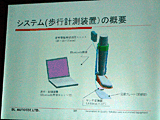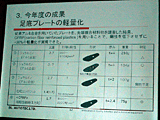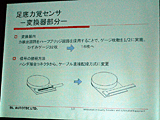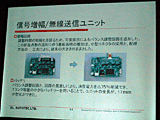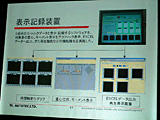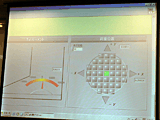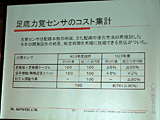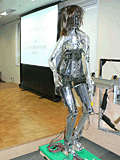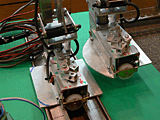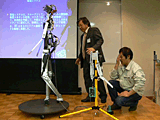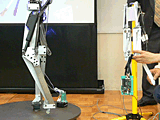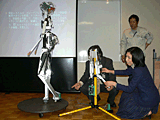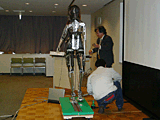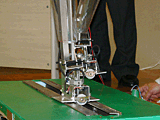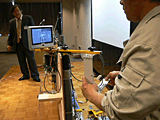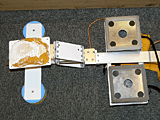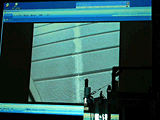|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
神戸ロボット研究所、「kobe Robot Meeting 2009」を開催 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3月17日、神戸市産業振興センターにおいて、「kobe Robot Meeting 2009」が開催された。主催は、財団法人新産業創造研究機構(NIRO)神戸ロボット研究所と神戸市。 神戸市では、平成14年度から「神戸RT(ロボットテクノロジー)構想」を推進し、ものづくり技術の高度化と市内産業の振興に取り組んできた。神戸RT事業開発補助制度は、RTを活用した製品開発及び事業化に取り組む市内中小企業を支援するのを目的としている。本稿では、NIROの取り組みと平成20年度に採択された4件のプロジェクトの進捗報告をレポートする。
● 神戸RT構想及び神戸ロボット研究所(NIRO)の取り組みについて
神戸市には、ロボット開発に必要な要素技術をもつ企業が多数ある。神戸RT構想は、そうした企業の連携を強め技術を進歩させて、ものづくり技術の高度化と子供たちのロボットに対する夢を育み、豊かなまち作りを目指すことを目的としている。 そのため、NIROは神戸RT研究会を作り、企業間の情報交換等を進めてきた。また、国際レスキューシステム研究機構を設立し、大大特(大都市大震災軽減化特別プロジェクト)の終了後も、引き続き防災ロボットの研究開発を続けている。 他にも、神戸市ではポートアイライド地区が医療のスーパー特区となり、医療産業都市構想のもと介護福祉ロボットプロジェクトが進められつつある。 神戸ロボット研究所は、主に1) 活動の中心となるRT研究会の運営、2) 神戸RT事業開発補助事業推進、3) 新技術開発、4) 啓発・人材育成活動を中心に活動を行なっている。
大築氏は、経産省の戦略技術マップを示し、2008年はロボットが本格的普及の前段階になると述べた。今後は、次世代ロボットの安全性確保ガイドラインを制定し、社会的に受け入れられるための体勢を作っていく段階となる。国としてこうした状況を推進していくために技術開発の支援システムがあり、平成21年度からは「生活支援ロボットプロジェクト」が予定されている。これはロボットそのものを作るのではなく、今後ロボットが実際に使われていく上で非常に重視される安全性を確保するための指針を官民一体となり、構築していくプロジェクトである。「NIROもこうしたところに積極的に参画してゆきたい」と語った。 今後の方針として、NIROがこれまで技術開発支援してきたものを、ビジネスとして商品化するところまで支援していくことに力を注いでいきたいという。そして「神戸発のロボットを提案していきたい」と大築氏は強調した。そのために、例えば農業用ロボット分科会、福祉介護ロボット分科会を新設して強力な体勢を取り、産学官だけではなく、ユーザーの意見を取り入れ現実性の高いロボット開発を目指していく。中小企業からニーズが出てきた時に産官学がタイアップしてもの作りをする「ニーズ型」、大学等研究機関から生まれたシーズを元に、新しい製品として作っていく「シーズ型」と、案件に応じた形で産官学連携のもと開発に取り組む体勢を整える方針を打ち出した。
次に、平成20年度神戸RT事業開発補助採択テーマのプロジェクト4件について、各社から進捗報告が行なわれた。 ● フィールド用近接検知センサーの開発と実用化検証
渡辺氏は、自宅の庭に入ってくるノラ猫対策にさまざまな市販グッズを試したが、効果が限定的なため、RTを活用してノラ猫を追い払うシステムを開発したいと神戸氏主催のRTビジネスセミナー等を受講し、開発に着手したそうだ。 まずフィールドで使用可能なセンサーを調査したが、それぞれ検知エリアの限定が困難であったり、太陽光や枯葉の影響があったり、コストの問題があり適さなかったという。そこで、静電容量の変化を検出し、物体の近接を検知するセンサーを開発した。赤外線センサーや画像認識センサーと比較して、環境条件の影響が少ないという特性がある。アンテナの設置が容易であるため、任意の検地範囲にユーザーが簡単に設置できるのが特長だ。 2カ月間にわたってセンサーの長さを変えてテストを実施し、庭に侵入した猫や鳥の検知を確認している。信号が入ってきたときに、10秒前からの画像を記録する装置を作りデータをとった。現段階では、センサーが反応すると音を鳴らすだけなので、今後は検地物を識別し、猫を追い払う装置を他社と連携し開発したいという。 本センサーは、汎用電子部品で構成され部品点数も少なくローコストで実現が見込めるそうだ。消費電力も少なく、単4電池2本で1年ほど連続稼働する。まずは家庭用のノラ猫侵入検知センサーとして、センサー+アラームで5,000円程度で販売を考えているそうだ。フィールドでの実績をあげ、将来的には農業分野で害獣検知センサーにも使用できる汎用RTセンサーを目指す。
● 足底力角センサーを用いた歩行計測装置の開発
同社は、装着型の歩行計測装置を開発した。一般的な歩行では、踵から着床し、つま先に重心が移る。しかし、足の不自由な方の場合は、足裏全体に均等に力がかかる。センサーを用いることで、正しい歩行ができているのか? リハビリや装具の効果が出ているのかを数値で検証可能となる。 従来の歩行計測システムは、床面に埋め込まれた床反力計を用いるため持ち運びができず、被験者が計測のために施設を訪れなければならないという制約があった。また被験者の歩幅に計測装置を合わせる必要があるため、計測準備にも多くの時間が費やされる、パネルが高価なため複数歩数を計測するための設備を用意できない、階段歩行時の計測ができないという問題点もある。しかもコストは、システム全体で1,000万円以上になるという。 そこで同社は、6分力を計測できる力角センサーをユーザー所有の下肢装具の足底に装着し、歩行幅や歩数を意識せずに歩行反力を計測できる装置を開発した。センサーが感知した電気信号は、腰部分に設置した装置によりBluetoothでPCへ送信するため被験者の歩行を妨げないシステムとなっている。このシステムの特徴は、ユーザーの足に直接センサーを取り付けるため、複数歩数の計測が可能であり、さまざまな条件の下で使用できる点にある。 今年度は、足底力角センサーと装具の取り付けインターフェイスを簡素化するとともに、足底プレートにCFRPを採用することで剛性を低下せずに30%軽量化を実現した。また商品化を視野にいれ、足底力覚センサー変換器内の配線を簡略化しコストダウンを可能にした。 PCへ転送されたデータは、専用ツールで6成分の力、トルクデータをグラフィカルに表示できる。被験者の重心位置やモーメントを表示したり、Excelへ出力したり、また再生機能などの機能を強化した。 今後は、臨床歩行分析研究会や使用者の意見を収集し、問題点のさらなる改善を図る。またデータの分析・表示機能について、使用者にとって使いやすいユーザーインターフェイスを研究し、限定販売の可能性を検討していくという。
● 関節駆動型マネキンの脚教示装置と隣接狭隘部点検補修ロボットの開発
同社は、平成19年度兵庫県COEプログラム推進事業により「関節駆動型マネキン」を開発した。従来のマネキンでは表現できない「動いた時の洋服のラインや美しさ」を展示できるのが強みで、大型商業施設のショーウィンドウ等の活用を想定している。 今回開発した直線歩行するマネキンロボットは、足裏に搭載したロック/アンロック機構でレール上を移動する。上半身のモーション作成は、ロボットの腕を直接動かしてダイレクトにモーションを教示することができる。しかし、体重を支えバランスをとっている脚を人が直接動かしてモーションを作ることは無理がある。歩行モーションやモデルのように脚を動かすモーション作成に、シミュレータ等で数値データを作成しするのは容易ではないため、教示装置を開発した。
開発したシステムは、マスター&スレーブ方式を採用し簡単に教示できる。マスターはマネキンの1/2サイズモデルとし、スレーブには既に開発済みの関節駆動型マネキンを使用している。マスター側のセンサー情報を、RS-485シリアル通信でスレーブ側に伝える方式。マスターを動かして思い通りのモーションを作成した後に、データを片足固定の関節駆動型マネキンに移し微調整をすることで、容易に歩行モーションや決めポーズを作成できる。 軽量なマスターを動かすだけでモーションを作成できるため、非力な女性であっても思い通りにマネキンロボットを動かすことが可能となった。
最後に狭接狭隘部分点検補修ロボットを紹介した。商店街などの建物密集地帯は、隣接する建物との間隔が15cm程度しかない場合が多いと井辺氏はいう。こうした狭接狭隘部には人が入れないため、壁面に亀裂等があったとしても点検・補修が困難である。そこで人が入らなくても漏洩部の点検・補修ができるようビルのベランダや屋上から吊り下げて、壁面に吸着固定し作業するロボットを開発した。 このシステムは、上部から吊り下げられ壁に吸着するベース、作業アーム、各種点検部と補修ユニットで構成されている。点検時はビデオカメラを搭載し、壁面の状態をモニタリングしデータを記録する。補修ユニットは、防水保護コート剤のスプレー等を時間をかけて塗布する方式を採用している。 また、棒の先に補修ユニットを接続して、下から壁を補修するユニットも用意した。
■URL 神戸RT構想 http://www.kobe-rt.jp/ 新産業創造研究機構 http://www.niro.or.jp/index.php 国際レスキューシステム研究機構 http://www.rescuesystem.org/tmp/NEW/framepage01.htm ■ 関連記事 ・ 第31回神戸RT研究会「農業用ロボットの開発と生物機能の有効利用」 ~食の安全確保と地域活性化を目指したRT技術の活用(2009/02/16) ・ 神戸空港ターミナルで、男性用トイレ清掃ロボットのデモを公開 ~神戸RT構想、平成19年度神戸ロボット研究開発費補助金採択案件(2008/04/22) ・ 神戸ロボット研究所の活動報告「kobe Robot Meeting 2008」開催(2008/04/08)
( 三月兎 )
- ページの先頭へ-
|