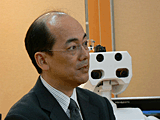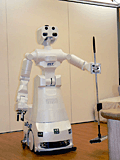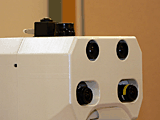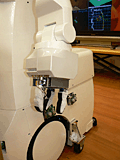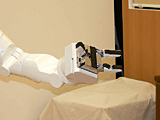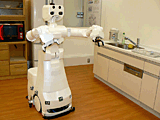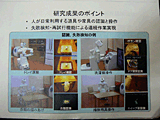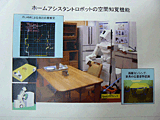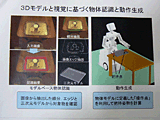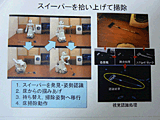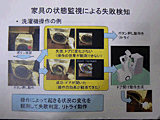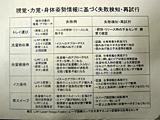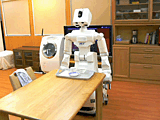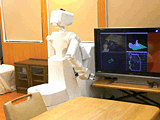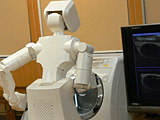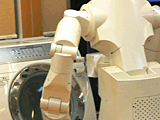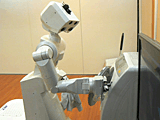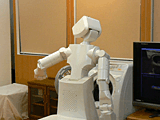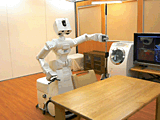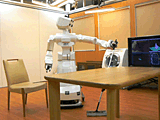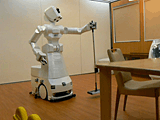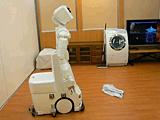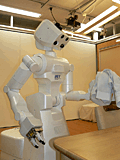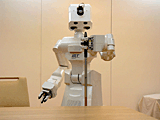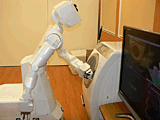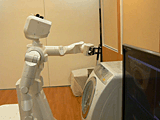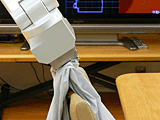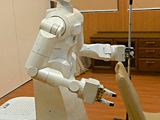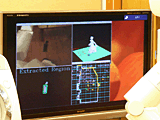|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
東京大学IRT研究機構、ホームアシスタントロボットによる掃除片付け技術を発表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年から東京大学は、トヨタ自動車株式会社、オリンパス株式会社、株式会社セガ、凸版印刷株式会社、株式会社富士通研究所、パナソニック株式会社、三菱重工業株式会社と、「文部科学省が公募した科学技術振興調整費『先端融合領域イノベーション創出拠点の形成』事業」に参画して「少子高齢社会と人を支えるIRT基盤の創出」というプロジェクトテーマで10年~20年先のイノベーションを目指して研究を進めている。今回のロボットはその枠組みのなかで開発されたもの。 ロボットを開発したIRTシステム研究部門部門長の稲葉雅幸氏は、「専用作業を行なう家電と家電の間を運ぶ役割を担わせたい」と語り、今後の展望として車と同じくらいの価格で数個の家事をこなせるロボットを企業と産学共同で開発していきたいと述べた。 東京大学IRT研究機構は今年4月1日に東大総長直轄として誕生した研究組織。ロボティクス(RT)と情報技術(IT)を組み合わせた「IRT」で、少子高齢社会の問題解決を目指している。今回の提案は「社会学と共同しながら科学技術がどういった役割を提案できるのか示せるものだ」と機構長の下山勲氏は語った。「機械でできることにはこのようなことがある、という一例を見せて、今後、議論を重ねていきたい」という。
● アシスタントロボット(家事支援ロボット) 「ホームアシスタントロボット」のハードウェア構成は以下のとおり。ホームアシスタントロボットは車輪移動型で腰軸を持った双腕構成のロボット。サイズは650mm×770×1,550mm(幅×奥行き×高さ)。重量は130kg。自由度は32(首と頭部3、腕7×2、手指2×3×2、腰1、移動部2)。広角ステレオカメラ、望遠ステレオカメラ、超広角カメラ(全方位カメラ)のほか、操作用の6軸力センサー、レーザーレンジファインダー、超音波センサーを備える。動力源はバッテリで稼働時間30分~1時間程度。車輪は駆動輪2のほか補助輪4で合計6個。固有の名前は特にないが、研究者たちの間では「AR(Assistant Robotの頭文字)」と呼ばれているとのこと。ハードウェアの機構に関してはトヨタが製作した。
機能は大きくわけて3つ。1) レーザーレンジファインダーとステレオカメラによる画像データを組み合わせて家具や道具、洗濯物などを認識する環境認識機能、2) 3次元幾何モデルを規範とした行動生成機能、3) 自分の作業が失敗しているか成功しているかを視覚で判断して操作機能と融合させる「失敗検知・動作やり直し機能」である。 ロボットはSLAM(Simultaneous Localization and Mapping)で地図を生成し、自己位置推定を行なっている。道具や家具そのものについては事前に3次元幾何モデルとして定義しておき、どこをどの向きで持てばいいかといった操作点情報も与えておく。ロボットは環境認識機能を使って対象にアプローチしつつ、幾何モデルを規範とした行動生成システムを使って物体に対する操作など自身の動作計画を生成する。アームが自己干渉しないための衝突防止機能、誤差を解消するための操作姿勢再生成機能なども備えている。 稲葉教授によると研究成果のポイントは大きく2つ。1つ目はロボットが環境を認識し、人間が扱う道具を使い、柔軟物を操作する機能の実現。もう1つは、作業を失敗したことに気がついたら、やりなおす認識・動作機能の実現である。特に、変形するため操作が難しい柔軟物の認識と操作、そしてこれまでの成功の記憶に基づいて失敗したことを認識できる点が新しく、家庭内でロボットが使われる上での非常に大きな技術だという。
デモンストレーションでは、1) まずテーブル上のトレイを持ち上げて運搬、シンクに持っていく。2) 椅子に無造作にかけられた柔らかな衣類(シャツ)をハンドで取り、洗濯機のところまで運搬し、ボタンを押して洗濯機のドアをオープン。洗濯機にシャツを入れたあとドアを閉める。3) 最後にスイーパーを取って床掃除を開始。椅子を引いてテーブル下を掃除したあと、両手掃除を行なうという3つの基本家事を実行する様子が示された。 外出時、つまり人がいない状況で、作業を頼まれたロボットが後片付けや掃除を行なうという想定だ。そのためには、失敗してもやりなおす機能が必要になる。洗濯機のボタンを押すときにはをまず広角カメラで洗濯機を発見する。洗濯機のなかでどこにボタンがあるかだいたいの位置情報をロボットは事前に知っており、その知識に基づいてボタンを発見して押す。
デモをよくよく見ると、手先と手首を使った道具の取り回しや、道具を持ったままの上体で椅子を押すときの腕部の使い方、体をそらせるようにして上体でできる仕事を広げた腰軸など、いろいろとよく考えられていることがわかる。指先を使ったトレイの把持など、実際に食器の中身が入っていたりもう少し重かったりしたら違う持ち方が必要だろうなと感じるものもあるが、今後、期待できそうだ。
ロボット独自の通信プロトコルや赤外線通信などを用いて家電と通信するのではなく、敢えてボタンを押したりしている理由は、ロボットが世の中一般にある道具を使うためにはどのようにプログラムすればいいか研究していくためだという。下山教授は、2年間研究して分かったことの1つとして、ロボットが実作業するためには人やネットワークとの協調が非常に重要だということだと述べた。ロボットは、仕事に応じて適宜、さまざまな必要な手段を取っていくことになるだろう。 なおIRT研究機構では今回の「ホームアシスタントロボット」を含めて4種のロボットを開発中。残り3種はパーソナルモビリティロボット(1人乗りの移動ロボット)、キッチンで働くロボット、そして人に密着するロボットで、12月中旬までに順次発表の予定だという。今回のロボットも、これまでの稲葉研究室での研究成果を合わせてさらに発展させていく。 東京大学IRT研究機構は、10年先、20年先のイノベーションを目標としている。下山氏は「20年あればだいぶ変わる。変えてみせます」と本誌に語った。 ■URL IRT研究機構 少子高齢社会と人を支えるIRT基盤の創出 http://www.irt.i.u-tokyo.ac.jp/ ■ 関連記事 ・ ロボットを実用化していくための課題 ~「ロボジャパンセミナー」3日目(2008/10/16) ・ 東京大学「IRT研究機構発足記念シンポジウム」レポート ~少子高齢化社会を救うロボット技術(2008/03/31) ・ アキバテクノクラブ「レビュー&プロモーション」ロボット関連セミナーレポート(2007/03/09) ・ 東大、人型ロボットをテーマとした第一回工学体験ラボを開催(2006/07/21)
( 森山和道 )
- ページの先頭へ-
|