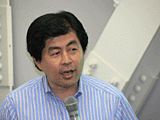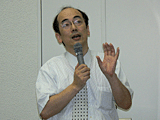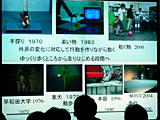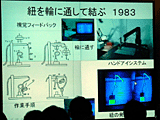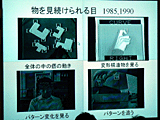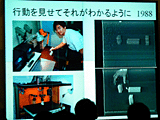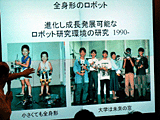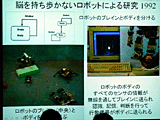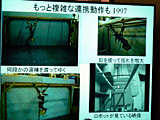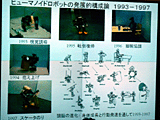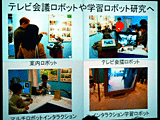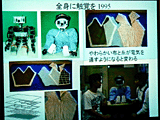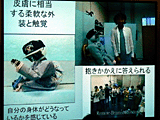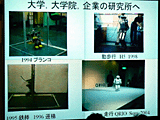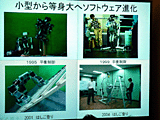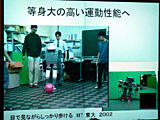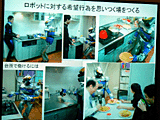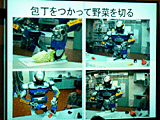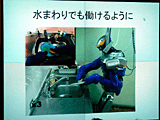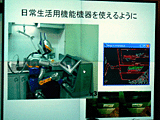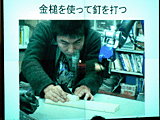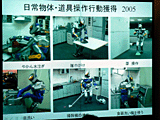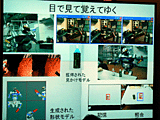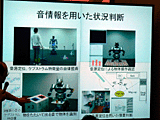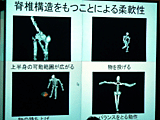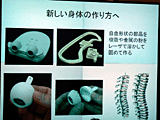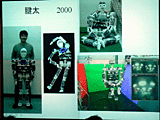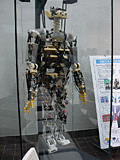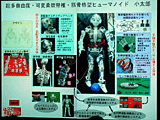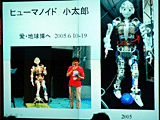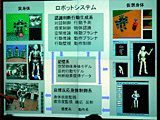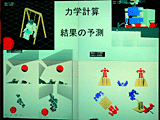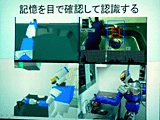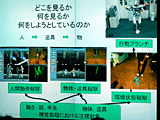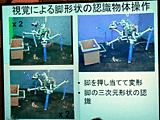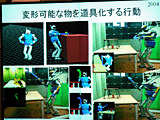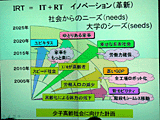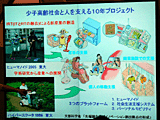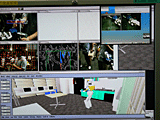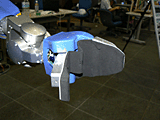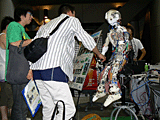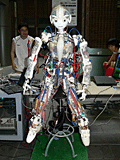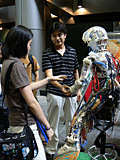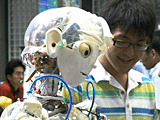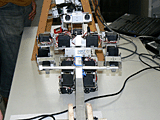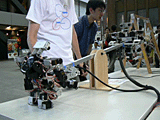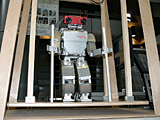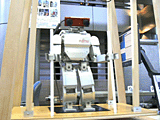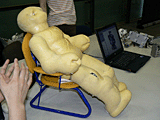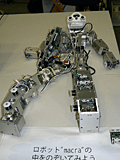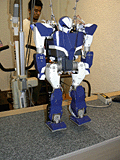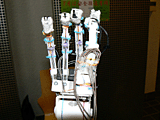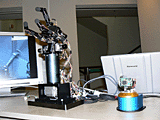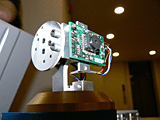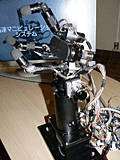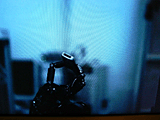|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
東大、人型ロボットをテーマとした第一回工学体験ラボを開催 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
~工学部広報センター「T-Lounge」新設
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学体験ラボの対象は高校生と予備校生で、講師は東京大学工学部機械情報工学科 稲葉雅幸教授。当日は定員を上回る47名が参加し、稲葉教授の講演とロボットのデモンストレーションを、熱心に聴講していた。 T-Lounge開設と工学体験ラボについて、簡単にレポートする。 ● T-Loungeとは 「T-Lounge」は「東京大学工学部でどのような研究がなされているのか、一般の方々向けに情報を発信し工学の魅力を伝えるため」に設置された空間。現在は稲葉研究室の脊椎を持つ全身腱駆動型ヒューマノイドロボット「腱次」と、工学部の研究成果がビデオで流される100インチモニターが設置されているだけだが、今後はさらに常設展示を増やす予定。照明も含めて演出を凝らすほか、一般と研究者がコミュニケーションする場として機能するように椅子やテーブルも設置し、ラウンジ機能も持たせていくという。なおT-Loungeの隣にはスターバックスがテナントとして入居しており、コーヒー片手に工学成果を眺めることができるようになっている。 「T-Lounge」担当の東京大学大学院工学系研究科・工学部 広報室 特任助手の宮島章子氏によれば、各展示も設置しっぱなしではなく、入れ替えが容易な形式とし、生きたコミュニケーション&イベントスペースとして機能することを目指すという。
● 工学体験ラボ 工学体験ラボは「日本の将来を担う若い世代に広く工学の魅力を伝えるために、工学部で研究されている最新の研究を、参加者が実際に体験できるかたちで紹介し、その面白さを肌で感じてもらえる」ことを目指した企画。研究者が自ら、大学入学前の若い世代に向けて講演することで研究への実感を持ってもらうことを目指している。工学部広報室室長を務める東京大学大学院工学系研究科 工学部社会基盤専攻 社会基盤学科教授の堀井秀之氏によると、第一回のテーマに「ロボット」を選んだ理由は「ロボットは高校生にも研究の魅力が分かりやすく、実感を持ちやすい。人気も高いから」とのことだった。 工学体験ラボは2カ月に1回程度のペースで開催する予定。対象は高校生。第2回は「航空宇宙」をテーマに現在計画中だが、詳細は東京大学工学部のホームページに掲載される予定とのことだ。
● 第一回工学体験ラボ(T-Lab) 当日は上述のように第一回工学体験ラボ(T-Lab)「ヒューマノイドロボットの成長 ~しなやかな動作で道具を使えるロボットへ~」が開催された。講師は東京大学工学部機械情報工学科 稲葉雅幸教授。受講者は工学部入学を志している高校生と予備校生たちだ。
始めに1時間弱ほどの講義が行なわれたあと場所を移動し、実際に稲葉研究室で研究開発されているロボットのデモンストレーションが行なわれた。稲葉教授は知能ロボット研究の歴史と今後の方向性を、自身の研究室の発展と合わせて多くのビデオとスライドを使って解説した。 外界の変化に対応して行動を作り出す知能ロボットの研究が本格的に始まったのは'70年代である。ロボティクスとは「感覚と行動の知的な相互作用の研究」であるという。ロボットは要素機能の統合システムであり、ロボットを作るためにはさまざまなセンシング技術や行動計画などの知能系、そして機械・電気などの能力が必要であり、ロボットは「ものづくり工学の代表選手」と言えるという。 まず稲葉教授は、自らが学生の頃に行なったハンドアイシステムを使ったビジョンと連携させたハンドの制御研究や、同じく現在は知能情報システム研究室教授となっている國吉康夫氏らが学生時代に行った、ロボットビジョンによる人間が行う作業の実時間視覚認識と教示の研究などを使って、注視点制御や硬いモノを柔らかく扱う研究などを紹介し、ロボット用の視覚システムとハンドの発展を追った。
その後、'90年代になると同研究室では小型のロボットを使った研究を行なうようになった。小さいが全身を持っているロボットを使った、ダイナミクスの研究である。ただし当時は、計算機は重たくて搭載が難しかったので、リモートブレイン方式とした。感覚に応じた反応をロボットに行なわせるのだが、そのための計算は、ロボットの感覚情報を外部の計算機に送って、計算させるのだ。 '93年~'97年くらいの間の研究では、ブランコや転倒復帰、ビジョンと協調した運梯動作などができるようになった。2000年くらいになると、ロボットをモジュール化して、作り替えが簡単になるようにしていたという。現時点ではコンピュータは小型化している。
稲葉教授は「大学では、ないものは自分たちで作らないといけない。だけど、それだけではなくて、作るための環境をどうやって作るかということが非常に大事だ」と強調し、'95年以降に行なわれたロボットに触覚を持たせるために導電性の布を使って服を作った研究を紹介した。 当時この研究を行なったときに4年生だった星野由紀子氏は博士号を取得後、ソニーで小型二足歩行ロボット「QRIO」の研究開発に携わった。 このように、今回の講演では、ロールモデル(将来像を描く上で参考になる目標のこと)を高校生に示しながら行なわれた。
その後、同研究室ではHシリーズなど、等身大ロボットも研究開発するようになり、分離していたブレインの一部がロボット本体に内蔵されるようになっていった。等身大ロボットになっても基本的には小型ロボットと共通化したソフトウェアを使うことで、例えば梯子を登らせるような複雑な動作も、ソフトウェアを継承して行なわせることができたという。このようなソフトウェアを含めた環境作りが、ものを作り続けるためには非常に重要だと強調した。 また、井上・稲葉研究室出身で、現在は産総研に在籍する金広文男氏の研究――HRP-2を使った起きあがり動作の実現などを例に挙げ、「皆さんも何年か後に研究室に入って博士号をとって、企業や研究所に入ってロボットを作る。そういうふうになるといいと思いますね」と語り、研究開発用プラットフォームヒューマノイド「HRP-2」の意義について述べた。 プラットフォームの登場で、体を作る研究だけではなく、使い方や知能の研究を行なうことができるようになる。稲葉教授は「これはとっても画期的なことです。大学に入ったら皆さんもヒューマノイドロボットが使えます。楽しみにして大学に入ってください」と語り、キッチンで道具を使うヒューマノイドの研究の様子をビデオとスライドで紹介した。 稲葉研究室では、包丁を使って野菜を切ったり、金槌で釘を打ったり、防水手袋を着けたHRP-2に食器を洗わせたり、食器を食器洗い機に入れさせるといった動作を学生達が実現している。道具にはさまざまな機能があるが、その機能や力の関係を把握させて操作させるのである。 たとえば、ほうきでゴミを掃くときには、どれがゴミであるかはもちろん、ゴミを道具で掃くと動く、といった環境変化についてもロボットは知っていなければならない。また、アルミ缶とスチール缶は叩くと音が違うことから区別が付く。そのような環境の知識を、ロボット自らが視覚や聴覚センサーなどを使って把握していく研究も稲葉研究室では行なっている。
これまでのロボットは大きなものも小さなものも身体が硬かった。稲葉研では、人のように柔軟な動作が可能な、新しい構造のロボットも研究している。それが脊椎を持つ全身腱駆動型ヒューマノイドロボット「腱太」、「腱次」、そして愛・地球博(愛知万博)のプロトタイプロボット展にも出展された「小太郎」だ。 これまでの機械加工で作られたロボットとは違って、レーザーで粉を焼結させて作っていく、いわゆるラピッドプロトタイピングの手法で作られており、脊椎や鎖骨、肩胛骨などを持つ。関節と関節をまたいだ形でアクチュエータが取り付けられている。 素人目にも非常に複雑な機構を持っていることが分かるロボットだが、故障時に修理しやすいようにメンテナンス性も考えられて構成されているという。また関節は球関節が用いられており、携帯電話に用いられている小型カメラで球の向きを把握している。現在は110程度の筋肉ユニットが用いられているという。
ロボットを動かすためには知能ソフトウェアが必要だが、同研究室では実際の環境でリアルタイムで動作するロボットと、環境変化を予想し動作計画を行なうための仮想モデル、どちらを動かす上でも、また大きさ、モーター数、センサー数や種類などが違った別のロボットでも、同じソフトウェアが使えるようにインターフェイスを共通化している。でないと統一的な作り方ができないからだ。その基盤が重要だと稲葉教授は繰り返し強調した。 今後は、さらに模倣機能を持たせていく予定だ。たとえば人間の子どもが母親の動きを見て、ほうきで掃く動作を学ぶためには、道具の動きだけではなく、道具が動かしているものがどうなるのか、そもそもそれは何のために行なわれているのか、その目的も把握してないといけない。「ロボットに必要な要素機能はまだまだ足りない。だけれども、新しいロボットを作りながら突き詰めていく」と稲葉教授は語った。 稲葉研究室では継承可能な形で発展の仕方を考えながらロボットをつくっているこのやり方を「発展的構成論」と呼んでいる。プラットフォームを作っておけば、体をどう作るかという研究だけではなく、どう活かしていくかという使い方の研究も可能だし、体だけではなく道具や知能の研究もできる。 さらに現在は、低融点金属を使って自分自身の身体を目的に応じて変形させたり、与えられた道具を目的に合うようにビジョンと力センサーを使って、適切に変形させたあと、それを使うといった研究も行なっているという。
最後に稲葉教授は、「このように、大学は、何かをやりたいという思いを持った人が集まってきています。我々はこのようなロボットを用意しておいて、皆さんを受け止められるように準備して待ってます」と語り、平成18年度科学技術振興調整費「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成」において採択された「少子高齢社会と人を支えるIRT基盤の創出(略称:東京大学IRT拠点)」について触れた。 「皆さんが大学院に入る頃には、このプロジェクトが進んでいる。我々のグループはロボットをこれからの少子高齢社会で役立てたいと思っているし、ロボットをいろんなところに活用していきたい。是非皆さん一緒にやりましょう」と講演を締めくくった。
講義のあとは工学部新2号館に移動。稲葉研究室のロボットを実際に見学した。
この後、再び11号館に戻り、他の研究室で研究開発されているロボットのデモンストレーション見学が行なわれた。 展示されたロボットは、中村研究室の小型ヒューマノイド「UT-μ2」、横井研究室の筋電ロボットハンド、石川・並木研究室のビジョンチップと高速ロボットハンドシステムの3種類だ。
体験ラボ聴講者たちに感想を聞いてみたところ、「稲葉研究室の研究はインターネットで知っていたし写真も見ていた。しかし実際に教授の話を聞き、実物のロボットを見せてもらうと、想像以上に進んでいた。ロボットの研究をしたいと思うようになった」、「東大に入りたいという気持ちに実感が出てきた」、「すごく楽しかったし面白かった」など、工学体験ラボというイベントそのものに高い評価を与える参加者が多く、大いに充実した時間を過ごしたようだった。 もともとモチベーションが非常に高い参加者が多かったこともあるのだろうが、実際に研究者の話を直接聞き、研究成果物であるロボットに触れることは、高校生・予備校生たちにとっては目標を発見する場所であると同時に再確認する場ともなったようだ。 上述のように、これからも工学体験ラボは企画されているので、将来、工学分野に進学を検討している人は、参加してみるといいだろう。 ■URL 東京大学 http://www.t.u-tokyo.ac.jp/ 東京大学工学部 http://www.t.u-tokyo.ac.jp/epage/ 工学体験ラボ(T-Lab) http://www.t.u-tokyo.ac.jp/epage/public/info/archives/2006/0614.html
( 森山和道 )
- ページの先頭へ-
|