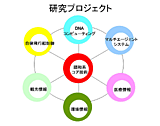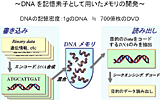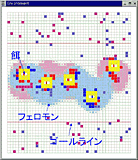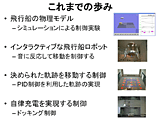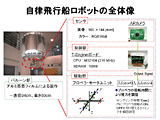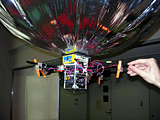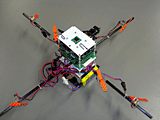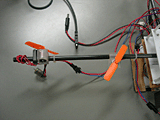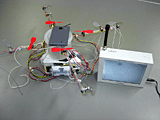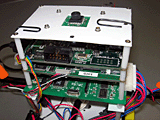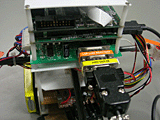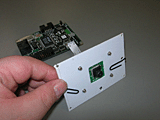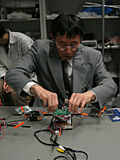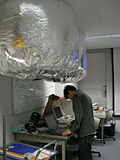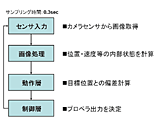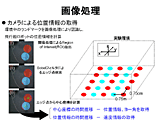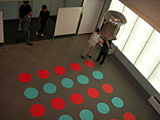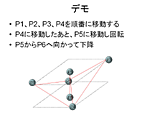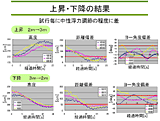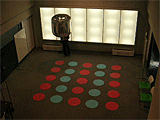|
記事検索 |
バックナンバー |
【 2009/04/17 】 |
||
| ||
【 2009/04/15 】 |
||
| ||
【 2009/04/09 】 |
||
| ||
【 2009/04/06 】 |
||
| ||
【 2009/04/03 】 |
||
| ||
【 2009/03/27 】 |
||
| ||
【 2009/03/24 】 |
||
| ||
【 2009/03/18 】 |
||
| ||
【 2009/03/11 】 |
||
| ||
【 2009/03/06 】 |
||
| ||
【 2009/03/04 】 |
||
| ||
【 2009/02/27 】 |
||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
調和系工学研究の一環として生まれた自律飛行船ロボット |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
~北海道大学大学院 調和系工学研究室訪問記
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reported by
井上猛雄
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そのような中で、空中に浮遊するエンタテインメントロボットという一風変わったジャンルの研究が行なわれている。北海道大学大学院の大内東教授(情報科学研究科複合情報学専攻 複雑系工学講座 調和系工学研究室)のもと、助手の川村秀憲氏らを中心に進められている自律飛行船ロボットの研究がそれである。 空を飛ぶロボットには、その浮上方式によっていくつかのタイプに分けられる。まず、プロペラ型ロボット。これはプロペラの揚力を利用するもので、先ごろ開催されたサッポロバレーE.T.プロジェクトで紹介したようなロボットだ。 次に、ヘリウムなど空気より軽い物質を充填して浮上する飛行船ロボットが挙げられる。また、電磁気力や静電気力を使って浮上するロボットも研究が進んでいる。このレポートでは、北海道大学のユニークな自律飛行船ロボットについて紹介しよう。 同研究室では、自律飛行船ロボットのほか、DNAコンピューティング、マルチエージェントシステム、観光情報、医療情報など、幅広い研究が行なわれている。一見すると、「えっ、こんな研究までも?」と驚くかもしれないが、今回の飛行船ロボットを含め、すべての研究が「調和系工学」というキーワードでつながっている。 たとえばDNAコンピューティングの分野では、生のDNAを抽出して工学的な応用を試みている。DNAをモノとして扱うという発想がユニークだが、これも化学反応のバランスという観点から調和系に入るそうだ。 この研究は、ATGCという4種類の塩基配列を4進数の並びとして考え、情報工学的にデータの表現方法として利用しようというもの。DNAの記憶密度は1gで700億枚のDVD容量に相当する。情報を書き込むためにDNA合成を行ない、それを溶液に混合するとDNAインクとなる。目的のデータを必要なときに取り出して、印鑑や個人認証などに活用できるという。
周囲4近傍を知覚できるアリを多数配置し、左右前後、待機、フェロモン(誘引物質)を発する、餌を引くといった行動条件を与えて、自分のたちの陣地にいかに多くの餌を持ち帰るかという振る舞いを研究していたそうだ。 前ふりが長くなったが、このようなユニークな調和系工学の一環として研究されているのが、この自律飛行船ロボットなのだ。 ● 生みの苦しみを味わって実現した自律飛行船ロボットの位置制御 さて、それでは話を戻して、今回のメインテーマである自律飛行船ロボットについて紹介しよう。同研究室で飛行船ロボットの研究が始まったのは10年ほど前から。当初は、飛行船に印をつけて、外部CCDカメラから位置情報を取り込み、ラジコン用のプロポ(送信機)で動作させていたが、2次元座標上での実験であり、なかなかうまくいかなかったそうだ。いまのような完全自律型の飛行船ロボットが確立されたのは3年前からで、現在4号機を開発中だという。 飛行船ロボットのメリットは、空気より軽いガス「LTA」(Lighter Than Air)を利用して浮遊するため、ヘリコプターなどと比べて推力が少なくて済むこと、移動時にはプロペラを利用することになるが、低自由度(5自由度)で3次元空間を移動できることなどが挙げられる。その一方で、飛行船ロボットは、外乱の影響を受けやすくて制御が難しい、出力に対して、いったん速度がつくとコントロールが困難といった問題もある。 つまり、ある位置でピタリと飛行船を停止させたり、安定して静止させるためには、慣性の影響や空気抵抗などを予測して、それに適応する制御が必要となるのだ。このように飛行船ロボットの制御はとても難しい側面もあるのだが、「研究対象としての難易度があるため、逆に調和系工学の研究として面白い」と川村氏はいう。
インタラクティブな飛行船ロボットは、音に反応して、移動や回転ができる。拍手などの単発衝撃音を小型ワイヤレスマイクで拾い、空中で回転したり、上下に移動したりといった動作が可能だ。動作トリガーとして単発衝撃音を利用する理由は、急激な音強度の変化があるため、閾値以上の音強度を検出しやすい点にある。 このロボットの動作については、意外性のある動作をさせるために、ソフトウェアによって工夫を凝らしている。たとえば、拍手すると決まった動作を繰り返すのではなく、確率的な動作遷移モデルを実装し、「たとえば機嫌がよければ反応したり、機嫌が悪いときには遠ざかってしまうというように、人とのインタラクションを重視した」(北海道大学 大学院情報科学研究科 助教授 山本雅人氏)という。 そして、もっとも大変だったのが、やはり次フェーズの「決められた軌跡を移動する制御」だったそうだ。ここで川村氏は飛行船ロボットの制御の難しさを痛感したという。「最初のころは制御することがとても難しく、エアコンなどから風が少し吹くだけでも不安定になったりしました。そのため、誰もいない真夜中になってから夜な夜な実験を繰り返したりして、とても苦労しました」(川村氏) いまでこそ、うまく位置の制御ができるようになったものの、その当時は飛行船ロボットの研究はほとんんど例がなく(現在でもあまりないという)、「生みの苦しみ」を味わったという。制御に失敗したときには、飛行船ロボットが天井まで上ってしまい取れなくなってしまった。そのためガムテープ付きのレスキュー風船をつくって、飛行船ロボットを救出したというエピソードもあるくらいだ。 さまざまな実験を繰り返して、分かったことは、大きさと重さが制御性能に大きく効いてくることだった。「始めは大きなバルーンで実験していたが、バルーンを軽量化して慣性の影響を小さくすることが成功のポイントになった」(川村氏)という。 また移動制御も、目標となる位置から制御するのではなく、速度によってコントロールするほうがよいことが分かったそうだ。現在までの研究では、バルーンを決められたランドマークに対して移動し、そこに充電器が置いてあると想定して、下降させるところまで実現できるようになった。 ● 自律飛行船ロボットの構成とデモンストレーション では具体的に自律飛行船ロボットの構成を見ていこう。【図4】にハードウェアの構成を示す。ヘリウムが充填されたバルーン本体、ロボットの視覚となる「ARカメラ」、駆動源となるプロペラ型のDCモータユニット、画像処理や駆動をコントロールする制御ユニットなどで構成されている。【写真2】のように、バルーン下部には駆動ユニットと制御ユニットが取り付けられている。駆動ユニット【写真3】では、垂直に交差するカーボンファイバのパイプに、上下方向を制御するプロペラ×2基と、方向を制御するプロペラ×4基が搭載されている。以前の駆動用ユニット【写真5】では、プロペラ×8基が用いられていた。またカメラの映像を無線LANで飛ばしていたという。
制御ユニットは【写真6】、【写真7】、プロセッサにM32014(216MHz)を搭載した「μT-Engine仕様ボード」や、プロペラを駆動させるドライブボードなどを搭載。「T-Engine」は、トロンプロジェクトがユビキタス環境を目指して構築したプラットフォームだ。 標準リアルタイムOS「T-Kernel」を使って、組込みソフトウェアを効率よく開発できる。対象となる製品に応じて、標準/μ(マイクロ)/n(ナノ)/p(ピコ)の4種類がある。μT-Engineは家電機器向けとなるものだ。このμT-Engine仕様ボードには、人工網膜カメラも付属している。このカメラで位置情報を検出する。
電源はリチウムポリマー(7.2V)を採用し、レギュレータで5Vにして、コントロールボードとモータドライバに供給している。 次にバルーン本体だが、これはすべて手作りだという。バルーンにヘリウムを充填するので、ガスが漏れないように材質にはアルミ蒸着を施した強化フィルムが使われている。これは某メーカーのお菓子を入れる袋に用いられているものを特別に譲ってもらったそうだ。
飛行船ロボットは、以上のようなハードウェアで構成されているが、制御系の内部処理の流れについては【図5】のようになっている。まず、床にある格子状(5×5)のランドマークをカメラで検出し、画像処理を行なう。
ランドマークは交互に色が異なるように配置されており、もし画像を見失うようなことがあっても、位置がわかるようになっている。ここで位置や速度などの状態を計算し、次に目標位置となる偏差を求める。そして移動に必要なプロペラ出力を決定するという流れになる。この一連の処理は0.3秒ほどかかるが、そのほとんどは画像処理に要しているという。 画像処理については、2つ以上の異なるカラーのランドマークを関心領域(ROI:Region Of Interest)として抽出し、そのエッジを取って中心点を求めている。そして目標の位置に対してどれぐらいズレているのかを確認しながら、設定範囲内に収まるように制御していく。また高さの制御(高さ方向)では、円の大きさを検出して判断する。 プロペラのモータ出力についてはPWM(Pulse Width Modulation)をベースに制御をしている。ただし、プロペラの出力特性は、平均電圧を上げてもリニアリティが保証されるわけではないので、その特性を調べて、データテーブルのパラメータからプロペラの回転数(10段階)を決定しているという。このような細やかな制御を繰り返し、慣性や空気抵抗などのファクターを考慮しながら、やっと目標位置に到達できるのだ。 今回の取材では、実際にこの自律飛行船ロボットの動作をデモンストレーションしていただいた。このデモでは【図7】のように自律飛行船ロボットを目標地点に移動したあと、ロボット本体を回転し、最後に下降するまでの一連の動作(ドッキング)が再現された。移動速度は平均で15cm/sぐらいと比較的ゆっくりした動作だったが、確実に目標地点まで到達し、うまく制御できていることがよくわかった。
「3次元空間でロボットを協調行動をさせる研究はまだ未開拓の分野です。調和系工学で培った技術を利用すれば、このような研究もできるでしょう。赤外線センサで人を検出したら、追従するといった実験なども考えています」(川村氏) また実用的な分野としては、企業内での無人監視や、バルーンにモップをつけた天井掃除ロボットとしての利用もある。
災害時の偵察・監視などの用途で屋外に出す場合には、目印となるランドマークは利用できなくなるが、GPSを利用して位置情報を拾ってくることも可能だ。位置情報がわかれば、基本的な技術は現在の研究を転用できるという。 3次元レベルでのロボット制御はまだ緒に付いたばかりと言えそうだが、実用レベルにまで研究が進めば、我々の手の届かない範囲まで活動空間を広げてくれる、さまざまな事例が登場することになるだろう。 ■URL 北海道大学 http://www.hokudai.ac.jp/ 調和系工学研究室 http://harmo.complex.eng.hokudai.ac.jp/ 2006/10/23 16:28 - ページの先頭へ-
|