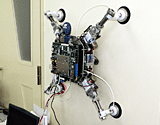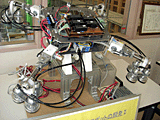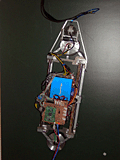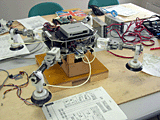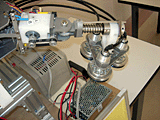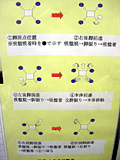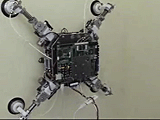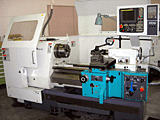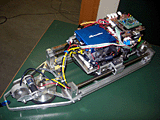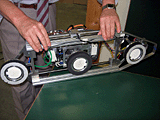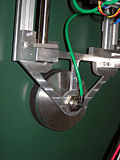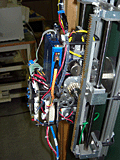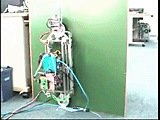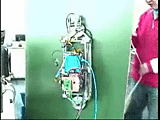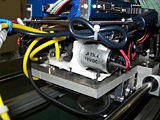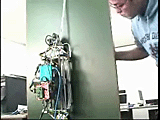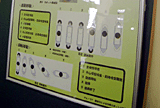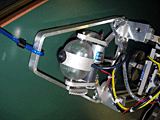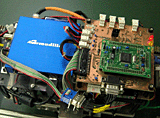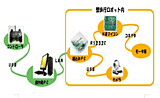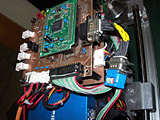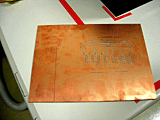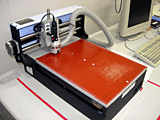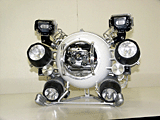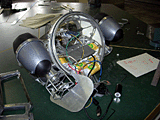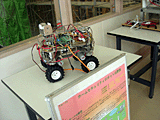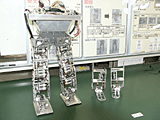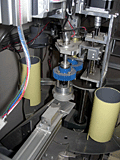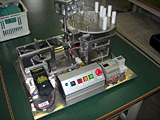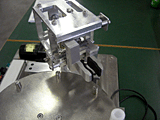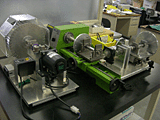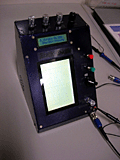|
記事検索 |
バックナンバー |
【 2009/04/17 】 |
||
| ||
【 2009/04/15 】 |
||
| ||
【 2009/04/09 】 |
||
| ||
【 2009/04/06 】 |
||
| ||
【 2009/04/03 】 |
||
| ||
【 2009/03/27 】 |
||
| ||
【 2009/03/24 】 |
||
| ||
【 2009/03/18 】 |
||
| ||
【 2009/03/11 】 |
||
| ||
【 2009/03/06 】 |
||
| ||
【 2009/03/04 】 |
||
| ||
【 2009/02/27 】 |
||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
壁面歩行ロボットで実践的な技術を学ぶ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
~北海道職業能力開発大学校訪問記
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reported by
井上猛雄
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● ワーキンググループ方式による教育訓練システムの成果
同校は、実践的な「ものづくり」の専門知識から、企画・開発能力までを習得できる新しい教育システムを導入し、生産技術管理分野におけるリーダー的な人材の育成に力を注いでいる。専門課程では機械、電子・電気、情報、居住システム系の5学科があり、2年間をかけて専門知識を学び、さらに総合的な知識を得たい場合には、2年制の応用過程へ進めるようになっている。 同校の応用過程では、生産現場を教育の場に置き換えた教育訓練システムとして「ワーキンググループ方式」を取り入れている。これは、生産現場に密着した製品の企画開発から製作までを1年かけて実習する学習方式。いわば一般大学の「卒業研究」にあたるものだ。 ただし、他のそれと大きく異なる点は、応用過程の生産システム技術系3学科(生産機械・生産電子・生産情報技術)を横断したグループ編成にすることで、各学科の専門知識を十分に発揮できるような体制づくりをしていることだ。ものづくりという共通課題を通じ、実際の現場を想定した実学を融合させながら、地域産業に密着した優秀な技術者を輩出している。 この壁面歩行ロボットも、ワーキンググループ方式による教育訓練システムの成果の1つだ。壁面歩行ロボットというテーマを開発課題として取り上げてから今年で3年になる。当初、学生から室内掃除ロボットをテーマにした企画の提案があった。中田氏は「ロボットは人間にできないことをさせるための機械」だと考えていた。そこで、単なる室内掃除ロボットではなく、壁や天井など人の手の届かないところで作業できるロボットにテーマを絞って指導したという。 ● ユニークな4脚機構を採用した壁面歩行ロボットを開発! さて、この壁面歩行ロボットの概要だが、現在4号機を開発中とのこと。1号機と2号機は4脚歩行タイプで、3号機は歩行原理を大幅に改良したモデルとして進化を遂げた。
それでは、まず4脚タイプの壁面歩行ロボット(1号機と2号機)から見てみよう。1号機は機構部・制御・通信部などで構成されている。機構部を生産機械学科、制御部(回路設計・製作)を生産電子学科、通信部(通信と全体制御)を生産情報学科の学生が分担し、それぞれの責任範囲を明確にしたという。 壁面歩行ということもあって、機構部はユニークな構造だ。4つの脚に真空ポンプによる吸盤が装備され、これらが壁に吸い付きながら歩行できるようになっている。歩行動作は下記のとおり。 まず原点位置から右後脚を回転させる。次に同様にして左後脚を回転。ここで4つの脚を同時に回転させながら胴体を進行方向へ進める。この際、脚はバネで収縮するようになっている。胴体が進んだら、右と左の前脚をそれぞれ回転させ、脚の位置をデフォルトに戻す、というしくみである。 脚を動かす場合には、まず吸盤部の真空ポンプの電磁弁がオンオフし、吸着状態を圧力線センサで確認しながら動作させるため、安全で着実な歩行が可能だ。吸着力は1脚あたり20Nに想定して設計されている。
なお、2号機はコンクリート壁で歩行するために、1脚につき3個ずつ(合計12個)の吸盤を装備できるように設計したという。ただし、自重が想定よりも大きくなってしまい、あまりうまく歩行できなかったそうだ。 前述のように歩行動作をするために脚部が回転するようになっているが、この機構はウォームギアとウォームホイールの組み合わせで実現した。必要なトルクを得るため、またセルフロック機構を備えるためだという。脚の動力は、モータからタイミングベルトを使って伝達させ、180度まで旋回できるように設計されている。 一方、胴体前進時に、脚を吸盤方向にスライドさせる(収縮させる)機構では、スムーズにスライド運動ができるようにリニアブッシュを利用している。駆動モータはギヤドDCモータを利用しているが、回転(位置検出)をするためにエンコーダが取り付けられている。エンコーダから回転に必要なパルスを検出し、モータを動かしている。市販品のメカパーツ以外は、学内の機械工作室で学生が製作しているそうだ。
1号機の制御部は、ロボット脚部を動作させるDCモータや吸着盤電磁弁の開閉などを担当する駆動ボードと、ロボット全体のコントロールをする制御ボードで構成されている。 駆動ボードにはワンチップマイコン「PIC16F877」(20MHz)×2を搭載。操作データについては、外部PCからのコマンドを無線LANで送信するかたちだ。全体を統括する制御ボードにはサーバー機能があり、無線LANからのコマンドを受け、PICマイコン側にデータを送る。PICマイコンはコマンドに対応するように吸盤を開放し、脚を上げ、回転させ、また壁面に吸着するという一連の動作を行なう。また、制御ボードには固定USBカメラが接続されており、壁面の状況を観察することが可能だ。 操作アプリケーションはJava(アプレット)で開発しており、外部PCのWebブラウザから上下左右に動作させるボタンをクリックするだけでよい。前述のカメラからの映像も、このアプリケーションで観ることができる。 この1号機は完成度の高さが評価され、平成15年度の北海道ブロックポリテクビジョンにおいて、応用過程の開発・製造部門最優秀賞に選出されたという。 ● 大幅に歩行機構を改良した、最新の壁面歩行ロボットとは? 最新の3号機は、スムーズな動きと歩行スピードのアップを狙って、従来の機構を大幅に改良したもの。4脚歩行から、直線状に並んだ3個の吸盤が壁に吸着しながら前進する構造になっている。そのぶん機構もシンプルになり、主要メカは外部フレームと、内部の稼働機構部で構成されている。外部フレームの両端には1個ずつ吸盤があり、稼働部の中央にも1個吸盤が付いている。1号機と比べて吸盤の数が少ないため、吸着力も123Nと強力なものを採用している。また、左右のリニアガイドを備え、稼働機構部が滑るようになっている。 歩行動作のシーケンスは、まず稼働部の吸盤が開放され、駆動モータとラックギアにより稼働部がフレームのリニアガイドに沿って上昇するしくみだ。フレーム部の端にはリミットスイッチが付いており、これがオンになると稼働部が停止し、吸盤が壁面に付く。 次にフレーム部の両端の吸盤が開放され、同様に駆動モータとラックギアにより、フレーム部が移動し、リミットスイッチがオンになると停止。ここで再び吸盤が壁面に付く。この一連の動作を繰り返すことで前進歩行を可能にしている。
方向の変更については、フレーム部の両端にある吸盤を開放し、稼働部の吸盤を中心に回転させることで実現している。
また、壁面の状態を調査したり監視するカメラは、1号機では固定式であった。3号機ではカメラ部を可動式(回転角90度)になるように機構を改良し、映像もほぼリアルタイムで外部PCから確認できるようになったという。
次にロボットの制御に関してだが、駆動ボードやコントロールボードなど、ロボットのコントロールを司る中枢部は稼働部に搭載されている。
3号機ではロボットのコントロールは有線LANで行なわれている。駆動モータやセンシングのコントロールにはワンチップマイコン「AKI-H8/3048F」が利用されており、全体の制御には組込み専用ユニット「Armadillo」を採用。このユニットのボードは、ARM系のCPUを搭載しており、OSはLinuxでサーバー機能を備えている。ロボットやカメラの操作は、新しく開発したアプリケーションによって、外部PCから行なわれる。
アプリケーションは、操作サブシステム(ロボットの操作)、カメラ画像表示サブシステム(映像のリアルタイム表示)、通信サブシステム(データの送受信)、制御サブシステム(ロボットの動作制御)から成る。ロボットを動作させるためには、アプリケーションから「Armadillo」にコマンドを送り、それをH8マイコンが受け、コマンドに対応する動作を選択することで、それぞれのモータを駆動したり、真空ポンプの電磁弁を開閉したり、センサなどの情報を取得するかたちだ。 制御用の電子基板は、生産電子システム技術化にある電子回路基板自動加工機でつくられた。この加工機は多品種少量に対応している。一般的なプリント基板ではなく、銅版の表面を削ってプロトタイプの回路基板を製作するマシンだという。このように専門的な知識をもつ、異なる学科の学生たちがミーティングをしながら協力しあって、1つのロボットをつくりあげていくのだ。
この壁面歩行ロボット3号機は、従来のものと比べて、動作やスピード面などで大幅に進化を遂げた。とはいえ、まだ課題もいくつか残っているという。 たとえば、壁面が平らでないと上ることが難しい点や、回転移動したときに角度によっては自重で壁面を滑ってしまうこともあるそうだ。これらの問題をクリアするにはもう少し時間がかかりそうだが、ロボットにポリッシャを付けたり、放水機構などがあれば、さらに面白い壁面清掃用のロボットが実現できるかもしれない。 また超音波センサやバッテリを積み、完全自律で徘徊歩行できるようになれば、社内の無人点検などに応用も効きそうだ。 ● 水中探査ロボットや2足歩行ロボット――小樽から生まれるユニークなシステム 同校では、これら壁面歩行ロボット以外にも、たくさんの興味深い研究テーマが課題として製作されていたので、ここで紹介しておきたい。たとえば、水中探査ができるロボットは、とてもユニークなもので筆者の琴線に触れるものであった。水中での作業ロボットは、水圧に耐えうる十分な密閉機構が必要であり、またロボット自体をコントロールすることも難しいからだ。 移動機構となるスクリューの製作も大変だ。これは同校のワイヤー放電加工機で作ったという。また、ホームセキュリティロボットや、2足歩行ロボットのほか、飲料容器分別装置、模型型Pick&Place装置、設備診断システムなど、生産技術に関連する自動システムなども多数あった。 生産機械システム技術科以外の学科にも枚挙にいとまがないほどたくさんの面白い課題が用意されている。生産電子システム技術科の標準課題実習である手作りの「デジタルストレージオシロスコープ」などは、その好例であろう。
こういった技術は、現場ですぐに応用が利くものばかりだ。筆者の経験も踏まえて過去を振り返ってみると、大学を卒業して社会に出て、いきなり現場に配置されても、すぐに戦力にはならない場合が多いように思える。 実学に即した実践的な技術を学生時代から習得しておけば、社会に出てから必ず大きな力となるにちがいない。北の文化の発信地である「OTARU」から、ものづくり大国、日本を支える優秀な技術者がたくさん生まれている。本当に頼もしい限りだと強く感じた。 ■URL 北海道職業能力開発大学校 http://www.ehdo.go.jp/hokkaido/sisetu/tandai/kai01.htm 2006/10/19 00:04 - ページの先頭へ-
|