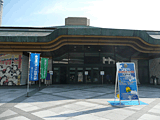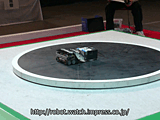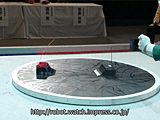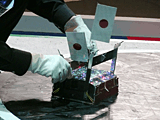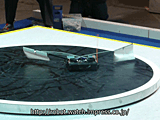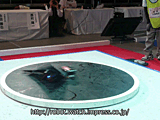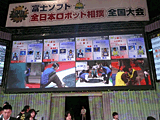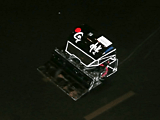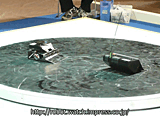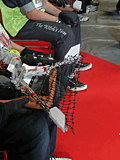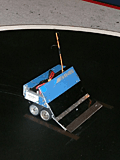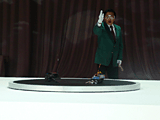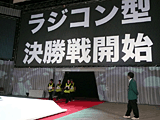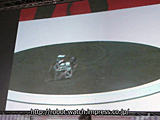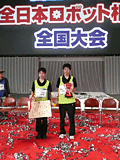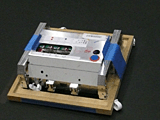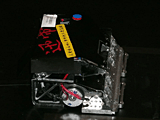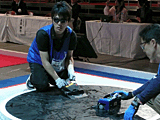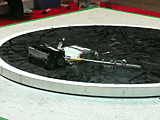|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全日本ロボット相撲全国大会レポート |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● 成人式を迎えた由緒あるロボット大会 12月21日、東京・墨田区の両国国技館において「第20回全日本ロボット相撲全国大会」が開催された【写真1】【写真2】。本大会は1990年よりスタートし、歴史のあるロボット競技会として知られている。
20回目の節目にあたる大会の開会式では、主催者である富士ソフト株式会社の野澤宏氏(代表取締役会長)が、本当の相撲と同じように海外に巡業したことや、貴花田、若花田関を来賓として招いたことなど、過去の大会について印象に残るシーンを振り返った【写真3】。また参加ロボットの歴史と進化についても解説した【写真4】。 さらに過去に出場者の中から、大会の発展に貢献した人物に対して、特別賞や功労賞が贈られた。20回までの大会で最多出場となったのは、相撲ロボット愛好会(大阪電通大含む)の累計112台。2位は三重県立四日市中央工業高校(以下、四中工)の100台、3位は富山県立大沢野工業高校の80台だ。いずれも1回あたり4、5台のロボットを出した計算になる。個人では千野隆之さんが14回で最多出場を果たした。また累計賞金の順位も発表された。賞金王の吉田直樹さんは、これまで合計446万円を獲得【写真5】。2位の田村友幸さんも396万円というから相当に大きな金額だ。
● 個性あふれるさまざまなタイプの相撲ロボットが参戦 話を競技大会に戻そう。今回の大会では、全国9ブロックの予選で勝ちあがったチームから合計128機のロボットがエントリー。田村科学研究所、チーム両国、大阪電通大、四中工、香川県立三豊工、大分県立国東高など、お馴染みの強豪チームも出揃い、第20代ロボット横綱を目指して、激しいバトルが繰り広げられた。この競技の勝敗は、ロボット本体の一部が相手より先に土俵外の地面に着いたら1本となる(土俵上で倒れてもOK)。試合時間3分間のうち2本を先取したほうが勝ちになるルールだ。時間切れの場合は1本取ったほうが勝者となる。また引き分けの場合は主審判定か延長戦で勝敗を決定する。競技種目はプログラムによってスタート5秒後に自動的に動く「自立型」【写真6】と、プロポ(コントローラ)によってロボットを遠隔操作する「ラジコン型」【写真7】の2タイプがある。ロボットのサイズは、ラジコン・自立型ともに幅・奥行きが各20cm以内、高さは自由で、重量は3kg以内となっている。
自立型は、ロボット自身のセンサーによって外界の状況を判断しながら対戦するため、ハードウェアとソフトウェア両面でバランスがとれた開発が重要だ。一方のラジコン型も、最近ではセンサーを搭載した半自立型が進展しているようだ。センサーによって土俵際での白線検知や相手を発見し、操縦者とロボットが協働する。とはいえ、基本的には操縦者がロボットを遠隔操作するため、普段の練習量がものをいう競技である。 駆動系の制御方法は、速攻を重視した「スピード重視型」【動画1】と、力技で攻める「トルク重視型」【動画2】に大きく分かれるようだ。トルク型は動作は遅いものの力があるため、粘り腰のガチンコ勝負が期待できる。高性能なマクソン製のモータを使用したり、モータを定格電圧以上で駆動させたり、ギア比を変更したりと、いろいろなノウハウがあるようだ。また電源もニッカド電池だけでなく、リチウムポリマ電池を利用することにより、昔と比べてパワーが期待できるようになってきた。
一方、速度型のほうはトルクはあまり出ないものの、素早い動作で勝負に挑めるメリットがある。スピードが速くなれば運動エネルギーも大きくなり、相手ロボットを弾くことができる。近年の傾向としてはロボットの高速化が進んでおり、勝負が数秒で決するスピード重視型に移行しつつあるようだ。実際にロボットの速度は秒速4mから5m以上もあるという。そのためスピード重視の試合では、操縦者だけでなく、司会者も見学者も一瞬たりとも目が離せない状況が続いた。 外形についてもラジコン型、自立型いずれも共通して、さまざまな創意工夫が凝らされたロボットが出場していた。たとえばダブルのブレードにしたり、鋭く刃を改造して相手ロボットに潜り込むもの【動画3】、フラッグの付いたアームを広げながら相手ロボットをかく乱させて攻撃を加えるもの【写真8】【動画4】【動画5】、相手ロボットをアームで囲い込んで押したり、マントですくい上げるもの【動画6】など、バリエーションに富んだタイプが見受けられた。 またロボットの攻撃プログラムは単一ではなく、攻撃のバリエーションを何十種類も用意しているチームも多かったようだ。本当の相撲のように、対戦相手に合わせて立ち会い時に攻撃プログラムをチョイスできる工夫を凝らしているのだ。
● スピード感と迫力ある衝突が魅力! ガチンコ勝負が始まる 全国大会の予選では4つの土俵が設けられ、同時進行で競技が進められた【写真9】。まず自立型の競技が行なわれ、次にラジコン型の競技が行なわれた。フィールドは大相撲の土俵の3分の1ほどで、直径は154cm【写真10】。参加者によると、昨年に比べて土俵の表面に付いている鋼板の厚みが半分ほど薄くなったため、これが微妙に影響を与えたとのこと。相撲ロボットには磁石が搭載されており、この鉄板に機体を吸着させることで、タイヤの空転を防止したり、相手からの押し出しを防げる。土俵への吸着力は約40kgから100kgぐらいまであり、相当な力がかかるが、吸着力は磁石とのクリアランスでも変化する。今回から土俵の鋼板が薄くなったため、吸着力が微妙に変化し、攻撃にも変化が出たチームがあったらしい。
ラジコン型、自立型ともに予選から迫力のある試合が始まった。優勝まで進むためには計6回の試合を勝ち進まなければならない。激しいぶつかり合いの連続であるため、試合が進むにつれて、徐々にロボット本体の損傷も激しくなってくる。もちろん試合の合間にメンテナンスをしているのだが、途中でコネクタが断線したり、ハードウェアの故障などで、うまく動作しなくなるトラブルも多かったようだ。 また以前の大会でも見られたが、今回もロボット本体から煙が噴くハプニングがあった【動画7】。これは一進一退のガチンコ勝負で機体に過負荷がかかり、電流が流れすぎて起こるもの。過電流保護回路をつけているロボットも多いが、その機能が効かないケースもあり、モータが焼け焦げて使用できなくなることもあるようだ。リチウムポリマ電池を利用している場合は下手をするとショートして発火する恐れがあるので注意が必要だ。 試合中には想定していないさまざまなトラブルが起こりえるため、優勝の切符を手にすることは本当に至難の業といえるだろう。いかに頑強なロボットを作れるか、そして複数の戦いに備えてベストコンディションをキープできるか、最終的には「耐久性」が勝敗を左右する大きなポイントになるようだ。 今回の大会では、ラジコン部門、自立部門から各2台すつ海外招待チームも参戦していた。ただし、残念ながら国内ロボットのレベルが高かったためか、あるいはアウェイでの戦いのためか、いずれも予選で敗退してしまった【写真11】【動画8】。
● 操縦者の俊敏なテクニックがものをいうラジコン型競技 ラジコン型競技において、熾烈な戦いから勝ち進んできたベスト16チーム。その中で、特に目立っていたのは四日市中央工(以下、四中工)だ。同校はOBチームも含めて、「天雷」【写真12】「神句」【写真13】「木の芽風」【写真14】や、「神撃」「神星」「雪華」「yrobo」という7機がベスト16に残り、圧倒的な強さを見せ付けていた。
これ以外の強豪チームとしては、三豊工業高校(以下、三豊工)の「顧動」と「Wリンク」【動画9】、千葉工業高校の「蒼空」と「L」(リキッド)【写真15】が、それぞれ2チームずつ駒を進めたほか、パルピゾンファミリーの「魔女の鼻R1」【写真16】、横手工業高校(以下、横手工OB)の「一心同体」【写真17】【動画10】、紀北工業高校の「紀北牙突零式」、MTY-OBの「ラインスピア」も残った。 いずれも個性ある機体だったが、この中で魔女の鼻R1は、2007年大会で3位と4位をとった福岡工業大学附属城東高校の「魔法の剣」を製作したOBチームのもの。今回はパルピゾンファミリーとして、魔女の鼻を製作し参戦していたようだ。魔女の鼻は、魔法の剣を踏襲した双アーム型ネット構造で、ラジコン型では異彩を放っていた。このアームを広げて相手を囲い込む形だ。ネットによって相手の勢いを吸収し、さらに相手をネットにからめて押し出す攻撃手法となっている【動画11】。今回も作戦はうまくいったのだが、対戦相手である神句のパワーが優っていたようだ。
三位決定戦は、神撃(四中工)と一心同体(横手工OB)の戦いとなった。いずれもスピードを重視した低重心の小型ロボットだった【写真18】。この試合は目にも留まらぬ速攻によって、神撃が一心同体を土俵外に弾き飛ばし、2本を先取して勝利をつかんだ。決勝戦は、神句と木の芽風の戦いとなった【写真19】。両者ともに四中工同士の戦いで、手の内を知っている身内同士のため、少し戦いづらそうに見えた。この決勝戦もカメラで追えない速さの瞬間的な戦いとなり、あっという間に勝負がついてしまった【動画12】。いずれのロボットも優劣つけがたく、あとは僅差の操縦技能や、勝負運で決まってしまう印象だったが、木の芽風に勝利の女神が舞い降りた。 最終的にラジコン型の結果は以下のようになった。今年は第3位までを四中工が占めている。なお優勝した木の芽風は、2008年高校生ロボット相撲全国大会でも優勝しており、2冠を達成した【写真20】。 【ラジコン型の部】 ・優勝:「木の芽風」(四中工) ・準優勝:「神句」(四中工) ・第3位:「神撃」(四中工) ・第4位:「一心同体」(横手工OB)
● 激しいバトルを繰り広げた自立型の決戦の行方は? 自立型競技はラジコン型に比べて、羽やフラッグ、アームを備えたユニークな形状のロボットが多かった。というのも、ロボットのスタートボタンを押した後は自動的に攻撃する方式であるため、白い羽やフラッグによって相手のセンサーを誤動作させる作戦が有効だからだ。フラッグを広げて相手ロボットを引きつけておき、その隙に相手の死角に回り込んで攻撃する。どちらかというと自立型のほうがラジコン型よりも試合時間が長いように感じられたが、対戦時のぶつかり合いはどちらも迫力満点だ。ロボット同士が衝突した瞬間にブレードの刃の一部が欠けて飛び散るようなシーンもみられた。ベスト16チームの中で、それぞれ3台ずつ駒を進めたのは「黒津崎シリーズ」を擁する昨年の横綱・国東高校(旧・国東農工)と、関西地区から出場したチーム両国だった。国東高校の黒津崎III【写真21】【動画13】は、フラッグ付き双アームを備え、スタート時にアームを倒して両方の旗を下げることで相手をかく乱させる方式。一方、チーム両国からは「酒豪旅心」【写真22】「カール君」と「六次元K」【動画14】が勝ち進んだ。酒豪旅心も2つのアームを備えているが、こちらはアームを広げながら相手を囲い込んで押し出す方式を採用。六次元Kはフラッグ付きのアームを備え、一方のフラッグのみを下げて相手を誘い出し、斜め横から攻めることができる。 また常連チームとして、三豊工の「軌跡」と「MITSU丸」、田村科学技術研究所(以下、田村科学)の「TMR-GO」【写真23】と「TMR-TB」、四中工の「迅帝」【写真24】と「涼風」(四中工OB)がベスト16に2台ずつ残った。このほかの強豪としては、茂原樟陽高校の「ハヤブサ」とTRCの「メカテレサF」【動画15】、チームDの「ランクD」【写真25】、マルす同好会の「GREEN」が残った。ハヤブサもフラッグを大きく広げて相手をかく乱させるタイプだ。
準決勝は、六次元Kと軌跡【写真26】、黒津崎IIIとハヤブサ、TMR-GOと酒豪旅心【写真27】、TMR-TBと迅帝の戦いとなった。3位決定戦は六次元Kと迅帝の戦いとなるはずだったが、迅帝はここまでの激戦でロボットが壊れてしまったようだ。すでに前試合でも煙を出しており、満身創痍の状態。六次元Kは不戦勝となり、3位入賞を手にした。 自立型の決勝戦は、黒津崎IIIとTMR-GOの一騎打ちとなった。国東高校の黒津崎IIIは、昨年大会で優勝を果たした横綱。やはり決勝戦まで実力で勝ち上がってきた。一方のTMR-GOも田村科学として常に上位に食い込んでおり、昨年は前頭の成績を残している。高性能な大出力モータを採用しており、ゆっくり相手を押しやるトルク重視型で、見た目の派手さはないが、粘り腰でとても安定感がある。決勝戦までの試合では、何度か相手から体当たりされて場外にはじかれるシーンもあったが、ひとたびがぶりよりになれば、相手を土俵外まで追い出せるパワーがあるのだ。 決勝戦では、黒津崎IIIは自慢の双アームを外してTMR-GOと戦っていたが、ロボット本来のパフォーマンスを十分に引き出せたTMR-GOが優勝の栄冠を手にした【動画16】【写真28】。最終的に自立型の入賞は以下のようになった。 【自立型の部】 ・優勝:「TMR-GO」(田村科学) ・準優勝:「黒津崎III」(国東高校) ・第3位:「六次元K」(チーム両国) ・第4位:「迅帝」(四中工ロボット研究部)
■URL 全日本ロボット相撲大会 http://www.fsi.co.jp/sumo/ ■ 関連記事 ・ 「第16回高校生ロボット相撲全国大会」レポート ~四日市中央工業が2部門制覇(2008/11/12)
( 井上猛雄 )
- ページの先頭へ-
|