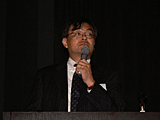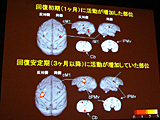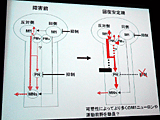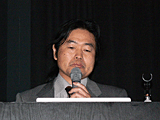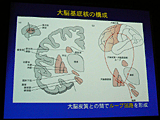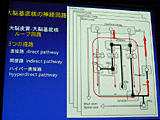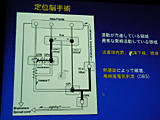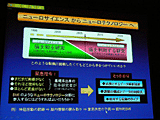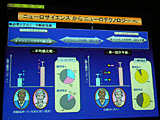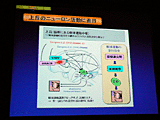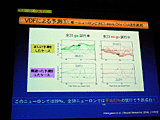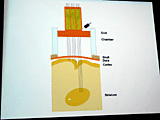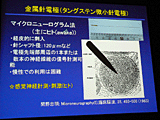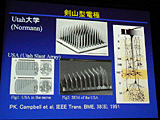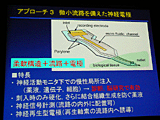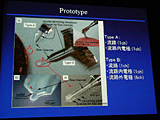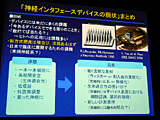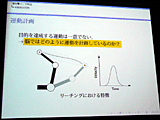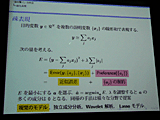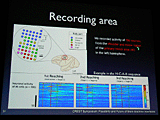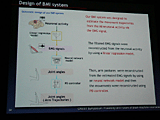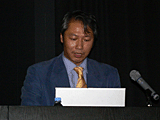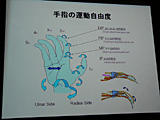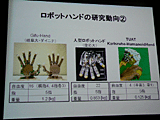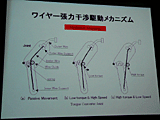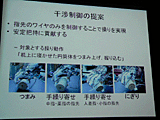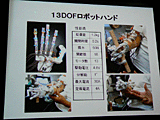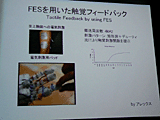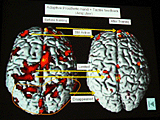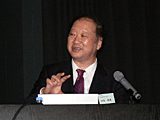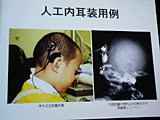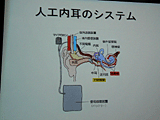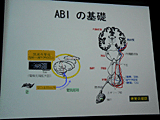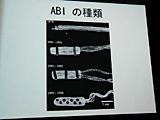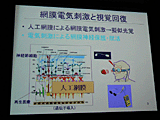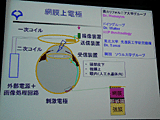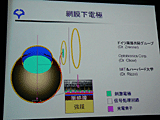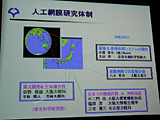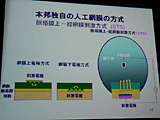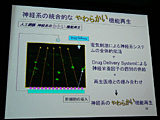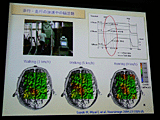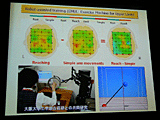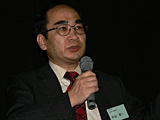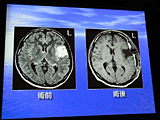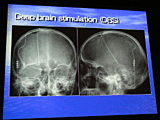|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
脳と機械を繋ぐテクノロジーのいま |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
~「脳を繋ぐ」分科会レポート
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11月6日、京都大学芝蘭会館にて「脳を活かす研究会」の「脳を繋ぐ」分科会が開催された。主催は「脳を活かす研究会。共催は、社団法人 日本生体医工学会、日本神経科学学会、電子情報通信学会ニューロコンピューティング研究会、電子情報通信学会ブレインコミュニケーション研究会、日本神経回路学会、脳と心のメカニズム、医療・福祉分野におけるヒューマンインターフェース研究会、NPO法人 脳の世紀推進会議、電子情報通信学会HCG脳情報通信時限研究専門委員会。後援は、特定非営利活動法人 日本せきずい基金。
脳科学の成果の実応用を目指す「脳を活かす研究会」のなかでも「脳を繋ぐ」分科会は、ブレイン・マシーン・インターフェイス(BMI)などの技術を使って、障害を受けた人のもつ機能を手助けすることを狙う。 伊佐氏は、日本は米国に対して10年近くスタートが遅れたが、今後、米国の研究動向を追随するのではなく日本独自の研究を進めていく方向がありえるのではないかと述べた。 神経活動のマルチユニットデコーディングだけではなく、ほかの手法を適宜組み合わせを探求するほか、フィードフォワードだけではなく感覚にフィードバックを戻して正確な制御をしたり、外界の情報を人工器官で受けて神経系に入力したり、既に臨床応用されている深部脳刺激やロボット技術との融合を行なっていきたいと語った。そのために幅広い分野の研究連携や共同研究が必要であり、広く情報交換を行なっていくという。 ● セッション1:基礎研究の現状把握 午前中は基礎研究の話から始まった。はじめのセッションは「基礎科学の現状把握」。まず「脳・脊髄損傷後の機能回復に関する研究の動向」と題し、引き続き生理研の伊佐氏が講演した。脊髄損傷になって麻痺が起こってもリハビリしていくと徐々に機能が回復していく。そのとき、脳神経系では何が起こっているのか。 伊佐氏らは、脊髄損傷のサルを使った実験で、普段は抑制されている間接的な経路が存在することと、それが回復の初期には用いられることを発見した。直接経路が損傷されていても間接経路が残っていれば、一週間から2~3カ月の経過で手指の巧みさが回復してきたという。 伊佐氏らはこれまでの実験・観察結果から、回復初期には既に存在する神経系の活動を脱抑制することで活発化させ、また、回復が進んでくると、神経系の可塑性によって、これまでには使われていなかった領域や反対側の領野などを使うことで運動を回復させていると考えている。 では何を脳は学んで指の制御を回復するのだろうか。普通、ものをつかむときには直前にいったん指を開いたあとにものをつまむ。だが麻痺が起こると、人差し指が接触したあとにはじめて親指が開いてものをつまむようになる。つまり麻痺しはじめたときは、感覚入力をトリガーとして指を動かしているらしい。それが回復してくるに従って、だんだんフィードフォワードになっていくのだという。 現在は、機能的ネットワークの再編過程を調べるために、機能回復のさまざまな過程でどんな遺伝子が発現するか調べているところだという。 最後に伊佐氏は何が機能回復のモチベーショーンになるのかについて述べた。実験によれば、いったんうまく使えることと、それによって注意が麻痺した部位にむくということが重要だそうだ。現在、注意、モチベーション、報酬系にかかわる神経回路と、再編成を促進する神経成長因子などについて調べているところだという。将来的には行動療法と電気刺激を適切に組み合わせることができないかと考えいてるそうだ。
南部氏は大脳基底核の専門家の立場から、BMI技術への期待と貢献の可能性について、機能や病態の解明におけるブレイクスルーに期待するという。 大脳基底核(だいのうきていかく)とは脳の深部にある部位で、左右に一対ある。大きく分けて5つの神経核から構成されており、大脳皮質とループ回路を形成していると考えられている。大脳基底核は、発火したがっている視床に対して「運動のブレーキ」のような働きをもっており、ブレーキを弱めたり強めたりすることで、運動を制御していると考えられている。大脳基底核が障害されると、筋肉の緊張が正常と比べて亢進あるいは弛緩してしまい、運動がうまく行なえなくなる。 筋肉が硬くなるのがパーキンソン病である。運動がうまくスタートできなかったり、数ヘルツの振るえが起きたり、姿勢や歩行の異常が起こる。特に旋回動作が難しくなるという。 またジストニアは主動筋と拮抗筋の両方が筋収縮することで、ねじれのような体の不随意運動が起こる病気だ。これは出力が落ちたことでブレーキがきかない状態になってしまっていると考えることができる。 最近、大脳基底核の出力部である「淡蒼球内節(たんそうきゅうないせつ)」という部位に刺激電極を埋め込むと回復することがわかってきた。 これは、淡蒼球内節での抑制が弱くなり、視床を興奮させることができなくなると運動ができなくなり、逆に視床下核が壊れると、淡蒼球内節ニューロンが抑制されやすくなって視床または大脳皮質の活動性が亢進し、ランダムなタイミングで不随意運動が発現するようになる。 そこで現在、大脳基底核刺激電極を埋めて脳深部電気刺激(DBS)を行なう手術が注目されている。だが現段階では視床下核を興奮させているから効果があるのか、抑制しているから効果があるのかさえ分からないという。 将来的には、電気刺激だけではなく、情報伝達物質であるGABAなど特定の薬物を合成して適切に放出したりできるマイクロ工場などが「脳を繋ぐ」分科会への期待であるとまとめた。
産業技術総合研究所 脳神経情報研究部門の長谷川良平氏は「サル上丘ニューロンの活動にもとづく意思決定過程の予測」と題して講演した。いまは、脳を知る研究(ニューロサイエンス)から、脳を利用する研究(ニューロテクノロジー)へと移行しつつある段階だと捉えており、基礎科学の研究者が「脳を繋ぐ」といったBMI研究に参入するためにどのようなアプローチがあり得るかという観点で講演を行った。 基本的には神経活動を計測してそこから意図を読み取ろうとするわけだが、ニューロサイエンスでは一般的にオフラインでの平均値比較が行なわれる。ある刺激を提示して、そのときのニューロンの活動を計測することで、おおざっぱに「これが関係している神経活動である」と述べるわけだ。これに対してニューロテクノロジーではオンラインでの単一試行予測が必要になる。ある神経活動がどの予測カテゴリーに属するのか、ある予測モデルに基づいて一定の精度で判断しないといけない。 長谷川氏は、その中間段階として、オフラインでの単一思考予測の研究を行なっている。上丘(じょうきゅう)と呼ばれる部分のニューロンを複数計測し、眼球運動に関する神経活動、特に運動を抑制する活動を計測しているという。 サルにある課題を与えて、その反応をニューロンのスパイクで見るわけだが、普通は加算平均した結果をあてはめる。上記のとおり、BMIに使うのであれば加算平均は使えない。また、ニューロン一つとっても中間的な活動を示すニューロンもあるし、そもそも発火の様子を見ていても、いつ決断したのかわからない。そこで長谷川氏は1試行ごとの意志決定経過を反映する「仮想意思決定関数(VDF)」を提案した。 予測の確からしさを示すVDFを使うことで、未知の発火の様子から、ある時間において、どのくらい意思決定が進行したか推測できるという。もちろん複数のニューロンの活動を計測することで、予測の精度は上げることができる。95%以上の予測精度を出すためには領野ごとに違うが、100~300個程度の神経活動を計測すればそのくらいの精度にはなるそうだ。 産総研でも2005年にBMIが重点政策課題となり、2006年にはニューロテクノロジー研究グループが発足したという。今後もこの分野に力を入れていくという。
藤井氏らは「社会的脳機能(Social Brain)」という観点で研究を行なっている。我々は、いつでもどこでも自由に行動できるわけではない。自分が選択できる行動の可能性は他者に非常に影響を受ける。たとえば、目の前のテーブルにケーキがあったとする。誰もいなければいつ食べても問題ない。ところが目の前にものすごく偉い人が座ったとしよう。そうするとたとえ手を伸ばせば簡単に手が届く距離にあったとしても、躊躇してしまう。他者の存在によって行動が抑制されるのだ。我々は、なぜ他人を気にしてしまうのか、というテーマである。 他者の存在によって自分の行動が変容してしまう。そのときに脳の活動はどのようになっているのか。このようなテーマはまだあまり研究されていない。我々の脳の中には、たくさんの領域があり、情報をやりとしている。脳は、複雑で多層性の巨大なネットワークだと捉えることができる。さらにそのような脳が、相互に他の脳とインタラクションしているのである。これが藤井氏らのいうところの「社会脳」の姿だ。 社会脳を調べるためには、単一個体の単一領野だけを調べていたのでは無理だ。そこで藤井氏らは、複数の個体の脳の多くの領野から記録をとると同時に、実際の行動も詳細に記録するというアプローチで研究を行なっている。つまり神経活動の計測とモーションキャプチャを同時にやっている。 講演では電極を頭部に刺した2頭のサルにモーションキャプチャースーツを着せた実験の様子が紹介された。サルは上半身は頭も腕も自由に動かすことができるので、自然なインタラクションの様子をあとから再現できる。 サルの頭頂葉から運動関連の神経細胞の活動を記録することで、手の運動に関係した領野をひろうことができる。藤井氏らの研究によれば、自分より強い他者が横、特に利き手側に来るだけで、運動関連の細胞の活動が変化するという。 また、社会的文脈において主として変化するのは頭頂葉の細胞で、前頭前野の細胞群はあまり変化が起きない。藤井氏は、前頭前野は自分と他者を区別せずに、上から鳥瞰図で見ているように環境全体の様子を認識し、頭頂葉では身体的拘束性に基づいて状況を見ているのではないかという。 今後は、サルが自分の位置を変えることができるテーブル型の拘束器具を使ってさらに詳しい実験を行なっていくそうだ。
● セッション2:工学
神経ブローブにはいくつかのタイプがあるが、細胞の近傍に先端だけを露出した針電極を置いて神経細胞の発火を計測するモノが一般的だ。また最近では、神経電極を複数束ねたフォーク型、あるいは剣山型の電極もある。一本の太さはおよそ100ミクロンほどで、先端に計測点があり、複数の神経細胞の活動をまとめて計測できる。最近はワンチップ化や無線化の研究も進んでいる。 しかしながら100本の電極のうち、20本程度しかデータが取れていないことも多く、また先端は細いが基部は太いので周囲の神経組織を押しつぶしてしまうという問題もある。また、電極の周囲を結合組織が覆ってしまうという問題もある。 そこで現在、柔軟で、なおかつ、例えば神経活動をモニタしながら薬液を流せるような機能を持たせた電極の開発が研究されている。具体的には、針ではなく、糸のようなものにすることをねらうという。 また、予め信号処理回路を作っておき、任意の場所で針を成長させるといった技術の検討も行なわれているという。 このほか鈴木氏は、末梢神経における、軸策再生を利用した電極などを紹介した。
人間は腕を動かすとき、はじめにゆっくり動かし始めてやがて速度最大に達し、目標地点でゆっくり腕を止めるような軌道を描くように動かす。そのために脳がどんな計算をしているのかについて、トルク変化最小モデルをはじめとして、さまざまなモデルが提案されてきた。 池田氏はこれらのモデルに対して、運動指令それ自体の性質から最適化を考える枠組みを考えた。基本的な背景として、脳はどんな関数でも表現できるわけではないだろうという考えがある。また、タスクに慣れればなれるほど、脳はあまりリソースを使わずに活動できるようになる。すなわち多くの細胞は発火せずに休んでいる状態が好ましい、ということだ。また視覚野の受容野を説明する計算モデルのなかにも「疎」表現を用いて成功した研究がある。 これらを背景に池田氏らは基底の線形和として筋肉への運動指令を表現し、そのなかで、細胞活動が疎になるような運動指令が選択されていると仮定し、一関節モデルによる実験を行なった。この問題は線形計画法、あるいは2次計画法によって解けることから、今後は多関節モデルや非線形モデルでの検証、ロボット制御への応用も考えていくという。
小池氏らは特に、ボタン押し動作に見られるように、対象を押し続けるような、ある一定時間、安定してその運動を続ける、姿勢支持の推定に力を入れているという。具体的にはサルにリーチングタスクを行なわせ、そのときの神経活動を計測する。同時に筋肉の硬さも計測する。神経活動から筋電への変換を行ない、それを3層ニューラルネットワークを使って姿勢推定を行ない、さらにサーボモデルというモデルを使って動きを推定する。最終的に40個の神経細胞の活動から筋電信号を推定し、姿勢推定を行なうこともできたという。手先位置だけではなく、ひじの動きもほぼ推定することができたそうだ。 最後に腕の制御モデルとして、小池氏は以前いったん否定された「終端位置制御仮説」を出し、脳が自分の腕の位置を遠心性コピーによって知る内部モデルを脳内にもっていると考えると、再現できると述べ、まだこの仮説は死んではいないのではないかと述べた。
手は精密なグリップだ。それに対して現在のロボットハンドは、ひっかけてみたり、球体を握るといったことができる程度である。義手やロボットのハンドとするために人間の手をまねた研究は各国で進められているが、もっとも進んでいるのはイタリアのハンドだという。 人間の筋肉は2つの関節をまたぐ形で筋肉がつく、2関節筋の構造になっている。義手もこの形をまねようとしているものが多い。ひとつのモーターの出力を軽減して、より大きなトルクを出すために、よく用いられているのが干渉駆動である。横井氏は「ワイヤー張力干渉駆動メカニズム」の性質について述べ、ものを引き寄せる動作に対しては非干渉駆動のほうが有利で、干渉駆動は把持するほうに有利だという。その後改良をほどこし、現状では、握力と操作力双方の面において、「子供の手レベルを実現できた」段階だそうだ。 これにより、たとえばコップを握るような動作においても、被験者がものを落とさなくなった。そのため、かなり安心して使えるようになったという。いまは処理装置を小型化して外で使えるレベルにまで達している。 いまは筋電位の信号から周波数解析をして、特徴抽出をし、3層型のニューラルネットワークを介してロボットハンドの腕を動かしている。特徴データから混ざりやすいデータを自動削除し、新しい機能や運動を追加するときには、もう一度NNに手動でデータを追加していくのだそうだ。 現在は、「握った」という情報を被験者にフィードバックすることで、ものを握って、手首を回転させて液体を注ぐという運動ができるようになっている。 この様子はNHKなどで放映されたこともあるので、ご存知の方も多いだろう。
● セッション3:臨床
人工内耳は、マイクが録音した音をスピーチプロセッサで解析し、AD変換されたその信号を、体内に埋め込まれたインプラントに電磁誘導で送り、蝸牛に埋め込んだ電極を通じて聴覚神経に流すようになっている。電極の数は22。現在、世界では大きくわけて3社が人工内耳を作っているという。 価格は人工内耳だけで300万円、手術費用が100万円。そのためなかなか日本では普及しなかったが、'94年に保険適用が認められてからは、毎年4,000人が手術を受けているという。いまはできれば早期に手術を受けたほうが聞こえがよいということで、2歳児~3歳児くらいから手術が行なわれている。就学年齢に達したときの学校側の対応が課題になっているという。かつては、音楽を聞くことは無理だと思われていたが、最近ではむしろ人工内耳と音楽に関する研究が世界中で盛んになっているそうだ。 聴覚脳幹インプラント(ABI: Auditory Brainstem Implant)については、加我君氏自身もその結果に「非常に驚いた」そうだ。脳幹インプラントは蝸牛神経が機能を失った場合に用いられる手法で、人工内耳が蝸牛神経を刺激するのに対し、脳幹の表面に多電極刺激を与える。機械としては、人工内耳と違うのは電極だけだ。いかに正確に電極を置くかが鍵になるが、何も聞こえなかった人が、中程度の感音難聴程度にまでなる。今後は、新しい電極開発、電極の移植部位の同定法などが課題だという。 いろいろ課題はあるようだが、「こんなことでこんなに分かるとは本当に驚き」だと加我氏は語った。なお補聴器をつける年齢も現在は臨界期における可塑性があるそうで、子供のころのほうが良いようだ。
人工網膜とは視細胞のかわりをするデバイスを目に埋め込むものだ。網膜の上に置くか下に置くかで2つのタイプがある。基本的にCCDカメラで撮った画像を電力と一緒に2次コイルに送るという仕組みになっている。人工内耳と同じだが、目はいつも動いているため、眼球運動に耐える耐久性のある配線技術も必要になる。 網膜の下に置くタイプだと目の奥に置くことになるので眼球運動と連動できるが、視細胞のような情報変換効率のよい素子はない。また、結局外から電力を送らないといけないので、同じ問題をかかえている。一番効率がいいのは視神経刺激型電極で、視神経に電極をまきつけて信号を送るというものだそうだ。 ただいずれにしても患者はかなりのトレーニングを要求されるそうだ。しかもせいぜい1~2度、指の本数が分かる程度の分解能を得られる程度であるようだ。将来的には多電極刺激によって、24度程度の視野角、最低3文字程度の文字が読めるようにするのが目標であるようだ。 そのほか不二門氏は、適切な電気刺激は、軸策の伸展や神経細胞死の抑制になるのではないか、神経細胞保護にも電気刺激が役立つのではないかと示唆する実験結果を示し、「(人工器官による)かたい機能再生だけではなく、やわらかい機能再生を」考えるべきと述べた。
リハビリテーションを神経科学的なスタンスから行なおうという考え方が神経リハビリテーションだ。現在のリハビリ現場では、段階的な難易度の設定が大事だと考えられており、何よりもリハビリの量と介入の早さが重要だという。 宮井氏らは島津製作所との共同でfNIRSを使って運動時にどのような脳部位が働いているか計測している。では、リハビリテーションによって脳活動の変化はどのように変わるのだろうか。患者が常に報酬を受けるような形でリハビリを行ない、イメージや鏡像を使ったトレーニングなどを行なった様子を見せ、自発的な動きを増すほうが脳活動が増すことを示した。 興味深いことだが、トレッドミルなどでの歩行スピードを増していくと、オートマティックな運動が現れるそうだ。むしろゆっくり足を動かすほうが難しいのだという。宮井氏は、真の回復であろうが代償であろうが学習が大事だと述べた。 また、練習においてはコンテキストが非常に重要であり、リハビリと薬剤の併用もまた重要だという。リハビリによって脳は変わっていくのだが、その変わり方はさまざまであるようだ。
片山氏は、自身の実際の手術例を示しながら、大脳皮質の機能局在がダイナミックに変化することを具体的に示した。脳腫瘍になった場合、腫瘍は摘出しなければならない。だが腫瘍だからといって機能がないわけではない。摘出の際には、腫瘍そのものと周辺に存在する機能を見極めるために覚醒下開頭術を行なうことが多いが、片山氏は「いまではほとんど役に立っていないと思っている」と語った。 たとえば言語をつかさどるブローカ野という部位がある。そこが腫瘍になった患者さんの場合は、喋ってもらいながら摘出を進め、従来であれば喋ることができるかできないかのあたりで摘出手術をやめることになっている。だが、片山氏は8年くらい前から、摘出しても良いのだという考えにいたったという。摘出して一時的に喋れなくなっても、その後、大脳皮質の機能の再組織化によって、再び喋ることができるようになる例を実際に見せた。いわば配線にあたる白質を残しておけば、そのような再編成が可能なのだという。 だが良い再組織化だけではなく、脳は困った再組織化をすることもある。一言で神経系といっても、いわばケーブルのような性格をもっているのは脊髄までだという。皮質のどこかを適当に刺激しただけでは知覚は起きない。かなり広い範囲で活動が起きて、はじめて知覚として意識上にのぼってくる。ところが脳卒中を起こすと、ちょっとしたことで疼痛が起こるようになる。 これは、大脳皮質の機能が正常の場合と病気の場合で、ぜんぜん違ったものになってしまうことを示しているという。そこで外科的介入によって、視床や大脳皮質運動野に電極を入れて、外科的に制御しようという考え方が出てくる。DBSである。 不思議なことに、DBSで制御をしていると、症状がだんだんよくなっていくのだそうだ。しかも、刺激をしてなくてもよくなっていくのだ。短時間だけ刺激すればよくなっていくのだという。片山氏は、再組織化をDBSが促進していると言えるのではないかと述べ、たとえば特定の姿勢をとったときだけDBSをするといった方法が有効だという考えを述べた。 なおDBSを使った片山氏の治療に関しては前回の「脳を活かす」レポートをご覧頂きたい。
「脳を繋ぐ」分科会は、研究者の間を繋ぐこともまたテーマのひとつだそうだが、現時点ではまだ始まったばかりで、それぞれの研究者がこれまでやっていたことを続けているだけであり、いまひとつ繋がっていない印象は否めない。今後に期待したい。 ■URL 脳を活かす研究会 http://www.cns.atr.jp/nou-ikasu/ 脳と機械を直結させるインターフェイスの未来 http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0511/kyokai48.htm
( 森山和道 )
- ページの先頭へ-
|