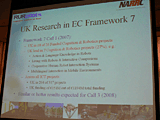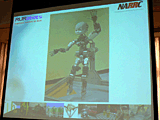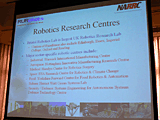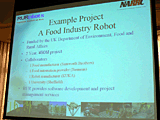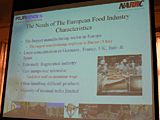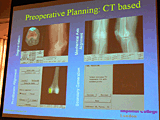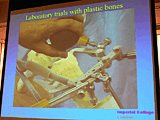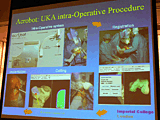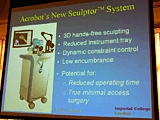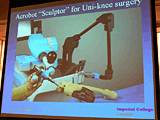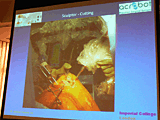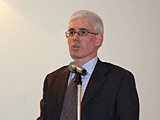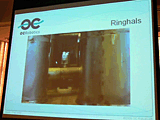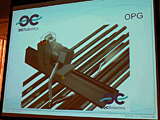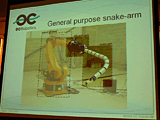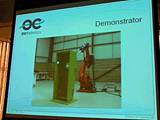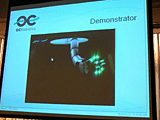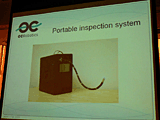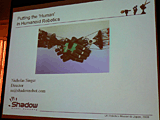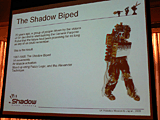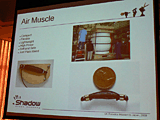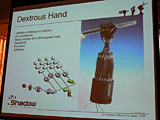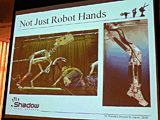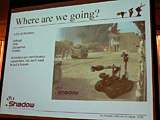|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
英国大使館セミナー「英国の先端ロボット研究開発の現状」レポート |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● イギリスのロボット
ペグマン氏はロボット市場のうち1/3程度がサービスロボットのマーケットであると見ているという。イギリスには工業用ロボットの市場は存在しないが原子力、セキュリティ、海中などの領域でロボットが活躍する領域があるという。統合されたロボットプログラムは存在しないが英国のEPSRC(工学・物理科学研究会議)を通して資金提供は行なわれている。イギリスはヨーロッパの一部であり、資金の多くはEUから来ているものが多いという。2007年~2012年の5年間で7億5,000万ユーロが認知ロボティクスに割り当てられている。 イギリスの位置づけとしてはヨーロッパで走っている26の認知ロボティクス関連プロジェクトのうち18に参加。そのうち7つでリーダーになっている。ペグマン氏は「RobotCub Consortium」にてイタリアのジェノバ大学を中心に16の大学・研究機関が共同開発し、さまざまな研究用のオープンプラットフォームとして使われている3、4歳くらいの幼児型ヒューマノイドロボット「iCub」を紹介した。このロボットの動画はBBCほかで閲覧できる。本誌でも2007年3月に開催されたシンポジウムのレポートで紹介している。「日伊共同研究拠点「ロボット庵」が開業~「身近なロボット」シンポジウムレポート」のなかで紹介している。 このほかペグマン氏はイギリス最大のロボット研究機関としてブリストル・ロボティクス研究所、そして多くの大学でCOE(Center of Excellence)が設置され研究が進められていることなどを紹介した。またコマーシャルサイドでは60社くらいがロボットの研究開発に取り組んでいるという。それらの多くは中小企業であり、そこが大企業主体でロボット研究開発が進められている日本の典型的モデルとは異なると述べた。
ペグマン氏は続けてRUロボット社の活動について紹介した。同社は主に受託研究開発を行なっており、その詳細を紹介することは残念ながらできないという。主な分野は原子力や国防、マルチロボットコントロール、操作インターフェイス、高次認知システムなどのほか、中にはロボットとはいえないものもあるという。また衝突回避、SLAM、食品ロボットの開発を行なっているそうだ。 食品ロボットの研究開発は110万ユーロの大きなプロジェクトで、KUKAそのほかと一緒に進めているという。ヨーロッパの食品関連メーカーは小さな会社が非常に多く労働集約的で、ほとんど手作業で行なわれている。実に99.1%が小企業だが、実際にそこで作っている食品の生産量は半分に及ぶ。そこにロボットシステムを入れることで効率化を図りたいという。目標は本質安全で、ローコスト、そして取り扱いもしやすいもの。位置ではなくタスクを教えられる高度なシステムをローコストで実現したいという。ペグマン氏は、既存技術を統合して働くロボットを作ることが家庭用ロボットを作ることの最初のステップになると考えていると述べた。
● 整形外科手術のためのロボット
デイビス氏が開発している外科手術用ロボットは、完全自動で手術を行なうものではなく、外科医のためのハンズオン・インテリジェント・ツールである。膝の整形外科手術において、骨を削り、補綴具を埋める必要がある場合がある。そのときに事前の計画通りに骨を削るために位置決めのサポートをしてくれるロボットツールだ。 デイビス氏は、足の3次元モデルをCTから作り、補綴具の適切な寸法を選び、位置を調整し、手術計画を立て、実際にロボットを使って高速回転するロータリーカッターで骨を削る様子をビデオで公開した。ロボットを使うことで必要最低限の侵襲で手術を行なうことができ、従来の手法よりも一貫性のあるハイクオリティな手術ができるという。この道具はあくまでツール先端の方向性を決めるものである。位置決めそのものはロボットが行なう。たとえば硬い骨を切っているときはよりゆっくりと動かさなければならないことなども力学で術者に伝わるのだそうだ。 このツールができたことによって、カルチャーが変わってきているとデイビス氏は述べた。患者のほうから、そちらの病院にはロボットがあるかと聞いてくるのだそうだ。つまり、患者側がロボットを求めてくるようになったというわけだ。手術用ロボットはさらなるコストダウンやセットアップの簡便さ、使いやすさに焦点を当てる必要があり、また、外科医が従来の手術では難しかった分野を対象として選ばなければならないと述べた。
● スネークアームロボット
バッキンガム氏はまず始めに、イギリスにおける研究開発をめぐる状況について述べた。イギリスではアメリカに比べてベンチャーキャピタルからの投資があまり大きくなく、そのためできるだけ早く市場に出て顧客を獲得することが重要だと強調した。 スネークアームロボットは閉鎖された空間で使えるロボットだ。バッキンガム氏は既存の原子炉のメンテナンスに使われている様子をビデオで示した。この業務が同社の主な収益源になっているという。また車輪型ロボットのアームにスネークロボットを使ったものや、飛行機工場で使うためにKUKAのロボットアームの先に自由度が20あるスネークアームを付けたロボットでボルト締めする様子をビデオで示した。40Nでボルト締めができるという。そのほか、アメリカ国防総省の委託で指の直径くらいの小型のスネークアームも作っていると述べた。 最後に、スネークアームは他にも切開しないですむ外科手術など多彩な分野に使えると述べ、「我々がVCから好かれたのは他の人と違う新しいことを考え、実際に開発できたからだ」と述べた。
● シャドウロボット社の研究開発動向
シンガー氏は最後にロボット市場そのものについて述べ、いわゆる4D領域(Difficult, Dirty, Dangerous, Distant)、人間の能力が必要だが人間が行きにくい場所にロボットの可能性があると述べ、戦場で活躍するロボットのイラストを示して講演を締めくくった。
このあと、マテリアルサイエンスや情報通信技術など広範囲にわたり研究費を配分する英国政府組織の1つ、EPSRC(工学・物理科学研究会議)ポートフォリオマネージャーのスーザン・ソルスビー(Susan Soulsby)氏と、英国インテグレイト・プロダクト知識移転ネットワークのポール・パーマー(Paul J. Palmer)氏が、それぞれEPSRCの役割と、イギリスの技術移転ネットワーク「KTN(Knowledge Transfer Network)」の仕組みについて説明した。現在も日本と共同研究を行なっているが、将来的にも新しくコラボレーションして日本との関係を作っていきたいと考えているという。
■URL 駐日英国大使館 http://ukinjapan.fco.gov.uk/ja/ R.U.ロボット http://www.rurobots.co.uk/ ACROBOT http://www.acrobot.co.uk/ OCロボティクス http://www.ocrobotics.com/ シャドウロボット http://www.shadowrobot.com/ EPSRC http://www.epsrc.ac.uk/ KTN http://ktn.globalwatchonline.com/ ■ 関連記事 ・ ユニバーサルシティウォーク大阪に、EU版ネットワークロボット「DustCart」が登場 ~ATRのRobovie-IIと連携サービスの実証実験を実施(2009/02/12) ・ 日伊共同研究拠点「ロボット庵」が開業 ~「身近なロボット」シンポジウムレポート(2007/03/26)
( 森山和道 )
- ページの先頭へ-
|