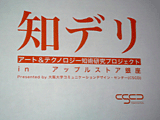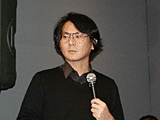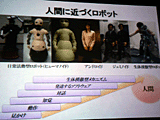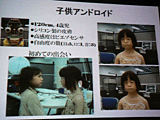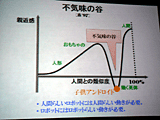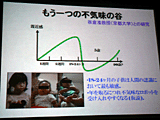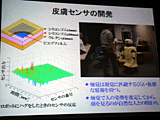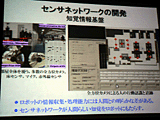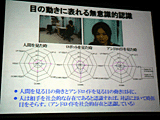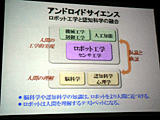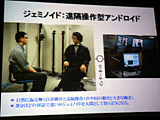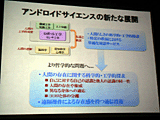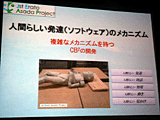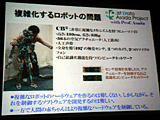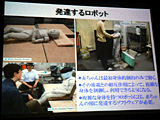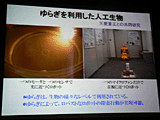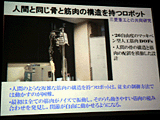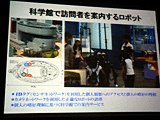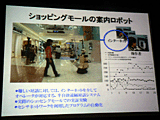|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大阪大学CSCD、「知デリ」in アップルストアを開催 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
このイベントは平成19年度JST地域科学技術理解増進活動推進事業「調査研究・モデル開発」の補助による活動の一環で、主催は大阪大学の科学技術・哲学・アートなど多分野の専門家で構成される大阪大学コミュニケーションデザイン・センター(CSCD)。アップルストア銀座が共催、NPO recip [地域文化に関する情報とプロジェクト]が協力として参加している。 「知デリ」とは、CSCDが2006年度から研究テーマとして掲げる「知術」を、人々にデリバリーするトークプログラム。さまざまな領域で活躍する人々に対話の機会を設け、各々の専門分野における「知識」や「技術」を、参加者と横断・交換することを通して新しい発想の創出やアイデアの実現に繋げることを目指しているという。年に3回程度行なわれており、アップルストア銀座にて「知デリ」が行なわれたのは今回が2回目。CSCDの木ノ下智恵子氏は開演に先立ち、「科学技術やアートを専門とする人たちがお互いに『異種格闘技』のように出会うことで、あたらしい『知の術』を共有することが目的だ」と語った。
● 人間と関わるロボットの研究
「人間らしい見かけ」のロボットに「人間らしい動き」をつけようとしたのが愛知万博のときのロボットだ。動きだけではなく、他のものと関わるための皮膚センサーや、センサーネットワークの研究も合わせて行なった。触覚は視覚以上に複雑な情報を持つという。 またロボットに搭載するネットワークだけではなく、環境側にセンサーを置き、それとネットワークすることで知能システム全体のパフォーマンスを上げる研究も行なっている。「ロボットとセンサーネットワークが組み合わされて、はじめてロボットは世の中に出て行ける」という。 石黒氏の研究に寄れば、人間は2秒あればアンドロイドを見抜くことができるが、目の動きを見ると、アンドロイドを見たときと人間を見たときとでは同じだそうだ。石黒氏らが提唱する「アンドロイドサイエンス」では、ロボットをより人間に近づけるだけではなく、ロボットをテストベッドとして脳の理解を進めていくことも目的としている。 石黒氏の知名度を一気に押し上げた「ジェミノイド(ATR知能ロボティクス研究所開発)」は実在人間のアンドロイドである。自然な動作は自律で行ない、しゃべったり右を向いたり左を向いたりといった大きな動作は操縦で行なう。5分くらい対面していると、人はおおむね普通に話すようになるという。面白いのは操作者も引き込まれてしまうことで、石黒氏は、ジェミノイドがつつかれると、操作者も不思議な感覚があると強調した。アンドロイド研究では人間らしさの動きを追求したが、ジェミノイド開発では「自分らしさ」などについて考えるきっかけになったという。
複雑なハードウェアは作れるが、複雑なソフトウェアを作ることは難しい。ところが人間は容易に制御している。ハードウェアとソフトウェア双方の関わりのメカニズムを探るための研究を行なうためのロボット、複雑化するロボットの制御の問題を研究するために作ったのが巨大な赤ちゃんのような姿をした「CB2(JST ERATO浅田共創知能システムプロジェクト開発)」だ。 ほぼ人間と同じ構造のロボットを作る研究もしている。こちらは阪大の「ゆらぎ」プロジェクトで行なっている研究で、生物が用いているメカニズムで人工物を動かそうとするもの。ほぼ人間と同じような筋肉に相当するアクチュエータをつけた腕のロボットを制御することを試みている。 ロボット単体で人間と関わりが持てるわけではない。センサーネットワークやIDタグを使って環境や人間関係の社会グラフを構築して、社会関係を基にしたサービスを行なうロボットの研究も行なっている。ロボットが人間関係を把握することができれば、たとえば孤立した子供を発見して支援を行なうこともできる。石黒氏によれば、ロボットが作るソシオグラムは、子供からアンケートで作るソシオグラムとは違っていて、(幼稚園の先生たちが捉えている)実際に起こっている人間関係をより反映することができるそうだ。「ロボットは複数の人が共有するメディアになれる」という。最近はショッピングモールでの実証実験も行なっている。 石黒氏は「人間の脳は人間を認識するためにできているので、人間型ロボットがもっとも理想的なメディアだし、人間型ロボットが街でサポートするのはありうる話だ」とまとめた。
石黒氏のプレゼンテーションについては、詳細はこれまでの本誌記事でも触れている。合わせて参照されたい。 石黒氏のプレゼンを受けて司会の平田氏は「人間とは何かという根拠はここ20~30年の間に溶けていくだろう。そうなるとそれに支えられていたシステムも変わっていかざるを得ない」とコメントした。 ● ロボット研究と演出活動の共通点は、箱庭作りと不自由さ? もう一人のゲストである飴屋法水氏は1995年、ペットショップ「動物堂」を経営していたときの様子をビデオで見せながらプレゼンをはじめた。「人がペットに求めている愛玩性は何か、どのへんからそれが発生するのかが知りたかった」のだという。ペットロボットを使った研究にも通じる視点だ。そのほか精液を冷凍して人工授精希望者をつのったり、血液を他者と入れ替えたり、ふくろうを刷り込みでなつかせてその仕組みを探索したりしていた。食べるとか子供を育てるといった動物らしい営みが、どこまでテクノロジーで変えられるのか、変えようとしたときに自分がどういう気持ちになるのか「考えるというよりは、実感したくて」それらの活動をしていたそうだ。 飴屋氏は、石黒氏のロボットのなかでは、赤ちゃんロボットCB2が、いちばん不気味ではないと感じたそうだ。だが石黒氏によれば、一般的評判はあれが一番気持ち悪いそうだ。石黒氏は「生々しさが不気味に見せているのではないか。もっと不気味なものを作ると人間らしさの本質が分かるかもしれない。ありとあらゆる不気味なものを作ることは研究としては大事かもしれない」と述べた。「ゆらぎ」プロジェクトでの研究を踏まえて、一番原理めいたところだけで動くと動きに「自然さ」が出るのかもしれないと考えているという。 平田オリザ氏と石黒氏は、2人でロボットを使った芝居を行なおうとしているそうだ。単なる見せ物ではなく、大人の鑑賞に耐えるものにするという。「言葉、人間とは何かという境界線に興味がある」という平田氏は、演劇の半分は観客が作るという寺山修二氏の言葉を引き、「我々演出家は、ロボットが本当は持っていない能力も持っているように見せかけることができる。お客さんの脳みそをのぞきたい」と述べた。
石黒氏は、劇場とは実験場だと別の研究者に言われたそうだ。「こういうシーンがあったらどうするのかと問いかける場が劇場。開発と実証実験の間に、ロボットと人間のかかわりあい方の可能性を見せる実験場として演劇の役割がある」という。たとえば吉本新喜劇を毎日見ることで関西人は日常生活で自然にぼけやつっこみをするようになるが、演劇にも同様の効果があると考えており、「ロボットとどういうふうに接していけばいいのか見せられる場所なのではないか」と述べた。 飴屋氏は20年以上前に、役者に母音と子音を喋らせて録音し、それを組み合わせて動かした機械を主役だといって舞台に出し、客に納得してもらえるのかしないのか試したりしていたことがあった。どこのラインを超えれば納得できるか知りたかったのだという。石黒氏は、ジェミノイドであれば学生指導程度ならば何の問題もないとこたえ、「髪型を変えたり印象が違うのと同様、人間が持っているバリエーションの許容範囲内ではないか。個人を認識できないほどの差はあのシステムにはないと思う」と述べた。 しかしながら、飴屋氏は素朴な疑問も感じると応えた。「背後にいる石黒さんとコミュニケーションしようという目的があって、それをするのにまったく支障がないことは分かる。でも違った目的だとどうか。たとえば『石黒さんのこの表情が素敵だな』とかそういうのは発生するのか」。 石黒氏は「発生すると思っている。無意識的な認識はそれほど精密ではない。人間らしい形や動きもわりと単純な認識の積み重ねだろうと思っている」と述べた。
飴屋氏は色々試した結果、「生まれてきた動植物がいて、それが死なないと生きていけない。ある種、トレードみたいなことになっている。その仕組みで自分は生きているなと思った」と実感するに至っているという。「技術の進歩は止められない。そのことは自分にとっても魅力的。自分が『これが人間だ』と思っている感覚も変容していくとは思う。だけど、一方で、ギブアップ感も強い」という。 「ある情報の組み合わせを与えれば、人間はその向こう側に存在や実感を感じる力を持つ。テクノロジーはそこを刺激している」(飴屋氏)。しかしながら石黒氏の活動を見ると「積極的に後退しているようにも見える」という。例えば映像であればコストがかからず世界中に配信することも可能だが、敢えて石黒氏はコストもかかる物質で、ロボットでそれを作っている。そこが「積極的に後退」しているようにも見えるという。 それに対して石黒氏は、だから「そぎ落とし」が重要なのだと答えた。「テクノロジーで置き換えられるところはテクノロジーで置き換えたい。そのためには本当に人間とは何かを知らなければならない。知るためにはどこまでそぎ落とせるか知る必要がある」。だから一度は全て作ってしまわないといけない、というわけだ。 「技術に置き換えることができた部分は、人間の本質からは引かれる。すべてテクノロジーで置き換えることができたら、人間とは何かがわかってしまう。そうすると、生きる意味はあるのか。人間は動物と自分がどこが違うのか、なんで生きているのかと考える。そこに人間性のロマンを感じながら研究している」(石黒氏) 飴屋氏は、石黒氏の研究に対して「もっとコントロールできるはずの対象を、わざわざ物質化している。支配できないものを作っている感じがある」と述べた。「それをやっている石黒さんを見たときに『負けよう』としている部分があるのかなと思った」とコメントした。 それは演出にも通じるところがあるという。「演出は世界を支配するものでもある。じゃあ白紙に描けばいいのに、わざわざ役者を連れてくる。そこで、もう『負けている』感じがする。2つのことが同時に走っている」(飴屋氏) 石黒氏はこれに同意し「演劇で、役者を通じて考えたいというのと同じで、人間を知りたくても、研究はなかなかストレートにいかない。人間の立場で人間を理解するのは無理なのかもしれない。鏡に映さないと理解できないのにあがいている。そこが面白いのかもしれない」(石黒氏)。 石黒氏が平田氏と共同で行なうロボット演劇では、ロボットだけで演劇を行なうのではなく人間も入れる予定だ。それによって「俳優も自分のアイデンティティをいままでとは違う視点で考える。そこが面白い」(平田氏)という。
なるほど演劇の半分は観客が作るものだろうし、ロボットと人間の関係や、ロボットに対する人間の接し方を考える上で、演劇が果たす役割については異議はない。しかしながら、ロボット実用シーンでは、一般客はステージの下から眺めるわけではない。人間もロボットも同じステージにあがることが要求されるのだ。見ることと参加することの間には大きな違いがある。そこに自発的に参加したのか知らない間にステージ上に立たされているのかでも心構えが違うだろう。 講演終了後、このような質問をした記者に対して平田オリザ氏は「観客を驚かせることができなかったら演出家ではない」と自信を見せた。演劇や今頃のロボット工学が、今後の社会に対してどのように踏み込んでいくのか。本誌記者も興味を持って見つめていくつもりだ。 ■URL 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター(CSCD) http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/ ■ 関連記事 ・ 人・ロボットの社会的発達を研究するための子供型ロボット「CB2」 ~「浅田共創知能システムプロジェクト」を訪ねて(2007/08/03) ・ 等身大“コピーロボット”で存在感の本質を追求する ~大阪大学 石黒 浩 教授(2006/08/01) ・ 研究者自身のコピーロボット「ジェミノイド」公開(2006/07/21)
( 森山和道 )
- ページの先頭へ-
|