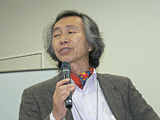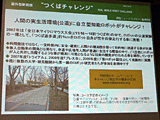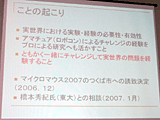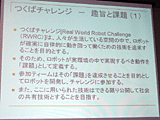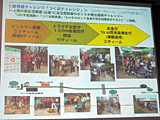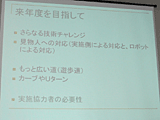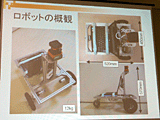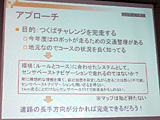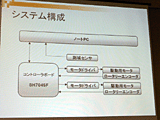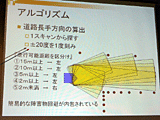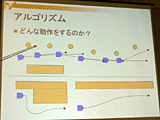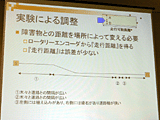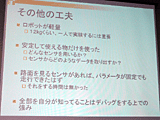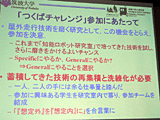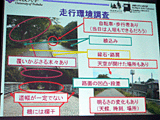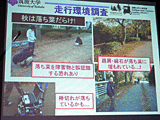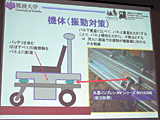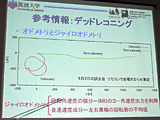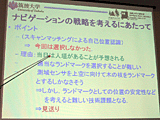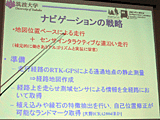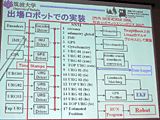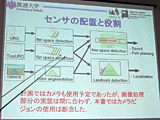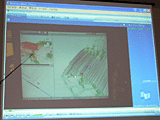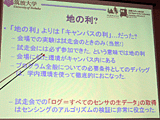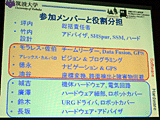|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「つくばチャレンジ」オーガナイズセッションレポート |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● 「つくばチャレンジ2007」とは
「つくばチャレンジ」は、人々が普通に生活する空間の中で、自律走行型ロボットが自律して共存するための技術追求をテーマにしている。2007年11月16日~17日に、第1回目がつくば市で開催された。 33台のロボットがエントリーし、11台が100mのトライ走行に成功した。トライに成功したロボットが1kmの本走行にチャレンジし、3台が課題を達成した。 「つくばチャレンジ2007」については、詳細な「つくばチャレンジ2007」レポートが掲載されている。 2007年の課題は、「つくば市内の約1kmの遊歩道を、外からサポートを受けずにロボットが自律的に目的にまで走行すること」だった。 コースは、公園内の遊歩道で、普通に人や自転車が通行している。委員会がコースを定めた時に、「ここならほぼ直線だから、ロボットも走行できるだろう」と考えたという。だが、実際にロボットを自律走行させるという視点で見ると、「意外とアップダウンがある」「路面状況が場所によって違う」「縁石がとぎれている部分もある」という点がクローズアップされた。途中には3カ所の橋もあり、人が何気なく生活している環境が、いかに変化に富んでいるか改めて気づいたという。
今回のセッションは、つくばチャレンジの参加者を中心に、実世界課題の解決に向けての研究成果を公開して議論を深め、技術の高度化・現実化をはかる目的で開催された。本稿では、つくばチャレンジ実行委員長の油田信一氏による「つくばチャレンジ開催趣旨と課題」と、1km走行を達成した2チームの報告をまとめた。 ● 「つくばチャレンジ」開催趣旨と今後の課題
油田氏が「つくばチャレンジ -趣旨と課題-」を語った。 油田氏は以前から、「ロボット開発において、実際に人が日常生活する中(リアルワールド)で、ロボットの実証実験をして経験を積むことが必要である。実験室の中のような、再現性が確保された環境での実験も学問として必要だが、再現性がないところでちゃんと働くロボットを作ることが一番重要だ。その方法論を確立するためにも、とにかく経験が必要であるというのを、常日頃から感じていた」という。 現在、各地でロボコンが盛んに行なわれていて、学生やアマチュアが高い技術を持って参加している。そうしたロボコンにおけるさまざまなチャレンジと、我々が行なっている研究の違いは、「新しいことにチャレンジしてみよう」という意気込みにあると油田氏は指摘した。 研究者は、どちかというと失敗することが許されない。だが、アマチュアの世界には、たとえ失敗しても新しいことにチャレンジすることを良しとする気風がある。そうしたアマチュア精神をもった方にも「つくばチャレンジ」参加し、技術を披露してもらいたい。その一方で、プロの研究者はプロとして課題にチャレンジする。そうして異なるバックグラウンドの立場の参加者同士で情報交換をしたいと思っているという。 「つくばチャレンジ」は、これまでにない屋外型のロボット競技であるため、事前に参加者のML(メーリングリスト)を設けて意見の交流や質疑を行なっていた。そのMLの中で、「GPSは自然環境と見なすのか?」という点が話題になったという。 これに関しては、GPSに限らずロボットを動かすために、現場環境に何か設備を増設するというのは止める。けれど、すでにある舗装道路を使う、道にある木をランドマークに使う、または近くの民家がたまたま無線LANを使っていたとして、漏れている電波を使うのはかまわないと考える。 ただし、そうしたものは“自然環境”であるから、木は当日に切り倒されているかもしれないし、無線LANは撤去されているかもしれない。あるがままのものは何を使ってもいいが、ロボットを動かすために環境に設備を付加することはしない。ということが前提となったという。 また、リアルワールドで活動するロボットだけに、安全性が一番重要となる。人に恐怖を与えないために、ロボットのサイズや移動速度など最低限のラインを決めた。また、非常停止スイッチは必ずつけることも定めた。 競技を行なう上で、ロボットの移動速度が速すぎても危険だが、遅すぎても困るので、スタートからゴールまでの制限時間(2時間半)を設けたという。 「つくばチャレンジ2007」を開催して、油田氏が一番想定外だったことは、「予想以上に多くの参加者があり、熱心に取り組んでもらえたことだ」と喜びを伝えた。また、開催当日の問題としては、「多くの見学者があり、彼らの行動が読めない」という点を述べていたのが印象深い。 そして競技会を通じて、「やってみたから、判った」ことがとても多かったという。油田氏は、「改めてチャレンジの必要性を強く感じた。チャレンジしたことを互いに評価し、参加経験を共有したいと思っている」と語った。 2008年度の開催については、「より高い課題を設けて技術チャレンジしていきたい」という。課題やコースに関しては、現在、参加者の意見を取りいれながら、つくば市と相談し検討している。 具体的には、もっと、広い遊歩道での実施、カーブやUターンもあるようなコース、またはロボット同士がすれ違う必要があるコースも可能ではないかと考えているらしい。 次回のチャレンジは、「運営側もロボット製作者も、競技見学者に対する対応がより必要になるだろう」と述べた。
● 「移動ロボットによる測域センサを用いたセンサベーストナビゲーション」
「つくろぼ」のサイズは、450×520×570mm(幅×奥行き×高さ)、重量は12kg。前輪駆動でマクソンモーターが2つ搭載されており、ノートPCで制御している。 本体はアルミフレームで組立、前輪はキックボードの直径155mmの空気タイヤを使用。後輪はキャスタを使い軽量化に努めたという。電源には12V5Aの鉛蓄電池を用いている。外部情報を取得するために測域センサーは、北陽電気から提供を受けたTop-URGを搭載している。 「つくばチャレンジ2007」に参加した多くのロボットが、GPSや測域センサーなど多くのセンサーを搭載しているのに対して、「つくろぼ」は、測域センサだけのシンプルな構成になっている。「つくろぼ」は、なぜ、測域センサだけで完走できたのだろうか? 大島氏は、「移動ロボットによる測域センサを用いたセンサベーストナビゲーション」をテーマに報告した。 大島氏は、「つくばチャレンジのコースを完走する」という目的に向けて、ロボットとシステムの開発を行なった。そのために、今年はロボットが自走するための交通整理が行なわれること、また地元開催でコースの状況をよく知っているという利点を有効に使ったという。
「つくろぼ」は、コースのマップを持っていないという。大島氏は、「1kmの限られた距離ならば、コースとルールに合わせたシステムを開発すれば、センサベーストナビゲーションだけでも走れるのではないか?」と想定し、基本的には、ロボットが前進するための道路の長手方向がわかれば完走できるだろうと考えたという。
この時、つくばチャレンジでは、道路の左側を走行することが決められているので、「つくろぼ」は左側と右側に別々の距離を設けている。 左側は障害物とロボットの距離を750~2,000mmの可変とし、右側は走行に必要最小限の650mm固定としている。その長方形の幅がどこまで伸ばせるか?(長手方向)を算出し、一番長いルートを走行可能距離としている。 道路の長手方向を算出する時は、測域センサのデータを元に、±20度きざみで前述の走行可能距離を計算している。【写真A】の場合、走行可能距離が長い4方向を得ることができる。 複数の長手方向からルートを選択するロジックには、15m以上の走行可能距離が複数ある場合は、その中から一番左のルート、なければ10m以上の中で一番左…というように決定しているという。 また、2m未満の走行可能距離しかなかった場合は、右へ旋回するという例外処理をしている。 上記アルゴリズムで、簡易的な障害物回避が行なわれている。
【写真B】下の図のように、もし前方に障害物があった場合は、ロボットは右側に回避する。また、左側の障害物とロボットの離れた時には、左方向20度の角度でロボットはなだらかに左に寄っていく。 大島氏は、「試走会に参加した結果、左側の障害物とロボットの距離を場所によって変える必要があることが判った」という。 スタートから直線200m程度の区間は、木々と道路の間隔が広かった。だが、700m位の位置にも道が左側に広がっていて、障害物までの距離が長い場所があった。また、植え込みと縁石の間隔が狭い場所もある。 それぞれの場所で、障害物とロボットの距離(【写真C】のA部分)を変える必要があった。「つくろぼ」は、スタート地点からそうしたチェックポイントの距離を計測するために、ロータリーエンコーダから走行距離の累積を得ている。 大島氏は本来、「カメラを使って自己位置を知る」をテーマにして研究を行なっている。「つくばチャレンジ」も、当初は画像認識を計画していたという。 春~夏には画像認識の搭載を検討していたが、夏に現地を見学したところ、人工物が少なく木や土しかないため画像認識の難しさを感じたという。カメラを下方向に向けて教示再生という方法を考え、テストを行なったが、試走会6回目の時点で秋になり、路上に落ち葉がたくさん落ちていた。落ち葉の影響は無視できないと判断し、このままでは走れないという結論になって、Top-URGによる長手方向算出でチャレンジすることになったという。 大島氏は、「実環境でロボットを動かすには、センサからよいデータを取得することが特に重要であった」と、今回のチャレンジで得た結論を語った。
● 「屋外走行ロボットのシステムインテグレーション」
坪内研究室では、数年前からGPSで屋外走行をするという研究を始めていたため、「つくばチャレンジ」を非常にいいチャンスと捉え、これまでの技術を試す機会として出場を決めたという。 ちなみに、ロボットの名前は1台目が「一坪」バックアップで用意した2台目が「二坪」という。 前述の大島氏が製作した「つくろぼ」が、今回のコースを走行することに特化したシンプルな構成のロボットであるのに対して、「屋外組」は、もっと広い範囲で普遍的に活動できるロボットを目指して開発した。となると、一人二人でできるプロジェクトではないため、10名でチームを結成して取り組んだという。 ロボットを開発するにあたり、事前に走行環境を調査したという。コース内には木が路上に覆い被さっていて、GPSが使えるかどうか判らない場所もある。また、路肩や縁石を見れば走行できるかもしれない、道幅は一定じゃない、などと、つぶさに見て判断した。 路上に木が落ちていると、ロボットはひっくり返ってしまう。そのため障害物を避けるためにセンサーで検出する必要があるが、落ち葉を障害物と認識しては困る。このような条件にあう解析を考えたという。
ロボットの基本的なCPUは、ToughBookを使用している。カメラで画像処理を行なうことも検討したが、秋になり路肩の木々が紅葉したら処理がうまくいかなくなったので、直前にカメラの使用を中止した。センサーには、北陽電機のTop-URGと普通のURGを搭載している。 実際に、石畳のガタガタ道を走らせてみると1G位の衝撃があることがわかった。試走会の時に振動でUSBのコネクタが緩んで外れたこともあり、ネジで固定するタイプのものを探した。また、普通のHubを使ったところは、ホットメルトで固定、URGのコネクタ部分も固定し、当日のトラブルに備えた。ロボット本体にも、振動対策を行なったという。 ロボットのナビゲーション戦略を考えるにあたり、GPSの受信状態が悪くても走れるシステムを構築する必要があった。ランドマークによる自己位置修正を行ない、自己位置の誤差が大きくなっても、道路沿いに走行できるようにする。また、予期せぬ障害物に衝突しないようにすることも基本としたという。 今回は、スキャンマッチングによる自己位置認識の方法は見送った。地図位置ベース走行による走行とセンサインタラクティブな道沿い走行を補完的に働き合うアルゴリズムと実装に留意した。 地図位置ベースというのは、事前にコース上を測量し、自己位置修正が可能なランドマークを取得しておくという手法をいう。実際には、縁石の縁を抽出している。 ロボットに搭載するセンサの配置は、TOP-URGは4m前方が見えるように下に向けている。ロボットの直前部分は、普通の測域センサで、障害物や人の検知を行なっている。近くに障害物が入った時はスピードを落とすなど安全のためのアルゴリズムを作成したという。
ナビゲーション戦略が複雑なため、ソフトウエアは分担して開発しなくてはならない。その際、デバッグを効率よく行なえる方法を考えなくては、開発が間に合わなくなる。そこで、分離実装しやすい構造化として、アドバイザとして参加している竹内氏が以前から提案している方法を取り入れたという【写真D】。 SSM(センターセルフマネージャー)という共有メモリを置き、生データや加工しても後で使えそうな5秒~10秒分のデータをSSMに置いておく。SSMからDataLoggerを取っているので、研究室に帰ってから、DataLoggerに値を与えることでアルゴリズムのデバッグを行なうことができる。 また、タイムスタンプをデータが来る毎においているので、非同期でデータがきてもタイムスタンプで補完することで任意の推定値を取ることができる。 センサは、落ち葉等があっても路面が検出できるアルゴリズムを作成した。カメラは使っていないので、ロボットはGPSによる情報と、測域センサによる障害物と縁石沿いを認識して走行を行なった。 実際には、本走行時はGPSの受信状態が悪く、橋の上で使えたくらいでほとんど使っていなかったという。ロボットがゴール手前80cmで停止してしまった原因は、自己位置認識が狂ったためだと、坪内氏は語った。
坪内氏は、今回の課題をクリアできた理由のひとつに、「会場が近いため試走会に必ず参加できた」と“地の利”をあげた。大学がコースの遊歩道とつながっていて、キャンパス内に会場に似た環境があったことが利点となったという。 試走会で得た貴重なデータは、全てのログに残して後で再生できるようにしていた。このログのおかげで、プログラム全般においてデバッグがしやすく、問題点をひとつひとつ徹底的に解決したことが、課題達成の勝因だったとまとめた。
■URL つくばチャレンジ http://www.robomedia.org/challenge/index.html ニューテクノロジー振興財団 http://www.robomedia.org/main.html ■ 関連記事 ・ 「つくばチャレンジ2007」レポート ~初開催で、33台のエントリー中3台が完走(2007/12/11)
( 三月兎 )
- ページの先頭へ-
|