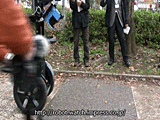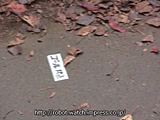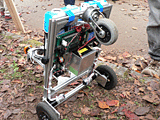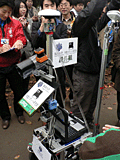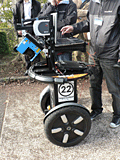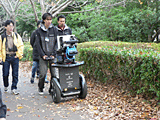2007年11月16日~17日、自律型ロボットによる屋外競技「つくばチャレンジ[Real World Challenge(RWRC)]」が開催された。つくばチャレンジは、人々が生活している空間(つまりリアルワールド)の中で、ロボットが確実に自律的に動き回って働くための技術の追求をテーマに、今年初めて開催されたものだ。主催は、財団法人ニューテクノロジー振興財団である、同財団は、長年にわたってマイクロマウス大会を主催してきており、今回のつくばチャレンジ2007は、第28回全日本マイクロマウス大会の併催イベントとして行なわれた。
つくばチャレンジでは、毎回、ロボットが実環境の中で実現するべき動作を「課題」として定義し、その課題を達成させることを目的とする。2007年度の課題は、つくば市内の約1kmの遊歩道を、外部からのサポート受けずに自律でゴールまで走行することである。いわば、マイクロマウスの屋外版だと思えばよい。
走行するコースは、新たに用意されたものではなく、普段から人間や自転車が利用している道である。今回は1回目ということもあり、基本的にほぼ直線的なコースではあるが、細かな凹凸やアップダウンはもちろんある。また、途中で橋を3回渡る必要もあり、人間には何でもない道であっても、ロボットが自律で走行するのはそう簡単なことではない。今回の走行ルートはこちらを参照していただきたい。
こうした大会は自律型ロボットとしては、日本初の挑戦であり、あくまで速さを競う「競技」ではなく、人と環境に対する安全性・親和性を課題として最重視することも特徴だ。
● 100mのトライアル走行を11台が達成
まず、11月16日にトライアル走行(100m)が行なわれたので、その様子からレポートしよう。トライアル走行は、本走行のコースの最初の100mだけを走らせるもので、100mを完走できたロボットのみが、翌日の本走行に出場する権利を得る。つくばチャレンジ2007には、大学の研究室や研究機関、企業、個人など、当初の予想を上回る多くのエントリーがあり、エントリー台数は合計33台となった。そのうち6台は棄権となり、トライアル走行に挑戦したのは27台だ。トライアル走行は、2回のチャンスがあり、1回目の走行で成功したロボットは2回目にチャレンジする必要はない。実際には、2回の走行で惜しいところまで進んだロボットに対しては、3回目のチャンスが与えられた。

|

|

|
|
トライアル走行のコース。遊歩道の左側を進むことが推奨されているが、中央より右側を走行してもペナルティなどはない。奥のほうは上り坂になっているが、トライアルでは坂の手前がゴールとなる
|
道の両端にはかなり落ち葉や折れた小枝などが積もっており、小型のロボットに対してはかなりの難関となっていた
|
ゴールとなる100m地点の目印。途中からはわかりやすいように赤いテープがゴールラインに貼られた
|
1回目の走行で成功したのは全部で7台、2回目の走行で成功したのは1台、3回目の走行で成功したのは3台となり、合計11台のロボットがトライアル走行を達成した。これは、油田大会委員長の予想を大きく上回る成果だという。
トライアル走行の100mの区間はほぼ直線で、アップダウンや橋などもないが、折しも季節は秋で、遊歩道には落ち葉がかなり積もっており、落ち葉に乗り上げてタイヤが滑ってしまい、うまく進めなくなってしまったロボットも見受けられた。
今回、つくばチャレンジにエントリーしているロボットの多くは、4輪あるいは3輪の車輪を持つ、車型ロボットであったが、セグウェイの走行ロボット開発支援プラットフォームである「Segway RMP」を利用した2輪ロボットやリンク機構を利用した多足ロボット、本物の三輪車を人型ロボットが漕ぐことで進むといったユニークなロボットも見られた。
ロボットのサイズは、数十cmクラスの小型のものと、1m前後の大型タイプに二極化されていたが、小型ロボットでは車輪も小さくなるため、路面の細かな凹凸を超えるのもなかなか大変であったようだ。逆に、走破性が非常に高く、縁石を乗り越えて植え込みまで進んでしまうロボットもあった。
なお、安全性などの観点から、最高時速は人間の歩行速度とほぼ同じ4kmに制限されており、非常停止スイッチ(重量が15kg以下の場合は不要)を設けることが求められている。

|

|
|
Suruga 丸 GT(代表者名:八木健吾氏)のロボット。模型自動車をベースにしているようで、かなり小型だ。上に乗っているノートPCは、10.4型液晶搭載のLet'snote Rシリーズ
|
Suruga 丸 GTのロボットは、走行開始直後に左に大きく曲がり、縁石にぶつかってリタイヤしてしまった
|

|

|

|
|
芝浦工業大学ヒューマンロボットインタラクション研究室(代表者名:水川真氏)のロボット。サイズは比較的大きい
|
【動画】芝浦工業大学ヒューマンロボットインタラクション研究室のロボットのトライアル走行の様子。この動画は1回目のトライアルだが、惜しいところでリタイヤ
|
【動画】芝浦工業大学ヒューマンロボットインタラクション研究室のロボットのトライアル走行の様子。最後のチャンスである3回目の走行でゴールに到達した
|

|

|

|
|
かぴばら(代表者名:中川友紀子氏)のロボット。本物の三輪車を人型ロボットが実際にこいで進むという、ユニークな機構を採用。普段目にする形状であり、実環境に違和感なく溶け込める
|
【動画】かぴばらのロボットのトライアル走行の様子。残念ながらスタートから3m程度進んだ場所で、それ以上進まなくなってしまった
|
【動画】PROJECT AKIRA(代表者名:葛武志氏)のロボットのトライアル走行の様子。やはり走行開始直後に左に曲がってしまった
|

|

|
|
つくば大学知能ロボット研究室屋外組(代表者名:坪内孝司氏)のロボット。GPSやDGPS用ビーコンアンテナ、測域センサー、カメラなど、多くのセンサーを搭載している
|
【動画】つくば大学知能ロボット研究室屋外組のロボットのトライアル走行の様子。3輪タイプで、移動速度もかなり速く、安定した走行を実現。1回目の走行で見事100mを走破した
|

|
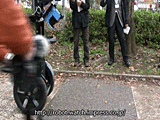
|
|
日本SGI(代表者名:五十嵐広希氏)のロボット。走行ロボット開発支援プラットフォームの「Segway RMP」を利用しており、走行安定性は抜群だ
|
【動画】日本SGIのロボットのトライアル走行の様子。いわゆる2輪の倒立振子タイプのロボットであり、1回目のトライアルで100mの走破に成功
|

|

|

|
|
東京農工大学ロボット研究会R.U.R.(代表者名:黒田啓史氏)のロボット
|
【動画】東京農工大学ロボット研究会R.U.R.のロボットのトライアル走行の様子。1回目の走行では、縁石にぶつかってリタイヤしてしまった
|
【動画】東京農工大学ロボット研究会R.U.R.のロボットのトライアル走行の様子。最後のチャンスとなる3回目の走行で見事100mを走破。サイズのわりに速度は速く、途中で何度か停止してまた動き出すことが特徴
|

|

|

|
|
【動画】SHINOBI(代表者名:宮澤克規氏)のロボットのトライアル走行の様子。走破性が非常に高く、街路樹の植え込みに乗り上げたりしているが、また道に復帰し、1回目の走行で100mを走破
|
Meiji Robotic Systems(代表者名:黒田洋司氏)のロボット。GPSや測域センサーを搭載している
|
【動画】Meiji Robotic Systemsのロボットのトライアル走行の様子。安定した走行で、見事1回目で100mの走破に成功した
|

|

|

|
|
宇都宮大学尾崎研究室(代表者名:小池琢也氏)のロボット。測域センサーやカメラを搭載。後ろにはデスクトップPCを丸ごと搭載するなど、かなり大型のロボットだ
|
【動画】宇都宮大学尾崎研究室のロボットのトライアル走行の様子。こちらも1回目で100mの走破に成功している
|
【動画】CIT/Access Pelican(代表者名:小柳栄次氏)のロボットのトライアル走行の様子。クローラータイプのロボットで走破性は高いが、街路樹に向かって行ってコースアウトしてしまった
|

|

|
|
関東相撲ロボット研究会(代表者名:高橋勝氏)のロボット。比較的小型のロボットで、左側にセンサーアームが伸びている
|
【動画】関東相撲ロボット研究会のロボットのトライアル走行の様子。速度はかなり速いが、だんだん左にそれていってしまい、最後は縁石にぶつかってリタイヤしてしまった
|

|

|
|
東大生産研橋本研(代表者名:橋本秀紀氏)のロボット。地磁気センサーや超音波センサー、測域センサーを搭載している
|
【動画】東大生産研橋本研のロボットのトライアル走行の様子。2回目の走行で、100mの走破に成功
|

|

|
|
ロボット工房(代表者名:大河原正氏)のロボット。車輪で走行するロボットが多い中、リンク機構による多足ロボットで出場。8足で歩く姿は昆虫を思い浮かべる
|
【動画】ロボット工房のロボットのトライアル走行の様子。ロボットが小型なので、移動速度はかなり遅い。残念ながら右にそれていってしまいリタイヤ
|
● 1kmの本走行では3台が課題を達成、時間は20分台
11月17日には、前日のトライアル走行を達成した11台のロボットが1kmの本走行に挑戦した。本走行は1回のみ挑戦が可能であり、途中でスタックしてしまった場合は、記録はそこまでとなるが、データ取りのためなどにその後も走行することが許される。コースは途中でアップダウンや微妙なカーブがあるほか、路面もアスファルトの部分と石畳の部分があり、陸橋を3つ越えなくてはならず、トライアル走行に比べて難易度が向上している。また、17日は土曜日ということもあり、前日のトライアル走行に比べて観客も多く、ロボットにとってはより過酷な条件となった。
トライアルのタイムがよかった順に5分間隔で順次スタートしたが、1km先のゴールに到達したロボットは、金沢工業大学チーム(代表者名:岩崎健吾氏)、筑波大学知能ロボット研究室つくろぼチーム(代表者名:大島章氏)、筑波大学知能ロボット研究室屋外組(代表者名:坪内孝司氏)の3台であった。最初に述べたように、つくばチャレンジは、時間を競う競技ではなく、特に順位は付けないとうことだが、タイムはそれぞれ、28分9秒、23分45秒、23分であった。Meiji Robotic Systemsチーム(代表者名:黒田洋司氏)のロボットは半分以上の530mまで到達したが、残念ながらそこで植え込みから脱出できず、リタイヤとなってしまった。
今回、課題を達成した3台のロボットのうち、金沢工業大学と筑波大学知能ロボット研究室屋外組の2台は、GPSや測域センサーなど多くのセンサーを搭載した大型ロボットであるが、筑波大学知能ロボット研究室つくろぼチームのロボットは、測域センサーのみというシンプルな構成で、サイズも小さい。他のロボットは、数名で協力して製作されているのに対し、つくろぼチームのロボットは大島氏が一人で製作したという。製作コストも、本走行に進んだ11台のロボットの中では最も安いと思われるが、見事に1kmを走破し、課題を達成したのは素晴らしい。
実は、金沢工業大学と筑波大学知能研究室屋外組のロボットは、GPSで絶対位置を取得しており、ゴールに到達したと判断したら、自動的に止まるように設計されていた。しかし、GPSには誤差があるため、ゴールの数m手前で停止してしまい(課題は達成したとされた)、1kmのゴールラインを越えていったのは、つくろぼチームのロボットだけであった。

|

|

|
|
スタート地点からコースを眺めたところ。最初の橋の坂もかなり急に見える
|
これが最初の橋。街路樹がなくなり、周囲の環境も変わる
|
コース半ば。2つめの橋の手前で左にやや曲がっている
|

|

|
|
コース終盤。ここでも左にクランク状に曲がっている
|
ゴール直前。最後は一直線で道も平坦だ
|

|

|

|
|
北陽電機・産総研ジョイントチーム(代表者名:川田浩彦氏、冨沢哲雄氏)のロボット
|
北陽電機・産総研ジョイントチームのロボットは、トライアル走行では最もタイムがよかったが、本走行では90m地点で縁石に乗り上げ、リタイアしてしまった
|
【動画】北陽電機・産総研ジョイントチームのロボットの本走行の様子。途中までは順調であったが、90m地点でリタイアしてしまった
|

|

|

|
|
金沢工業大学(代表者名:岩崎健吾氏)のロボット。安定した走行で、見事1kmを走破。タイムは28分9秒であった
|
金沢工業大学のロボットの本走行の様子。後ろにぞろぞろ関係者や観客がついて行っているのも面白い
|
金沢工業大学のロボットの本走行の様子。1つめの橋も問題なくクリアした
|

|

|
|
コースも後半。ガードレールがないので、左側に寄りすぎても危ない
|
【動画】金沢工業大学のロボットの本走行の様子。最初の橋を渡っているところ
|

|
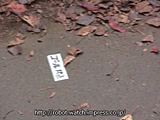
|
|
【動画】金沢工業大学のロボットの本走行の様子。コースも後半に突入
|
【動画】金沢工業大学のロボットのゴールシーン。本当のゴールは手前のシールが貼ってあるところだが、その数m前で停止してしまった
|

|

|

|
|
筑波大学知能ロボット研究室つくろぼ(代表者名:大島章氏)のロボットの本走行の様子。見事1kmを走破した
|
【動画】筑波大学知能ロボット研究室つくろぼのロボットのゴールシーン。ゴールの目印のシールの横を通過していった
|
筑波大学知能ロボット研究室つくろぼのロボット。センサーは測域センサーのみというシンプルな構成だ
|

|
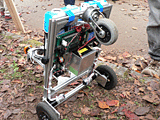
|
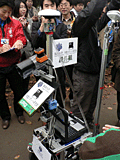
|
|
今回参加した多くのロボットが搭載していた北陽電機が開発中の測域センサー「Top-URG」。北陽電機からつくばチャレンジ参加者に製品モニターとして提供されている
|
筑波大学知能ロボット研究室つくろぼのロボットの背面。すべてを大島氏一人で製作したという
|
筑波大学知能ロボット研究室屋外組(代表者名:坪内孝司氏)のロボット。23分で見事1kmの走破に成功した
|

|

|
|
Meiji Robotic Systems(代表者名:黒田洋司氏)のロボットの本走行の様子。530m地点まで到達したが、ここで植え込みから脱出できなくなってしまった
|
東大生産研橋本研(代表者名:橋本秀紀氏)のロボットの本走行の様子。20m地点でリタイヤしてしまったが、それ以降はデータ取りのために走行させている
|

|

|
|
東大生産研橋本研のメンバーと油田委員長。記録は20mだが、リスタートさせてゴールまで到達した
|
【動画】東大生産研橋本研のロボットの本走行の様子。リスタート後だが、橋も上手にわたっている
|
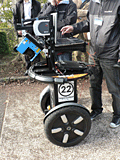
|
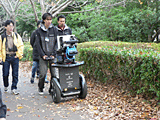
|

|
|
日本SGI(代表者名:五十嵐広希氏)のロボット。Segway RMPを利用しており、ノートPC2台を載せても、駆動トルクには十分余裕がある
|
日本SGIのロボットは、220m地点でリタイヤしたが、その後リスタートさせてゴールまで到達した
|
【動画】日本SGIのロボットの本走行の様子。リスタート後だが、さすがに歩行は安定している
|

|

|
|
芝浦工業大学ヒューマンロボットインタラクション研究室(代表者名:水川真氏)のロボットの本走行の様子。記録は250mである
|
【動画】芝浦工業大学ヒューマンロボットインタラクション研究室のロボットの本走行の様子。最初の橋の手前の段差をなかなか上れず苦労している
|
つくばチャレンジは、今回が初開催であったが、3台のロボットが課題を達成するという、委員会の予想以上の結果となった。ロボットによって、経路を決定するアルゴリズムが異なるため、ほぼ直線状のコースとはいえ、移動の仕方にはそれぞれの特色が出て、見ていてもなかなか面白かった。
つくばチャレンジ委員会によれば、つくばチャレンジは、実環境で活躍できるロボットの実現を目指すために、毎年、課題のレベルをアップしていく予定だという。単に距離を長くするというのではなく、道の途中で何か目的のものを見つけて運んだりするなど、チャレンジという名に恥じない、挑戦的な課題を設定していきたいとのことであり、来年の開催が楽しみだ。
■URL
つくばチャレンジ
http://www.robomedia.org/challenge/index.html
ニューテクノロジー振興財団
http://www.robomedia.org/main.html
( 石井英男 )
2007/12/11 15:16
- ページの先頭へ-
|