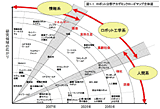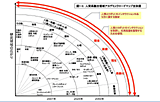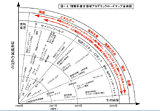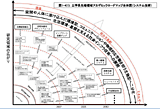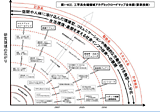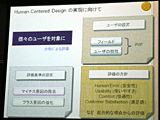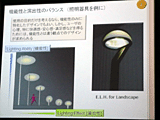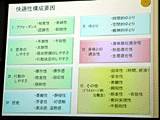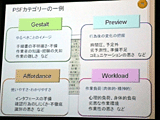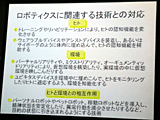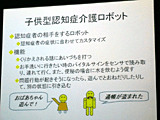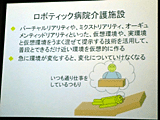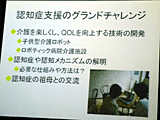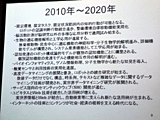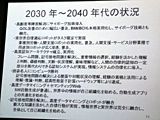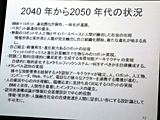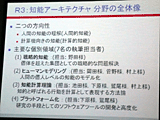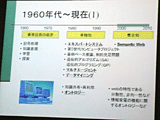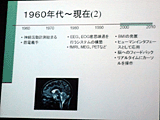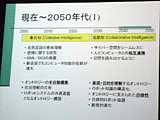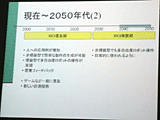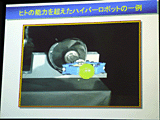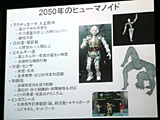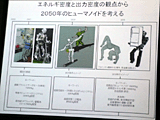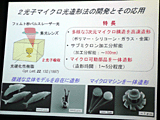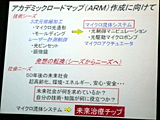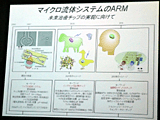|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
未来のロボット技術を占うアカデミックロードマップ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9月13日から15日の3日間、千葉工業大学の津田沼キャンパスにおいて、第25回日本ロボット学会学術講演会が開催された。「ロボット研究と実用化」をメインテーマに、多様化したロボット工学関連の研究者が一堂に会し、最新の研究成果を公表した。ここでは一般公開セッション「2050年のロボット社会に向けて」と題されたジョイントパネルの模様や、研究成果を展示したブースについて報告する。
まず、日本ロボット学会会長の佐藤知正氏(東京大学大学院 情報理工学研究科知能機械情報工学専攻 教授)が冒頭挨拶。「ロボットには3つの役割がある。それはヒトを知る、ヒトの役に立つ、ヒトを感動させるということ。ロボットの研究は原理だけではない。サイエンスがあり、心理学などさまざまな分野に広がっている」と述べた。 人間社会の理解を深めることは、人間系融合領域で強く出る部分だ。役に立つという観点では、社会問題やニーズに応えることが重要になる。また佐藤氏は、「人間へのラスト1mは、形と動きを持ったロボットしかないと思っている。それを強く意識して、工学系先端領域、あるいは情報系複合領域でのレポートができた。ヒトを感動させるロボットの役割も研究、教育、意識高揚という点から大事な教材であり材料になる。今後さらに新しいプロジェクトも育っていくだろう。ARMの議論が、これらの役割の一助になれば幸いだ」と抱負を語った。 次に、日本ロボット学会RT学術技術融合調査研究委員会、委員長の内山隆氏(富士通研究所)が、「2050年のロボット社会に向けた展望」をテーマに、ARMの全体概要について説明した。 ARMは、2050年という長期的な視野でロボットの研究領域やターゲットを明確化することで新たな研究課題を提示し、ロボットが将来社会にどのような役割を果たせるのか、あるいは貢献できるのか、という点について考えるものだ。また、ARM以外の技術戦略マップや産業界のロードマップと連携することで、基礎から応用までの研究・開発を連続的なプロセスとして方向付ける狙いもある。「これらによりナショナル・イノベーション・システムを構築していく」と内山氏は説明する。 ARMの策定は、昨年5月の検討準備会を皮切りに、日本人間工学会、人工知能学会、日本ロボット学会という3団体の委員会が連携・協力して開始。人間・知能・ロボットという異分野が融合した将来動向を探る「人間系複合領域ARM委員会」、ロボットと知能に関してITとRTの複合化による知的進化をさぐる「情報系複合領域ARM委員会」、ロボット最先端工学から将来のロボット進化を探る「工学系先端領域ARM委員会」が、それぞれの学会を中心に発足(人間系は3学会による構成)。そして、この3月にARMとして報告書がまとまった。 ARM全体のロードマップは【写真2】のとおりだ。さらに各領域をブレークダウンしたARMは【写真3】【写真4】【写真5】【写真6】のようになる。共通テーマとして、エネルギー、環境、食料生産、高齢化社会、福祉、医療といった問題が挙げられている。 今回のARM策定は、3つの学会の横断・連携という点で意義が大きい。異分野領域が融合することで、新たな研究領域と価値の創出が期待できるからだ。冒頭の佐藤氏の言葉のように、次世代ロボットの範疇は、その原理面だけでなく、人間との共生、家庭・社会システムまでを内包する広範な領域に渡る。異分野からの課題や技術が融合することで、ブレークスルーの創出を目指すという。以下、本セッションで発表された3学会による2006年度調査検討結果を中心に報告する。
● 社会ニーズと多様な技術に対して橋渡しをする人間系融合領域ARM 最初のプレゼンターは、日本人間工学会から、慶応義塾大学の富田豊氏(理工学部教授、人間系融合領域ARM委員長)が登壇。「人間工学とロボット社会」をテーマに、人間系融合領域ARMの概要について説明した。富田氏はARMの性格について、「ARMは一般企業や行政がつくる戦略的ロードマップとは異なるユニークな役割を担っている。教育・研究機関がつくるロードマップとも異なるものになっているはずだ。学術団体は、革新性の中軸を考えて、技術によって未来世界を描くことに長けている。また基礎技術に対する確かな目と、将来技術についてバランスのとれた目を持っている」と述べた。 その一方で、本来ロードマップは有限の時間内に有限の資産(資金)を投資し、最大の成果を得るための優先付けと事業プロセスを示すものであり、学術団体では投資する資産を持っていないという弱点も指摘。では、そういった学術団体がARMづくりを通じてどのような役割を担えるのであろうか。 富田氏は「将来の社会ニーズを明らかにすること。それを満たす基盤や革新的な技術や、合理的に技術開発を行なう上でのプロセスを明らかにすることもできる。長期的な視野に立った指針を産業界や行政側に与え、技術開発に対して自身がリーダーシップを取る機会を得られる」と、ARMの役割について強調する。特に人間系融合化領域は、「変化する社会ニーズと多様化する技術に対して橋渡しをする、触媒的な働きを果たせる」と見ている。 人間系融合化領域では合計20もの重要な要素が挙げられているが、その中で最も重要と思われるのは「人間・機械融合分野における教育の必要性だ。言葉、文学、歴史などの学習と同じ様に、若い頃からこの分野を学ぶことで見識を深めてもらいたい。倫理面でも、技術として実現できることなら何でもやってよいのか、どこでコントロールするのか、といった点も常に意識しておかなければならない」とした。 いずれにしてもARMの策定は新しい時代を象徴する試みだ。富田氏は「いままで疎遠だった学会同士が連携しあって意見交換をすることでARMを策定できた。今後は、企業や行政側とのコミュニケーションを広げ、日本のみならず発展途上国や世界にも役立つ指針をつくっていきたい」と語った。 ● 機械の知能化により、人間と機械との関係性も変わる 慶応義塾大学の岡田有策教授(理工学部助教授)は「人間とシステムとの調和」と題する発表を行なった。「ロボットは従来の機械とは異なる特徴があり、利用者となる人間や社会にとって、安全・安心・快適といったキーワードを満たす観点から多角的に検討しなければならない」と強調した。たとえば、人間とロボットのインタラクションにおける基本的な技術課題として、ロボットから呈示される情報がどのような表示媒体によって行なわれるのか、逆に人間からロボットへの伝達はどのような情報や手段を使うべきか、あるいはロボットが受け取った情報をどのようなタイミングや形式で人間にフィードバックすればよいか、といったことが挙げられるという。 こういった課題を考える際に必要となるのは「Human Centered Design」の考え方だ。岡田教授は「人間と機械の関係性を考える場合に、あくまで人間主体で考えていきたい。どのような対象のユーザーやシチュエーションで利用されるのか、結果としてそれがどう評価されるのか、総合的に見て判断していくことが重要」と述べた【写真7】。 人間の行動はさまざまな要因によって影響を受けるが、状況や環境が変化することで、同一行動でも異なった結果になる場合がある。人間工学の分野では、行動に影響を与える要因を「行動形成要因」(PSF:Perfomance Shaping Factor)と呼び、このPFSと行動の関係を明らかにすることで、ユーザービリティや人的エラーを低減できるとしている。これは、マイナス面だけでなく、人間の快適性や満足感など、プラスとなる影響を研究する上でも重要な考え方だ。 たとえば、照明器具では「明るさ」といった機能性だけでなく、概観を考慮した「演出」や「デザイン性」が求められることもある【写真8】。デザイナーによって意図される演出・デザインが、ユーザーに対してどのような影響を与えるのか検討することも、人間工学の大きな課題の1つだ。
岡田教授は、このようなPSFの概念から人間の快適さに影響する要因と例を挙げた【写真9】。大規模システムに対するインターフェイスの快適性を考える場合は、「さまざまなタッチオペレーションやGUIがあり、一般的に単純化、知覚化などの要因から、作業者の意思決定や思考過程、特に認知的な部分を考えていくことが重要」とした。また、ロボットのように機械自体が知能化してくると、人間側の考え方も大きく枠組を変える可能性があるため、人間と機械との関係性を改めて再考する必要が出てくる。 もちろん人間工学の観点からは、機械の事故やトラブル、人的エラーなどの対策も重要だ。人間の行動要因としてPSFをしっかり分析することで、このような原因も見えてくるという。たとえばPSFのカテゴリとして、「Gestalt」(すべきことのイメージ)、「Affordance」(使いやすさ、分かりやすさ)、「Preview」(行為後の変化の把握)、「Workload」(肉体的・精神的な負荷)という4つの観点からさまざまな問題点を明らかにすることができ、実際に対策が講じられるようになってきたそうだ【写真10】。このような手法を活用することで、作業現場にロボットが導入された場合に、安全面での問題などをクリアできるようになると考えている。
● 認知障害の支援に役立つロボティクスの将来を考える 次に、東京大学の大武美保子氏(人工物工学研究センター助教授)が、「認知障害支援ロボティクス」をテーマとして発表を行なった。高齢者が認知障害になると、感覚から取り入れた情報を加工・統合して行動するような脳の高次な働きができなくなる。大武氏は、現在のロボティクス技術を発展させることで、認知障害や認知症に対し、具体的にどのような支援が可能になるかという点を中心に研究を進めている。認知症支援の方法としては、「ヒト」「環境」「ヒトと環境の相互作用」という3つの観点から解決策を考えているそうだ【写真11】。まずヒトの観点では、トレーニングやリハビリによって認知機能を変化させる、あるいはウェラブルデバイスやアシストデバイスを装着したり、体内に埋め込んで認知機能を補助するというアプローチだ。これはヒトに改変を加える技術ともいえる。 環境の観点では、仮想環境を構築したり、実環境に仮想環境を反映させる、ユビキタスデバイスを環境に埋め込んでモニタリングしたり、ヒトに適用するように環境を知能化する技術などが挙げられる。ヒトと環境の相互作用については、癒し系ロボットなどを導入して精神状態を安定させたり、異常行動を抑制する技術が考えられるという。 大武氏は、認知症支援のアプローチの1つとして「子供型介護ロボット」と「ロボティクス病院介護施設」を中心に論じた。子供型介護ロボットは、前述の「ヒトと環境の相互作用」にあたるもの。認知症者の症状に合わせてカスタマイズすることで、きめ細やかな介護が可能になるという。 たとえば、繰り返される話にあいづちを打ったり、トイレなどに行きたい時にバイタルサインをセンサで読み取って連れていく、現実と異なることを語るなど問題行動が起きそうなときには注意を喚起して、別行動に引き込むめるようにする【写真12】。また、ロボットのデザインを子供型にすることで、認知症者に対し威圧的に命令するのではなく、おねだりする子供に接するような対応を誘発することも可能になるという。 病院で寝たきり状態になると、短期間に認知症が進むことがある。急に環境が変化して、その変化に付いていけない場合には急激な記憶障害も起こる。そのような場合には、環境をできるだけ普段と変わらないようにすることで、認知症の発症を抑えることが期待できる。具体的にはロボティクス病院介護施設にバーチャルリアリティやミクストリアリティなどの仮想化技術を導入し、「病院内仮想在宅環境」を作り出せれば、問題を解決できるという【写真13】。
同様に寝たきり状態になると、外部環境との相互作用が制限され、受身の状態になって認知症が進むケースもある。これは、自己意思によって外部環境に影響を及ぼす「意思作用感」がなくなることが原因だと考えられている。そこで、最近注目を集めているBMI(Brain-Machine Interface)技術を活用して、認知症者自身が外部環境に対して、脳波や筋電位などで手足のように動くロボットを直接操作できるようにすれば、認知症を抑止できるようになるかもしれない。 また、認知症者にRFIDタグやウェアラブルデバイスなどを装着してもらう。病院内には受信機を埋め込んだり、タッチセンサやカメラを設置して行動履歴(日時・場所・状況)を記録する。認知症者が現在の自分の状況をうまく認識できない場合には、これらの情報をモニタや壁に繰り返し呈示すれば、現実世界との橋渡しをすることも可能になる。
● 情報と実世界を結合する媒体としてのロボットの役割 続いて人工知能学会のメンバーが情報系複合領域ARMの取り組みを発表した。情報系複合領域ARMの委員長である淺川和雄氏(富士通研究所)は、「これまでの50年の技術を振り返り、その連続性の中から今後を予測する方針で100年ロードマップを作成した」と語った。過去50年については、認知・脳科学・インターフェイス、知能システム・ロボット、サイバーワールド(知能システムから情報基盤まで含む)という3分野について大きく分けて考えたという。一方、以降、未来の50年については、これらが融合して実世界に応用されるという観点からARMを作成したそうだ。 1960年から1980年までの20年間の潮流は、直接記述・指示に従う自動システムとしてロボットが登場してきた時代だという。つまり、さまざまな処理を計算機に搭載することが主眼であり、それをどのようにプログラムに記述するかという点が問われた、まだ知能システム・ロボットの初期発展期だった。ヒューマンインターフェイス自体も、人間からの指示をシステムの動作として変換する観点で語られていた。 一方、情報基盤についてはいろいろな発展があった。代表的なものには、ハイパーテキスト、公開暗号化技術、広域分散ネットワークなどがあり、後の情報社会の基盤として影響を及ぼした。しかし現在と比べると、まだ個別の計算機に閉じた集中型処理が主流だった。 その後、1980年から2000年までの20年間は、情報基盤としてネットワークが発展し、計算機もワークテーションやPCが急速に台頭、分散化の時代が始まった。知能システム・ロボット分野は、これまでアドホック的に記述していた処理を、数理的に厳密に定式化して扱うことが主流になってきた。 知能面では、エキスパートシステムが第5世代として展開されたが、まだ実用面では機能が限定的な部分もあり、AI冬の時代を迎えた時期でもあった。とはいえ、この状況は現在では大分改善されているという。「ロボットの実用例が急速に増加している点も背景にあるかもしれないが、'90年代までに作ってきた知能システム関連技術が融合し、インターネットの成熟と合わせて新しい世界が展開しているのではないか」と淺川氏は推測した。 また、これらに合わせて、人間がどのような知能を持っているのか、脳科学を中心に見ていこうという流れも出てきている。認識に関する処理手法も、モデル依存から統計的な実データによって学習する方向にシフトし、実用化が進んでいる。 さて、今後の予測についてだが、2020年ぐらいまでには、ロボットの認識判断が進歩するという予測のもと、限定的な環境・タスク・状況範囲の中で、知的な行動が可能になっていくという。また、脳の活動計測がかなり進展し、この研究がさまざまな応用分野と結びついて実適用が始まると見ている。生物の適用機能の解明により、工学的な応用も発展する方向だ。 人工知能は、高度なデータマイニングが知識発見と結びつき、ロボットとの統合が始まると予測。数値データのみならず、構造や時系列、テキストなどから、実世界データマイニングの研究が大きく展開され、有用性が確認されるものと考えているそうだ。一方、ネットワーク上での知識やサービスが「Semantic Web」としして展開されるという。これらがうまく結びつき、「ユビキタス」の世界に適用される可能性があると示唆した【写真15】。 2030年までには、前述のBMIが普及し始め、脳と機械の直接融合が始まる。このあたりになると、我々の生活も大きく変わっていきそうな予感だ。日常作業、人間のサポートでの実用化も視野に入ってくる時代になる。コンピュータ系も自然知能が出てきて、自律性が具体的に表現されるようになるという。このような中で、モバイルエージェントの発展も大きく、場所に縛られないアプリケーションが普及し、ネットワークでの安全性やセキュリティ技術もさらに進む【写真16】。 2040年には、高齢者などの障害解消を目的としたサイボーグ技術が実用化される。ここでは実世界自律適応ロボットがタスク限定で実現し、高度な認知アーキテクチャが確立される。また、量子計算ハードウェアなどによって、コンピュータが囲碁名人に勝利するといったことも可能になるかもしれないという。データマイニングも高度化し、世界中の情報が自己組織化を始めると予測。そして高度データマイニングとロボットが融合していく。 2050年になると、「希望的観測もあるが、BMIとロボットが違和感なく操作でき一体化が進む」と淺川氏。この頃になると、ぺタビット級の通信が普及し始め、ネットワークを介してさまざまなロボットが連携しながらサービスを始めるものと予測している。そして、「すべての人間・情報・機械・実世界が、物理的な結合から、知的インタラクション、直接的な脳結合までさまざまなレベルで完全に融合して、ダイナミックに適合し共振するような、まったく新しい世界が出現する」と結論づけた【写真17】。 最後に淺川氏は「ロボットは情報と実世界を結合する媒体として、社会のキーテクノロジーになるだろう。その際に、自律ロボットが意図や意味を実世界と結びつける高度な適応能力を持つようにすべきだ。ロボットは人間を認識・理解し、共感する能力がなければならないし、逆にそのようにしないと人間社会に導入することは危険である」と警鐘を鳴らした。
● 知能アーキテクチャ分野における4つの課題に求められるもの 続いて情報系複合領域の技術として、山川宏氏(富士通研究所)が「知能アーキテクチャ」をテーマに発表を行なった。知能アーキテクチャの分野は、情報系複合領域において、主に要素技術に近い分野を扱っているという。知能アーキテクチャの将来には2つの方向性があるそうだ。1つは人間のような知能の理解を目指すもの、もう1つは計算機向きの知能を目指すものだ。委員会では、これらを踏まえて主要な個別領域を課題としてセレクトし、専門の担当者に執筆を依頼して原稿を取りまとめたそうだ。
山川氏は、これらの現状の問題点にについて説明した。戦略的知能については、高い抽象度で記述できる理論がない点が問題として挙げられるという。ヒューマンモデリングでは、人のようなロボットを作るために、「思考」や「主観」などの状況依存性を含む認知・感性モデルを可能にする認知アーキテクチャが求められている。これは従来のニューラルネットワークや感性的な手法では開発が困難だという。また、実世界の現象やデータを扱うために、効率的で柔軟な学習手法も必要になるという。 知能計算理論に関しては、さまざまなデータ形式や高次元のデータに対応すること、モデル化、オンライン化技術への適用拡大、さらに個別技術を適切に組み合わせて利用する技術などが課題になるという。最後のプラットフォーム化については、運用管理に苦労せず積極的に使える共通基盤を推進したり、情報のセキュアな管理技術、それらを許容する社会的なコンセサンスを形成しなければならない。 山川氏は、これらを踏まえて、将来に向けたあるべき姿として「汎用プラットフォーム化」「認知モデルの学術的融合の促進」「拡大される適合領域への対応」「他分野からのインパクトの導入」「対人インタラクション能力の向上」「セキュア化」などの項目を挙げた。 ● もはやSFの世界ではない、ブレインマシンインターフェイスへの適用 東芝の森田千絵氏は、人工知能の見地から「知能情報学」について説明した。森田氏は、まず人工知能の研究を過去からさかのぼって振り返り、現在に至るまでの流れを説明した。人工知能の研究は50年ほど前からスタートした。初期は記号処理が中心であり、知識の表現や獲得方法、問題解決の探索法などの要素技術がメインテーマだった。1980年代に入ると、いわゆる「エキスパートシステム」や「マルチエージエント」「データマイニング」などへ広がりをみせる。 1990年代にインターネットが花開き、大きな影響を受けるようになった。この頃になると、エキスパートシステムの知識を共有したり、メンテナンスの必要性から工学としての「オントロジー」(巨大な辞書のようなもの)が研究され、意味や概念の体系化を扱う分野が注目されるようになった。 2000年になると、ますますWebを意識した研究が増え、情報の収集や検索を容易にする技術として「Semantic Web」の研究が進んだ。Webの特性としての分散性や非均一性などを意識したオントロジーの研究も盛んになった【写真19】。 一方、BMIの分野も知能情報学に属する。こちらも50年ほど前から脳の神経活動の計測がスタートし、生体信号を利用したヒューマンインターフェイスとして、筋電義手の開発が1960年代から始まる。 1980年代に入ると、脳波はもちろん、MRIやPETなどさまざまな検査技術が発達してきた。そして2000年代に入ると、いよいよBMIやヒューマンインターフェイスとしての応用も始まり、計算機のカーソルを脳波で動かしたり、ロボットを制御することも可能になった。BMIでは、人間の感情や思考なども脳波を使って調べるような研究も始まっている。さらに力の制御や環境からのフィードバック情報を脳へ戻す研究まで進んでいるそうだ【写真20】。
さて今後の人工知能の予測については、自然言語の意味理解や感情に関する研究が進む。オントロジーは半自動構築が行なわれ、物と物との関係性を含むようになる。また、ロボットシステムの共通基盤となるものも構築される、としている【写真21】。一方、BMIについては「2010年代には無線式電極の開発が進み、BMIの応用例が増える」と森田氏は予測。BMIは手術によって脳に電極を埋め込む侵襲型だが、キャップのようなものを被って計測するBCI(Brain-Computer Interface)も普及し、簡単な動作の生成ができるようになる。 2020年から30年にかけては、「ゲームなどの分野で、一般の人にもBCIを使ったインターフェイスが広まる。2040年~50年にかけては予測が難しい面もあるが、人間がサイバー空間をシームレスにやりとりする、ヒトとコンピュータのコラボレーションが進む、ヒトの記憶を直接脳から読み取ることができるようになる」としている。 最終的には、非侵襲型のBCIで多自由度のロボットを操作できるようになり、日常的なシーンでも利用されるようになってくると考えられる。オントロジーもヒトの意図や目的をベースに理解できるようになり、ロボットの知識の構造化や、オントロジーに支えられた自律性、ロボットの協調なども進展してくると予測【写真22】。
とはいえ、将来に向けての課題も多い。知能情報学の観点からは、コンピュータによる自然言語や感性の理解、あるいは多層的な知識表現、推論法の開発が必要だという。また、BMI/BCIでは時間的・空間的な分解能を同時に高精度で計測できる装置ができていない。オントロージも構築方法をどうするか、メンテンンスなどにも問題がある。 最後に森田氏は、「世の中では、人と、機械やロボットが自然なコミュ二ケーションをできるように技術が進んできているが、ロボットが我々に歩み寄ってきて、人間の世界を理解しようとしている。ところが、ロボットが人間に与える影響については、まだあまり議論されていない。こうした技術が我々にどのような影響を及ぼすのか、十分に考えていく必要がある」とし、発表を終えた。 2050年には、かなりSFチックと思えるような話も実現できると期待が膨らむ。しかし、その前に技術的な側面だけでなく、人間側で解決しておかなければならない問題も数多くありそうだ。 ● 専門家が経験と勘をベースに、確度の高い未来予測に努める 工学系先端領域からは、同領域のARM委員長である金子真教授(大阪大学工学研究科機械工学専攻)がARMの概略と策定のキーポイントを中心に説明した。工学系先端領域ARM委員会は、ロボット技術の予測に際し、「どのような可能性があるのか、どこに研究投資される可能性があるのか」といった点を考慮に入れ、まず2050年の社会について議論することから始めたそうだ。 今回のARMを策定するにあたり、高齢化社会、環境問題、エネルギーなどを論点に専門の研究者に執筆を依頼したという。内容は濃く、ページ数は薄くというポリシーだ。金子教授は「分野によっては、技術が進化するスピードは大きく異なるケースがある。ものによっては爆発的、突発的に革新が起こることもあり、政府の重点政策により予算が大きく付く。それが一番予測しづらかった」という。 金子教授は、自身の経験を踏まえて、専門領域である「高速アクチュエータ」をテーマに、どのような予測をすべきか、具体例を挙げつつ、将来のビジョンについて説明した。電総研が製作した3本指ハンドを見て感動した金子教授は、1978年頃から人間の手の研究を始めた。その後、さまざまなロボットハンドを開発してきた。 ところが、人間の場合は、訓練によって指でペンをクルクルと器用に回すような芸当をすることも可能だ。一方、ロボットはそう簡単にいかない。人間の機能性は素晴らしいものがあり、それをロボットで実現することは相当に難しいことだ。 そこで金子教授の場合は、「それならば逆にヒトが劣っているような点、たとえば高速性に着目し、ロボットで実現していくことを考えた」という。正面から秒速4mのボールを投げると、人間はボールをつかめない。それは人間の能力を超えた作業だからだ。目から脳に信号が伝わり、筋肉を動かす時間よりも、速いアクションが必要になる。 高速なビジョンとアクチュエータを取り付けたロボットならば、このようなアクションに容易に対応できるようになる【写真23】。金子教授は、「ロボットにもヒトに勝てる分野がある。ヒトの眼の能力は1秒間に15文字の処理が限界。もし機械ならば約600倍のスピードを達成できる」と語り、研究分野によってはロボットのほうが人間の能力を遥かに超えられることを示した【写真24】。つまり、そういった可能性のある分野に対してアプローチしていけば、やがて技術革新が生まれ、それが未来予想にもつながるということだ。 金子教授は「ARM策定に際して、専門家が経験と勘をベースにした予測には大きな意味がある。自分の専門分野を予測する場合には、その確度をさらに高められる可能性があるからだ」と説明した。とはいえ、50年も先のことなので、熟考しても予測できない部分もあるだろう。であれば、ある意味で夢を追いかけるのもよいのでは、と考えたという。ただし、その場合でも専門家によってある程度は実現が期待できるような、見込のあるものに絞って、予測の確度を上げていったという。
東京大学大学院の水内郁夫氏(情報理工学系研究科知能機械情報学専攻 講師)は、2050年のヒューマノイドロボットの行方について占った。この頃になると、いわゆる超高齢化社会の時代に突入している。それと同時に、労働力も減少するため現役世代のほとんどが共働きとなり、さまざまな支援が必要になると予測される。ヒューマノイドロボットは、高齢化世帯の家庭作業を補助するほかにも、重労働作業にも役立つ。 水内氏は「専用装置がPCに置き換えられたように、汎用性を持つヒューマノイドロボットが器用さと高出力を兼ね備えた機械として広まっていく可能性がある。また、ヒューマノイドは人の夢を加速するエンジンの役割を担い、IRTの集約・発展によって新しい形に変容するかもしれない。たとえばサイボーグなど、身体機能の拡張や代替への応用・転用も想定できるだろう」とし、2050年のヒューノイド全般の技術について予測した【写真25】。 まずアクチュエータは電気利用でない原理で動くものが登場するという。自由度・関節は人間並みから人間以上になってくる。エネルギー源は電池のエネルギー密度に比べて遥かに高密度な蓄エネルギー装置が発明され、自立的なエネルギー補給行動も可能になる。 ロボットの外装も人のような皮膚を持ち、全身に触覚や感覚を備えるようになる。制御系については、人間のような体の扱い方をロボットができるようになる。インターフェイスに関しては、生体信号を利用したり、ユビキタスやネットワークで結ばれ、どのようなロボットでも同じ様に使えるものに進化すると考えられる。 次に水内氏は、これらの予測から、ヒューマノイドの技術的なキーポイントとして、エネルギー蓄積装置とアクチュエータの飛躍的な向上について的を絞って説明をした【写真26】。 たとえば現在、高性能リチウムイオン蓄電池を利用しても、エネルギー密度は0.4~0.7MJ/kg程度だが、2025年になると超高密度2次電池が出て数MJ/kgに、さらに2050年には100MJ/kgぐらいまでになる、というシナリオを描いている。そうなるとアクチュエータの出力密度も高まり、最終的にグランドピアノを運べるぐらいの超重量物の搬送や、重労働現場における長時間利用シーンも想定される【写真27】。
もちろん、このような技術を実現するには何がしかブレークスルーとなる技術が必要だが、水内氏は「蓄エネルギーとして、原子力の利用が考えられるかもしれない。たとえばウランならば66TJ/kgで、人間の一生分以上のエネルギーを充電不要で使えるようになる。エネルギー変換に関しても、電磁力でなく、化学変化を使ったアクチュエータが出てくるかもしれない」と述べた。 また、水内氏はセンシングや情報処理についても言及した。センシングについては、精度や再現性だけに依存しない技術や、非線形の多自由度複合入力から情報を抽出できる技術が必要になるという。 一方、情報処理に関しては、常識など妥当性を持つ知能がブレークスルーになるかもしれないという。水内氏は「いずれにしても、2025年には半導体の進歩は原理的に限界に達すると考えられいる。2050年にはまったく異なる技術で、情報処理が行なわれている可能性が高い」と説明した。 ● 2050年には、ミクロの決死圏のような体内治療が現実のものに! 横浜国立大学の丸尾昭二准教授は、独自開発の「3次元マイクロ・ナノ光造形法」を駆使し、新しい原理マイクロマシンの開発を進めている。従来、マイクロマシンの作製には半導体製造プロセスが主に用いられてきた。しかし、この3次元マイクロ・ナノ光造形法は、レーザー照射によって液体から固体に変化する光硬化性樹脂を用いる手法。10μm以下の3次元微小構造を任意に短時間で形成できるというメリットがある画期的な技術だ【写真28】。 この技術によって、丸尾准教授はレーザー光で駆動するマイクロタービンや、ナノピンセット、複雑なマイクロ流路を持つマイクロ化学分析チップなどを開発しており、将来のバイオ研究や医療に役立つツールとして応用できると期待されている。 50年後の未来社会に貢献する工学系先端領域ARMを予測する際に考えたことは、超高齢化社会で医療や健康管理が大変重要になってくる点だという【写真29】。丸尾准教授は、マイクロ流体システムをベースに、体内に埋め込んで診療・診断・治療ができるようなマイクロチップの可能性について述べた。
現在、マイクロ流体システムの要素技術で、流路の製作については材料・加工方法も含めて、かなり確立されている。しかし、流体制御に関しては、ダイヤフラム型で空気圧で駆動するようなマイクロポンプが主流であり、まだ発展途上の段階だという。実用レベルとしては毎分μLの制御が必要になる。このような技術を利用し、チップの中で薬剤をつくったり、分析したり、細胞を入れて診断する研究が進められている。 体内埋込技術として現在進められている研究としては、名古屋大学の「人工細胞デバイス」(化学IC)などがある。これは化学ICの中で化学合成を行なってタンパク質を作るもの。このようなデバイスが体内に埋め込まれれば、体内で薬を合成して放出するDDS(Drug Delivery System)が将来的に実現するかもしれない。海外でもシリコンチップに薬を内蔵し、ある時刻になると蓋を破って薬を放出する研究もあるという。 丸尾准教授は2025年には、動物の中に埋め込む「インプラント型診断チップ」が登場するものと予測している。これは情報伝達や電源供給を行なって、新型インフルエンザやBSEなどを早期に検出したり予防できるチップだ。体内で用いられるため、生体適合性の高い材料を用いて、微小でも高い感度で検出できるセンサが求められる。前述のように異常時に薬やワクチンを放出するDDS技術や装置も必要だ。 研究がさらに進み、2050年には本当に人体に適用できるようになるかもしれない。悪性腫瘍を検出して治癒するキャンサーチップや、アルツハイマーをケアするチップなどが登場すれば人類に大きな福音をもたらすはずだ。
バイオのエネルギーを利用して、体内でマイクロマシンを動かす「バイオハイブリッドマイクロマシン」と呼ばれる分野の研究は、現時点でも進められている。心臓から取り出してきた神経細胞を用いたマイクロポンプ(東京農工大学)や、滑走バクテリアを用いたマイクロモータ(北陸先端大学)、ATP合成酵素を用いたナノモータ(大阪大学)などの研究があるという。 丸尾准教授は、「このような分野の研究は、ロボットや機械、電気など、1つの枠組みにとどまる研究ではなく、医学、化学などさまざまな分野において横の連携を深め、議論を進めて行かなければ実現できないと思う。この分野で少しでも役立てるような研究をすることで、技術に貢献できるようにしたい」と述べて、発表を終えた。 ● 産学官をつなぐコミュニケーションのパイプ役としてのARM 最後の発表では、経済産業省の渡邉政嘉氏(製造産業局 ものづくり政策審議室長、素形材産業室長)が、「ロボット研究/技術ロードマッピングで可視化されたブラックボックス」をテーマに発表を行なった。渡邉氏は、いわばARM策定の仕掛人的な存在だが、経済産業省で推進している「イノベーション・スーパーハイウェイ構想」と、これをベースに進められている技術戦略マップの概要についても説明した。「イノベーションのプロセスを考えたときに問題となるのが、アカデミズムと産業界の相互コミュニケーションをいかに取っていくかということだ。学術的な価値観と産業界のビジネス的な価値観は異なることが多いからだ。まず互いが何を考えているのか知ることが重要」と渡邉氏。 そしてARM策定に際して、企業が作る技術ロードマップと異なる価値機軸の上で、自分の研究がどのようなフェーズで発展していくのか、議論しながら絵に描く形で協力を要請したという。各学会における研究のトレンド、流れ、可能性、意志を「見える化」してロードマップを描き、産業とつながっていく部分を議論することが、本当の意味での産学官連携の進展になると考えたからだ。 渡邉氏は「行政がトップダウンで動くのではなく、アカデミズムの知恵をしっかりと吸い上げるようなネットワークとコミニュケーションツールを作らなければ、今後の研究・開発は進まない。研究/技術ロードマップを策定していくうえで、異分野から触発されて考え、議論するというプロセスが新しい何かを生み出すコミュニケーションツールになっている」と指摘する。 産学官連携の「学」は大学だけでなく、学術組織も内包している。それを意識した政策が重要であり、「ARMが産学官をつなぐコミュニケーションのパイプ役として実質的な意味を持つもの」とし、ARMの役割を強調した。 ■URL 日本ロボット学会 http://www.rsj.or.jp/ 第25回日本ロボット学会学術講演会 http://www.robotics.it-chiba.ac.jp/RSJ2007/ ■ 関連記事 ・ ペットボトルロボからゾウリムシロボまで、研究者がロボティクスを解説! ~第25回日本ロボット学会学術講演会一般公開セッション(その1)(2007/09/21)
( 井上猛雄 )
- ページの先頭へ-
|