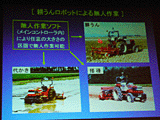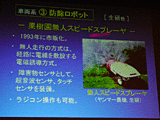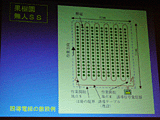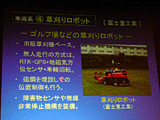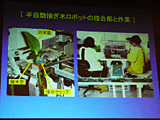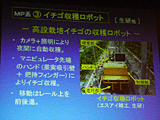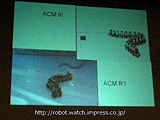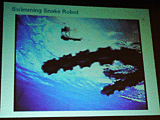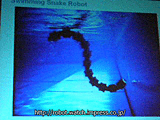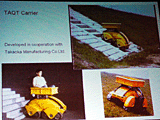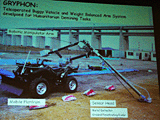|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「進展するロボット化技術と農業機械の開発改良」セミナーレポート(前編) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
~人の役に立つロボットとは? 農業分野や被災地で活躍するロボット
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● 市販の耕運機や田植え機を改良して無人化 3月7日、埼玉県の大宮ソニックシティーホールにおいて、「進展するロボット化技術と農業機械の開発改良」をテーマにしたセミナーが開催された。主催は、独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構、生物系特定産業技術研究支援センター、新農業機械実用化促進株式会社。最近では二足歩行ロボットの進化によって、ホビー用ロボットや家庭用ロボットが注目を浴びている。とはいえ、第一次産業分野でも人間の作業をサポートするさまざまな専用ロボットが開発されている。ここでは、農業用ロボットを中心として、少し変りダネの面白いロボットについて紹介する。
農業用ロボットは、大別すると3つの種類がある。既存の機械を改良して無人運転する「車両系ロボット」、まだ機械化されていない作業を自動化する「マニピュレータ系ロボット」、もうひとつが農業施設自体を自動化したり、植物工場などを実現する大規模なもの。ここでは、前者の2つの分野について解説がなされた。 車両系ロボットの歴史は意外に古い。20年ぐらい前から大学、研究機関、企業などで開発が始まった。従来の市販機械をベースに走行部や作業部を改造し、無人走行やさまざまな作業ができるように工夫されている。2000年ごろまでに研究はひと段落しており、現在は実用化に向けた改良や、各種の要素技術を具現化する段階まできている。実用化されたロボットもいくつかある。 松尾氏は具体的な車両系ロボットとして、「耕運ロボット」「田植えロボット」「防除ロボット」「草刈ロボット」の4タイプについて、写真やビデオを交えながら紹介した。 耕運ロボットは32馬力の市販トラクタを改造したもので、無人耕運、代かき、種まきなどの作業が可能だ【写真2】【動画1】。航法システムは、光学測量方式、GPS、電磁誘導方式といった方法を選択できるようになっている。このほかに、制御コントローラ、車両制御システムなども搭載している【写真3】。【写真2】では「XNAV」という光学測量システムを使い、ターゲットとなる光反射標識や方位センサも据付けられている。基準局として「ほ場外」に自動追尾型測量装置を設置し、前述の光反射標識を追尾しながら位置を計測する仕組みだ。
求められた位置は無線通信で耕運ロボットに送られ、その情報をロボット側で取り込む。一方、方位や姿勢の情報はロボットの地磁気方位センサや傾斜センサで検出する。制御系のシステムで、操舵機構、前後進切り替えシャトル、ポンパ、スロットル、左右独立したブレーキなどをコントロールできる。 また、運転モード、油圧レバーの位置、燃料残量、冷却水温、障害物などさまざまな情報もセンサで計測され、メインコントローラ側に送られるので信頼性も高い。ロボットの作業はメインコントローラに搭載されたソフトで実行されるが、ソフトを変更すれば異なる作業も可能だ。ロボット自身が自己位置を確認するため、作業残しや無駄な作業もなく効率的だ。 田植えロボットは、つくばの中央農研で開発された無人田植え機が紹介された【写真4】。これも市販の田植え機がベースになっている。ロボットの構成要素は耕運ロボットとほぼ同じだ。航法システムには、高性能なRTK-GPSとFOG(光ファイバジャイロ)が用いられており、位置と方位を求めている。 田植えの実作業ではマット苗を利用する。苗を頻繁に補給しないようにロングマット苗を搭載すれば、30アールまで無人で田植えが可能だ。「ソフトウェアでは旋回や幅寄せのアルゴリズムが難しいが、うまくいくと高効率でスムーズな無人走行ができる」(松尾氏)という。最新機種では、走行経路からのズレが10cm以内に収められるように高精度な制御が行なわれている。 防除ロボットは10年ほど前にヤンマー農機と生研センターで開発し、市販化されたもの【写真5】。果樹園に敷設された経路上を電磁誘導方式で無人走行し、薬品を散布する【写真6】。果樹の列に沿って往復作業できるように誘導電線が敷設されているが、果樹は毎年植え代える必要がないため、このようなケースでも有効となる。安全対策もしっかりしており、超音波センサやタッチセンサを搭載し、障害物を検出すると停止する。ラジコンによる操作も可能だ。
草刈ロボットは富士重工業が開発したもので、これも市販の草刈機がベースになっている【写真7】。RTK-GPSと地磁気方位センサに加え、車輪回転も検出しながら制御する仕組み。また磁石を埋設して位置も検出している。安全面では4つのレベルを設けており、超音波センサによる障害物の回避、磁力センサによる進入禁止領域での停止、リモコンによる非常時の停止、メカニカルスイッチによる緊急停止などの配慮がなされている【写真8】。 このほか車両ロボットとしては、大ほ場でスプレー作業ができるロボットトラクタ(北海道大学)、有人運転をするコンバインに追尾して無人で収穫作業が可能な自動追走コンバイン(京都大学)、変りダネとしてカルガモのように水田を走り回って除草作業をする水田除草ロボット(九州農研)なども開発されている。
● トマトやナスの収穫も自動で行なうマニピュレータ型ロボット 次にマニピュレータ型ロボットについて見てみよう。マニピュレータ型は機械化できないような分野に適用されるため、とてもユニークなロボットが多い。まず筆頭に挙げられるのは、ウリ科・ナス科の苗を接ぎ木するためのロボット。こちらは半自動と全自動の2タイプがある。前者は、穂木や台木を手動で補給し、ロボット側で接合部を切断・クリップ止めしてから、コンベアに排出する【写真9】。一方、後者はセルトレイごとに穂木や台木を自動供給し、全苗の接合部を切断・接合する。さらに、つがれた苗を空トレイに挿入し排出するというもの。このほかにもマニアックなロボットとして、トマト収穫ロボットが紹介された。こちらはパイプレールの上を移動しながら、施設栽培されたトマトを収穫する。6軸多関節マニピュレータとフィンガー開閉式のハンド(4つの指)でトマトを保持。2台のステレオカメラ(CCDカメラ)で3次元的にトマトの位置を認識できる。さらにハロゲンランプも装備されており、トマトの表面反射によって背景の識別や、果実の中心を検出することで、高精度に収穫できる工夫がなされている【写真10】。現在、15秒から20秒に1個程度の速さで作業できるそうだ。 エスアイ精工と生研センターが昨年まで開発していたイチゴ収穫ロボットも面白い。こちらは高設栽培されたイチゴの収穫用に開発されたもので、夜間にレール上を移動しながらマニピュレータでイチゴを収穫する。果実の認識はテレビカメラと超音波センサで行ない、ハンド部の保持フィンガーによって果実を保持してハサミで切断するが、ここでもひと工夫が凝らされている。果実を引き寄せるために吸着壁があり、これで吸引する仕組みを取り入れているのだ【写真11】。 そのほかユニークなロボットとしては、野菜研のナス収穫ロボット【動画3】や、キクの穂の挿し木ロボット、搾乳ロボットなどもある。
次に松尾氏は最近の農業ロボット技術の動向について、車両系ロボットを中心に解説した。ロボットの要素技術のひとつ、航法システム・センサは、GPSの低価格化と高性能化が進展しており、国内でのGPS利用環境がかなり改善されてきているそうだ。 マニピュレータ型でもキーとなるビジョンセンサが小型・高性能化され、ステレオ画像処理システムが使いやすくなっている。Webカメラについても通信が容易なため、サブ的なセンサシステムとして利用できるようになったという。安全確保の面では人・障害センサも重要だ。こちらは小型で安価なレーザーレンジファインダなどを利用できる。 またコントローラについては汎用小型PCが高性能化されてきており、モバイルや屋外での使用が可能になってきた。とはいえ、汎用機はデータ入出力機能が弱くなってきているため、小型専用コントローラやI/Oコントローラを充実する必要がある。車両内情報の通信技術はCAN(Controller Area Network)が主流になっているそうだ。 今後の開発戦略については、この4月から「農業用ロボット車両による農作業システムの研究」というテーマで研究を行なっていく予定だという。これは車両系ロボットの実用化への取り組みとなるものだ。航法システムやコントローラを共通化する形で、耕運ロボットのような従来ロボットを改造しながら実証実験を試みる。 一方、果菜類収穫ロボットに関しては、次世代緊プロ共同開発の一環として、ロボットや新技術の開発を企業と共に実施していく予定だ。この共同研究では、視覚・認識技術として、夜間作業を前提にした果実の熟度や着色度の判定技術を進展させる目的がある。 またロボットの作業に適した栽培様式やシステムの研究を各地で試験していく方向だ。車両系ロボットはかなりのレベルに到達しているので、今後は低価格化を進めるべく共通部品を活用していく必要があるという。 もちろん安全面でのセンシング技術なども研究を進める。マニピュレータ型ロボットについては、「まだ進展中の技術も多いが、今後は収穫適期判定のセンシング技術や、傷つきやすい軟弱な農産物のハンドリング、人との協調作業などについて確立したい」(松尾氏)と述べて、講演を締めくくった。 ● ヘビ型ロボットと歩行ロボットの変遷
広瀬教授がヘビ型ロボットを開発した出発点は、「そもそもヘビがなぜ移動できるのか」ということだった。文献では、ヘビは鱗を立てて移動すると説明されていたが、実はそうではなかった。いろいろな実験を繰り返しているうちに、アイススケートやローラスケートで滑る原理と同じことだとわかり、理論的な解析や裏づけを重ねていったという。実際にシマヘビを料理屋から買ってきて解剖したり、電極をつけて活動させるといった地道な実験もしたそうだ。 広瀬教授は、1972年に開発したヘビ型ロボット「ACM III」によって、世界で初めて蛇行運動の原理で匍匐前進に成功した。これは20節あるセグメントを前から後ろに屈曲させる指令を与えることで、前進運動させるもの。それぞれのセグメントには左右にキャスタが付いており、ローラスケートのように前後方向には滑りやすく、横方向に滑りにくい構造になっている。 次に屈曲の指令方向を変えて、前進だけでなく後退もできるタイプのヘビ型ロボットをつくった。その後も斜面を登れるように横方向の力を検出できるセンサをつけて蛇行させたり、自律的な動作をさせるためにニューラルネットワークの仕組みを取り入れたりしながら改良を進め、合計で20体以上ものモデルを作ったという【動画4】。 2005年の愛知万博では、水中遊泳ができる完全防水タイプのヘビ型ロボット「RCM-5」も開発している【写真13】。これは比重を限りなく1に近づけて無重力状態にし、ピンで水をかいて波を後ろに伝えることで水中遊泳を実現する仕組みだ。また、ひれの先端にローラーがついており、地上ではローラーで動くようになっていた。先端にはテレビカメラも付けられており、360度どのように動いても水平に映像を送れる【動画5】。
さらに、このヘビ型ロボットを実用的に使うために開発を進めた。その実例として、広瀬教授はレスキュー用途のロボット「蒼龍」についても紹介した。こちらは3つのセグメントで構成され、1つのモータですべてのクローラを回し、残りの2つのモータで関節を動かすようになっている。 1号機ではセグメントの先端が楔(くさび)型になっており、狭い瓦礫の中でも入れるようにしていたが、穴が小さいと機体が入った後に抜け出せなくなることがわかり、通常形に戻したという。 3号機は床下点検ができるモデルにした。「ポイントは通常の生活でも利用でき、さらに災害時にも救助に使えるもの」だという。そして5号機では、全面クローラの蒼龍を製作【写真14】。クローラはトピー工業と共同開発し、薄いスチールベルトにゴムを焼き付けたものを採用。屈曲部もウレタンゴムの伸び縮みで弾性的なジョイントにしたそうだ。レスキュー時に瓦礫が散乱している場合は機体をブリッジにして移動できるメリットがある【動画6】。こちらは昨年の夏にワシントンD.C.でレスキュー隊に使用してもらったという。 広瀬教授が開発しているロボットはヘビ型ばかりでない。ザトウグモをヒントに、通常の車両では近づけない荒地でも移動できる歩行ロボットの開発にも着手。1976年のことだ。教授は、まず歩行ロボットを作る場合に最適な脚の数を検討した。なるべく機構が簡単で、なおかつゆっくり動いても立っていられるような安定性を得るために4本の脚が最適だと判断し、「TITAN」を製作した。 さまざまな改良を加え、1985年の筑波科学万博では3次元パンタグラフ機構で機体を保持する「TITAN IV」を出展した。その後、土砂崩れを防ぐ土木工事でも利用できるように「TITAN XI」も開発した。こちらは総重量が7トン、脚長4mという巨大な歩行ロボットだった【動画7】。 クローラ型ロボットも'80年代から開発を始めている。建設現場の資材運搬などを目的とし、高岳製作所と共同で「TAQT Carrier」を実用化【写真16】【動画8】。こちらは荷物を載せても重心が常に中心にくるように工夫している。安定した姿勢制御が可能な機構で、アダプティブに動き回ることができた。また、クローラ型では作業用アームを移動補助として利用した「HELIOS-VII」もレスキュー用途に開発している。アームを利用して大きな障害物があっても難なく移動できるロボットだ【動画9】。 さらに全天候の環境でも可動できるように、アクチュエータレベルから要素技術を研究し、「極限アクチュエータ」を商品化。このアクチュエータは、DCブラシレスサーボモータとハーモニックドライブギアを組み合わせ、防塵・防水タイプにしたもの。後述する地雷探査ロボットのマニピュレータでも利用されているという。広瀬教授は「レスキュー時には瓦礫の中に布団などの繊維性の材料が含まれていることがあり、クローラに絡み込まないような工夫が重要だ」という。そこで、クローラベルトをカバーで覆い、ベルトの淵にヒダをつけて絡み込みを防止した。
● ロボット工学は目的達成学であり、形状にこだわる必要はない さて、広瀬教授の研究として、もうひとつ重要な柱がある。それは地雷探知除去(Demining)をするロボットだ。現在でも世界では対人地雷による被害が後を絶ない状況である。広瀬教授は1995年ぐらいからこの分野の研究を始めているそうだ。すでにアフガニスタンやカンボジアなどで、開発したロボットを持ち込み、地雷撤去のテストも試みている。地雷探査には3つのレベルがある。レベル1は、どのあたりに地雷があるか調査する段階。文献記録や住民からのヒアリング、空中からの探査を行なう。レベル2は重機で地雷を爆破撤去する段階だ。ただし、これだけでは2、3割の地雷が取り残されてしまう。また重機を持っていけない場所もあり、結果的に人手で撤去しなければならない。第3段階として、地雷探知機や地雷犬などで反応のあった場所を調べ、その周りにある土を取り除いて目視検査を行ない、最終的に火薬で爆破する。そこで無人の地雷探知除去ロボットが必要になる。 当初、広瀬教授はツールチェンジャを装備した歩行ロボットを開発しようとしていたという。地雷のある場所まで移動して、もしそこに草などがあれば刈り取り、地雷を探査したあとに掘り出して撤去したり、起爆ハンマーで叩いて爆破するというロボットを考えていた【動画10】。その後、2002年度から科学技術振興事業団の研究領域「人道的観点からの対人地雷の探知・除去活動を支援するセンシング技術、アクセス・制御技術の研究開発」の指定を受け、現地調査を行ない、その様子もだんだん分かってきたという【写真17】。 地雷探知除去ロボットを作るにあたり1番の問題はコストだった。そこで、既存のバギー車を改良して移動ロボット「Gryphon I」を製作した。このロボットにはアームと、金属探知機、地中レーダ、ステレオビジョン、GPSなどが装備されており、遠隔で操作できるようになっている。【写真18】【動画11】【動画12】。
ステレオビジョンで地形を計測し、スキャニングをプランニングして地面の凹凸を検知。斜度の大きい場所でもアームを可動できる。コントローラも防塵・防水構造で熱対策も施した。アーム部には、前述の極限アクチュエータが用いられた。 このようにさまざまなロボットを開発してきた広瀬教授は、「ロボット工学は目的達成学である」と主張し続けている。つまり、ロボットの開発で重要な点は形状ではなく、「目的を達成するための手段を探って、最適な解を模索することだ」という考え方である。そのような観点から考えると、「マシンデザインにおいて、ヒューマノイドロボットは制約が多く、人の形は必ずしも最適解にはならない」と説く。技術の進化によっては、他のツールの形態も変化する。ヒューマノイドロボットが完成したときには、すべてのマシンがロボット化し、ユビキタスロボット社会になっているかもしれない。 また、ヒューマノイドロボットと共存する未来の生活では生きがいが感じられないという。広瀬教授は「たとえば介護などの分野でも、老人ホームで老人がいつも同じことを繰り返し話すので、それを辛抱強く聞いてくれるロボットが欲しいという声も聞くが、そういうことは大変でも人間がやったほうがいい」と考えている。人間同士が人間的に触れ合える社会も大切だからだ。 ロボットはあくまで縁の下の力持ち的な存在であり、3Kなどの肉体労働を陰で支えるもの、という原点に立ち返る必要がある。また、「ロボットコンテストなどによって新しい遊びや知的スポーツを創生したり、新しい知的労働や価値観を見つけることで、人間的な作業の再評価を行なうべき」とした。さらに、現在開発している地雷探知除去ロボットの利用法も、世界の消防国家としての日本として、「世界各地の災害時に迅速に対応し、機器や人材を派遣できるような国際的な事業に発展させたい」と考えているという。 ■URL 農業・食品産業技術総合研究機構 http://www.naro.affrc.go.jp/ 生物系特定産業技術研究支援センター http://brain.naro.affrc.go.jp/ 新農業機械実用化促進株式会社 http://www.shinnouki.co.jp/ ■ 関連記事 ・ ロボット業界キーマンインタビュー 東京工業大学 広瀬茂男教授(2006/09/01)
( 井上猛雄 )
- ページの先頭へ-
|