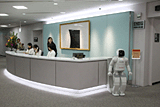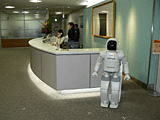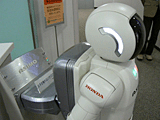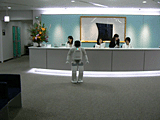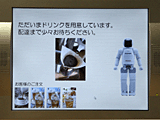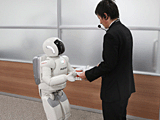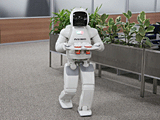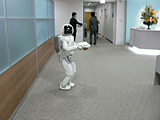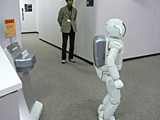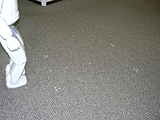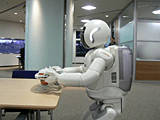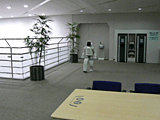|
記事検索 |
バックナンバー |
【 2009/04/17 】 |
||
| ||
【 2009/04/15 】 |
||
| ||
【 2009/04/09 】 |
||
| ||
【 2009/04/06 】 |
||
| ||
【 2009/04/03 】 |
||
| ||
【 2009/03/27 】 |
||
| ||
【 2009/03/24 】 |
||
| ||
【 2009/03/18 】 |
||
| ||
【 2009/03/11 】 |
||
| ||
【 2009/03/06 】 |
||
| ||
【 2009/03/04 】 |
||
| ||
【 2009/02/27 】 |
||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASIMOの案内・デリバリーサービスを体験してきました |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reported by
森山和道
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● ASIMOの受付・案内サービス ASIMOの受付サービスを体験といっても、いきなり始まるわけではない。まずはごく普通に人間のいる受付ブースで受付をしてもらうのだ。受付のある2Fフロアに上がると、まず、受付ブースの横に設置された充電ステーションに接続された状態でASIMOが立っていた。電源は入った状態で、大きなファンの音を立てている。それと同時に、フロアの各コーナーにインカムを着用した人が立っていることに気づいた。この人達は試験運用期間限定のASIMOの監視役で、ASIMOにポーズをかけることができるPDAを所持しているとのことだった。 うち一人はドリンク作成係である。ASIMO自身がドリンクを作ることは残念ながらまだできないからだ。現状のASIMOはあくまで紙コップの入ったトレイを手に持たせてもらい、それをテーブルまで運ぶことしかできない。将来あり得るとすれば、ドリンクサーバーからドリンク入りのカップが、スポッとASIMOが持つことのできるトレイのなかに収まって、それをASIMOが運ぶような形式だろう。だがそれはまだ今後の課題である。これ以外にもう1人、運行管理者がバックヤードにいるので、合計で4名がASIMOの面倒を見ていることになる。
「では、はじめてよろしいですか」と、今回の取材を受けて下さった開発責任者である株式会社本田技術研究所基礎技術研究センター第2研究室主任研究員の大津明彦(おおつ・あきひこ)氏が我々に声をかけ、ASIMOによる案内サービスが始まった。 筆者とASIMOの間にいた人が横にずれた瞬間、ASIMOが「森山様」と筆者の名前を呼んで声をかけてきた。まだ距離は遠かったのだが、受付機能がスタートしたときに、光通信カードがASIMOから「見えた」ら、とにかく呼びかけてくるという仕様のようだ。もう少し近づいてから案内を開始するなど、将来は改善してもらいたいところである。 取りあえず、同行してもらった編集者二人に写真撮影を任せつつ、ASIMOに近寄る。するとASIMOが歩き出した。やや唐突な印象だ。筆者はASIMOの行き先は分かっているので「ああ机まで案内されるんだな」と思ったが、何も知らなければどうすればいいのか、どこへ連れて行かれるのか分からず不安に思う人もいるにちがいない。 そう思いつつ取りあえずASIMOのあとをついていく。曲がり角でASIMOが曲がったところで、少し意地悪をしてみようと考え、ASIMOについて行かず距離を置いてみた。以前、新型ASIMOが発表されたときに、案内する対象者が離れたら、そのことを検知して待ってくれる機能がASIMOに実装されていることを知っていたからだ。それが実際にどの程度動くのか試して感じてみたかったからである。 しかしながらASIMOどんどん進んでしまう。仕方ないのでASIMOのあとを追いかけることにした。後で聞いたところ、現在はASIMOが案内者を待つ機能は外してあるとのことだった。人が歩くペースに合わせて案内するなど、今後の改良に期待したい。 ASIMOはそのままさらにコーナーを回り、中央のテーブルの前で止まる。そして「こちらです」と、そのテーブルで待つように身振りと音声で指示してきた。テーブル側に筆者が回り込むと、「どうぞこちらでお待ち下さい」「失礼します」と一礼して充電ステーションに戻っていった。現在試験運用されている受付機能は、ここまでである。 ASIMOが動き出すと大勢の人が注目する。ホンダの社内なのだが、多くの人が会話を一時中断し、ASIMOを物珍しげな表情で追っている。その一方で、案内されたほうは、やや素っ気なく、もう少し愛想があってもいいかな、という印象を受けた。機械に愛想を期待するというのも変な話なのだが。
● 飲み物のデリバリー この季節の建物内は暖房によってどこも乾燥している。実際に喉が渇いていたこともあり、早速、ドリンクデリバリー機能を試してみることにする。まず、ドリンクの種類をタッチパネルで選択する。同時に頼めるドリンク数は4つまで。ASIMOが運べるトレイには4つまでしか入らないからだ。取りあえずコーヒー、麦茶、烏龍茶を選ぶ。そして最後にオーダーボタンを押す。 オーダーが入ると、ドリンク作成を任されている男性がそのために働き出すのが見える。機械であるASIMOへオーダーしているというよりは、その男性をタッチパネルで動かしているようで、何となく悪いことをしているような気がしてしまう。 やがてタッチパネル上のステイタスが変化し、ドリンク運びが始まることを知らせる。見ているとタッチパネルの表示は意外と細かく状況を知らせているのだが、ASIMOが動くのを心待ちにしており、かつASIMOのほうばかり見ているせいで、それに最初は気づかなかった。我々だけではなく、実際にほとんどの人がそういう状態になってしまうらしい。
ドリンク・トレイを手にもたされたASIMOが歩いてテーブルまで寄ってくる。ASIMOは足元のマーカーを確認しながらテーブル前まで来ると、今度は頭部のカメラでテーブル上のマーカーを確認して、こちらがオーダーしたドリンク名を読み上げながら、おもむろにトレイを置く。近くで見ると、腕の動きはかなり硬く感じられる。 トレイをテーブルの上でいったんバウンドしながら置いているように見えるが、実際にはASIMOは、持っている荷重が抜けたことを手首の6軸力センサーで検知して、力を抜くようになっているのだという。つまり、少し軽くなったということを判断して置きにいっているのだ。トレイそのものの傾きは持たせ方に寄る。 こうして無事にデリバリーを終えたASIMOは、一礼する。我々は返礼しなかったが、実際に他のテーブルにデリバリーしている様子を見ていると、席についている人みんながASIMOに合わせてお辞儀している。実際に多くの人が何となくお辞儀を返してしまうそうで、その様子はなんともユーモラスだった。人型ロボットならではだろう。 こうしてASIMOは再び充電ステーションに戻っていった。充電ステーションは2台あるが、両方空いている場合は、もっとも近い充電ステーションに戻っていくようになっている。 ASIMOが戻ろうとしたときに「ASIMO」と呼びかけてみた。ASIMOには音声認識が実装されているはずだ。呼びかけに止まって振り向いてくれることを少し期待していたのだが、ASIMOはこの呼びかけには反応せず、まっすぐに充電ステーションへと帰っていった。後ほど確認したところ、今回の運用に関してはその手のインタラクション、人間とのやりとりに関する機能は全てオミットしたとのことだった。
ASIMOはデリバリーはしてくれるが、トレイの片づけは残念ながら人間が行なわなければならない。大津氏へのインタビューは、その話から始まった。 ● ASIMOに対する反応
はい。ワゴンからトレイを取ることならできるんですけれども。というのは、行きはトレイの重さが分かっていますが、帰りは、例えばいたずらでいろんなものを載せられたりしたら、その重さが分かりません。特にものを運ぶときにはASIMOの腕を揺れないように制振制御するんですが、その時には、手首から先の重量変化はかなり影響があるんです。 ――数百グラム程度でも? 100gや200g程度ならば大丈夫ですが、「運用」を考えると、何kgになるか分かりませんので。 ――先ほど、ASIMOとわざと距離を置いてみました。待ってくれないんですね? 2005年に発表したときにはその機能を入れてましたが、今回の運用に関してはやめました。お客様と距離が離れても今は待てないんです。理由は、タグとの通信の安定性です。例えばタグを見失ってしまうと、お客様がついてきていても、ASIMOは「見失った」という動作をしてしまいます。それを懸念しました。 ――さきほど、トレイを置いたあとに呼びかけてみたんですが、それもオミットしたんでしょうか? そうです。そういったところは今後の検討課題です。いまは定型的に受付案内とデリバリーしているんですけど、我々もコミュニケーションやインタラクションが不足していると思っています。発話も含めて、人とロボットの共存環境のなかで、どういう動きをASIMOがしていけばいいのか。それを今回の試験運用の中から抽出していきたいなと思ってます。 ――いままでのお客さんの反応は? はい。先ほどまでも席は埋まっていたように、多くの方に使ってもらっています。「物珍しい」ということで使っている面もあると思いますが、ここにASIMOが来てトレイが置かれたときの、お客様の嬉しそうな顔は、こちらとしても励みになります。 ――皆さんは、なんておっしゃってますか? そうですね。まず、皆さんのように取材で来られる記者さんには「本当に動いているんだ」という方々が多いです。実際に人がいる中で自律で歩いているASIMOを見て驚かれる方が多いですね。 また、弊社の社員でも、間近でASIMOを見た方はそんなにいないんです。1Fでデモはやっていますが、それはステージ上のデモで、近寄れないですし、こういったごく身近なところでASIMOが動くのは社員の方も体験していないんです。そういった面での驚きは、社員の表情を見ていると感じられます。記念撮影している人も多いです。 ――1日のデリバリー回数は? 平均9から10ですかね。最大11回です。3つしかテーブルがないので、打ち合わせ一回30分だと、多くても12回なんですよ。 ――今回の試験運用の一つのポイントは複数体協調です。実際に2台が活動するシチュエーションはありますか? はい。複数のオーダーが入ったときにはそうなります。ASIMOはどのテーブルの端末からオーダーが入ったかで動きます。たとえばテーブル2から4つ、テーブル1から2つ頼むと、それぞれ持ってきます。 ――人間がドリンクを作るのが気になります。思わず「頼むと仕事させてしまって悪いなあ」と思ってしまいますね。 確かに、いま大変なのはドリンク係なんです。紙コップがトレイにスポンとはいってASIMOがそれを運べばいいというようになれば、システムとして完結してるのかなと思いますが、それはまた難しいです。 ――テーブル上のマーカーにものがあると、ASIMOはそれをどかすまで待っているんでしょうか? そうなんです。それも改良したいところなんです。ASIMOがどういう状態なのかが周囲の人にわかりづらいんです。待ってる姿が固まっているようにも見えるんですよね。「どけてください」とか「置き場所がありません」とか、何かしらASIMOが意思表示してあげるといいのかなと思っています。実際に人が気づかない場合もありますので。 ――ASIMOから一言言ってくれれば、人間がサポートできることもありますね。 ● 複数体協調を実現したアーキテクチャー
ASIMOは複数で連携して動けるようになりましたが、それぞれネットワーク経由で情報共有しています。情報を共有して行動生成する部分を大きく変えました。情報とは何かというと、仕事するための距離やタスクの処理、そして充電の残量などのパラメーターのことです。パラメーターを加味して、仕事をするうえで一番最適のASIMOはどれなのかと連携したり、効率よくASIMOが動けるようにするというふうに変えました。 ――優先順位がかぶった場合はどうなりますか。 まるっきり同じスコアになった場合は、番機になってます。1号機と2号機と両方のスコアが同じになったら、1号機です。 ――ASIMO単体に行くのは単純な指令のみですか。 そうです。ASIMO単体が「いまどういう状況か」ということをサーバーに打ち上げて、「何番のテーブルにデリバリーしてください」という命令がサーバーからおりてくるわけです。あとはASIMOが自立的に、たとえば移動するときに邪魔をされたり通行人と対面した場合も、移動経路を自分で生成して避けていくわけです。バッテリの残量がある一定の閾値まで下がってしまったら、今度は充電するタスクが下りてきて、一番近い充電ステーションに戻ります。 ――今回、2台にしようという数字は、どうやって決まったんですか。 ここは人が通るにはじゅうぶん広い通路ですが、ASIMOが通るにはそんなに広い通路ではないんです。ASIMOがいっぱいいると、タスクが入っても、ASIMO自体がつまってしまって、シーケンシャルにしか動けなくなります。それで受付前と給茶機側の2体がこの空間ではベストだと判断しました。もっと広い空間なら台数は増やしてもいいと思います。 ● 自律移動技術 ――ASIMOは、基本的に人間はどうやって認識しているんですか?顔についているステレオカメラを使って、頭や肩の輪郭から人間らしさを検出しています。 ――ホンダの一部車両に搭載されている「インテリジェント・ナイトビジョン」と同じ技術ですか? あれも、頭と肩の輪郭から人間らしい物体を抽出すると聞いていますが……。 いいえ、関係ありません。考え方は似ていますが、まったく別の技術です。ASIMOと車とでは、速度域も見ている範囲も違いますので。 ――人間らしい影を発見したあと、移動体の速度や位置はどうやって検出しているんですか? ステレオカメラの差分で、移動体がどちらに移動したかベクトルを検出しています。ASIMOのカメラのシャッタースピードは明るさによって変えているんですけど、この明るさの環境だと、サイクルタイムは数十分の一秒くらいです。
ASIMOが見えるのは数メートル先程度までなんです。そのレンジで人とのすれ違いをしようとしたときに、自分も歩いていて人も歩いてくるわけです。本来ならばもっと先まで見えてほしいんです。単に止まるだけならいいいんですけど、判断してよけるとなると数十分の一秒くらいのサイクルタイムで見ていないと間に合わないんです。 ――人間に比べると、かなり近視なんですね。 そうですね。あまり遠くまで見えた場合、それが本当にこちらに関係あるのかといった問題も起きます。関係ないところまでよけてしまうという問題もありますので。 ――明るさの変動に対してはどう対応しているんですか? 直射日光が入らない限りは、この環境ですと、蛍光灯の明かりが支配的なので、ほとんど外光の影響はありません。 ――でも今後は、ロビーのような外光が差し込む環境も歩かなくてはいけないと思いますが? そういうのも視野に入れて研究は進めてます(笑)。現在のこちらの環境では、テーブルへの案内だけではなく、もうひとつ奥の会議室への案内というタスクがありまして、そちらに案内するときに、ガラス面から季節によっては西日が向かいのビルに反射して入ってくる可能性があります。そこでは床面のマークが見えにくくなることはあります。赤外線で見ているので、反射膜が点として見えなくなってしまうんです。 ――当然、最近流行っている高精度な地図作成と自己位置認識技術も研究していらっしゃると思います。現在は床にマーカーを貼るほうが現実的なんでしょうか? いまはマークを使って自己位置を測定するのを基本にしています。マークは、なくしたいといえばなくしたいんですけど。現在はマークを使った自己位置補正だけしか使っていません。見た目はよくないんですがマークの部分に赤外光を吸収する黒い布地の上にマークをはっておくと直射日光の問題も回避できるんです。ステージ上でのデモでも使っています。 ――床を見ると机等の位置などもきちんとマークされていますね。いまはマップは固定ですか? 随時更新はしないんですか? 固定です。あらかじめ地図を持っていて、そのなかで障害物発見を常に行なっています。 ――経路上の床に何かが落ちていたら? 落ちているものがあったら停止します。ファイルや紙一枚だと高さ的に厳しいので、そのまま踏んづけていってしまうかもしれません。 ――先月の記者発表のときに、ASIMOはホンダが研究してきた知能化技術を集めたとのことでした。もう少し詳しくお願いします。 「移動知能」という面では、「すれ違い」のようなところです。いままではマークがあって、いわば見えない線の上を歩いていたわけですが、今回は一本のラインではなく面の移動ができるようになりました。領域内であれば自由に障害物を避けて目的地まで歩けるようになりました。 ――決められた経路があってそれを選ぶのか、そうではないのでしょうか? 決められた線があるわけではありません。碁盤目状のポイントがあって、それを繋ぐような形で経路を予めルート生成して、その経路にそって歩いていきます。そのなかで障害物があると、避けて、いったん経路から離れるんですが、障害がなくなるとまた経路まで戻っていくという形です。 ● ヒューマノイドならではの立ち居振る舞い
それは意図的にやっていることなんです。ASIMOが見ることのできる距離が数メートルなので、対向する人に対してASIMOがどっちに避けるのかということがはっきり分かるように、意識的にかなり腰を振っているんですよ。クビもそうなんですけれども、「自分があちらに行きますよ」ということを意思表示して、相手がよけやすいようにしているんです。 ただ、今はそのやり方をとっているんですが、そのやり方が、「そっぽを向いている」とか、「嫌がられて避けているように見える」という人もいるんです。 ――今後どうするべきかは難しい課題ですね。 ええ。人間のコミュニケーションは言葉だけではなく体の色々な部分の動きで伝わっているので、そのへんの頃合いですね。人間の形をしているぶん、ヒトにとって違和感のない動きがあると思うんです。 そういうことも、やって初めて出てくる課題なんです。研究所のなかでもいろいろテストをやってるんですけど、研究所の人間はやっぱりASIMOを知ってるし、ちょっと違うんですよね。だからあまり参考にならないんですよ。ASIMOを知ってる分、手加減をしてしまうんです。自然にASIMOに接してくれる、まったく知らない人がASIMOに対してどのように接してくれるのか。いままだほとんど出来ていませんが、そういうデータを今後のインタラクションに役立てていきたいなと思ってます。この環境を通じてそういうデータを抽出したいと考えています。 ● 自動充電機能 ――自動充電についてお伺いします。ほとんど足を踏み換えることなく一発で位置決めして充電できることに驚きました。あれはマーカを使った位置制御の精度の高さによるものですか?そうです。スタンドのところにマーカーがありますが、あのマークの位置精度がまず大事です。ASIMOは、それがほとんど数ミリの誤差で再現できるんです。その数ミリの誤差はコネクタのほうから出ているガイドのピンがテーパーになっていて、許容できるようになっています。もちろん号機によってバラつきはあるので、充電ステーションに対して最初に位置決めのテストを行ない、どれだけのオフセットがあるかをそれぞれデータベースに入れておきます。そして充電ステーションとASIMOの関係で、オフセットを補正しています。 ――さすがですね。しかしモーターだと、だんだんへたってくると思いますが……? 何日もやってますけども、一回も失敗したことはありません。
● 運用における安全性の課題 ――天井カメラのようなインフラ装置を使わなかった理由は?検討は行ないました。ですがマークでかなり精度よく自己位置は取れるんです。ただ安全面からいうと、運用に用いるためのカメラは必要かもしれないと思っています。オペレーターや監視用のカメラです。いまは人間が「サポーター」という形で見ていますけれども曲がり角の監視をするためのカメラは必要かもしれません。インフラを使って、カメラに人が映っていたらASIMOに対してそこの通路は行かないように指令を出すとか、そういった形はあるかなと思っています。 ――屋内にカーブミラーをつけるわけにはいかないでしょうしね。しかし、かといって、あのように人が立ってると、見張られている感じがあります。 ええ。 ――さきほど私は敢えてASIMOの邪魔をしました。私が敢えて邪魔していたのは監視の方にもすぐに分かったと思います。ですが、だんだん邪魔なのか、ASIMOとじゃれているだけなのか分からなくなることもあると思いますが。 運用の立場からすれば、明らかに邪魔しようとしている人のほうがいいんです。ASIMOを意識しているわけですし、よっぽどの人じゃなければ押し倒したりはしないと思いますし。いちばん困るのは、ASIMOをぜんぜん意識してなくて横からぶつかるといったケースです。現在のASIMOには転倒制御は入っていませんので、ぶつかりそうな人がいたら、目視でASIMOを止めるという手段で対応してます。 ――実際にぶつかった人はいますか? ぶつかった人はいませんが、ぶつかりそうになった人はいます。急いで通ろうとして、少し狭くなっている通路を走るようにすりぬけていったときには、ちょっとひやっとしました。 ――なるほど。人間は平気だろうと思ってるだろうけど……。 はい。ASIMOのほうからは移動体として抽出できるといいんですけど、走っている場合だと検出が追いつきません。6、7m先に見えたとしても、分かって次の行動を起こすまでには、もう通り抜けているでしょうし。走られると対応できません。 ――そこは応答サイクルをあげていくんでしょうか? そうですね。あるいは遠くまで見えるようにしていくか。そういうものがどういうケースなのか、こういう場所を使って、その事象に対してどれだけの距離が必要か、走ってくる人がいた場合はどれだけの処理が必要か、今回の試験運用のなかで蓄えていきたいと考えています。次の開発のための課題を抽出するというのが今回の試験運用の大きな役目ですので。ASIMOの機能として不足している部分は運用で、人がサポートすることでカバーしながらやってます。 ――非常停止を押したことはありますか? ポーズボタンを押したことはあります。お客様のほうがASIMOに気づいてなくて、ぶつかりそうになったときです。 ――ASIMOは54kgですね。実際にASIMOと人間がぶつかるとどうなりますか? 分かりません。転倒試験はやっていますが人間とASIMOがぶつかるというテストはやっていませんので。人間はかなり柔軟ですが、ロボットの場合は硬直しますので、54kgの塊となるとかなりでしょうね。 ――人がいる空間で動くとなると、例えば駅の構内で大きな機械が動くときに音楽を鳴らしていますが、そういうやりかたはどうでしょうか? ここでは外していますが、ASIMOが行動を起こすときや向きを変えるときに「ピンポン」と音を出すテストは、やっていました。しかしながら常時音楽を流すのは商談スペースでは迷惑ですので、ないのかなと思います。 ――そのあたりは今後ますます問題になりそうですね。いまはみんな、ASIMOが動き出すと注目していますが……。 ええ。いまは、暖かい目で見てもらっていると感じてます。それが時間が経って飽きてきたり慣れてきたときにどうなるのか。逆に、そういうふうになったときに、実際に、生きた情報やデータがとれるのかなと思ってます。いまは人間のほうが気を使って、一歩引いてますから。 ● 人間のリアクション ――先ほども話に出ましたが、人間がどう反応するのかというのも調査のテーマですか。そうです。ASIMOが仕事をすることで人間がどう反応するかということと、どのようにASIMOが動けば人と違和感なく共存できるのか。人の形をしているぶん、人に対して違和感のある動き、違和感のない動きがあると思うんです。 ――これだけ近い距離で、しかもステージ上のデモではないとなると「ASIMOに触りたい」という人もいると思いますが……。 そこは、ちょっとご遠慮致しますとお願いしています。握手したいという方は多いです。バッテリ充電中でも手を差し出したり、ASIMOの手を握って手をとろうとする方もいらっしゃいます。 ――ASIMOがお辞儀するとみんなお辞儀しかえすんですね。 ええ。ほとんどの人がします。 ――人型ならではの反応だと思いますが、今後、同機能だけど人型ではないロボットで反応を見るといった実験は? そこまでの実験予定はないですが、ASIMOが接客するとき、お辞儀するときやしゃべり方の「間」は、いろいろ変えてやってます。不自然じゃない形を探すためです。まだちょっとワンテンポ遅いと思うんです。今後、そういうところを詰めていきたいなと思ってます。 ――先ほど案内してもらいましたが、残念ながら、まだASIMOと目線があっている感覚はありませんね。見られているという感覚も、思っていた以上にありませんでした。 目線があうと、すごく不思議な気持ちになりますよ。ASIMOは握手するときには人間を見上げて目線を合わせるんですけれども、ASIMOを見下ろすと不思議な感じがします。 ――開発されている大津さんご自身でもですか? 頭のなかでプログラム・コードが走るわけではなく(笑)? ええ、それを飛び越えてくるんです。不思議な感覚があります。 ――先ほど、ASIMOに呼びかけてみましたが無反応でした。止まって振り向くくらいの反応は欲しいように思います。 反応してほしいでしょうね。受付のASIMOにも話しかけてくれるお客さんいるんですが、反応しないんです。そういうところは改善する余地があると思います。例えば今までのデモ用のASIMOでも、手を振ったときに振り返すだけで喜んでくれるお客様はいました。それは、これまではオペレーターが後ろで操作していたものなんです。逆にここのASIMOは完全に自動なので、そういう反応を返さないんです。 ――愛想をふりまくことがなくなってるんですね。 そうですね。仕事に集中しちゃってる感じなんです(笑)。 ● 交通シミュレータ技術とASIMO 私がASIMOの開発に関わりはじめたのは2005年からです。それまでは交通シミュレーターの仕事をしていました。今のASIMOにすれ違いの機能がありますが、それを車のシミュレーターでやっていました。 ドライビングシミュレーターの中では周囲の車はシナリオどおり動いていますので、こちらが突っ込んでいっても避ける動作をするわけじゃないんです。ああいった不自然な世界を実際の環境と同じように、例えば自分が突っ込んでいったら向こうの車は止まる、避けるようにする。つまり、まわりの車がそれなりの自律で動くようなシミュレーションをやっていました。その時の経験を生かし、ASIMOの実機を使って人間を避けるという動作を実現しました。 ――なぜ車ではなくてASIMOに? 実車に乗せるとなると自動運転となりますが、周囲の状況をセンシングするのは速度領域も高いですし大変なんです。ですがASIMOの速度域ならば、なんとかなるのではないかと。実際には当時のASIMOではまだ厳しかったんですが、もうちょっと遠くまで見られるようにして、今回、すれ違いが実現できたんです。 ● システムの狭間 ――新型ASIMOが発表されたのが2005年12月です。2007年になってからも、発表前にかなり長い間、こちらで運用前の試験をやってらっしゃいましたね。はい。まずは運用の問題です。人間がいる環境に入れてロボットを動かすということになりますと安全面の運用体制の確保が非常に重要になります。万が一の対策をどうするかで調整に時間がかかってしまいました。 また、システム的にも課題がありました。決められたステージ上のデモではないので、日々、違うことが起こります。それに対してシステムがちゃんと対応できるかどうか。それを調べるために研究所の人間が検証も含めて夜な夜なやってきて、「意地悪テスト」をしたりしました。色んな不具合含めて、機能を向上させていきました。 例えば、決められたタスクのシナリオを実行中にすれ違いが起こったときに、その繋ぎはうまくいってるかどうか、すれ違いが起こったあとに、すぐにデリバリーに戻れるかといった問題です。すれ違いできる領域も決まっているんですが、その領域の狭間みたいなところでイベントが起きたときにうまくいかなかったときどうなるか。システムのつなぎ目みたいなところで何が起こるかを調べていました。 ――具体的にはどうしたんですか? そこは申し上げられませんが、例えば目的地を設定して、中間の目的地を設定して、そこまでの経路を設定したりといったことです。自分たちが予想してなかった動きが起きるんです。決められたとおりに動いているわけではありませんので、自律で動いているぶん、自律になったときの動きの信頼性については慎重にやっています。 ● 次はワゴンを使った片づけ? ――今後は? 例えば本当に人間がやっているようにワゴンを押してお茶碗を片づけられればすごいと思いますが。予定には入ってます。ASIMOが自分でトレイをワゴンに載せるのは難しいですが、ASIMOが押せるワゴンを置いておき、そこに「飲んだトレイを置いて下さい」としておいて、ASIMOが定期的に回収することはできると思います。 ――先日の発表でもASIMOはなかなか上手にワゴンを中心に回っていましたが、人間はさらに重たいワゴンであっても非常にうまく遠心力を利用して回ることができます。 そうなんです。先ほど申し上げたように、この通路はASIMOにとっては狭いのでコンパクトに回る必要があります。ワゴンを押すとなると、かなりマージンが必要なんです。それに壁に沿って押すことができないと実際の運用で使うには厳しいんです。そういったところをこういった現場を使って作り込んでいくことが必要だと考えています。 最後にASIMOは、バックヤードからの指示で自分で歩いて戻っていくとのことなので、その様子も見せていただいた。ASIMOは「バックヤードに戻ります」と言ってスタンドから離れ、歩いていった。なお、サービス開始のときも自分で充電ステーションの位置まで歩いていき、準備するそうだ。 ついに実社会へと踏み出したASIMO。実社会では時々刻々なにが起こるか、誰にも分からない。なかには既存のロボット工学の枠組みだけではなく他の様々な知見を組み合わせなければ解けない課題もあるだろう。そこからまた新たな知恵が見出され、工学の形で記述されるのかもしれない。今後もASIMOの歩みに期待しつつ見つめていきたい。
■URL ホンダ http://www.honda.co.jp/ ASIMO http://www.honda.co.jp/ASIMO/ ■ 関連記事 ・ ASIMO、実社会へ一歩踏み出す ~複数台による協調動作を公開(2007/12/12) 2008/02/06 00:26 - ページの先頭へ-
|