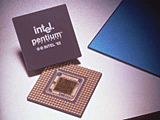|
記事検索 |
バックナンバー |
【 2009/04/17 】 |
||
| ||
【 2009/04/15 】 |
||
| ||
【 2009/04/09 】 |
||
| ||
【 2009/04/06 】 |
||
| ||
【 2009/04/03 】 |
||
| ||
【 2009/03/27 】 |
||
| ||
【 2009/03/24 】 |
||
| ||
【 2009/03/18 】 |
||
| ||
【 2009/03/11 】 |
||
| ||
【 2009/03/06 】 |
||
| ||
【 2009/03/04 】 |
||
| ||
【 2009/02/27 】 |
||
|
|
|
||||||||||||||||
|
鹿野 司の「人生いろいろ、ロボットもいろいろ」 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Reported by
鹿野 司
|
||||||||||||||||
|
過去50年の間に、人類の文明に決定的な変化をもたらした技術とは何だろう? たぶん、多くの人は、それはコンピュータだと答えると思う。 コンピュータの発明は、確かに凄いものだった。なにしろそれは、手回し計算機で延べ1年はかかった弾道計算を、数日で解くほどの圧倒的な進歩だった。 でも、1958年に集積回路が発明されず、コンピュータが大型のまま留まっていたら、世界の変化はわずかなものに限られたろう。集積回路というアイデアの発明こそが、世界を本質的に変化させる力を持っていた。 1940年代半ばに作られた初期の電子計算機は、たくさんのリレー(スイッチ)や真空管などの部品を、1つ1つ組み合わせて作られていた。 やがてその部品は、1947年に発明されたトランジスタに置き換えられていく。 なにしろリレーや真空管は壊れやすいので、それを膨大な数必要とした計算機は、頻繁に故障していたのだ。 たとえば、アメリカ最初の電子計算機であるENIACには、約1万8千本の真空管が用いられて、それが20分に1本の割合で切れていたという。
これに比べると、トランジスタは滅多に壊れないので、複雑でも毎日きちんと動かすことができる。また、小型で、発熱が少なく、消費電力も少なく、動作が速く、全く良いことずくめだったわけだ。 でも、トランジスタを素子=1個の部品とする限り、そこには自ずと限界がある。 コンピュータの処理能力を上げるには、部品の数をどんどん増やしていかなければならない。すると、それを組み上げる手間やコスト、動作の検証、設置スペースや必要な電力、メンテナンスの作業量なども、それに比例して増加していく。その結果、やがて現実的な値段での性能アップが図れなくなっていく。 一方、集積回路は、部品を集めて回路を作るという従来の概念を変えて、シリコン基板上に一度にトランジスタ回路を作ることを可能にした。しかも、それはフォトリソグラフィーという、一種の印刷技術で行なわれる。つまり、印刷を縮小しさえすれば、コストをほとんど変えずに、詰め込む部品を増やしていけるわけだ。 このアイデアこそが、真の変化をもたらした。 その集積度の向上は凄まじいもので、それを言い表したのが有名なムーアの法則だ。 1965年、当時Intelの社長だったゴードン・ムーアは、「Electronics」という雑誌に、半導体チップに集積されるトランジスタ数は毎年倍増する(その後1975年の論文で2年ごとに倍増と修正された)という経験則を発表した。 このムーアの法則の数値は、CPUとメモリで違うなど微妙に諸説あるので、ここではざっくり、情報処理に必要なコストが15年ごとに千分の一になってきたとしよう。 つまり、1958年の集積回路の発明から48年を経た現在、情報処理のコストは往時の10億分の1以下になっている。50年に満たない短時間に、何かの性能が10億倍になることなど、人類史上かつてなかったことだろう。 赤ちゃんのハイハイも千倍するとジャンボジェットの速度になる。工学の多くの場面で0.1%、つまり千分の1以下の誤差は無視できる。千倍という変化ですら、これほど大きな差異を生むというのに、千倍の、千倍の、さらに千倍の変化が、たった半世紀のうちに達成されたわけだ。 では、もし、集積というアイデアが生まれなかったら、どうなっていただろう。 トランジスタを組み上げるまでの技術で、どれくらい複雑なものが作れるかというと、たぶんアポロ宇宙船+サターンロケットレベルくらいまでなら可能なはずだ。 アポロ計画は、1961年5月25日のケネディ大統領の「10年以内に人類を月へ」という声明で始まった。当然、そこには集積技術は、ほとんど使われていない(注1)。基本的に全ての部品を、1つ1つ組みあげて作られたわけだ。
そして、アポロ計画の予算は1969年の貨幣価値で254億ドル、当時のレートで9兆円以上で、そのときの日本の国家予算が7兆円だった。それから推定すると、低く見積もっても、これを1つ作るのに当時の金額で10億ドルはかかったろう。 また、根拠は不明だが、ウィキペディアのアポロ計画の項を見ると、アポロ宇宙船とサターンロケットのみの費用は、2005年の価値で約830億ドルだという。 まあ、いずれにせよ、とんでもない額の金が必要なことは間違いない。
つまり、集積技術が存在しなくても、1兆円くらいかければ、初代Pentiumと同等のコンピュータは作れるだろう。 ただ、これだけ高価では、応用分野も需要も限られてしまう。たぶん大国に数台設置するのが精一杯で、使い道もほとんど軍事に限られるだろう。それに何より、性能も今からすると貧弱だ。 2006年現在のPentium Dは、90nmのプロセスで作られ、面積200平方mmのチップに、ゲート長32nmのトランジスタを、2億3千万個集積している。ちなみに、インフルエンザ・ウイルスが80~120nmくらいだから、今のMPUの基本単位はウイルス並ってわけだ。 そしてこのプロセス技術なら、2mm角で460万トランジスタが可能になる。その値段は10円くらい。 つまり今では、アポロなみの複雑さを持つものを、10円で作れるようになっているわけだ。 この圧倒的な変化によって、高度な処理が、コンパクトで、安価に提供できるようになった。あらゆる機械にコンピュータを組み込み、自動制御することができるようになったわけだ。 これは最終製品の性能を上げただけでなく、半導体製造装置を含む、すべての製造装置の性能も向上させた。その結果、さらに優れたマイクロプロセッサやメモリの製作が可能になり、それがまた製造装置の性能を上げると同時に、マイクロプロセッサやメモリの応用範囲を広げるという、正の循環を産み出した。そして集積技術の生み出す複雑さは、かつての技術では越えられなかった壁を、易々と乗り越えてさらに先へ進もうとしている。 この技術は、現代文明の全てに大きな影響を与えている。 たとえば今では、1800年代の人口と同じくらいの人(10億)が、毎年飛行機で世界を移動する。これ1つとっても、集積技術の存在が不可欠だ。 1機のジャンボジェットのコントロールがMPUなしには不可能であると同時に、大空港での数分に1機の離発着を可能にする管制システムも、これなしではありえない。 集積技術の発展によって、世界はすでに、ある意味でロボット化されている。コンピュータ、メモリ、センサ、アクチュエータが組み込まれたメカトロニックな装置群が、家庭にも、街角にもみちあふれている。そして都市や地球すらも、1つの巨大ロボットと見なすことができるようになりつつある。世界はもはやロボットなしにはいられない。 我々を取り巻くこのロボットたちのあり方を、これから読み解いていくことにしよう。 注1:アポロ宇宙船には、アポロ誘導コンピュータ(Apollo Guidance Computer)と呼ばれる、初期の集積回路を使った装置が搭載されていた。 初代のBlock Iバージョンは、4,100個のトランジスタ回路を集積しており、実際に月まで飛んだBlock IIバージョン(1966年に設計)は、5,600個のトランジスタ回路を集積していた。トランジスタ回路の集積というと、今の感覚だと非常に細密なものをイメージするが、このころの集積回路のトランジスタは1つ1つ肉眼で十分見える大きさで、全体のサイズもかなり大きなものだった。 ちなみに、1971年から出荷された世界最初のマイクロプロセッサ、Intelのi4004は、3mm×4mm角のチップにトランジスタを2,300集積して、動作周波数は500~741KHz。 アポロ誘導コンピュータで使用されたRAMは、磁気コアメモリでできていて、16bitを1ワードとする4Kワード、つまり今のコンピュータでいうなら8KBの容量があった。また、ROMはコアロープメモリを使用して32KBあり、サイクルタイムが12マイクロ秒だから、83KHzくらいで動作していたわけだ。 こんなに貧弱なハードウェアで月までの往復を成し遂げたのは、今からするとまさに驚異的で、初期のコンピュータ・ハッカーたちが、いかに優秀だったかがわかる。 ● ミニコラム:奢れるムーアも久しからず 微細化の限界は、2020年くらいにはやってくる。そうなると、集積がもたらす圧倒的な技術文明の進歩も、ついに滞り始めるのだろうか。すでに現状、集積をあげるためには色々な工夫を組み込む必要があって、その結果、集積の割に性能が上がらなくなってきている。たとえばマルチコア化の流れは、膨大な数のトランジスタを素直に生かせるシングルコアのアーキテクチャを、思いつけなくなってきたことを意味しているわけだ。インテルの偉い人などは、まだまだ行けるよというけれど、終わりは着実に近づいている。 ただ、仮に2020年に集積が限界に達しても、まだまだ技術は伸びていくだろう。 なぜなら、これまでの集積のペースがあまりにも速かったため、それが内在している可能性のわずかしか試されないうちに、次の世代の技術に移行するということがずっと続いてきたからだ。つまり量的拡大が速すぎて、質的可能性の探索が追いついていない。ちょうど、過飽和とか過冷却みたいな状態だ。 今の生物の基本形はカンブリア爆発期に作られた。そして、それが起きたのは以前に大量絶滅があったからだ。大量絶滅のあと、生き延びたわずかな種類の生物が短期間に爆発的に増え、地球に満ちたことがわかっている。そしてその、割と単純だけど膨大な量の生物がいる環境で、カンブリア爆発が起きたのだ。これと同じように、集積技術はいま、大量絶滅後の、限られた生物の爆発的な増殖期みたいなところにある。つまり、集積技術におけるカンブリア爆発は、2020年以降にこそ起きるんじゃないだろうか。 2006/07/11 00:12 - ページの先頭へ-
|