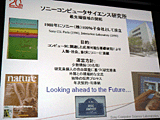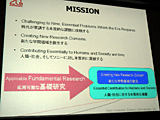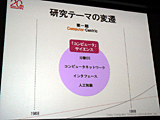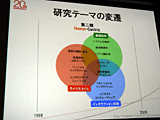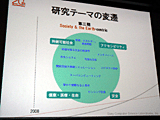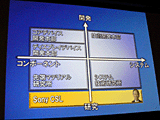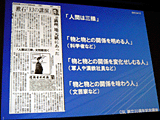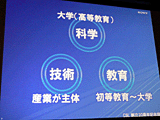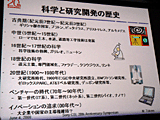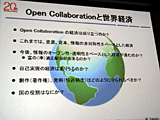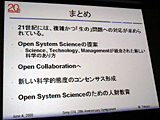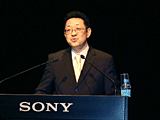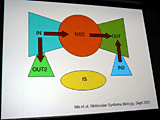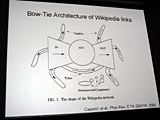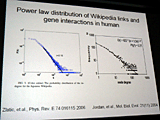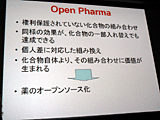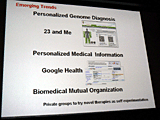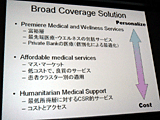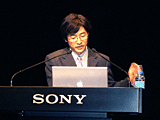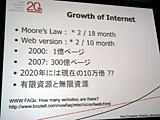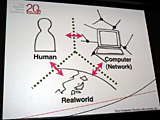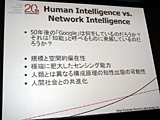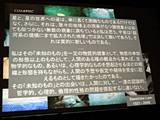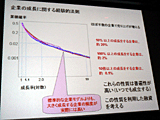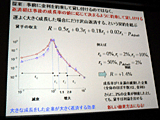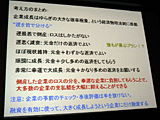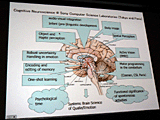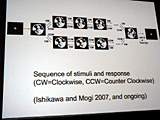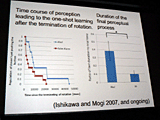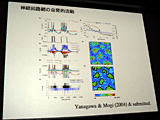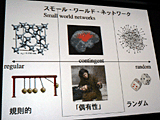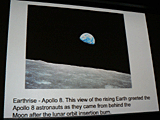|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ソニーCSLの考える「21世紀の社会と科学・技術」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンピュータは最初の10年を経て、コンピュータを使ってはじめて実現可能な、いわゆるコンピュータ・サイエンスを生むにいたった。では次の10年、何をするべきか。ソニーCSL代表取締役社長の所眞理雄氏は21世紀に本当に解決しなければならないと考え、資源やエネルギー、環境問題などの持続可能社会、アクセシビリティ、健康・医療・生命、安全を研究テーマに選んだ、と述べた。今回のシンポジウムは、我々が置かれている現状を見据えつつ、何を研究するべきかに対する表明だという。
● キーノートスピーチ「21世紀の科学と技術」 ~これからは「不安の払拭」の時代
中鉢氏は、研究所のミッションは2つあると考えて、研究所の再編を行なった。1つ目が既存事業への貢献、2つ目が現業の事業領域に入らないシーズを生み出すことへの期待である。そこに至るプロセスを研究から開発へという軸と、コンポーネントからシステムへという流れの軸を考えて4象限に分け、それぞれに役割を与えた。先端マテリアル研究所はコンポーネント研究、コアデバイスは次世代デバイス、ディスプレイは有機EL関連、システム技術研究所はセキュリティほか、技術開発はソフトウェアや信号処理、UIである。そしてソニーCSLは直接ソニーの事業ではない部分で貢献してくれることを期待しているという。 中鉢氏は、5月24日の朝日新聞に掲載された、夏目漱石が昔、満州で行なったと伝えられる講演内容を引いて話を続けた。それは「物の関係と三様」と題された講演で、「人間には三様がある」というものだったという。三様とは、「物と物の関係を明らかにする人(科学者タイプ)」「物と物の関係を変化させる人(軍人や主な講演の聴衆だったと考えられる満州鉄道社員)」、そして「物と物との関係を味わう人(漱石自身を含む文学者など)」だ。社会においては3者のバランスが取れていなければならない、と漱石は述べたという。 中鉢氏は学生時代に夏目漱石の著作をむさぼるように読んでいたそうだ。だがこの記事を読んで、目から鱗が落ちた。これまでは夏目漱石の著作物を読んでも今ひとつ腑に落ちない部分があり、作者である漱石が本当に言いたいことが掴みきれなかったが、漱石が言いたかったことはこれではなかったか、と思ったという。 漱石が語った三様は今日では、「科学」「技術」「教育」と置き換えることができるのではないかという。たとえば政治や会社の経営などもある種の「技術」と見ることができる。物と物との関係を味わうのをartだと考えれば、教育の世界だと捉えられるからだ。そこで今回の演題を科学と技術と、教育としたという。
中鉢氏は1968年春に大学に入学した。専門は資源工学。時代をやや遡ると1960年代は学園紛争などで日本が揺れた時代だった。中鉢氏もその流れに飲み込まれたという。大学では産学共同反対、中教審反対、佐藤栄作内閣打倒のスローガンが叫ばれていた。騒然としており、落ち着いて勉学に励むことは難しく、社会的騒乱がどこまで広がるのかと不安に感じていたという。当時の若者は、いやがおうにも社会的なことに無関心ではいられなかった。 当時は、大学教員たちも批判対象だった。また公害問題が発生していた時期でもあり、科学技術にも疑問がわきあがっていた。そして学部に入った1970年11月、三島由紀夫が自決する。それまで騒然としてはいたものの学部に入って研究に従事しはじめいた中鉢氏は、フィクションと現実のギャップを実感し、学生運動にむなしさを感じたという。 物財だけがあふれていて精神性が失われていくということを訴えていた三島。いっぽう、学部に入ってのうのうとしている自分に対する自問。当時に、これまで愛していた三島に対する憎悪感、裏切られたという感覚もあった。この結果、三島を嫌いになったわけではなかったが、それ以来、彼の本は一冊も読んでいないという。 中鉢氏は、溶鉱炉のなかの亜鉛の挙動に関する研究で卒論を書いた。きわめて溶けにくい亜鉛の化合物から亜鉛だけを除去するための研究で製鉄会社からの受託研究だった。つい先日まで、産業界と大学が連携することに嫌悪感を持っていたことに自分自身が手を染めているという反省もあり、非常に複雑な思いだったという。また、国内の鉱山は閉鉱していく時代で、これからの資源工学をどう教えるかということが学科のなかでは話題になっていた。 鉱山を継続して運営するためには、探鉱して隠されていた埋蔵量と、掘って採掘したものとがバランスが取れていなければならない。だが掘った量は増えるが見つけた量は少なくなっていく。こうなると将来は見えている。にも関わらず、採油学とか、採炭学、採鉱学が学科では教えられている。無意味じゃないかと思ういっぽうで、でも大学とはそういうものだという気持ちもあったという。 そんなとき、北海道に1泊2日で出かけた。北海道大のキャンパスに行くと、日本数学会の学会が行なわれており、市民講座として「あなたはマンモスを殺したことがありますか」という講演が行なわれていた。講演者は京大の三輪哲二氏。マンモスはもちろん現代の世界には生きていない。マンモスの殺し方を教えたって、現実には使いようがない。中鉢氏は、石炭のない時代に採炭学を学んだ自分は当然これを聞かなくてはいけない、と思ったという。要するに、講演者であった三輪先生が仰りたかったのは、数学とは、マンモスの殺し方を教えているようなものであり、つまり、実生活には役に立たない知の鍛錬、修練のようなものなのだという講演だったという。 やがて中鉢氏は鉱山会社への就職推薦をもらった。鉱山が閉じていく時代に鉱山会社を推薦してもらうことは稀有なことだったため、非常に誇りに感じたという。だが、教授からは進学しろと言われて、結局進学することになる。1972年のことだ。 同年5月に沖縄返還。「これで世の中が変わったな」と思ったという。アメリカが沖縄を返還するとはありえないと思っていたからだ。そして同じころ、ローマクラブから「成長の限界」が出た。中鉢氏は「ああ出たか」と感じ、特に驚きはなかったそうだ。1973年、石油ショックが起こる。これまた想定内だったという。 もっとも当時、ローマクラブの提言が出たことから教授から「君は結婚したら子供を何人作るんだね」と聞かれたところ、何気なく「5人」と答えたところ教授に「自分の欲望をコントロールしないといけない時代が来るのに君はエゴイストだ」と怒られたという。中鉢氏は「もう一度学生運動やってやろうか」と思ったと語り会場の笑いを誘った。 いっぽう環境の変化を受けて、新しい研究をやろうではないかと教授たちは言い出した。こうして鉱物処理の技術を使った水処理・公害処理関連の研究と、人工鉱物としての電子材料の研究が始まった。中鉢氏は後者を選んだ。ちょうど1970年にフランスのルイ・ネールらが反強磁性およびフェリ磁性に関する基礎的研究でノーベル物理学賞を獲得した時期でもあり、ターゲットはマンガンジンクフェライトなどのフェライト化合物だった。これをコア材料にしようと考えた。目標はハードディスクのメディアを開発することだった。 修士を終えたあと、最初はある公的研究機関に対する就職が決まっていたが、トイレで連れションしていたときに急に教授から「あそこは定年がはやいからやめろ、そして進学しろ」と言われた。そのときは「実力を認めてくれて自分を後継者にしようと思ってくれているに違いない、研究者としての道は決まったな」と思ったという。 それでドクターコースへ進むことになる。当然、ジンクニッケルフェライトの研究をすると思っていたのだが、急にマグネティックインクの研究をしろと言われることになる。「磁性流体」である。もともとNASAが宇宙服のシール材として研究していたものだ。非常に高価だったが、これを水で作れ、つまり磁石でくっつく水をつくれと言われたのだという。中鉢氏は、また一から出発か、しかも博士課程の後期過程は3年間しかないため焦った。おまけに水処理はケミストリーであり、もともと水が嫌いだったから材料系に行ったのに、と苦手意識もあったという。これはないだろうとものすごく不安だったことを良く覚えているという。博士課程の最中、1975年に結婚する。その経緯は省略されたが、仲人はもちろん教授だった。 当時、研究室にはソニーの重役が来ていた。ソニーの仙台工場の初代の工場長が教授の同僚であり、もともとソニーとゆかりのある研究室だったのだという。そのソニーの人が「大学の設備は劣悪だ。だから夏はうちに来てやりなさい」と伝えた。ソニーの研究室は大学と違って、冷房が効いていた。 とは言うもの、やはり学生だったため躊躇いもあった。ところがソニーは奨学金をやろうと言う。ソニーには今も昔も奨学金制度はない。だがある日突然、現金書留の封筒が届き、中にキャッシュが入っていた。領収書のハンコを押せばそれでいいという。そのカネは「なにせ学生ですから飲んで何もありません」とのことだったが、実のところは生まれたばかりの子供のミルク代として大いに生活を助けたようだ。 というわけで、博士課程取得後は、ソニーから声がかかるのではないかと期待があったそうだ。しかしながら何もなかった。そうこうしているうちに教授から紹介状を書くから試験を受けろと言われた。1977年、ソニー入社。首相は福田赳夫で、日本のGDPは世界17位。そこそこの国だったが、世界経済を引っ張っていくんだという気持ちはあった。しかしながら、オリンピックがあった当時から比べると、いささか陰りが出てきていた時期だったという。 ドクターをとっていた中鉢氏は横浜の中央研究所に赴任すると思っていた。結婚して両親と同居していた氏は、横浜戸塚に行けるなら親子3人で暮らせる、しめしめと思っていたが、配属先は仙台だった。これにはがっくり来たという。宮城県で生まれて育って就職もこれかと。あとでわかったことだが、大学の教授とソニーの人事担当がゴルフをしながら決めてしまったのだそうだ。 さて入社したときにはフェライトやマンガンジンクフェライトの研究を進めろと言われると思っていたそうだが、仙台で実際にやれといわれたのは磁気テープだった。当時はベータが出たばかりの頃だ。'80年代くらいに実用化する予定のベータの次のフォーマット「80P」をやれというのが会社からの命令だった。メタルテープだ。中鉢氏は「ドクターの実力拝見」という感じなのかな、と思ったという。同時に、これをスバッとやれば理解されるとも思った。ところがここから8年間足踏みすることになる。 ここで講演時間は予定では残り3分を切った。だが中鉢氏は「いよいよ本題ですが」と講演を続けた。ソニーの教育財団においても来年が50周年記念になるから記念事業の意見をもとめるというアジェンダがあった。事務局からは今回同様のシンポジウムをやろうという提案があったという。これまでの50年とこれからの50年、というテーマだ。だが委員の中から誰に聞かせるんだという質問が出た。 教育財団はもともと理科教育振興を考えて設立された。量的な成長の時代はもはや終わった。日本の成長率は1950年代は10%だったが、いまでは1%そこそこになってきている。これからは科学者と技術者の連携が必要なのではないかと考えられるという。 講演冒頭の夏目漱石の親世代は、幕末と明治維新の世代だ。その子供たちである漱石たちには閉塞感があったのではないかという。中鉢氏は漱石の小説「それから」の主人公・長井代助の境遇を引きながら紹介した。代助は裕福な家の次男で、実家からお金をもらって生活している。だが食うための仕事は切実かもしれないが劣等だといってバカにしており、それにあまり接点を求めない生き方をしており、文明や哲学を考えるところに自分をおしやって自分のアイデンティティを確認しようとしている。この閉塞感はいまの若者と共通している面があるのではないか、という。例えば今の若者は、自分でものづくりをするのは古いのではないかと考えているのではないか。 100年前と今の時代が違うのは、成長の限界が見えていることだ。「欲望の充足」と「不安の払拭」、この2つの側面を考えると、これからは「不安の払拭」が重要になるのではないかという。不安は経験を踏むことで払拭されていくが、経験しなれば払拭されない。 これからは科学と技術の連携が重要になるという。そもそも日本では科学と技術をまとめて「科学技術」とまとめて言ってしまうところが課題であり、本来は「科学・技術」と分けて考えなければならないと語った。ソニー社内では、技術者コースと研究者コースが複線で勧められるような体制を進めていくという。 中鉢氏は、若者時代は産官学の癒着を批判していたが、今の立場になってみて初めて分かるのは「本当の意味で産官学が一緒になって話し合ったことはないのではないか」ということだという。最後に「あらゆる取り組みがソニーの社会貢献だ」と述べ、公私にわたって世話になった大学時代の教授に対する献辞で講演を締めくくった。
「グローバル化とはなにか」というテーマについて触れた。国際化(インターナショナル)とグローバル化という2つの言葉は意味が異なるという。ボーダーレス、国境が低くなったこと、そして世界でさまざまな事象が同時に進むことがグローバル化の特徴だそうだ。いまから見ると当たり前に思われるが、このような時代が始まったのは20年くらい前のことだ。国際化とは国と国とが水平に関係を持つことだが、グローバル化においては、国々は多次元な関係を結んでいる。このような時代に日本は適切な教育を行なっているだろうか。 「教育」とは、もともと非常に東洋的な考えだという。もともとは孟子のなかの言葉だ。孟子は、君子には「三楽」があると述べた。1つ目は父母兄弟に病気そのほかがないこと、2つ目は天に恥じることがないこと、そして3番目が天下の英才を得て「教育」することである。教え育つのが教育の原点だ。だが日本の教育は「育てる」という部分が不十分だという。知識は伝授するが人を育てていないというわけだ。 また、戦後教育は平等主義に陥ってしまった。これからの大学は英語でしっかり物が書ける人材をもっと出すために、カリキュラムを見直さなければならないと持論を述べた。 ● パネルディスカッション「ソニーCSLが考える21世紀の科学と技術」
科学はもともと社会の役に立つために生まれた。デカルトを経て要素分解が定着し、専門領域化が進み始めた。20世紀に入ると企業が研究所を持つようになり、最近ではベンチャー企業やイノベーションという言葉もにぎやかになっている。20世紀型の科学・技術は境界領域内の問題解決がすべての問題を解決するという立場で進められてきた。だが個別の問題として解決できることはおおむね出尽くしたようにも見える。これからは地球環境、エネルギー、資源の問題、健康・医療・生命の問題、安全性の問題、アクセシビリティの問題を解かなければならない。これらは互いに深く関わりあっている。クローズドシステムに対して有効だった要素分解の手法のみでは解けない。よって、新しいサイエンス、オープンシステムサイエンスが必要だと所氏は提案する。 オープンシステムサイエンスの特徴は、大きく分けて2つあるという。1つ目は、(準)最適解を求めることだ。境界領域や境界条件は動的に変化し、システムの定義や仕様は時間とともに変わり、システムは相互作用するサブシステムからなる。 もうひとつの特徴は、生きている形、実用状況での問題解決に役立つことが求められることである。動いている対象に適用可能な準最適解が求められる。要するにオープンサイエンスとは、複雑な、生の対象を相手にした科学だといえるという。そのためには、科学と技術、マネージメントを統合・融合した新しい科学・技術が必要になる。ではどうやって解くか。 科学からのアプローチは、時間発展系、指数関数的で且つ有限、相互関連モデルや多重連立方程式、テクノロジからは、問題の表現方法と実現手法、大規模数値シミュレーション、大規模エージェントシミュレーション、マネージメントからは正しい設計製造プロセスや、試行錯誤の方法が求められる。科学、技術、マネージメントを同時に考えていかなければならない。そのためにはどんな体制が必要か。 今はオープンなコラボレーションの時代だ。これからはネット/ソフトオタクだけではなく一般の個人も含んだ、研究開発を含む広い範囲で、非階層構造の対等な関係にいおいて、情報ならびに成果の共有が必要だという。だが理想はともかく、課題も少なくない。たとえばこれまでは資源、資本、情報の非対称性をベースとした経済が前提だったが、情報のオープン性、透明性をベースとした経済が進むのだろうか。だが速度は分からないものの、徐々にこういう方向に進むのだから我々は準備しておくべきだし、研究所は積極的に利用していくべきだろうと述べた。ベースとしての教育も重要だ。専門知識だけではなく、広い視野や思いやり、コラボレーションができる人材が求められているという。
● オープンファーマ
ひとはなぜ病気になるのか? 遺伝的素養だけではなく進化的な背景も原因にはある。遺伝子と生活習慣の組み合わせで我々は肥満になったりしてそれが病気に繋がる。ではなぜ太るのか。進化的には、これまで人類は長い間、飢餓に悩まされていた。基本的には飢餓環境に適応するようにわれわれは進化している。だが先進国はいまや昔のような状況にはない。その結果、我々の体は新しい環境に適応しきれず生活習慣病になっている。 疾患は、ロバストネスの脆弱さによって起こるとも言える。生物は北極圏にも砂漠にも住んでいる。生命は非常にロバストに対応する。だが個体レベルでは限られた環境にしか適応できない。 我々の代謝ネットワークの入力と出力をまとめると、「棒タイ構造」のネットワークになる。これはいろんな生物のアーキテクチャの基本だと見なせる。生物のネットワーク構造と、インターネットのリンク構造は同じ形になる。どちらもオープン環境で機能的に最適化を繰り返しているからだという。 さらに詳細に見ると、良く使われるノードと、そうでもないノードがべき乗分布しており、本当に同じようなネットワーク構造を持っていることが分かる。生物は工学システムと違うといわれるが、共通している部分は少なくない。 多くの疾患には複数の遺伝子が関与しており、そのためきわめて制御が難しい。どこのノードを動かせばいいのか分かりにくいからだ。がん細胞はスパムみたいなものと見なすこともできるという。近年、製薬会社では研究開発費用は3倍になっているが、アウトプットは半分になっている。ではどうすればいいのだろうか。1つの方法は複数のパスウェイを阻害する薬を併用することだ。 さらに「コンビナトリックス」という考え方も出てきている。想定外の効果があるような薬の組み合わせがあるか探すことだ。これによって例えば向精神薬と抗生物質を組み合わせると抗がん剤になるという驚くべき発見も行なわれている。システムレベルを複数のターゲットでおさえるのだ。問題は、さらに次の段階では何が起こるかということだ。 北野氏は「オープンファーマ」という概念を提唱している。権利保護されていない薬を組み合わせることで、新しい薬効を生み出すことだ。そうなるとこれまでは薬というコンポーネントそのものに価値があったが、これからは組み合わせ方そのものに価値が生まれる時代になる可能性が出てくる。 また、今は個人でもゲノムのシーケンスをしてくれて、病気のリスクを教えてもらうことができる。グーグルヘルスというサービスもある。カルテのような病院が持っていた情報が個人のコントロール下におかれようとしている。薬の治験も患者グループがカネを出して行なう時代が始まりつつある。いま、まさに薬のオープンソース化、医療の変化が起きているという。これらの動きが融合する。これまではカスタマイズといっても、既存のものを選択するしかなかった。これからは開発すべきものを患者が主体的に指導することも始まるかもしれないという。富裕層によるパーソナライズだけではなく、簡単に安くアクセスできることも重要だ。そのような流れもオープンファーマのなかでは起こりえるという。 このように、いろいろな社会的解決も出来るというと、それは夢物語だという人も多い。だがアーサー・C・クラークは「Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic(十分に発展した技術は魔法と区別がつかない)」と語った。そのことを忘れてはならないという。
● オーガニック・ユーザー・インターフェイスとサイバネティック・アース
ムーアの法則は半導体の集積度が18カ月で2倍に上がるとしたものだ。インターネットはそれを遙かに上回り10カ月で2倍の規模になっており、2020年には10万倍になるという。数倍程度までなら変化も予想できるが10万倍規模になることは想像を絶する。暦本氏は人間のクリエーションはまだまだテクノロジーによって制限されていると考えているという。では10万倍のリソースを使えば何ができるのだろうか。 まずあらゆるセンサーで体験する情報を共有できるようになる。Wikipediaがわずか数年で長い歴史のあった百科事典を超えてしまったように常識では考えられなかったセンサーの集積が容易におきる。協力して環境センシングすることで個人のライフケアの意識も変わる。やがて地球は必然的に超大規模な情報を抱えるようになり、電子世界は自然界に匹敵する規模と複雑性を持つ。現実世界と電子世界は並存するのではなく不可分なものになる。地球は全体でサイボーグ化するという。究極のユビキタスである。そのための要素技術はある。だが、こういうものをどうやって構成するかということは必ずしもうまくできていない。これは想像ではなく既に現実に、そこにある問題として横たわっている。 エネルギー消費がもっとも多い都市は人口一人あたりだと、アメリカではヒューストンなのだという。ニューヨークや東京は実は比較的成績は良い方で、高度に文明的ではあるが、広い範囲で分散している都市はエネルギー効率が悪くなる。地球にやさしい暮らし方は田舎で暮らすことではなく、一人あたりのエネルギー消費を効果的にすることを考えると集中したほうが良いという考え方もあるのだ。環境問題もネガティブにいくのではなくポジティブに、たとえばユビキタスコンピューティングでもっと最適化するといった方向もあり得るという。 インターフェイスも、これまではモノと人間の間の問題しか捉えてなかったが、人間、モノ、そして現実世界との三者間で考えなければならなくなる。これまではマウスに代表されるように、道具を使って現実世界をコントロールしようとするインターフェイスが主流だった。だがそれは技術が未熟だったからで、これからは逆にストーンからスキン、すなわちプリミティブでオーガニックなインターフェイスが復活するのではないか、と考えているという。「『オーガニック・ユーザー・インターフェイス』は『サイバネティック・アース』の重要なエレメントになる」と語った。 現状のグーグルは単純なインデックスをしているだけだが、50年後のグーグルは何をしているのかと考えると、現状では出現していないセンサー群の情報をどんどん収集していることになると考えられる。そこから人間とは異なるインテリジェンスが出現する可能性があるという。 暦本氏はスタニスワフ・レムの小説「ソラリス」を引いた。普通のSFに出てくるのは人間の延長的な存在でしかないが、「ソラリス」では惑星全体が知性を持っていて、人間と異質の知性のコミュニケーションギャップを描いた作品だ。映画化もされた。暦本氏はこれは20世紀に書かれたSF作品のなかでももっとも重要な作品の一つだと考えているという。このような存在が21世紀には出現することになるのだろうか。
● 金利に代わるシステムの必要性
投資・融資は現在社会の最重要事項の1つだ。たとえば環境問題においても何かアクションをするためにはカネが必要になる。またこれからの世界では定常的な状態を維持しなければならない。金利は指数成長を想定するが、それはあくまで空想の世界でのみ実現するものであり、現実の世界では一定の割合の成長は実現し得ない。空想の世界と現実のギャップがやがてひずみになり、不連続な大変動が起こる。これがバブル崩壊そのほかのような数年に一度の現象である。それを防ぐためには我々の発想を変え、もはやどこまでも成長することはありえないと考えるしかない。 金利はこれまでもずっと悪いものとして考えられてきた。常識的にはリスクが高ければ金利が高くなる。倒産しそうな人には貸し手が現れないので高い金利で借りざるを得ないのだ。だがこれは高い金利で貸し付けることで倒産リスクを上げていると見なせるし、また、イスラム銀行は金利なしの運用を既に実行している。ここから宗教色を抜いて、どこでも動く仕組みを実現したいという。 日本の企業の成長率を観測すると、売り上げの成長・減衰の確率はほぼ50%であり、過去に依存しないことが分かる。ほぼ半数の企業で売り上げが増えるわけだ。そこで、事前に金利を約束して貸し付けるのではなく、返済額は事後の成長率に応じて決まるよう約束して貸し付ける。そうすれば成長しなかった半分の企業には金利ゼロで貸しても貸し手が儲けられる仕組みが実現可能だという。
● 新しい鏡を手に入れていくのが人類の歴史
人間の脳には、他者の行動を見たときにも自分自身が行動を起こしても反応するミラーニューロンと呼ばれる細胞集団がある。このことは自己と他者が脳のなかで繋がりを持って表現されていることを示す。東工大での茂木氏らのグループではいま、化粧顔の研究を行なっている。スッピンの自分の顔を見たときと、化粧をした自分の顔を見せたときでは脳の反応が異なり、化粧をしたときの自分は、ある種の他者として認識している可能性が強く、しかも自分自身とアイコンタクトを繰り返すことで、その行動が強化されているのではないかと考えられるという。 つまり人間にとっては自己は他人との関係において位置づけられるものとして社会的に埋め込まれており、自分と他者が常に映し合わされているのではないかという。独創性がないと日本人はいわれてきた。だが個人の独創性は一つのフィクションである。独創的であるためにはネットワークのなかに自分を入れたほうがいい。多くの研究者たちも自分一人で考えていたことで成果を出したわけではなく、他人とコミュニケートした結果、成果が出せたのだ。 茂木氏がテレビやゲームのなかでよく見せている「アハ体験」というものがある。何かが隠れている図形を回転しながら示したときの脳活動を見ると、もうすこしで分かりそうだというところから、早とちりで間違えたときの反応のほうが速く、いっぽう、本当にわかったほうはゆっくり進行することが分かり始めているという。 脳は神経細胞ネットワークだ。特に、入力がなくても自発的に活動することを前提にしたネットワークである。脳内のネットワークは、短距離は結構決まっているが、長距離のパスは意外とランダムになっており、ランダムなネットワークとレギュラーなネットワークが組み合わさっているという。これはネットワークで情報がどのように処理されているかに関係している。茂木氏は有名な数学者エルデシュと論文を共著で書いた人間を示すエルデシュナンバーの図を示し、創造性のネットワークはこれに似ている、と語った。 創造性を導き出すためにはオープンにすべきであり、自己を確立するためには他者と向き合わなければならない、個性は他人とのかかわりのなかで生まれるものだと語り、これは私のフィロソフィーではなく脳科学から明かなことだと述べた。進化論のダーウィンは彼自身も偉かったが、当時の人たちといろいろ文通していた。「ダーウィンはあの時代からオープンイノベーションを実現していたとも言える、オープンでない研究所は滅びるだけだ」と語った。 人間だけが「他人」という『鏡』を手に入れた存在だと考えられるという。アポロが撮影した地球の写真によって、人類は人類全体としての『鏡』を初めて手にした。「新しい『鏡』を手に入れていくのが人類の歴史。心脳問題も実は我々の知らない新しい鏡を開発することだ」と述べた。
● パネルディスカッション
最近、サンゴ礁に興味を持っているという北野氏は、システムとしての生物の根本原理が知りたい」と語り、世界で渡り歩くためには「頭が良いだけではなく度胸が大事」と述べた。 高安氏は「これまでは勝者は全部もらえるのが当然という価値観になっていた。これからは運のないときはみんなが助けてくれるような価値観が必要なのではないか。私は物理学者なのでぜひ実験してみたい」と語った。 茂木氏は「これまで思いもつかなったところとの融合領域を思いついた人がこれからはいいんじゃないか」と述べた。機械の速度が速くなることにより、知能とAIの議論も様相が変わりつつある。仕組みは違うが十分に速い速度で機械が回答を出すことが可能になりつつある。だがまだ機械翻訳はできない。日英の機械翻訳が仮にできるようになったらどうなるかと考えることがあるという。
いっぽうパネリストたちの間では既存の教育システムに対する批判が起こり、東大教授になったばかりの暦本氏は立場上、東大を弁護する側に回らされた。暦本氏は「ときどき強制的に環境を変えるのは重要。ソニーCSLももっとフィジカルにオープンになっていくことが大事なのではないか」と答えた。また、これからの技術やユーザーインターフェイスの進歩によって、我々のクリエイティビティはまだまだ上がる、と述べた。 所 所長によれば、ソニーCSLは昨年から環境やサステナビリティの研究、直流送電の可能性を探り始めたという。環境問題がやがて起こることはローマクラブの報告書を読めば当時から自明だった。だが人間は理性としては容易に理解できても現実を見ない性質がある。所氏は、人間は現実との折り合いをつけることができるのだろうか、と茂木氏に問いかけた。 茂木氏はそれに対して「脳は楽観的に見るバイアスがかかっている。たとえば、みんな平均年齢よりも長く生きると思っている。楽観的に見るバイアスは脳や身体にとっては大事な働きだが、システム的な脆弱さに繋がっている。そこは客観的なデータで補うしかないだろう」と答えた。
このあとも議論は続いたが割愛する。所氏は最後に個人の研究への希望として「リアルタイムな全地球シミュレーターを作ってみたいなと思っている」と語った。固体地球や大気・海だけではなく、生態系や人間圏も含めたシミュレーターだ。あとひとつのテーマは文化と文明だという。「ソニーCSLが将来の文明を作るための核になれたらと強く感じて今日一日議論ができた」と語った。 ■URL ソニーCSL http://www.sonycsl.co.jp/ ■ 関連記事 ・ 「SolidWorks WORLD 2007」基調講演レポート ~早大・高西教授、ソニーCSL・茂木氏らが日本のロボット技術について語る(2007/09/26) ・ ソニーコンピュータサイエンス研究所オープンハウスレポート(2007/06/11)
( 森山和道 )
- ページの先頭へ-
|