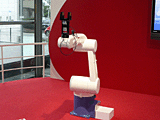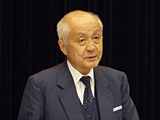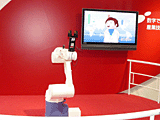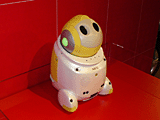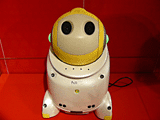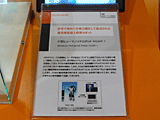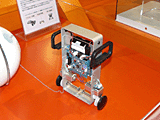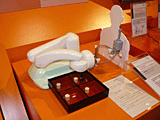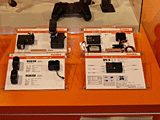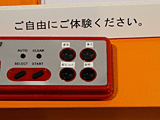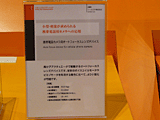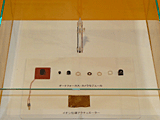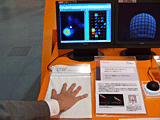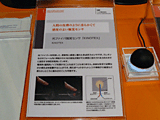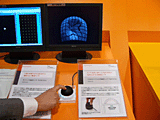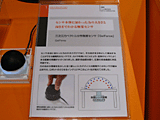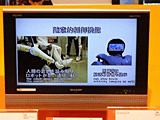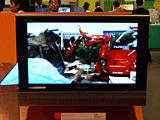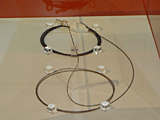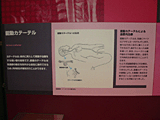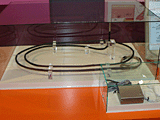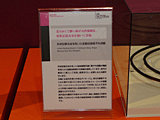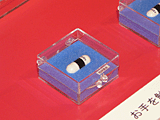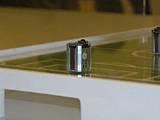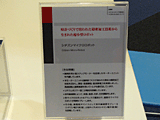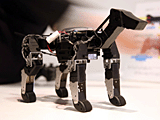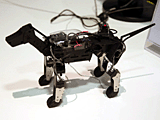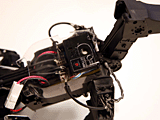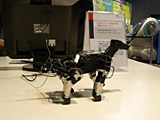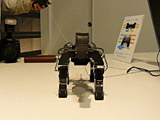|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TEPIAが「先端技術館@TEPIA」としてリニューアルオープン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内覧会の前に、まず記者発表が行なわれた。出席したのは、TEPIAを運営する財団法人機械産業記念事業財団会長(TEPIA)の福川伸次氏、同展示部長の久保俊介氏、企画を担当した株式会社電通テックテクニカルプランナーの北村公一氏の3名。 福川氏によれば、TEPIAの展示事業開始から今年で20周年の節目に当たることから、今回先端技術館@TEPIAとしてリニューアルすることにしたという。これまでは、毎年テーマを設けて展示内容を入れ替えるという方式だったが、それを改め、先端技術の主要分野(クラスター)を選定し、その最新の製品やサービス、技術やシステムを常設的に展示することとした。これまでは、さまざまな先端技術の個々を知ることはできたが、分野としての理解がしにくい展示だったため、それを分野ごとにまとめてその分野全体に対する理解を得やすい構成にしたというわけだ。 なお、平成22年度までの3カ年計画で、展示を強化していくとしている。そのほか、これまでは日曜日が休館だったが、今回は月曜日を休館とすることで(月曜が休日の場合は火曜日が休館)、家族連れや社会人の来館をよりしやすくした。さらに福川氏は、「日本の子供たちの理科離れを食い止めることに貢献したい」とも述べていた。
● 6つのゾーンに分けられた展示会場 館内は、大きく6つのゾーンに分かれる。エントランス/ロビー展示、プロローグ展示、メイン展示、テクノスタジオ、トピックス展示、エピローグ展示となっている。エントランス展示には、2輪の楽しさと実用性を持つ次世代コンセプトカーやナノ技術、顔認証技術を駆使した体験型の展示品をラインナップ。プロローグ展示は、生活・社会の発展を支える産業技術の進化を、性能や効果などを現す「数字」によって象徴的に示すというコーナーで、トヨタ系のカーエレクトロニクス企業デンソー製のロボットアームが活躍。モニタに出題された産業技術に関する問題を、来場者と一緒に○×を選ぶなどして回答する仕組みだ。 ちなみに、ロボットアームは必ずしも正解を選ぶわけではないようで、間違えるとシュンとしている場面もあって笑えた。そのほか、デモンストレーションも行なわれ、シャッタースピードが遅いとブレてしまうほどの速度で大きなロボットアームが動くところを見られるようになっている。 ちなみにそのすぐそばには、「シンボル展示」として、表情認識技術の一種であるオムロンの「笑顔度推定技術」という体験型展示物が用意されている。このソフトを利用することで、デジカメなら笑顔を撮影する瞬間を逃さないようにできるし、ロボットなら人の笑顔を認識してコミュニケーションに応用できるというわけだ。
その先に、NECが愛・地球博で披露したロボットの「パペロ」がおり、TEPIAオリジナルの挨拶「TEPIAへようこそ」を聞かせてくれる。そしてその左が、メインの展示コーナーだ。先端技術を5つの領域に分けて紹介。その内訳は、まず5つの領域が、「くらしとコミュニケーション」「健康と医療」「都市とモビリティ」「環境とエネルギー・資源」「マテリアルとデバイス」となっている。 テクノスタジオは、実際に触れて体験できたり、ワークショップやミニイベントが開催されたりする多目的ルームだ。トピックス展示は、日本が世界に誇るものづくりの心や技、文化・感性・デザインなどに関わる話題の技術を企画展示していく。最後のエピローグ展示は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が発表した、「2025年技術戦略マップ」から、近未来の生活・社会の発展のために必要な技術開発の方向性をパネルで紹介となっている。 ● 「生活支援ロボット」コーナー メイン展示の5領域に属する技術分野だが、くらしとコミュニケーションが、「薄型ディスプレイ」「生活支援ロボット」「ユビキタス」「RFID」。健康と医療は、「ヘルスケア」と「先端的医療機器」だ。都市とモビリティは「耐震・免震・制震」と「モビリティ」。環境とエネルギー・資源は、「自然エネルギーと環境」「バイオマス燃料とバイオマスプラスチック」「燃料電池」の4つだ。マテリアルとデバイスは、「ナノテクノロジーと高性能素材」「デバイス」となっている。どれもハイテク&サイエンス好きにはたまらない展示内容なのだが、今回はRobot Watchらしく、くらしとコミュニケーションの生活支援ロボットと、健康と医療の先端的医療機器を中心に紹介していく。 生活支援ロボットのコーナーの最初にあるのは、富士通オートメーション製の研究開発用の小型ヒューマノイドロボット「HOAP-1」。現在、「HOAP-3」まで発売されているヒューマノイドシリーズの第1号だ。2001年9月から発売され、53台の販売実績がある歩行特化モデルである。なお、HOAP-2は全身運動モデルで2003年7月より販売開始し、45台の実績。HOAP-3はコミュニケーション機能搭載完全無線制御モデルで、2005年7月より販売して33台の実績となっている。
続いては、ZMPのブースで、「今年のロボット大賞2007」でサービスロボット部門の優秀賞を受賞した音楽ロボット「miuro」と、2輪による倒立振子を採用したロボット教材「e-nuvo WHEEL」が展示されている。どちらも動作させることが可能。 この2体の関係は、どちらも同じ姿勢制御技術を使っていることだ。ジャイロセンサで姿勢を検知し、ふたつの車輪を動作させているという基本部分が通じているというわけだ。miuroに関しては、障害物センサや段差検知センサなど、動作するための技術的な工夫に関しての解説がなされている。
次が、セコムの食事支援ロボット「マイスプーン」のコーナー。2006年度の今年のロボット大賞で、サービスロボット部門の優秀賞を獲得したので、ご存じの方も多いはずだ。手の不自由な高齢者・障害者の自立した食事を支援するためのロボットである。実際に自分で触って動かすことが可能だ。
さらにその隣が、双葉電子工業とHPIジャパンによるホビーロボット用パーツのブース。HPIジャパンの「G-ROBOTS」に加え、同社が夏発売予定の新製品の犬型4足歩行ホビーロボット「G-Dog」(仮)が展示。犬型ロボットは、コントローラーを用いてその場での歩行動作や走行動作などを見られる。それ以外には、双葉電子工業製のホビーロボット用のサーボの展示解説がされていた。なお、後述する「テクノスタジオ」と呼ばれるコーナーでは、この犬型ロボットを実際に操作することも可能だ。
ここからは、具体的なロボットではなく、部品を紹介。まずは、イーメックスの「携帯電話カメラ用オートフォーカスレンズデバイス」だ。現時点ではロボット用途ではないが、応用が可能な部品である。「オートフォーカス・カメラモジュール」と、「イオン電動アクチュエータ」の部品が分解展示されていた。高分子アクチュエータと呼ばれるシステムで、ボイスコイルモータやピエゾモータよりも小型化が可能なのが特色だ。
生活支援ロボットコーナーで展示されているロボット関連機器の最後は、ロボット用途としても研究開発されている、ニッタの2種類のセンサだ。ひとつが、人間の皮膚のように柔らかくて、なおかつ感度のよい光ファイバ触覚センサ「KINOTEX」。 光ファイバを利用した、柔軟性と感度に優れた多点圧力型のセンサで、ウレタンなどのフォーム内に照射された光の散乱状態が、その表面に加えられる力の大きさに依存する特性を利用した仕組みである。 特徴として、電気的・時期的なノイズを受けることもなければ出すこともなく、自由な形状で必要なだけ感圧点を配置可能。ベッドのマットレスや車いすの座面などの柔らかいところに組み込めるのが特徴だ。 実際に展示されているウレタンのセンサの上に手の平を置いたりして圧力をかけると、その通りにモニタに表示され、感知されている様子がすぐ見られる。「人肌のような触り心地のセンサ」と紹介されていたが、本当に触り心地がいいので、思わずアダルト方面での使用も考えてしまった(笑)。そのぐらい気持ちのいいセンサなので、来館した時は必ず触っていってほしい。
ニッタのセンサのもうひとつは、三次元力ベクトル分布触覚センサ「GelForce」だ。センサ本体に加わった力の大きさに加え、その向きと分布も検出できるという画期的な内容である。センサはドーム状の弾性体で、その内部下方には魚眼レンズ搭載のCCDカメラが設置されている。ドーム部分を押したりつまんだりすることで、その歪みをカメラがとらえ、力の大きさ、向き、分布を検出できるというわけだ。カメラを活用することで配線の問題が少なく、設計自由度も高いといったロボットへの組み込みに向いた特徴を持っている。
このほか、サイバーダインのロボットスーツ「HAL」と、テムザックのレスキューロボット「T-53援竜」も映像で紹介されている。HALはZMPブースの後方に、T-53援竜はHOAP-1の後方にそれぞれモニタが設置されている。HALはデモンストレーション映像だが、T-53援竜は2007年8月1日から10日まで実際に新潟県中越興地震の被災現場で復旧作業に活用した際の記録映像を見られる形だ。
● 「先端的医療機器」コーナー イーメックスの「血管内手術用能動カテーテル」は、4方向の湾曲が可能な、脳内血管の患部へも誘導しやすいカテーテルだ。先端のアクチュエータ素子の働きで、リード線を介して体外からジョイスティックなどで先端の方向をコントロールできるという仕組みである。2~3Vと駆動電圧は低くて人体に安全で、外径0.8mm、内径0.5mm。
東北大学大学院医工学研究科生体機械システム医工学講座芳賀研究室で開発されたのが、「形状記憶合金を用いた能動屈曲電子内視鏡」だ。形状記憶合金を用いた屈曲機構を先端に備えており、体内奥深くに入って観察を行ない、必要に応じて治療を行なうというシステムである。ジョイスティックで操作できる仕組みだ。試作品は大腸用で外径9mmだそうだが、現在は微細化高技術を駆使したさらに外径の小さいタイプを開発中だそうである。
アールエフが開発したのが、次世代カプセル内視鏡「Sayaka」だ。風邪薬などより少し大きめのサイズで、飲み込んでしまえば、あとは8時間ほどで消化管全体を約87万枚の画像で撮影してくれる。カプセルが二重構造になっているのが特徴で、内側のカメラ部分が360度回転する構造だ。取得した多量の画像はモザイキング技術と超解像度技術によりつなぎ合わされ、パイプ状の消化管をはさみで切り開いたような体内マップを作成してくれる。カプセルはバッテリーレスで、被験者が着用したジャケットに内蔵された電磁コイルを介して電力と画像データの送受信を行なう仕組みだ。
● 体験して楽しめる「テクノスタジオ」には2種類のロボットがスタンバイ テクノスタジオはワークショップやミニイベントが行なわれたり、実際に製品を操作して楽しめたりするスペース。ここにはロボットが2種類用意されている。シチズンのマイクロロボット「Eco・Be!」3体と、双葉電子工業のサーボを使用した新製品の犬型ロボットだ。Eco-Be!は、コントローラで操作できるほか、パーツを並べた分解構成図も用意。縦横高さどれもがわずか1~2cmという小型のボディの中に、どんな部品が詰まっているかのがわかるが、驚くのは1mm台のネジ。くしゃみで吹っ飛んでしまいそうな微細なパーツは驚くはずだ。それを普通に前進、後退、旋回させられるようになっている。
HPIの犬型ロボット「G-Dog」は、実際に歩かせたり走らせたりすることが可能。後ろ足2本で立ち上がらせたり、前足2本で逆立ちさせたり、お手やおしっこのポーズなども取れる。モーションは今後もアップデートされていく模様。
このほか、まだまだお伝えしたい展示製品や技術、サービスがあるが、それはぜひ直接訪れて確認してみてもらいたい。またぜひお願いしたいのが、ロボットスーツHALと、レスキューロボットT-53援竜の実物展示。実物の借り受けは難しいのは想像がつくが、映像だけの紹介は逆に寂しい感じだったので、せめて実寸モデルは設置してもらいたいところである。そうした大きなモデルも、今年は3~4台、3年かけて最終的に10台ほどにするということなので、今後に期待したい。 また、開館日の11日(金)から13日(日)までは、オープニングキャンペーンとして、来館者にTEPIAオリジナルの記念品をプレゼント。そして、来週14日(月)から20日(日)まで文部科学省が主催する「第49回 科学技術週間」にも参加することが発表されている。 ■URL TEPIA http://www.tepia.jp/ 先端技術館@TEPIA(案内) http://www.tepia.jp/exhibition/ ■ 関連記事 ・ TEPIA「ちえものづくり展~社会を豊かにする最先端技術~」PART-IIIが開催中(2007/04/13)
( デイビー日高 )
- ページの先頭へ-
|