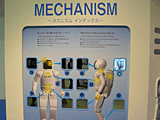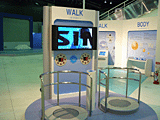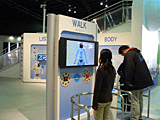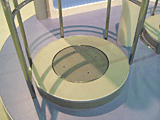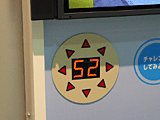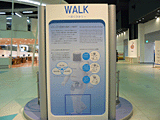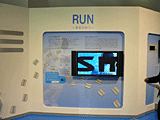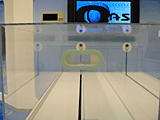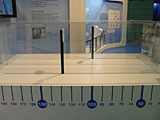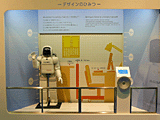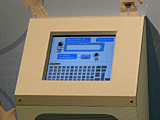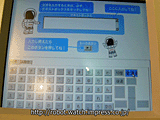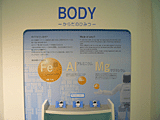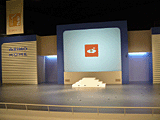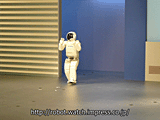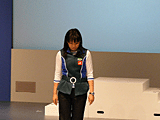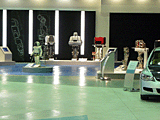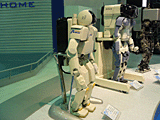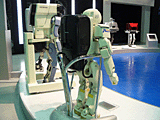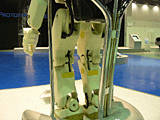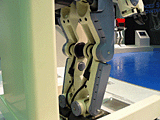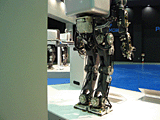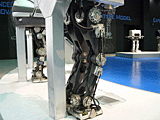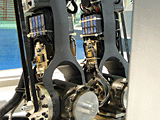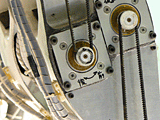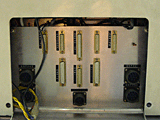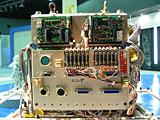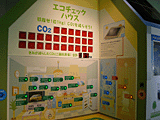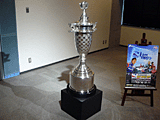|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ツインリンクもてぎ、ASIMOの拠点施設「ファンファンラボ」をリニューアルオープン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンファンラボは、1998年にホンダ創立50周年を記念し、「Joy of Mobility」をテーマにして設立されたイベントホールである。定期的にリニューアルが行なわれており、2000年には「遊んで、つくって、学ぼう」をテーマにした新技術発信館となった。2004年には、ホンダのものづくりを継承したいということで、ものづくり体験館に。そして、今回は、「夢・体感フィールド」としてリニューアルされた形だ。リニューアルのポイントは、来場者が見る・聞く・触るができ、体験して楽しい展示となっている。 今回リニューアルされたのは、エントランスをくぐった先の左手から中央にかけての部分だ。これまではASIMOホームと呼ばれていた部分とモビリティラボ、そしてモビリティラボの一部としてホンダ製ジェット機を展示していた2階部分が大幅に展示物を刷新されたり、一部の内容の追加・変更がなされたりした形だ。これらのフィールドは、「ASIMOフィールド」、「エコラボ」、「スカイドリーム」として新生。一方、親子でペーパークラフトなどの工作を楽しめる館内中央の「ドリームスタジオ」と、キッズが自らパーツを組み立てた後に実際にそのカート(手動・電動の2種類)で走れる館内右手の「モビリティワールド」は従来通り。今回のリニューアルによって、5つのフィールドで構成される形になっている。 ロボットファンにとって最も気になる部分といえば、いうまでもなくASIMOフィールドだろう。ここは、かつてASIMOホームと呼ばれていたスペースである。ASIMOフィールドは、大きく「ASIMOのひみつ」「ASIMOホーム」「ロボットギャラリー」に分かれる。 エントランスから入ってすぐ左手にあるASIMOグッズなどが置いてあるファンファンショップはそのままだが、その左手のホンダが開発した歴代ロボットたちが並ぶ「ロボットギャラリー」がまず場所が移動になった。館内左手奥になったのだが、これはまた後ほど詳しく説明する。その代わりに新たにエントランス入ってすぐから左手に用意されたのが、「ASIMOのひみつ」だ。8つの体感型の展示物が用意されており、見聞きしたり、実際に身体を使ったりしてASIMOの秘密に迫れるようになっている。 8つの展示物は「ASIMOストーリー」「MECHANISM-メカニズム インデックス-」「WALK-歩くひみつ-」「RUN-走るひみつ-」「SEE-見るひみつ-」「DESIGN-デザインのひみつ-」「LISTEN&TALK-聞く&話すひみつ-」「BODY-からだのひみつ-」だ。 ASIMOストーリーは、ASIMOのことをまったく知らない人でも、どんなロボットかを立体映像で学べる。基本スペックや特徴を紹介してくれたり、自分で確かめたりできる仕組みだ。マウスを使わずに、手をかざすだけで立体映像画面上のカーソルを動かせる「Air Touch」が導入されている点が特徴。項目を選んだり、立体映像のASIMOの身体を触ったりできる内容だ。 ASIMOストーリーの左手にあるのが、メカニズム インデックスだ。これは、これまであまり語られてこなかったASIMOの全身10カ所の機能について、ASIMO自身が映像で説明してくれる。目、耳、首、身体、腰、手、足、センサー、バックパックセンサー、ランプの10カ所だ。また、その名の通り残りの6つの展示物に関する目次的な内容になっている形だ。 ちなみにどんな話を聞かせてくれるかというと、一番左側のモニターでは、頭部の3カ所のくぼみについて教えてくれる。黒いフェイスプレートの上にある3カ所のくぼみだが、これはなんとただのデザイン上のものではなく、ASIMOの耳なのだ。ここの解説だけでも思わず感心すること間違いなし。大人も真剣に見聞きしてしまう内容である。
ASIMOストーリーの奥にあるのが、歩くひみつだ。これはASIMOの歩きに関して、とりわけ「バランス」と「踏ん張ること」に関する解説を聞ける。ただし、それを体感できるようにと、バランス感覚を確かめられるゲームになっており、ふたりで競争できるのが特徴。一定時間、グラグラする円状のボードの上に乗り、どれだけバランスよく立っていられるかを調べる。バランスが悪いと、どの方向に傾いているかを知らせる三角マークが点灯し、カウンターがひとつ追加。バランスが悪い人だと、ストップウォッチ並みにカウンターが進んでしまうという具合である。自分では一見すると両足に均等に体重をかけて立っているつもりでも、意外と変なクセがあったりして、「バランスを保って立つことの難しさ」がわかる仕組みだ。
再び壁際に戻り、メカニズム インデックスの(壁側に向かって)右側にあるのが、走るひみつだ。ASIMOがどうやって走っているかという解説を映像で見られる。面白いのは、ここのパネルには足跡が描かれていること。実は、ASIMOの歩く時の歩幅と走るときの歩幅が描かれており、よく見るとエントランスの方から床にずっと描かれており、ここでパネルを垂直に駆け上がって再び降りて、左手奥のステージの方へ向かっているのがポイントである(ここのパネルの足跡はイルミネーションとなっており、光る仕組みになっている)。 その右隣は、見るひみつ。ASIMOはカメラを2つ備えていることで立体視し、正確に物体までの距離を測ることができるのだが、その理由を教えてもらえるコーナーだ。ASIMOと距離感で勝負する「ピタットストップゲーム」も用意されている。2m先から手前へとターゲットが接近してくるので、スコープをのぞいた状態で、その距離まで来たと思ったときにボタンを押して止めるという内容だ。しかし、これが意外と難しく、指示された距離よりもずっと手前で止めてしまうことが多い。かなり難易度の高いゲームとなっているので、目に自身のある人は挑戦してもらいたい。
そのさらに右隣が、デザインのひみつ。なぜASIMOの身長が120cm(新型は130cm)となったのかが、家庭内やオフィス内のさまざまなものの高さなどと比較してわかるようになっている。 今度は反対側の壁(館内中央側)に移って、聞く&話すひみつ。ASIMOがどうやって人の言葉を聞いているかを映像で教えてもらえる。人の発した言葉をオシロスコープで波形としてとらえ、その波形で認識しているという説明だ。そして、タッチパネル式のキーボードが用意されており、ここで好きな言葉を入力すると、ASIMO(の合成音声)がしゃべってくれるという形だ。文字入力は漢字変換も行なえ、いろいろとしゃべらせることが可能だ。 その右隣(エントランスに近い側)は、からだのひみつ。ASIMOの外骨格製のフレームがマグネシウム合金製であることの説明と、マグネシウムがどれだけ軽いかを体感できるようになっている。鉄、アルミニウム、マグネシウム製の3種類のASIMOをかたどったマスコットが置いてあり、持ち上げるとその違いがよくわかるという仕組みだ。比重7.85の鉄は「小さい子は両手でも持つのが大変なのでは?」というぐらいズシリとしているが(お子さんが指を挟んだりしないよう保護者の方は注意しよう)、比重1.8のマグネシウムは同じ金属なのに驚くほど軽い。マグネシウム製だから、ASIMOはロボットながらも成人女性並みの体重でいられるのがわかるのである。
以上がASIMOのひみつの8つのコーナー。そこを通り抜けて、館内左手を進んだ最奥は、リニューアル前と同じでステージと2階への階段兼腰掛けスペースがある。リニューアル前は、ASIMOに関するゾーン全体のことをASIMOホームと呼んでいたが、リニューアル後はこのステージがASIMOホームと呼ばれるようになった。階段兼腰掛けスペースに関しての変更はないが、ステージのデザインは変更されている。 ステージでは、リニューアルに合わせて最初に登場する際の挨拶とパフォーマンスが変更された。そのあとのASIMOの機能紹介をするステージイベントはこれまでと同じだが、春休みに合わせて変更するそうである。しかし、1点だけ、大きく変更になったところがあり、これまでは常にASIMOとともにステージに立って観客とのやりとりなどを行なっていた、お父さん人気の高い(笑)「ASIMOお姉さん」がビデオの中のみの出演となってしまった。同サーキットの広報の方に伺ってみたが、正確なところはわからない模様(フル稼働だったために、しばらくお休み?)。個人的な希望だが、復活を希望したい。それから、ファンファンラボのスタッフの制服も変更されている。なお、昨年12月に発表された実用機能進化ASIMOに関しては、現在はまだ配備されていない。
そしてASIMOホームの右手にあるのが、これまではエントランスから入って左手の壁際にあったロボットギャラリーだ。従来型ASIMO(その中でも初代)を中心に、ホンダ製の歴代ロボットたちが円を描くように並べられているのだが、最大の特徴は背後からも見られるようになったこと。ロボットたちの関節、とりわけ脚部のヒザや足首などは、背後から見た方が、メカニズムがよくわかり、メカ好きにはたまらない。触るのはもちろん厳禁だが、穴が開いてしまうぐらい間近で入念に観察するのは可能なので、網膜に残像が残るぐらいたっぷりと堪能しよう。背後から見ると、初期のロボットなどはこれまでは見られなかったインターフェイス類を見られるし、開発スタッフの手書き文字なども見られたりする。ASIMO誕生までの息づかいが聞こえるようで、感動ものである。ちなみに、ホンダ製の歴代ロボットが一堂に展示されているのは、世界でもファンファンラボのみ。実はファンファンラボは、ASIMOとホンダ製歴代ロボットの施設としては世界唯一なのである。
なお、今回ロボットギャラリーが設置されたスペースには、これまではASIMO Cafeがあったが、あまり回数をこなせないイベントであることから、このリニューアルを限りに姿を消すことになった。実用機能が進化したASIMOが配備されたりすれば、また復活するかも知れないが、しばらくASIMOからドリンクを受け取るのはできないようだ。それから、同じくロボットギャラリーのスペースにあったモビリティラボの人気アトラクションのドライビングシミュレーターとライディングシミュレーターは、モビリティワールドの方に移動している。 このように、ASIMOに関しては「ASIMOのひみつ」コーナーができたことで解説に関する充実度が増した。ホンダ本社の1階にあるショールームHondaウェルカムプラザ青山や、同じホンダ系の鈴鹿サーキットでもASIMOは常駐して連日の如くステージイベントが行なわれているし、日本科学未来館に至っては常駐の上に各種解説もなされているが、それでもツインリンクもてぎが最も充実している施設なのである。ASIMO好きなら一度は訪れないとならない聖地として認識したい。 ASIMOフィールドについては以上だが、そのほかのコーナーについても簡単に紹介しよう。まず、これまでモビリティラボと呼ばれていたスペースだが、こちらはエコラボとなった。ホンダが開発したFCX(水素燃料電池実験車)のプラットフォームや、実用車のシビックハイブリッドのカットモデルが展示されている。 さらに、擬人化した歴代ホンダ製クリーンエンジンが自分の特徴や環境問題などについて寸劇を見せてくれるキッズ向けの「エコエンジンシアター」や、日常生活でどういうことをすればどれだけ二酸化炭素を減らせるかを具体的に数値で見られる「エコチェックハウス」などもある。 また、地球環境とモビリティが共存していく姿をイメージした巨大な「エコピストン モニュメント」が置かれており、のぞき窓からは地球の美しい風景などを見られたり、吹き抜けになっている2階から見下ろすと美しい青空を見られたりするという具合だ。ちなみに2階の一部もエコラボとなっており、ホンダの環境への取り組みや、環境技術エンジンのカットモデルが展示されている。 そして2階の右手には、ホンダ製ジェット機の実験機MH02の実機が展示されている。これまでは、モビリティラボの1コーナー「大空への夢」だったが、今回からホンダの空への夢と挑戦を扱った「スカイドリーム」と名付けられてひとつのフィールドとして独立。生産が始まった商用の小型機HondaJetの1/20スケールの模型や、各種解説などが追加された形だ。フィールド全体は、滑走路をイメージしたデザインになっている。
またツインリンクもてぎでは、4月18日(金)・19日(土)に、今年もアメリカのレースのトップカテゴリーのひとつであるインディー・レーシング・リーグ(以下、インディー)の唯一の海外戦、「2008 IRL インディカー・シリーズ第3戦 ブリヂストン インディジャパン 300マイル」を開催。それに合わせて、同サーキット内にあるレース系展示施設の「Honda Collection Hall」では、今年もインディ関連の企画展を行なう(ファンファンラボからクルマで数分の距離)。招待会では、Honda Collection Hallでその企画展「CONTACT Honda F1がインディを走った日」の案内も行なわれた。1960年代にホンダがF1に挑戦して勝利を収めたことは有名だが、同時にインディにも挑戦しようとしていたという事実が明らかになり、今回はそれについての展示を行なう。 当時のF1チームの監督やスタッフらのインディ挑戦に関する貴重なレポートやメモのほか、'60年代のインディーマシンや、インディの聖地であるインディアナポリス・サーキットで走行したホンダのF1マシンRA301などを展示。また、現在はホンダが唯一インディにエンジンを供給しているメーカーなのだが、1990年代に1エンジンメーカーとして供給を開始し、初勝利を収めた際の近年のインディーカーなども展示されている。レースにも興味がある人は、ツインリンクもてぎを訪れた際は合わせてHonda Collection Hallにもぜひ足を運んでみてほしい。
■URL ファンファンラボ http://www.mobilityland.co.jp/fanfunlab/ ファンファンラボリニューアル http://www.mobilityland.co.jp/fanfunlab/renewal/ CONTACT Honda F1がインディを走った日 http://www.mobilityland.co.jp/collection-hall/new/08indy/ ツインリンクもてぎ http://www.mobilityland.co.jp/motegi/
( デイビー日高 )
- ページの先頭へ-
|