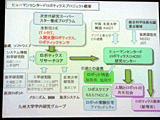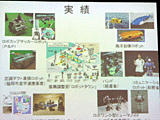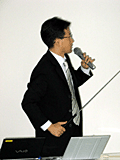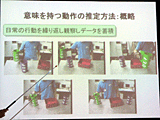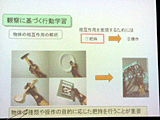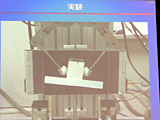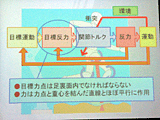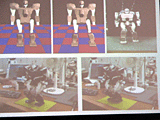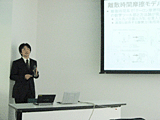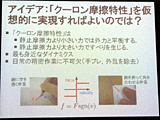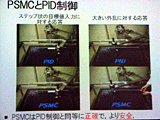|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「第18回次世代ロボット研究会」レポート |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9月27日(木)、福岡市早良区のロボスクエア内セミナールームにおいて、第18回次世代ロボット研究会が行なわれた。 次世代ロボット研究会は、福岡市がロボットに関する産学官連携の場所として設置したもので、年に数回研究会を開いている。
今回の次世代ロボット研究会は、九州大学が進めているヒューマンセンタードロボティクスプロジェクトの活動について紹介し、またその中心となる三人の特任准教授による講演が行なわれた。
具体的には九州大学内部にロボティクスリサーチコアを作り、これに九州大学でロボット技術について研究している研究室が協力し、人の間で使うことのできるロボット技術の確立を目指す。また福岡市やロボスクエアなどとの連携をとり、将来的にはヒューマンセンタードロボティクス研究センターの設立を目指したいとしている。 もう少しわかりやすく言えば、九州大学内部に組織横断的なプロジェクトを立ち上げ、それを核としてロボット研究センター設立を目指すようである(4、5年先を目指しているとのこと)。 今回の次世代ロボット研究会は、そのヒューマンセンタードロボティクスプロジェクト専任で研究開発に当たる三人の特命准教授の紹介を兼ね、三人のこれまでの研究成果についての講演が主な内容だった。
● 人間行動のモデリング
最初に画像認識のできるロボットに、人間の行動を繰り返し見せて、それから行動パターンを抽出させる(行動の意味を理解させるのではなく、あくまでも行動パターンの把握)研究についての説明。この「有意動作の推定」能力をロボットに持たせることで、予めすべてを教えるのではなく、ロボット側に行動を理解させ、適切な動きで行動を再現させることができるのではないかとのことだった。 またロボットと人間の腕は同じ構造ではないので、ロボットに物体を把持させるとしても、人間と全く同じにはできない。従って物体の把持という動作を研究(物体を手と指でどんな状態で持つのか、あるいはどの部分に圧力がかかっているかなど)することにより、物体の把持という動作をモデリングし、ロボットのハンドへ応用するという説明があった。 小川原氏は、これらの人間の行動をモデリングし、モデリングされた行動をロボットで再現させることで、人の間で使うことのできるロボット技術につなげようと考えているようだった。
田原氏は「人間はいくつもの関節を持ちながら、関節冗長性を自然に解消して動いている」という。これを解明するために二指のロボットハンドによるピンチング動作や、腕モデルの研究を続けた。この研究により、人間は親指の「転がり力」などを利用して、割と単純な制御で動いていて、ロボットやシュミレーターによる動きの再現も可能だった。 この研究結果をロボットハンドに応用すれば、複雑な制御系を使わなくても、スムーズな動きが可能ではないとかとの発表があった。
● 人型ロボットの力学と制御
杉原氏は「冗長な空間の中で意味ある行動を取らせるにはタスクが必要」として、力点の移動による二足歩行の仕組みについて講演。「力点を台車、重心を先端とした仮想的な倒立振子とみなし、力点の位置を操作して安定化するように目標反力決定」して、二足歩行は進んでいくのだと解説。しかし、実際の歩行はこれに加速度が加わるので複雑になり、理論的には解けない部分も出てくる。それを小型の二足歩行ロボットを使った実験により、研究中なのだという。 そして現在研究中の二足歩行ロボット「mighty」「magnum」についての説明もあり、分解能の高いマクソンのコアレスモーターを駆動系に使い、NEDOで開発した制御ボードを積んで動かしているそうだ。 人型ロボットは「技術の個人化」と「(親しみの持てる)擬人化」の融合したインターフェイスとして有効であり、ヒューマンセンタードロボティクスに相応しいものとの説明もあった。
● 扱いやすいメカトロ機器のための制御技術とセンシング
特にクーロン(普通)摩擦力についての講演は興味をひいた。機械の動作においてやっかいものであるはずの摩擦力を、逆にプログラム上で仮想的に実現し、機械に組み込む試みを行なっているという。 たとえばロボットハンドに使用すれば、(仮想摩擦による制御がかかるので)急に動き出したりすることなく、安定した動作が可能になるという。意外なところにロボット技術を安定させるヒントが隠されているのかもしれない。
現在、さまざまな大学の研究室でロボットの研究が進められているが、どうしても研究室単位で研究が進められている感は否めない。 これに対して九州大学が組織横断的なプロジェクトを立ち上げて、実際に使えるロボット技術の確立につなげようという試みは評価すべきだろう。いったんプロジェクトが終了する4、5年先にどのような成果を上げられているか、期待したいと思う。 ■URL 九州大学 http://www.kyushu-u.ac.jp/
( 大林憲司 )
- ページの先頭へ-
|