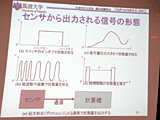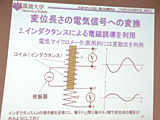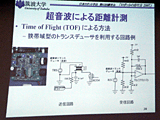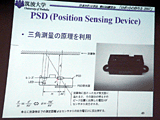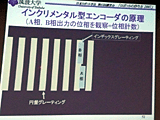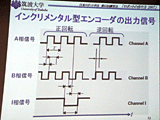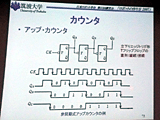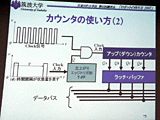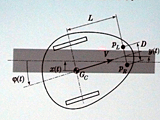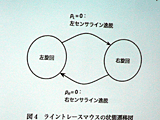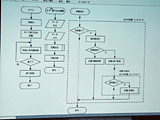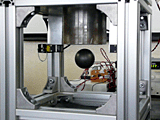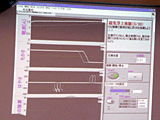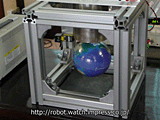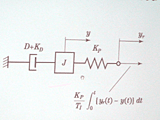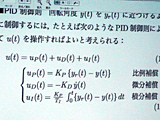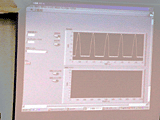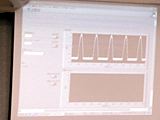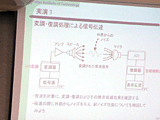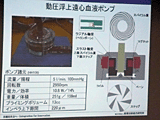|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロボット工学セミナー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このロボット工学セミナーは、ロボット制御系の設計開発に携わる大学・大学院生や企業の新人などを対象に、毎年開催されているもの。今年のテーマは「センサの信号処理」。ロボット用センサ、各種アナログデータの取扱い方法、デジタル制御のノウハウなどを中心に、講義と実習が行なわれた。ここでは、センサやデジタル制御技術の基礎から、人工心臓のセンシングまで盛りだくさんだった第1日目の内容についてレポートする。
センサは、検出した物理量を電気信号に変換する。信号を電子回路で整形したあと、パラレルあるいはシリアル通信などによって計算機側に送る。センサから出力される信号の形態を見ると、スイッチのオンオフ、信号電圧の大きさ、周波数や周期、時間間隔、伝文形式(プロトコル)による通信に大別されるという【写真4】。 次に、さまざまな物理量をセンサで計測する際、どのような原理で電気信号に変換するのか、測定対象別に解説がなされた。変位の長さを電気信号に変換するには、ポテンショメータなどの抵抗変化による分圧や、コイル(インダクタンス)による電磁誘導を利用するケースが代表的な手法。実用的な電気マイクロメータでは、電磁誘導によって変位を測定する際に、2つのコイルの巻線を逆に配し、差動方式として外乱ノイズをキャンセルする工夫がなされているという【写真5】。
移動ロボットやマニュピレータでは、自分自身の変位や動きも測定する必要があるため、速度や位置の変化を調べるセンサが必要だ。坪内教授は、歪サンサを利用して、並進加速度を検出する一般的な加速度計のほか、負荷によって回転角の加速度を測定するサーボ型回転角加速度計、コマの高速回転による慣性力を利用する機械式ジャイロスコープの原理についても説明した。最近では機械式ジャイロスコープは使われなくなり、コリオリの力を利用した振動式ジャイロやレーザー式ジャイロも登場している。
一方、周波数スキャンでは、広帯域の超音波トランスデューサを用いる。連続的に変化する周波数の超音波を用い、戻ってくる周波数の差をとると、位相差によって「うなり」が生じる。これを計測することで距離を測る方法だ。 坪内教授は、「超音波を利用する場合は、指向性に注意する必要がある。また方向分解能がなく、一番近い対象物から到達する信号を受けるので、人間の目とは違うように見えることもある」とし、超音波センサの使い方の考慮点を述べた。 また、TOFにおいて強いレベルの超音波を出力させるために、同研究室で開発した送信回路の例も示した。あらかじめ高電圧発生回路(コッククロフト・ウォルトン回路)から約120Vの電圧をかけておき、高電圧なパルスを発生させ、コイルを通じてトランスデューサをたたく方式で、5mぐらい先までの計測が可能だという。 光による測距法では、PSD(Positison Sensing Device)方式を紹介した。LED発光で対象物に光を当て、返ってきた光を受光部で感知すると、明るさに比例した電圧がセンサから出力される。これを基に三角測量の原理によって、測定距離を求める【写真7】。このほかにも、ラインビームや走査型レーザーを利用した距離計についても言及した。 回転センサの例としてはエンコーダがある。エンコーダは相対的な位置を知るインクリメンタル型(光学式/磁気式エンコーダ)と、絶対的な位置を知るアブソリュート型(光学式エンコーダ、レゾルバなど)に大別される。光学式エンコーダの基本原理は、シャフトと共に回転する盤に細かいスリットをつけ、LEDの光がスリットを通過したときに、フォトトランジスタがオンになることでパルスを計測できるようにするもの【写真8】【写真9】。信号出力にはA相とB相(1回転を検出するZ相もある)があり、これによって回転方向を検出する。また、A相とB相の信号の排他的論理和(XOR)をとれば、電気的な分解能を4逓倍にして計測することも可能だ。
力やトルクを計測したい場合には、剛体の変形に比例する物理量を出力できる歪ゲージが活躍する。歪ゲージは、歪によって抵抗が変化(比例)するリニア領域を用いて力を検出する。これを複数ぶん利用して多軸のトルクセンサなどが作られている。 続いて、信号を処理するインターフェイス部についての解説もなされた。計算機(マイコン)からみれば、信号の処理はデータバスにつながれたデバイスの読み書きとして扱えればよく、スイッチのオンオフならばビット値、信号電圧ならばA/Dコンバータ、周波数・周期・時間間隔ならばカウンタ回路によってデジタル信号として取り込める。 坪内教授は、T型F-F(フリップフロップ)を直列に接続したアップダウンカウンタの構成や、アップダウンカウンタの出力にラッチをかけてデータバス側に送出する方法などを紹介した【写真10】。また、アップダウンカウンタの前段にAND回路を置き、一定時間にパルスを計測する方法なども説明した【写真11】。これは前述の超音波センサのTOFなどで、よく用いられる回路だ。このように坪内教授は、コンピュータへのセンサ信号の取り込みが重要として、講義を終えた。
● ロボットのためのディジタル制御基礎の基礎
FSMとは、ロボットのふるまいを、行動ルールが一定となるシーン(状態あるいはモード)として分類し、その行動を状態遷移として表す手法。「FSMには2つのコンセプトがある。ある一定の規則に従って動いている状況をモードとして捉える。そして、そのモードをいくつか用意し、その間を条件によって遷移する。これによって行動を抽象化することで、かなり複雑なシステムでも、実現したい機能が表現できる」と松尾准教授。 たとえば、ライントレースロボットでは、2つの光学式センサを搭載し、ラインを検出する。もしラインから外れるとセンサが反応し、軌道を修正するように駆動系が右旋回、あるいは左旋回することで軌道に沿うように進行する。これを状態遷移図として表現すると、【写真14】のようになる。
このような状態遷移図ができたら、次に安価な組み込み用ワンチップマイコンに制御プログラムを実装するプロセスに入る。松尾准教授は「その際に重要となるのが割り込みの考え方」とし、タイマ割り込みによる同期構造について解説した。 ロボットは常に外界と相互作用する機械システムであり、制御を行なうタイミングが重要。ところが、状態遷移図には処理を実行するタイミングの概念はない。状態遷移図で表現されたFMSをプログラムで実現するには、マイコン側に備わるタイマ割り込み機能を利用して、割り込みを発生させてメイン処理を一時中断し、データの入出力処理、状態決定、行動計算をするようなタイマ割り込み処理のルーチンに飛ばす。 「OSを使用しない簡単な実装では、割り込み処理関数にすべての演算処理を含めるほうがよい」(松尾准教授)という。 次に連続的な制御の実例として、同大学の授業で利用している「磁気吸引浮上系実験装置」によるデモンストレーションを披露し、制御を安定化させるためのPID制御の基本的な考え方を紹介した。ライントレースロボットのふるまいは反射型光センサでラインを検出し、ラインから外れたら場合に駆動系を制御するというオンオフ的なもの。ラインをギクシャクと動き、制御性にも限界がある。PID制御は、さらにきめ細かい制御を実現するために、連続量を用いて制御するという考え方である。 デモで用いられた磁気吸引浮上系実験装置は、電磁石で鉄球を吸引し、それを中空で浮かせるようにしている。変位センサによって鉄球の位置を検出し、常に一定間隔(目標値)を保つようにフィードバック制御をかけ、電磁石に流す電流を制御する。鉄球を中空で一定間隔で浮かせるために、PID制御では、P(比例補償)、I(積分補償)、D(微分補償)という3つのパラメータを用いる。 Pによる補償は、目標値からの偏差に対して比例するように制御をするもの。鉄球が目標位置から離れると、それに比例して電磁石の電流を流すが、鉄球は上下に振動を繰り返して目標位置で静止することができない。変位が生じてから、電磁石に流す電流値を制御するため、鉄球の運動の調節が時間的に間に合わないためだ。 そこで、変位ではなく鉄球の速度に着目し、変位を微分して、わずかな時間の変位の変化量によって、電流を制御する考え方が次のDによる微分補償だ。つまり、瞬間瞬間の位置の変化をとらえて、鉄球の運動をすばやく調節できるようにする制御である。この場合は、パラメータを適切に設定すれば、鉄球の振動が収束に向かい、やがて中空で鉄球が停止する。 さらに、もし鉄球に外力が加わってバランスを崩した場合などは、鉄球の位置の偏差が収束に向かわないこともある。また、鉄球が目標値でないところに誤差を含んだ形で、停止してしまうこともある。そのため、誤差を吸収させ、常に目標の偏差をゼロにするように、鉄球に流れる電流値を調整し続ける制御も必要になる。こちらの場合は、Iによる積分補償を行ない、偏差の時間積分を利用することで解決する。 松尾准教授は、比例・微分・積分という3つの補償を行なうことで、磁気吸引浮上系実験装置の鉄球が安定して一定位置で静止できることを示した【写真16】【写真17】【動画01】。このような制御教材には、倒立振子による制御などもあるが、見た目にはこちらのほうがインパクトがあり、とても面白いと感じた。 次に、このようなPID制御をロボット制御でも活用するために、DCモータの回転角(位置)を制御する方法についても解説がなされた。これにより、モータを目標位置でぴったりと止めるような制御が可能になる。松尾准教授は、DCモータの基本的な駆動系をモデル化して、微分方程式で示し、さらにモデルを一般化するために、慣性、ダンパ(粘性)、バネという等価な力学モデルも紹介した【写真18】。モータの回転角を目標値に近づけるために、モータにかける電圧をP、I、Dという3つの補償として表して、フィードバックをかける【写真19】。
最後に松尾准教授は、PID制御の微分方程式をデジタルとして表現する手法について解説した。デジタルへの落とし込みは、PIDそれぞれの要素ごとにサンプル値をとって近似する。 たとえば、D(微分補償)であれば、変位の時間変化率に比例した値を出力させるので、タイマ割り込みでサンプリングした変位(変位はエンコーダからのパルスカウントによって求める)をサンプリング時間で割って速度を求め、次のサンプル値で、1つ前に計算した値の差分を取るといった演算を行なうプログラムを書けば表現できる。ここで制御は離散化されるが、サンプリング周期が短いので問題がないものとしている。 このようにして求めたモータ電圧指令値を、次にタイマ割り込みが掛かった直後に出力することで、デジタル制御が可能になる。また、モータの出力電圧をパルス幅変調(PWM)で出力する場合は、周期の平均電圧を操作量としてみなす。 ● センサの出力信号を正確にロボットに伝えるためのポイントとは?
まず、高山助教は、ノイズ対策として「ノイズ混入自体を抑制する」「混入してくるノイズの影響を低減する」「混入したノイズを除去する」という3つのアプローチを挙げた。 ノイズ混入自体を抑制する方法には、外界の影響を受けづいらい選択性の高いセンサを利用すること、そして信号伝送時のケーブルの適切な選択があるという。たとえば、測距デバイスでセンサを用いる場合は自然光の影響を受けにくい赤外線センサを用いたほうが耐ノイズ性が向上する。ケーブル類にはベーシックな平行2本ケーブルのほか、ツイストペアや同軸、さらに同軸にシールドを施したケーブルなどもある。平行2本ケーブルは電磁誘導によるノイズの影響を受けやすいため、後者のようなケーブルを使用し、ノイズを抑制することが重要とした。 次に高山助教は、混入してくるノイズの影響を低減するために、信号強度を高めてS/N比を向上する方法と、必要となる信号成分とノイズ成分を分離させる方法について述べた。信号強度を高めるには、伝達経路にアンプを置いて信号成分を増幅することで、見かけ上のノイズの影響を低減させる。「この際に、なるべくアンプをセンサデバイスの近くに置くようにするほうがよい」(高山助教)と注意点を述べた。ノイズが混入してからアンプで信号を増幅しても、同時にノイズ自体も増幅されてしまい、改善の意味がなくなってしまうためだ。 また、高山助教は信号成分とノイズ成分を分離するための手法として、通信工学的な見地ではなく、計測工学から信号の変調・復調について述べた。変調・復調処理では、ノイズ成分が周波数成分をもたない帯域の搬送波を利用して、信号伝送中のノイズ源の影響を排除できる。具体的な変調方式には、通信と同様にAM・FM・PM変調がある。それぞれ搬送波の振幅、周波数、位相差の変化によって変調を行なう。 一方、PWMやPAMといったパルス変調方式もある。PWMは一定間隔パルス信号の幅を、PAMは一定間隔パルス信号の振幅を変化させることで変調を行なうもの。特にPWM変調はマイコンとの相性がよく、センサの変調以外にも利用されている(サーボモータの速度や位置の制御など)。このような変調を施し、伝達信号を受信側で元に戻す(復調)ことで、ノイズを低減できる。 ノイズが入ってくる前になるべく混入を抑えることは重要だが、信号伝送時のノイズ混入は避けられないことも多い。高山助教は、すでに信号に混入してまったノイズを除去する方法として広く普及しているフィルタについても解説した。これは、ノイズ成分の信号レベルのみを低下させる方法で、目的とする帯域の周波数成分を通過させるもの。 具体的なフィルタとして、遮断周波数よりも低い周波数成分を通過させるローパスフィルタ、逆に高周波数成分を通過させるハイパスフィルタ、低域から高域までの間の周波数成分を通過させるバンドパスフィルタについて言及した。また、これらのフィルタをオペアンプで構成する回路も示した。 一方、オペアンプのようなアナログ回路ではなく、計算機によるデジタルフィルタリングの手法もある。こちらはA/D変換した離散化データをマイコンなどで処理するもの。離散化データに対して、フィルタの持つ周波数特性に応じた重み付けを行なって演算する。アナログフィルタよりも鋭い遮断特性を有するフィルタリングを実現できるという。 高山助教は、これらについて解説した後で、自作した実験装置を利用していくつかのデモンストレーションを実施した。まず始めの実験では、プリアンプの挿入位置によるS/N比の変化を確認。光センサデバイスの出力を信号ケーブルで伝送し、その信号をA/D変換してデジタルオシロスコープで観測するというもの。 信号ケーブル上にはプリアンプが置かれているが、センサデバイスの直近、ケーブルの中間、さらにセンサから遠ざけてA/Dコンバータの前に置いた場合の3パターンを比較した【写真21】【写真22】。プリアンプをセンサデバイスの直近よりも遠ざけた場合は、明らかにGNDにノイズが多く乗ってしまっていることがわかった。 2番目は、AM変調・復調によるノイズの低減効果を見るもので、マイクロフォンを対向に配置し、低音域の音信号を高音域の搬送波(500Hz)の上に重畳して伝送し、元の低音域の信号に復調する実験【写真23】。信号をそのまま伝送するのではなく、外乱ノイズとなる音を与えて耐ノイズ性も評価した。 最後に、高山助教は外部から混入する高周波ノイズ成分を除去するアナログフィルタ(遮断周波数400Hz)を使ったデモを行なった。これにより、高周波ノイズが低減していることが確認できた。ただし、遮断周波数の関係から、一部波形がまるめられる現象も出た。高山助教は「対象となる波形とノイズの周波数帯域の関係によっては、フィルタの設定を検討する必要がある」とし、講義を終えた。
● 生体信号のロボット利用とノイズ低減技術 セミナー第1日の最後の講義は、実用面に主眼を置いたホットな話題であった。産業技術総合研究所の小阪亮氏が「人工心臓におけるセンシング技術」について紹介した。小阪氏は、重度心疾患患者に対する治療管理・治療制御技術を研究している。その一環として、人工心臓のロボット化に関する研究を例に、人工心臓や心臓血管系のセンシング技術などについて紹介した。まず小阪氏は、心電や筋電など生体から発生する信号を、どのように利用するかという点について触れた。生体信号計測は、生体の機能解析、患者監視や臨床検査・診断、人工臓器などの生体制御を目的に行なわれる。 計測対象は、血管の内圧、脳圧の力学量から、体温・心電図・脳波などの電磁気量、あるいはグルコース濃度といった化学量まで幅広くあるが、こういった生体計測をする場合には、生体計測ならではの特殊性があるという。 「そもそも生命活動をするものを対象とするため、必要な操作を最小限にして、生理的状態を乱さないようにする必要がある。また、計測対象となる生理量は短時間でも長時間でも意味があり、高い再現性が要求される。センシングする部分も体内組織や器官であるため、異物に対する拒否反応もあるので、検出方法やセンサの素材を考えなければならない」と小阪氏。 こうした生体信号は、最近ではロボットにも利用されている。たとえば、筑波大学のロボットスーツ「HAL」のほか、産総研でも筋電義手を開発している。筋電は筋肉を動かす際に発生する電気信号だが、人が何かを見て反応して動く場合は、タイムラグが生じる。パワーアシストなどのサポート機器では、実際に力が出る前の筋電の大きさを検出して、必要な力を出す。筋電を検出するにも、皮膚が高い電気抵抗と静電容量を持つため、インピーダンス(抵抗)が大きく、とても微弱な電気信号(筋電は1mV、脳波は10~100mV)となるという。 そのため、ノイズには特に注意しないと生体信号は利用できないという問題がある。信号伝送の際には、蛍光灯のノイズ(インバータのノイズ)のような周囲雑音のほか、人が動いたときの静電容量の変化によっても、計測したい信号が埋もれてしまう。「そこで筋電を計測する際には、生体にできるだけ近づけて取り付けて、アンプで信号を1,000倍程度に増幅してから、計測系に伝送する」(小阪氏)という。 また第3話の講義のように、必要な信号成分を抽出するためにフィルタも用いられる。たとえば計装アンプの後にハイパスフィルタを置き、更に増設アンプの前にローパスフィルタをつけて高周波成分を除去する。計装アンプは差動方式とし、同位相の周辺ノイズが混入してもキャンセルする。生体信号もアナログ信号で伝送するのではなく、A/D変換してデジタル信号にしてから伝送するという。 これ以外にも、生体電気計測をする場合には、いくつも注意しなければならない点があるそうだ。小阪氏はその例として、「電源ノイズ(50/60Hz)が混入する場合はノッチフィルタをかけたり、周辺の電気機器の電源を切る。アルミホイルなどを巻くなどアース電極の設置面積を増やす。さらに計測時に使用する机などもしっかり接地する工夫をしている。また、シールドされているリード線を使ったり、磁界を発生を防ぐために電源ケーブルを丸めない」などの項目を挙げた。 もう1つ重要な点は、使う計測機器とそのほかの計測機器の電源を別系統にすること、GNDも他の場所から発生するノイズを拾わないように別系統にするという点だ。このように、生体信号を正確に計測するためには、さまざまな苦労と工夫があるようだ。 ● ロボット化する人工心臓とセンシング技術で生体情報の遠隔モニタリングも 次に小阪氏は、人工心臓をロボット化するためのセンサ技術や信号処理の話などについて言及した。ロボットを「自律的に作業を行ない、特殊な環境で活躍するもの」と定義すれば、人工心臓もロボットの1つになりえると考えられる。人工心臓は、心臓の左心室に取り付け拍出を補助するものと、心臓を完全に代替するものに大別できる。国内でもさまざまな研究や製品開発、臨床試験が進められているが、小阪氏の研究は後者にあたるという。 最近の人工心臓の中には、血液を送るための羽車を電磁気で宙に浮かし、非接触で回転させることによって、血液凝固や血液を壊すような反応を防ぐ工夫がなされているという。電磁気で羽根車を浮上させる場合は、その位置を知るために変位センサが取り付けられるが、電磁石やセンサが壊れる可能性もある。そのため産総研では、これらを必要としない動圧軸受けを応用した動圧浮上遠心血液ポンプを開発している【写真24】。 さらに小阪氏は、ロボット化という観点からメディカル機器を考えると、こういった人工心臓を埋め込んだあとに、病室ではなく自宅での療養が可能な集中管理システムができないかと考えている。その一例として、産総研と筑波大学によって共同で進められているロボット化人工心臓の概念について説明した。 筑波大学では、体内埋め込み型の血流量計測、血圧計、体温計など、スマート化センサを開発している。一方、産総研では流体の遠心力を利用した小型質量流量計を試作し、実験を進めている【写真25】。これは人工心臓の入口や出口に装着し、血液流量の遠心力をとらえて計測するものだ。このような生体情報をセンサによって遠隔でモニタリングし、異常時に病院に知らせられるようになれば、自宅にいる人工心臓の患者も安心できる。
すでに、羊に人工心臓を埋め込んで実験を行なっており、遠隔モニタリングシステムによってさまざまな生体情報を監視したり、その情報をデータベース化して過去のデータと照らし合わせながら診断することもできるようになっているという。また異常があった場合に通知したり、人工心臓の制御もできるそうだ。メディカル分野でのロボット技術の応用と進展には目を見張るものがあると感じた。 ■URL 日本ロボット学会 http://www.rsj.or.jp/
( 井上猛雄 )
- ページの先頭へ-
|