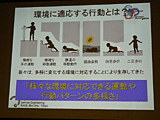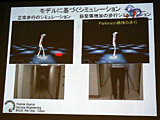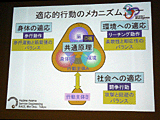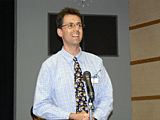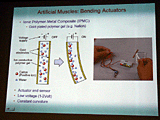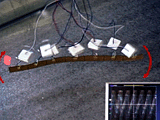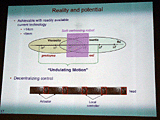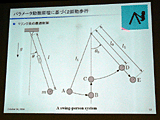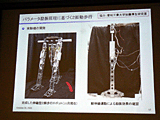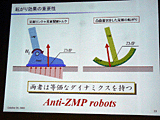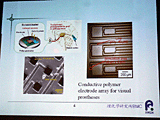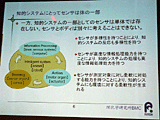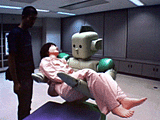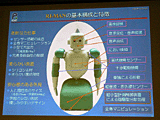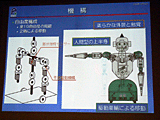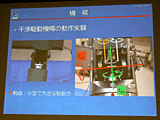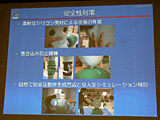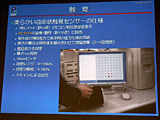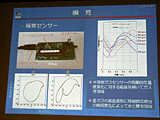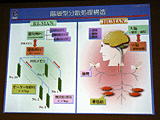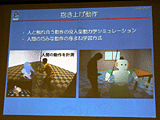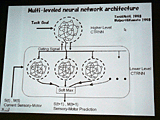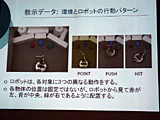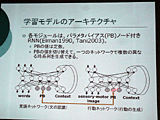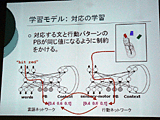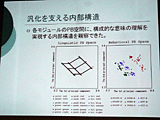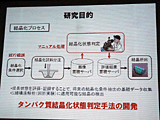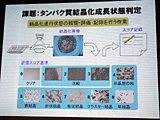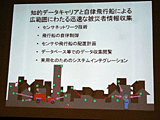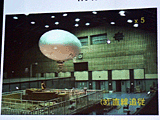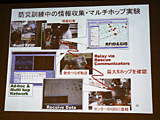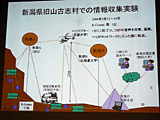|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シンポジウム「理研における人間共生ロボティクス」レポート |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10月26日、独立行政法人 理化学研究所(理研)は、シンポジウム「理研における人間共生ロボティクス」を開催した。理研は自然科学全般を扱う総合研究所で、ロボティクスにおいては、生物規範システム構築、適応的制御などの観点で研究が行なわれている。 理研では大きく分けると3つのグループがロボティクス関連研究を行なっている。生物模倣型のロボットを目指すフロンティア研究システム バイオミメティック・コントロール・研究センター(BMC)の生物型感覚統合センサー研究チーム、同・環境適応ロボットシステム研究チーム、ロボットを使って構成論的に脳科学研究を行なっている脳科学総合研究センターの動的認知行動研究チーム、そして中央研究所の分散適応ロボティクス研究ユニットだ。 4つのグループが一同に介してシンポジウムを行なったのは今回が初めて。理研内部の研究者たち自身にとっても相互交流の場となったようだ。それぞれのグループの発表を通じて理研のロボット研究の内容をのぞいてみよう。 ● 「移動知」~生物と工学の融合による構成論的アプローチ
「移動知」は昨年からスタートしたプロジェクトだ。環境に応じて適切に行動する知的能力――「適応的行動」に着目して研究を進めている。 人間は未知の環境、雑踏のなかでも普通に歩くことができる。あらかじめモデル化できない環境で動くことができるのはどうしてだろうか。また人間は多様な移動パターンを持っている。人間だけではない。どんな動物でも生存のために持っているもっとも知的で基本的な機能だ。人間に対して適応し、限定されない環境での動作が期待されるサービスロボットが一般市場に出て行くためには、適応的行動能力が必要不可欠である。
では生物はどうやって適応的行動を発現するのか。まだよくわかっていない。人間でもパーキンソン病などの病気になると行動障害が起きる。そのような社会的背景からも適応的行動の解明が待たれている。 ではなぜ移動知なのか。能動的に動くことで脳、身体、環境のインタラクションが生まれる。それが適応的行動発現において重要だと考えたからだという。 従来のロボティクスと移動知の概念は少し違うと淺間氏は言う。従来のロボティクスではまずセンシング、知覚があった。だが実際には動かないとリッチな情報は得られない。だから移動知ではまず動くことが重要だと考える。従来のロボティクスの考え方と組み合わせることで、身体とのインタラクションのループが生まれるのだという。 移動知では生物学で得られている神経生理学的なモデルと工学の間をつなぎ、適応的行動が発現するかどうかを検証していく。これを淺間氏らは「生工融合による構成論的アプローチ」と呼んでいる。 具体例として、パーキンソン病の運動障害がどうして起きるのかという神経生理学モデルと、生体システムモデルを構築し、シミュレーションを行なった例などを示した。パーキンソン病の状態に近いと考えられる、筋肉が緊張している状態だと、歩幅が短くなることが確認されたという。 また、シミュレーションではさまざまなパラメータを変えることができる。逆に筋肉の緊張をゆるめると、小脳前庭系に障害をうけたときのような動きが現れたことなどから、シミュレーションによって今までわからなかったことがわかるようになってきたと述べた。 「生工融合」によって、生物学も新たな知見を得ていくことができれば、うまい循環ができていくのではないかという。 移動知は4つの班構成で研究を行なっている。まず3つのグループはそれぞれ、歩行を中心とした身体の適応メカニズム、リーチングをテーマにした環境への適応メカニズム、昆虫などの社会的行動をテーマにした社会性行動選択のメカニズムの研究を行なっているという。もうひとつの班は、共通原理を探り設計論を模索する班だ。現段階ではまだ議論が進んでいないが、行動発現におけるバランスメカニズムの研究を行なっている。 最後に淺間氏は、北海道大学助教授の青沼仁志氏らによる、コオロギの社会的行動、主として闘争に関するメカニズム研究の現状を紹介した。実際のコオロギの行動を説明できるモデルを構築し、シミュレーションを行なっているという。 コオロギは脳内で情報伝達物質として機能しているNO(一酸化窒素)を取り除くと負けても負けても戦うばかりか、非常にアグレッシブに戦う個体になるという。また個体密度によって攻撃性が変わるそうだ。 今後、「移動知」プロジェクトでは、生物学の研究ができる工学者や、工学の研究ができる生物学者を育てていくことも目指すという。
● バイオミメティックグループの研究
生物の複雑なダイナミックな動きの仕掛けを知ることが目的で、生物の制御におけるロバストネス、環境への適応性、多様性、巧妙さ、複合運動、エネルギー効率など現在の機械とは比較にならない優れた特徴を学んで新しい機械を生み出すことを目標としている。 最初の演題は「A soft snake-like swimming robot : from bio-mimetics to autonomous robotics」。IPMCと呼ばれるイオン導電性高分子アクチュエータ、すなわち人工筋肉の一種を用いて、ヘビのように体をくねらせながら泳ぐバイオミメティックロボットの研究の現状についてジョナサン・ロシタ(Jonathan Rossiter)氏が講演した。 Rossiter氏らは7つの独立して駆動するセグメントで構成されたヘビ型ロボットの研究開発を行なっているという。すばやい旋回動作などを実現することに成功しているが、現状ではまだプリミティブなレベルに留まっているようだ。
浅野氏は「パラメータ励振」という手法で二足動歩行できる受動歩行ロボットの研究を行なっている。たとえばブランコを漕ぐときのように、遊脚を伸び縮みすることで質点を移動させれば、励起と制振を制御することができる。それを使ってエネルギー効率が良くて高速な受動歩行を実現しようという試みだ。現在、愛知工業大学と共同で実機の開発を行なっているそうだ。また、足裏のカーブによる「転がり効果」の活用にも着目して研究を進めているという。
向井氏は、アクティブセンシングやセンサフュージョンの研究を行なっている。同グループでは医用工学への応用として人工眼用の導電性高分子の電極を持ったセンサーなども開発しているが、今回の講演は主にバイオミメティックグループ全体が開発した抱え上げロボット「RI-MAN(リーマン)」に使われているセンサー技術について行なわれた。
「RI-MAN」とは「Robot Interacting with Human」の略称である。19自由度、高さが158cm、重さが約100kgの大きな上半身型のヒューマノイドロボットだ。足は2自由度の台車だが、複数のモータの出力を組み合わせる「干渉駆動」と呼ばれる方式で小型高出力を出せる6自由度の双腕と、左右前腕・上腕・胴体につけられた面状触覚センサーからの力の大きさや位置の情報を用いて、重量物を抱き上げることができる。 外乱をあたえても落ちないような動きをすることができる点が特徴で、現状では18kg程度の人形を抱きかかえることができるという。5年後には人間を持ち上げることを目標としている。今年3月にリリースされた。 全身は人間と接触しても大丈夫なように厚さ5mmのシリコンで覆われている。また、触覚以外に視覚・聴覚・嗅覚の4つの感覚を持つ。人間の外耳にあたる反響板を使った音源定位や、一つの半導体ガスセンサに周期的な温度変化を与えて抵抗値を非線形に変化させることで複数の種類の匂いを嗅ぎ分け、濃度を識別することができる。匂いを嗅ぐ機能がついているのは、RI-MANが介護を目的としており、尿の匂いを検知するためだ。 処理系には階層型分散処理構造が用いられている。2台のPCのほか、全身に14個の小型CPU「C-CHIP」をネットワーク化してモータ制御用と触覚処理用に用いている。多くの研究者による共同作業は苦労も多かったそうだが、階層型分散制御構造をとったことで、ソフトウェアの開発はだいぶ楽になったという。 開発構想が始まったのは2003年4月。全身をうまく使ってものを持ち上げることができるやわらかい体を持ったロボットとして構想された。検討を行なうなかで特に注目されたのが介護支援における移乗作業だったのだそうだ。今後は、さらに多様な環境への対処能力の強化と、より人間的な感覚の取得が目標だという。
生物運動を模倣するときには「解析する」という立場と「合成する」という立場がある。生物は機械には考えられないほど多様な動きを実現している。それは環境や仕事の多様性を反映しているのだろうが、行動規範そのものは単純であってもいいかもしれないと細江氏は語る。ただし、運動は比較的単純な評価に基づく最適行動だとしても、設計が簡単であるとは限らない。超多自由度、非線形性、離散と連続、不確かなモデルといった困難を乗り越えなければならない。 細江氏は例としてリーチング運動の研究を示した。「リーチング」とは例えばコップを取るときのように、腕をあるところからあるところに動かす運動である。人間は腕をあるカーブにそって、速度をスムーズに変化させながら動かす。それがどんな規範に基づいているのか説明するために、さまざまな規範が提案されている。 提案されている規範はどれもそれなりに人間の腕の動きを近似できるが、細江氏らは、拘束があるときの動きも統一して説明できる規範を探した。例えば、ドアをあけるときはドアにそってしか動かない。そういうときの腕の動きも説明できる規範だ。その結果、関節トルクを手先の力に変換した量の変化率の2乗積分を評価関数とすることで、うまく説明できることが分かった。 ただ、人は単純な最適規範で制御しているかもしれないが、ではそれに基づいて設計すれば話は簡単かというとそうではない。細江氏は、離散と連続のまざったハイブリッドシステム制御などのモデル予測制御や強化学習を使った運動合成のアプローチの提案を説明した。 ただ、生物のような柔軟性や多様性の表現は今後の課題だと述べた。
環境変化に適応可能な多様なタスクゴールを実現するためには、同じ1つのことを学習させるのではなく、さまざまなシチュエーションをロボットにまとめて学習させることが重要だという。 谷氏らは、「RNN-PB」――パラメトリック・バイアス(PB)で繋がれたリカレント・ニューラル・ネットワーク(RNN)を使って、記号操作をできるだけ廃し、力学的な引き込みを利用して多様な行動発現を実現するアプローチを行なっている。現在の状態から次の状態への移行を予測することができるような形のネットワークとなっている点が特徴。 実験の様子として、ロボットに同時に3種類のタスクを覚えさせるが自然に行動の分節化ができるようになり、様子、そして人間が軽く手助けすることでロボットにタスクを覚えさせる様子を見せた。
把持位置がずれていたりする場合も同様にちょっと手助けすることでうまくつかめるようになっていく。またこの仕組みを使って、ビジュアルフローが入ってこない場合も、あたかも刺激が入力されているかのようにロボットが自分でセンサー情報を作り出してネットワークに食わせて学習させることもできる。 ロボットが、実際にはやっていない行動を、あたかもやっているかのように捉えて学習していく様子は、子供が最初できなかったころがだんだんできるようになっていく様子を連想させ、なかなか興味深いものだった。
たとえば「赤を打て」というと、「赤」とか「打て」という言葉の意味を知らないのに、きちんと言葉を理解しているかのような行動を行なえるようになるのである(詳細は理研広報誌の記事が分かりやすい)。 従来の人工知能との大きな違いは、文全体がタスクに接地していることだという。ただし、文章と行動のインタラクション学習を収束させるのに5万ステップほどかかるそうだ。
1つ目は「タンパク質自動観察システムの知能化について」。研究ユニットリーダーの川端邦明氏が講演した。理研では2002年から2006年までの予定で「タンパク3000」プロジェクトを進めている。たんぱく質の構造を3,000個決めようというプロジェクトだ。構造解析の効率を向上させるための自動化ロボットが求められている。 「タンパク3000」以前からこの問題はあり、理研では全自動タンパク質結晶化観察ロボット「TERA」を作っている。さまざまな条件・試薬を使ってタンパク質を結晶化するためのロボットだ。同様のロボットは他の研究所にもある。 だがいったん自動化技術ができると、今度はデータがどんどんたまってくるが評価しきれないという問題が出てくる。タンパク質研究の場合は、結晶成長における画像を見るのが大変になってしまう。そこで川端氏らは、結晶の中からタンパク質の構造解析に使えるものと使えないものを自動選別する技術を開発し、TERAに搭載するべく研究を続けている。そこそこの精度にはなっているそうだが、今後はさらに、結晶化がどうやって起こるのかデータマイニングなどもできるようにしていきたいという。
具体的なデバイスとして、本誌でも何度かレスキューロボット関連で紹介している「レスキューコミュニケータ」を同グループでは開発している。レスキューコミュニケータは、無線LANや音声の入出力機能を持ち、情報を伝達・共有することができる小型サーバーだ。 動的にルーティングを変えられるアドホック性、数珠繋ぎにデータを送ることができるマルチホップ性が特徴であるメッシュネットワークを使って、インターネットが落ちているときでもデータを送受信できる。 その上を同じく同グループが開発したロボット飛行船や、レスキューを行なう各種ロボットや隊員たちが付近を通過することで情報をキャッチする。現時点では、自動音声認識などの機能を入れることは考えていないそうだ。というのは、声を出せないような状況でも、ドンドンと周囲のものを叩くことで助けを求める合図を音で送ることはできるが、そのようなものは人間が直接耳で聞くほうが遙かに確実で安全性も高いからである。 先月には、新潟県山古志村で実験を行なったそうで、その模様も紹介された。
まず向井氏が「理研におけるロボティクスはどうあるべきか」と問いかけた。理研は総合研究所であり、もともといろんな分野があるということが、ひとつのメリットになるだろうという。企業は利潤を求めるためにどうしても短期的研究が中心であり、「できる」とわかっていることをきっちりつくることが求められる。 また産総研も理研から見ると短期的な視点で研究を進めているように見えるという。理研は、もうちょっと踏み込んだところで、あやしいけれどできたらすごいと思われるようなことを目指すべきではないかと述べた。 谷氏は、もともとの興味として、一見、人間の頭のなかに記号があり、それを操作することでさまざまな情報処理をやっているように見えているが、実際には日々の活動の結果としてセンサー-モーター(感覚-運動)系の信号が構造化されたものが、外から見るとあたかも記号のように見えているのではないかという考え方が基本にあると述べた。それを脳の断面で見たらどうなのかという観点で研究を行なっているという。 また、対極に思われるフッサールに始まる現象学にも興味があり、脳、現象学、そして記号接地も説明できるような形で研究を行なっていきたいと述べた。理研における脳の研究も、どうしても要素還元主義になりがちだが、ロボットを使って行動を生成するという研究を行なうことで、脳科学の見方も変えることができるのではないかと語った。
羅氏は、ロボットには現在の制御工学はそれほど使えないのではないかと考えているそうだ。以前から環境適応に興味関心があったという羅氏は、「多くの人は統合化の技術としてロボットを見ているが、そうではなく、ロボットを問題意識の出発点とすることで波及効果が出てくる学問なのではないか」という考えを述べた。 また、現在の企業におけるロボット開発は成果を出せるのかどうか疑問視しているという。ロボットは自由な発想がないとできないと語り、十数名で3年間かけた「RI-MAN」開発過程では、1年間は喧嘩ばかりしていたとエピソードを紹介した。それぞれ価値観やイメージが違うなかで、どうやってひとつのイメージにするかが難しかったという。また現在のロボット技術ではアクチュエーター1つとっても社会の要求には応えられるレベルにないと述べた。 これに対し谷氏は、「ロボットにとって役に立つとはどういうことか」考え直し、ロボットは専用機械ではないので不安定ではあるが面白いことができる奴だというふうに一般社会が認知しないと、社会的需要はなかなか難しいという考えを述べた。 いっぽう、理研におけるロボット開発については、バイオミメティック研究センターセンター長の細江氏が理研の中の各グループについて「それぞれうまく住み分けて違う仕事をやっているのではないか。これから各グループが繋がって面白い仕事ができる可能性もあるなと思っている」と語った。 それに対して向井氏は、RI-MAN開発にあたって交流を研究者間で深めることができたと語り、このシンポを機会に理研のなかの各グループのなかで交流を深めていきたいとした。 コーディネーターを務めた川端氏は、「われわれのチームですらコミュニケーションが不足している。すみわけができているとすれば、それをコネクションする力が必要だ。これからもこういう活動を時折やっていき、理研におけるロボット研究を考えていくことが重要。相乗効果が生まれてくることを期待したい」と語った。 ■URL 理化学研究所 http://www.riken.jp/
( 森山和道 )
- ページの先頭へ-
|