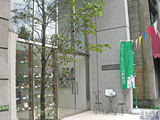|
記事検索 |
最新ニュース |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
「魅惑のオートマタ展」、明日から開催 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
~古くて新しいロボットの原点、オートマタの深遠なる世界へ
|
||||||||||||||||||||||||||||||
「オルゴールの小さな博物館」は、1983年に名村氏が日本で初めて開館したオルゴール博物館。その名のとおり、シリンダー式オルゴール、ディスク式オルゴール、オートマタ、ストリートオルガン、自動演奏ピアノなど、18世紀から20世紀にかけて発達したオルゴール類が約300点ほど所蔵されている。名前に「小さな」と冠されているが、実は7階建ての瀟洒な博物館で、6階と7階にある展示室のほか、ショップやくつろげるカフェもある。また、1階の大きな音楽ホールでは、さまざまなアンティーク・オルゴールや自動ピアノなどの演奏を聴くことができる。 この9月26日から開催される「魅惑のオートマタ展(からくり人形)」は、同館で年に数回催される企画展として用意されたもの。いずれの展示品も100年以上も前の貴重なオートマタの傑作ばかりだ。機械やロボットが好きな方ならば、目を釘付けにされるような作品がずらりと並んでいる。 2足歩行ロボットやペット型ロボットなど、いまや日本のロボット技術は世界のトップを走り、ロボットづくりにあこがれる子供たちも多くなってきた。 ロボットはメカニック、センシング、コンピュータ、制御技術など、さまざまな最先端技術の集大成であるため、どうしても新技術に目が向きがちだが、実は過去の先人たちが残していった素晴らしい技術や知恵もたくさんある。今回、オルゴールの小さな博物館で展示されるオートマタもそのひとつなのだ。
オートマタは、端的にいうと西洋の「からくり人形」というとわかりやすいと思う。ただし、日本のからくり人形とは少し異なる点がある。それはオルゴールの持つゼンマイを動力源として、音楽を奏でながら自動で動く、からくり人形であるという点だろう。オートマタはこのような複雑な機構や、からくりの仕組みが面白いだけではない。人形そのものの精緻な表情や衣装に加えて、美しく奏でられるオルゴールの音色がかけ合わさった「総合芸術」ともいうべきものなのかもしれない。 名村館長の説明によれば、「オートマタの原点は、14世紀以降の教会などに設置された、音楽を奏でる塔時計。鐘たたきのからくり人形・ジャックから始まった」。こうした伝統が1700年代になるとオートマタとして一気に開花し、オートマタづくりの祖といわれる2人の天才、ジャック・ド・ヴォーカンソン(フランス)とジャケ・ドロー(スイス)が登場する。 ヴォーカンソンが1730年代につくったアヒルは羽・尾・首を動かし、水を飲んだり穀物をついばんだり、さらにはこれらをお腹に蓄え、パンくずを練って着色した排泄物まで出したというから本当に驚きだ。一方、ジャケ・ドローが1770年代に製作したオートマタたちは、マリー・アントワネットの横顔など5つの絵を描くことができたり、名前や文章を書いたり、両方の手を使ってピアノの鍵盤を弾くことができる、現代の最先端ロボットに匹敵するような精巧なものだったという。 さらに1800年の初頭には、一般家庭で使われる懐中時計や掛け時計、あるいは置時計の中にも、音楽とオートマタが組み込まれるようになった。博物館所蔵のオートマタ付き懐中時計(1810年)は、「水が流れて、馬が水を飲み、水車が回り、釣り人が魚の付いた竿をあげる」といった一連の動作を事もなげにする。わずか数センチの懐中時計の中に、箱庭のような確固たる世界観があるのだ。 この時代になると、時計宝飾産業の中心地であったフランスに市販用のオートマタづくりの工房が続々と誕生する。そして1800年代後半から1900年代初頭にかけて、オートマタづくりは最盛期を迎えることになり、万博などの影響も拍車をかけるかたちで、さまざまな傑作が世に登場した。 名村明日子氏(本博物館マネージャ)は「ここにある19世紀後半のオートマタを見ていると、歴史の裏側が垣間見えてきます。技術的にはジャケ・ドローのような一品モノのほうが上かもしれませんが、商品としていかに家庭の中に浸透させていくか、たとえば工作機械が取り入れられ、同じ歯車やカムを作れるようになったことで量産が可能になったということもあるのでしょうが、当時のオートマタ産業の広がりを感じとることができます」と、その魅力について語る。オルゴールの小さな博物館では、この時代のオートマタを主に収蔵している。 ● 100年以上も前の貴重な作品を目の当たりにできる秘密とは? たとえば、1890年代ごろにつくられたレオポルド・ランベールの「トルコの煙草のみ」は、火がつけられた煙草をふかすオートマタだ。単に煙草を口元に持っていく機構ではなく、煙草の煙を口から吐くのだ(機構部に「ふいご」を利用しているという)。それも首をゆっくりと振りながら、まぶたを何回か閉じて煙草を味わいながら、いかにも美味しそうに一服する。その表情はお父さんが一週間の禁煙生活を解いて、久々に吸う至高の一服といった感じなのだ。ルイ・ルヌーの「手品をする少年」(1900年ごろ)や「クラウン・マジシャン」(1900年ごろ)という作品もとても面白い。前者はテーブルの小箱を持ち上げると、卓上に異なる色のボールが現れるというマジックを実演してくれる。一方、後者は大きな扇子で頭を隠した瞬間に頭がパッと消えて、次に隣の箱から頭がゆっくりと現れてくるオートマタだ。こういったギミックは大人も子供も理屈ぬきで楽しめるだろう。
ルレ・エ・ドゥカンの「ケン玉をする少年」(1890年ごろ)も、ときどきケン玉を額に当てるようなしぐさがあって(故意なのかどうかはわからないが)とても可愛らしい。ドゥカンの作品には「シャボン玉吹き少年」(1890年)や「梯子乗りの少年」(1900年ごろ)など、人をテーマにしたものから、「キャベツの中のウサギ」(1890年ごろ)、「プードル」(1910年ごろ)、「ドリンキング・ベアー」(1890年ごろ)というように、愛らしい動物までを題材にした作品も展示されている。
これらは単に静物として展示されているのではなく、動きそのものを実際に目の当たりにできる展示方式が採られている。世界でもこれだけ多くのアンティーク・オルゴールやオートマタを動かしてくれる博物館はほとんどないという。 100年以上の時を経てもなお、当時の状態を維持しながら動態展示を実施できる秘密は、この博物館の3階にある。実はここに修理工房があるのだ。この工房を入ると切削油の香りが漂ってくる。旋盤、ボール盤、フライス盤など、機械製作に必要なあらゆる工作機械一式が整然と並んでいる。この工房で専属のマイスターがアンティーク・オルゴールの修理はもちろんのこと、オートマタなどの修復も行っているそうだ。 実際、展示会の目玉となるギュスターフ・ヴィシーの作品「ピエロ エクリヴァン」(1895年ごろ)は、この工房で修復されたもの。この作品はある著名人の所蔵品であり、今年の春に怪我を治すために工房に入院してきた「大切な患者さん」だった。博物館でも同様のレプリカ(ミッシェル・ベルトラン作)を所蔵しているが、今回の展示会では、この個人コレクターの好意から特別に修復品を借りることができ、両作品の共演が実現したという。
ピエロ エクリヴァンの修復作業が極めて困難であったことはうかがい知れるところだ。展示会ではその修復の過程もパネルで紹介されていた。初めて修理をするものであるため、まずは構造そのものを理解することから始める必要がある。 とはいえ、もちろんオートマタが製作された当時はISOなどの国際標準規格もなかった。すべて独自の部品だ。修復するために参考になるような設計図や資料もない。不用意に分解すると、本当に取り返しのつかないことになってしまう。 そのため試行錯誤を繰り返しながら、慎重に不具合の調整をしたそうだ。オルゴール音源部の櫛歯を調整してダンパーノイズを消したり、ランプの灯火の強さや動作タイミングを調整したり、指や手、耳などの欠損部品はいちからつくり直し、さらに修復部がわからないように塗装の色あわせをしたりと、ちょっと想像しただけでも、雲をつかむような、そして根気と忍耐を要する作業の連続だ。 オルゴールにしてもオートマタにしても、100年以上も前の作品を実際に目の当たりにできるのは、こうした不断の努力が見えないところで続けられているからだろう。 ● オートマタの世界を垣間見て、「温故知新」をあらためて知る 現代の最先端技術には、ほとんどといってよいほど電気が使われている。コンピュータにしてもロボットにしても、日常生活に欠かせないものは電気がなければ動くことすらままならない状況だ。電気エネルギーの力をほとんど借りずに(一部電気で動くものもあるというが)、ゼンマイの力や空気圧だけで、人間のような繊細な制御をするオートマタを見つめていると、あらためて技術とは何なのか? という根本的な問題をつきつけられるような気持ちにもなる。科学の進歩によって、コンピュータの集積化が進み、ひとつのチップだけであらゆる処理を施せるほどパフォーマンスも向上した。しかし、その半面で機械のブラックボックス化が進み、一体どうやって動いているのか? という「ものの仕組み」自体がよくわからなくなってしまったように思われる。 チップの中のわずか1個のトランジスタが壊れただけでも、もはや我々には為す術もないのだ。そう考えると、テクノロジーがまだそれほど発達していない古き時代において、その当時の制約された環境のもとで使える技術を駆使して、創意工夫を凝らしながら作品をつくりあげていった職人気質の芸術家たちの知恵くらべに、ただただ感心させられるばかりだ。 今回の展示品を見ながら、20年近く前に筆者が新米技術者だったころ、研究所の所長に言われたことをふと想い出した。それは「知恵と知識は違うものだ。技術がなければ知恵を絞りなさい」。「あれがない、これがないから難しいという前に、身近にあるものを最大限に活かして、足りない点は頭を振り絞ってカバーしなさい」という言葉だった――本当はそういう姿勢こそが、いつの時代でも、何かに向きあうときにとても大切なことなのではないかと、あらためて気づかされた。 もちろん最先端の知識を追うことも重要なことだ。だが、その一方で「温故知新」という言葉のとおり、先人たちが苦労を重ねてきた世界には、忘れかけていた大事な何かや、驚きの英知がたくさん隠されているように感じる。 ここで紹介したオートマタの魅力については、筆者の力量不足でほんのごくごく一部しかお伝えできていないと思う。オルゴールや音楽が好きな方はもちろんのこと、芸術が好きな方も、ロボットが好きな方も、技術者を志す方も、熟練の技工士の方も、本物のオートマタを自分の目で確かめてみて、その魅力をじっくりと堪能していただければと思う。ハッとするような驚きや感動、新しい発見をきっと見つけられるにちがいない。 ■URL オルゴールの小さな博物館 http://musemuse.jp/
( 井上猛雄 )
- ページの先頭へ-
|