高エネルギー加速器研究機構の加速器「Bファクトリー」見学レポート
~秒速約30万kmや1兆分の1秒に挑む世界に誇る技術
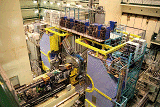 |
| メイン加速器のBファクトリーの最重要機器「Belle測定器」。衝突で生まれた素粒子を検出する |
世界一の実力を持つ粒子加速器を有する、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(通称KEK)の無料一般公開が6日に実施された。数ある施設の中で、直径1km、円周全長3kmに及ぶ広大な加速器の主要施設を中心に取材してきたので、その模様をお届けする。
●世界にも知られた日本の加速器科学の最前線・高エネルギー加速器研究機構
KEKは、1955年に東京大学原子核研究所という、原子核物理学の研究を目的とする大学付属研究所として設立されたのがスタート。1971年に当時の文部省(現文部科学省)の直轄の共同利用研究所として設立された高エネルギー物理学研究所も前身の1つで、その2つが1997年に統合され、高エネルギー加速器研究機構となった。そして、2004年4月に現在の大学共同利用機関法人となったという経緯を持つ。
KEK設立の目的は、日本の加速器科学の総合的発展の拠点として研究を推進し、国内外の関連分野の研究者に対して研究の場を提供すること。2004年4月1日時点のデータだが、KEKのスタッフ数は854人(役員7人、常勤職員690人、非常勤職員157人)となっている。年間予算は2007年度のデータで、約409億円。その内、運営費(特に施設を稼働させる電力料金)が約8割をしめているという。運営費の多くが、年間300日におよぶ加速器に使用される電気料金で、その使用量は2006年度のデータでは年間で41万6,600MW=一般家庭約11万戸分だそうだ。
所在地は、筑波研究学園都市の最北部に位置し(つくばエクスプレスのつくば駅から施設正門までバスで約20分)、東西に1km、南北に1.5kmほどの敷地を持つ。その広さは、東京ドーム約33個分だ。
 |  |
| KEKの航空写真。二重の円が見えるが、外側の建物をつなぐフェンスの下に地下トンネルがある。内側は道路 | KEKの施設案内図。航空写真を右側に倒した形だ(右が北) |
 |  |
| 敷地内にはずいぶんと緑が多く、タヌキやハクビシンなども出るとか | 北の方向に筑波山がある。手前の横長の大きな建物の奥にBelle測定器のある筑波実験棟が見える |
長らく、日本は加速器科学の分野では国際的に見て後れを取ってきたが、KEKにおける研究者や技術者の不断の努力の積み重ねによって、現在は世界一の加速器を要する研究・実験施設となっている。それにより国際的な知名度も高く、海外からも多くの研究者が来日しているという次第だ。実験によっては全世界約60の大学と研究機関から約400名が参加するものもあるほど。
ちなみに、高エネルギー加速器研究機構を英訳した「High Energy Accelerator Research Organization」も実はあまり国際的には通じないそうだが、日本名のローマ字の略称であるKEKは世界規模で通じるという。アメリカはもちろんのこと、韓国、中国、フランス、ドイツ、ロシアなどでもKEKが日本の加速器もしくはそれを有する組織ということで知られているのだ。
●電子と陽電子を衝突させてB中間子と反B中間子を生み出すKEKの主力加速器「Bファクトリー」
KEKにおいて主力として活躍しているのが「KEKB」(ケックビー)、通称「Bファクトリー」と呼ばれる電子・陽電子衝突型加速器だ。地下11m(だいたい地下4~5階ぐらい)に掘られた1周約3kmのトンネル内に電子と陽電子を走らせるための電子リング(HER)と陽電子リング(LER)が並んで設置されており、そのリングにさまざまな機器が取り付けられている。1984年に設計作業が始まり、1994年に建設開始、1999年6月に最初の素粒子反応を観測した。電子と陽電子(電子の反対のプラスの電荷を持った反物質の1つ)を衝突させ、B中間子と反B中間子のペアを大量に生成することから、B(中間子生成)工場=Bファクトリーとつけられたというわけだ。
 |  |  |
| リングの構造を表したCGイラスト | Bファクトリーの地下トンネル内。足下から奥までカーブしつつ伸びているのがリングだ | 地下11mは、おおよそ地下4階。一番上に見える明るい窓が地上1階だ |
電子は、リング内を80億電子ボルトのエネルギーでもって、580億個を1バンチ(およそ長さ7mm×幅0.6mm×高さ0.1mmのひとかたまり)として時計回りに進み、陽電子は35億電子ボルトで800億個を1バンチとして反時計回りに進む。リングを時間にして10時間以上、周回数にして10億周以上(およそ地球~天王星の距離)かけて加速を続け、最終的に光速(秒速約30万km/s)の0.999999997倍に達したときに、7種類の検出器で構成された「Belle測定器」のある衝突点に衝突させる仕組みになっている。リングには常に約1,400個のバンチが周回するようになっており、1秒間に約10万回もの衝突(6ナノまたは8ナノ秒ごとに1回)が行なわれており、結果、B中間子と反B中間子の対を1秒間に最大17個(2006年12月時点のデータ)、1年間なら1億個以上が生成されているという。ちなみに、Belle測定器の名称は長い英語名などの略称ではなく、フランス語の「美」から取られている。美=Bに引っかけているのかもしれない。
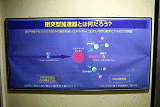 |  |
| 電子と陽電子が衝突して対消滅でエネルギーになり、そこからB中間子と反B中間子が生まれる | Belle検出器で測定された素粒子の軌跡 |
なぜ、電子と陽電子のエネルギーが同じではないのかというのは、電子の進行方向にB中間子と反B中間子をわざと飛ばすようにしているからで、その方が観測しやすいから。何しろ、B中間子や反B中間子の寿命はたったの1ピコ(1兆分の1)秒ほどしかなく、そんな短時間ではいくら現代の技術でも検出は不可能。そこで、わざと電子と陽電子のエネルギーに差を持たせることで、電子の進行方向にB中間子も反B中間子も秒速約11万7,000km/s(光速の約4割)で移動するようにし、寿命までに移動した距離を計測するというわけである(寿命が来ると、さらにほかの素粒子に分かれてしまう)。移動した距離で、結果としてどれだけの寿命があったかがわかるわけだ。
そして、B中間子と反B中間子では、壊れ方に差があるということが判明。それが2008年の小林誠氏(高エネルギー加速器研究機構名誉教授ほか)と益川敏英氏(京都大学名誉教授ほか)の2名による「CP対称性の破れ」を題材にした「小林・益川理論」のノーベル物理学賞につながったというわけである。
●世界一の性能を有するBファクトリー
衝突型加速器の性能は、粒子同士のビーム電流と衝突点でのビームサイズによって決まる「ルミノシティ」と呼ばれる単位で表す。1秒間に、1平方cm当たりに粒子同士が交差する回数を表したもので、ルミノシティ=「毎秒の反応数」/「反応の断面積」で求められる。B中間子と反B中間子の生成率をアップさせるには、このルミノシティの値を大きくすることがポイントだ。Bファクトリーは、この数値が現時点において世界一というわけである。
2001年4月に最大のライバルだったアメリカのスタンフォード大学のスタンフォード線形加速器センター(SLAC)の「PEP-II」(こちらも周長3kmのまさにライバル中のライバル)を抜き去り、現在まで世界一をキープしている。なお、スイスとフランスの国境にまたがる、ヨーロッパ核物理研究機構CERNが現在本格運転に向けて調整を行なっている全長27kmの世界最大の超巨大加速器「LHC」は、より重い陽子を扱えるという点ではもちろん世界一だが、Bファクトリーの方がルミノシティは上だ。
Bファクトリーではまず、2003年5月に当時の世界記録となる設計値の10の34乗cm-2s-1(cmの「-2」およびsの「-1」は乗数)というルミノシティを達成。1990年代から見たら、夢のような数値だったそうである。2006年末頃に、1.71×10の34乗cm-2s-1にアップし、再び世界記録を更新。しかし、そこからここしばらくは頭打ちになってしまったが、今年3月に設置した新たな調整器「スキュー六極電磁石」(電子リングに20台、陽電子リングに8台)が大当たりとなる。設計値の2倍を超える2.11×10の34乗cm-2s-1を6月にマークし、さらに世界記録を更新したのだ。
また、実際にどれだけ衝突事象を収集したかを表す積分ルミノシティでも963/fb(フェムトバーン、フェムトは1千兆分の1)に到達し、こちらも世界記録を更新。ちなみに、スキュー六極電磁石は女性研究者によって開発され、なおかつ予備部品を流用したり改造を施して低コストで開発したという。しかも、設計から設置までの全行程を3カ月で行なったそうだ。費用対効果は抜群だったそうである。
しかし、それでもまだまだ性能的に不足しているということで、来年度からアップグレード計画を開始する予定だ。このアップグレードは、リングの各種機器や検出器、コンピュータなどを最新技術で開発して置き換え、現在の50倍というけた違いの性能に引き上げるというもの。予算は数百億円をかけるという。
もう少し具体的に述べると、ビーム電流を現状の1.4アンペア(リング内は高真空なので、金属などの導体を伝わる際のアンペアとは異なり、この数値でも非常に高い値である)から4アンペアにアップさせる。結果、リングのアーク(曲線)部で電子や陽電子から出る放射光も強くなるため、破損しないようリング自体(真空パイプ)の強化も行なう。その方策の1つが、水平方向に出る放射光を引き込むための溝が設けられているアンテチェンバー型のパイプを使うことだ。アンテチェンバーは、正面から見ると土星のようなイメージで、パイプの両脇に溝の部分が突き出している。この溝は、放射光がリング内壁に当たるまでの距離を延ばすための仕組みで、それによってエネルギーが減衰するので、より強力な放射光が出るようになっても、リング内壁が破損してしまう心配がなくなるというわけだ。
さらに、ルミノシティを高くするため、衝突する電子と陽電子の断面積を小さくすることも行なわれる。衝突点のなるべく近くに、超伝導を利用した強力なレンズを設置し、強く絞り込む予定だ。焦点距離は現在よりも約10倍も短いものを必要とする。そのため、衝突点の改造も行なわれるという。有限交差角衝突の角度をさらに大きくするのだそうだ。さらに、高品質な電子と陽電子のビームを作るため、光学系の改造にも取り組んでいく。高品質なビームを表す指標としてエミッタンスが使われるが、その値が低ければ低いほどよく、現在より10倍も小さいエミッタンスを目指すとしている。また、さらなる高真空化するため、リングを構成するパイプのつなぎ目の強化や、より強力な真空ポンプも備えられる予定だ。
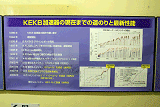 |  |
| ルミノシティをアップさせてきた歴史とそのグラフ、ライバル加速器たちとの競争などのグラフ | アップグレード計画。現時点でもルミノシティは世界のトップだが、その50倍を目指すという |
●Bファクトリーは「電子・陽電子入射リニアック」からスタート
続いては、主要施設4カ所を回ってみたので、順を追って紹介する。まずはBファクトリーの主要施設のトップバッター、電子と陽電子を作ってリングに送り込む「電子・陽電子入射リニアック」から紹介しよう。リニアックとは線形(直線)加速器のことで、全長600mほどの長さがある。実際には一直線に600mあるわけではなく、125mほど進んだらUターンして、そこからさらに483m進むとリングとの接続部(正確には4つのリングへのスイッチヤード)になるという構造だ。リニアックとしては、世界で2番目の長さを有しており、それだけ初期の加速を得られるというわけだ。
 |  | 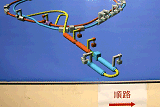 |
| 電子・陽電子入射リニアックは敷地内の西部にある | 航空写真で見ても、電子・陽電子入射リニアックは一目でわかる | 電子・陽電子入射リニアックのイラスト |
 | 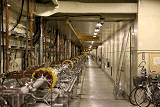 |  |
| 施設は横に長く続く | 実際のリニアックの加速管の部分。ここからは400mほど直進してリングに接続する形となる | Uターン部分 |
電子と陽電子の生成だが、まず電子から説明すると、リニアックの中でも最上流に位置する「熱電子銃」が、最大14アンペアのパルス電子ビームを発生させて生み出す。それを無酸素銅製の加速管240本で加速していく。加速管1本当たり4,000万電子ボルトのエネルギーをもって加速を行なう。加速管へのエネルギーは、地上階にある約60本のクライストロン(真空管)が2,856MHzの高周波電力を供給することで行なう。それぞれのクライストロンは4万kWの高周波を発生させているということで、なんだかあまりにも数字が大きすぎて、イマイチ把握しにくいのは致し方がないところか(苦笑)。リングに届く時点では80億電子ボルトまで減衰するようだが、それを考慮して、リニアックでは90億電子ボルトまで加速できる能力がある。
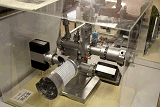 |  | 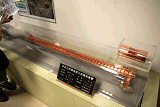 |
| 熱電子銃の1/2スケール模型 | 熱電子銃を別角度から | 加速管。ただし、Bファクトリーではなく、放射光施設へのもの |
 | 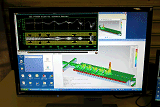 | 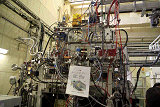 |
| 加速管の断面。無酸素銅で作られている | 加速していく様子を表したCGムービーの一画面 | クライストロン |
一方の陽電子の方は、40億電子ボルトまで加速する能力があり、生成は途中まで一緒。Uターンして150mぐらい進んだところで、陽電子生成用ターゲットが設置されており、タングステンにビームを当て、そこから陽電子を弾き出して生成する。その後残りの300mオーバーの距離を加速して、リングに入るときには35億電子ボルトにまで加速しているというわけである。
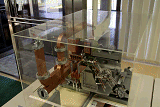 | 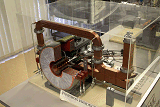 |
| 陽電子生成標的の1/2スケールモデル | 別角度から |
なお、KEKにはメインのBファクトリーの電子&陽電子の2本のリングのほかに、フォトンファクトリー(光工場:放射光科学研究施設)にある放射光を発生させるための「PFリング」(周長187mの楕円形加速器)と、フォトンファクトリーAR北西棟にある光源加速器「PF-AR(Advanced Ring for Pulse X-rays)リング」の小型リングがある。リニアックは、これら4本に同時入射できるのも大きなポイントだ。従来はどのリングに入射させるかの切り替えを手動で行なっていて、2分かかっていたのだが、ここで行なわれている実験は、ピコとかフェムトなど、すっかり耳になじんだナノ(10億分の1)よりもさらに下の超絶的な短時間の世界での話なので、性能が下がってしまう欠点があった(リング内を周回するバンチがどんどん減っていってしまう)。
そこで、機械的に短時間で切り替え、同時入射を行なうことにしたのだが、まず必要なのが、0.02秒で電子と陽電子のどちらの生成を行なうかの切り替え。その短時間で機械的にタングステンを引っ込めたり出したりを行なうのは不可能なことから、電子の軌道を変化させ、陽電子がほしいときは直進させてタングステンに衝突させ、電子をそのままほしいときは0.02秒で電磁的な切り替えを行なって、わずかに軌道をそらしてタングステンの横に開けた穴を通過させるという工夫を凝らしたのである。
しかし、そんな0.02秒なんていうのはとんでもなくゆっくりとしている方。入射をどのリングにするかを切り替える「イベントシステム」は、桁違いというか壮絶なほど短時間での作動が要求され、なんと10ピコ秒しかないのだ。しかも、1カ所の装置の制御というわけではなく、600mの長さの内の各所に備えられたさまざまな装置を同時に制御しているということなので、とんでもない制御技術である。
ちなみに、こんな極短時間で光に近い速さで走る超極小の電子や陽電子の固まりを操るには、制御室と現場の機器、または機器同士をつなぐ信号用のケーブルの長さまできっちり算出して計算し、信号が届くまで、そして機器が動作するまでの時間も計算に入れないと、狙ったタイミングの通りに電子や陽電子を操れないそうである(信号ケーブルを流れる電子もそれほど変わらない光の速さなので)。
なお、小型の2本のリングはBファクトリーの2本に比べると、PFが25億電子ボルト、PF-ARが30億電子ボルトとエネルギー的に低いので、それぞれに合わせて減速を行なう仕組みを備えて対応しているという。
●Bファクトリーのリングが設置された地下トンネル内を見学
続いて訪れたのが、Bファクトリーのメインのリングがあるトンネル内の見学コース。リングは、正確には真円、もしくは楕円といった全域でカーブを描いているのではなく、東西南北の4カ所で大きなカーブを描きつつ、途中には直線がある。その上、もしくは近くに各種施設が建てられている。エリア名として、電子・陽電子入射リニアックに近いエリアで、南アーク(リングがカーブしているところ)と西アークの間が富士。時計回りに、北西エリアが日光、北東エリアが筑波、南東エリアが大穂となっている。見学コースは富士エリアに含まれる。
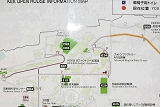 |  | 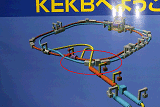 |
| トンネル内の見学コース。G01と記されたところに入り口があり、そこから時計回りに進んだところに出口がある | 航空写真で見た、見学コースの辺り(赤い四角の中) | 模式図だと、リニアックからリングへ接続する辺り(赤い楕円の中) |
トンネルへの入口のある施設から出口のある施設まで、リングのすぐ横を歩くようになっており、自分が電子になったような気分になれる(ような気がしないでもない)。この辺りは電子リングが外側で、陽電子リングが内側だ(場所によって内と外と入れ替わる)。ちなみに、見学コースは電子と同じ時計回り。
なお、機器点検などのために周長3kmのリング内を徒歩で移動するのはやはり大変なようで、自転車が置いてあったりする。物性の謎を突き詰めている世界最高の技術でできた加速器のリングのすぐ横に置かれているママチャリという図は、なんか面白い。後で乗るときに人体に害はないのか心配になったが、よく考えたら、そもそも自転車が危ないのならトンネル内も十分危ないわけで、こんなところを見学できるわけがない(笑)。放射性廃棄物が残留しているわけではないが、いうまでもなく運転中にリングに近づくのは身体に非常によくない。
 | 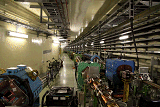 |
| Bファクトリートンネル入り口の建物 | 地下トンネルの様子。自転車が置いてある |
リング上には世界一を達成するため、研究者と技術者の血と汗と涙の結晶ともいえる、さまざまな機器が設置されている。基礎設計などはKEKで行なわれているようだが、各種機器の製造自体は地元企業といえる日立製作所のほか、三菱重工などが担当しているようだ。気がついたところでは、この2社の社名プレートがあちこちで見られた。
リングを構成する素材はリニアックでも触れたが、熱伝導性がよく、機械的にも強い無酸素銅で、パイプの直径は約100mm、厚さ6mmとなっている。そしてリング内を高真空状態にするために活躍しているのが、気体分子を金属表面に科学的に吸着させてしまう「非発熱ゲッター(NEG)ポンプ」だ。それで取りきれないアルゴンなどの不活性ガスを排気するのが、「スパッターイオンポンプ」。前者は1つのリングに約3,000個、後者は300個が設置されている。そのほか、ターボ分子ポンプとスクロールポンプからなる「粗排気システム」も見かけた。
ちなみに、リング内がどれぐらい真空状態かというと、1ピコ(1兆分の1)気圧。大気圧中を電子が通ろうとしたら、100万分の1秒以下で酸素や窒素などの原子と衝突して失われてしまうのだが、1ピコ気圧だと、10時間以上リングを周回できるというわけだ。なお、リング内面は凹凸が極力なくなるように化学的に洗浄されている。
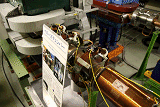 | 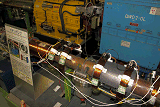 | 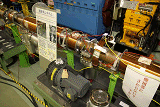 |
| パネルの裏に見える、リングの真下に突き出しているのがNEGポンプ | 見えづらいが、パネルの陰にある青い箱状の装置がイオンポンプ | グレーの装置が、粗排気システムのスクロールポンプ |
そして、多量の電子や陽電子を、1つのバンチとして散乱しないようにしたり、リングのアークに沿ってカーブさせたりしているのが、各種電磁石だ。先ほど紹介したスキュー六極電磁石のほかにも、偏向電磁石(300台)、四極電磁石(約900台)、六極電磁石(約200台)、小型補正電磁石(多数)などがある。偏向電磁石は光学系でいえばプリズムに相当し、電子や陽電子を一定の角度に曲げて閉じた軌道を作るのが役目(通常、素粒子が移動する時は直進する)。四極電磁石は光学系の凹凸レンズの役割に相当し、周回中の電子や陽電子をリング(パイプ)の中心軌道から遠く離れないよう収束力を与えている。六極電磁石は光学系の色収差補償レンズに当たる装置だ。電子や陽電子は有限のエネルギー幅を持つため、四極電磁石から受ける収束力が異なってしまうので、それを補償する役割を担っている。小型補正電磁石は、さらに補正を行なう。前述のスキュー六極電磁石は、六極電磁石よりも装置としては小型だがほぼ同じ構造のもので、異なるのは30度ほど回転させられてリングに設置されている点。これによって、加速器の誤差によってどうしても発生してしまう電子や陽電子の運動の水平垂直結合を補正する仕組みで、しかもそれをエネルギーがずれた粒子にまで適用してしまうという効果がある。
 | 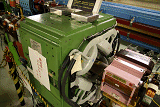 | 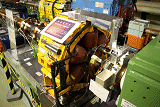 |
| 偏向電磁石 | 四極電磁石 | 六極電磁石 |
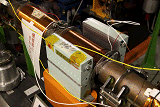 | 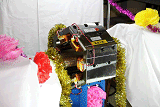 |  |
| 小型の補正二極電磁石 | スキュー六極電磁石 | スキュー六極電磁石は、新記録樹立の立役者として、代表して1台がお祝いされていた |
そのほか、この見学ルートでは、リニアックから来た陽電子のリングへの合流部分(鉄道のレールのポイントのような所)とその周辺に設置された各種装置、電磁波エネルギーを電子と陽電子の運動エネルギーに変換する高周波加速空洞の「ARES(アレス)空洞」なども見学することができた。
 | 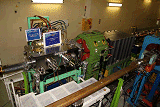 |  |
| リニアックから来た陽電子のパイプがリングへと合流してくる部分 | 入射点。ここでリニアックからのパイプとリングが実際に合流する | 合流地点の前後にはほかのカ所にはない機器が並ぶ |
 |  | |
| 電子と陽電子を加速させるための装置のARES空洞 | 展示施設のARES空洞 |
●バンチに傾きを与える世界初の設備「超伝導クラブ空洞」
続いて、リングの円周に沿って時計回りに進み、北西の日光エリアへ。ここでは再び地下トンネルに潜って、リングの施設を見られるのだが、ここにあるのが世界で初めて開発された「超伝導クラブ空洞」。何をする装置かというと、電子と陽電子のバンチを斜めに傾け、同じ角度で交差する瞬間に正面衝突できるようにしている。ルミノシティを上げるのに貢献している重要な装置の1つというわけだ。
 |  |  |
| 超伝導クラブ空洞のある施設の位置 | その位置を航空写真で見たところ | 超伝導クラブ空洞への入口のある施設 |
Bファクトリーは有限交差角衝突方式を採用しており、電子と陽電子のバンチは、従来は平面交差角1.3度でぶつかる形だった。イメージとしては衝突付近のリングのレイアウトはかなり横につぶれた「×」の字状態になっている。これだけでも接触率が高くなるのだが、ライバルのPEP-IIなどが採用している正面衝突方式に比べれば劣ってしまう。ただし、正面衝突方式にはない、衝突点付近の設計を簡単にできることと、寄生衝突(すれ違い衝突)の影響を小さくできるという大きなメリットがあり、Bファクトリーでは有限交差角衝突方式が採用されたというわけだ。ただし、正面衝突に比べれば接触面積が少ないのも事実。そこで考え出されたのが、電子と陽電子のバンチを同じ角度に傾けた状態で衝突させる「クラブ交差」だったのである。物騒なたとえで悪いが、同じ角度でドリフトした状態のクルマが、側面から衝突事故を起こすようなイメージといえばいいだろうか。何はともあれ、有限交差角衝突方式と正面衝突方式のいいとこ取りをしてルミノシティのアップを実現したというわけで、そのバンチをドリフト状態に持ち込むのが、超伝導クラブ空洞というわけである。
仕組みとしては、バンチの先端部分と後端部分をそれぞれ水平方向に電磁場で逆向きの力を加えて行なう(業界用語的にはキックするという)。バンチがカニの横歩きをしているようなイメージから取って、装置名にクラブ(Crab)と入っているわけである。超伝導が好きな人が集まっているクラブ(Club)ではないので、あしからず。記者的には、どう見てもバンチがドリフトしているようにしか見えないので、超伝導ドリフト空洞と名付けたいところ。しかし、Belle測定器内の荷電粒子の飛んだ軌跡を捕捉するための装置として「中央ドリフトチェンバー」があるため、差別化を図るべくこのような名称になったのだろう。キャラクターとしてカニを使っているので、柔らかい雰囲気が出せるというメリットもあるようだ。
超伝導クラブ空洞はニオブ製で、非軸対称形状をしている。その名の通り、液体ヘリウムで絶対零度より少々高い程度の極低温まで冷却し、超伝導状態において共振周波数509MHzで運転中だ。空洞内の内面は、バンチを傾けるための強力なキック電圧を達成するため、電解研磨で鏡面状になるまで研磨を行ない、超純水で高圧洗浄して微細な異物などを除去し、クリーンルームを設置して組み立てられたそうである。
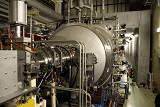 | 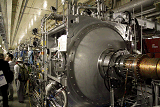 |
| 超伝導クラブ空洞の装置全体 | 装置全体を反対側から |
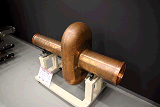 |  |
| 超伝導クラブ空洞の本体 | バンチが傾いて衝突するクラブ交差のイメージ図 |
●Bファクトリーのキモ、Belle測定器を要する「筑波実験棟」
次は、超伝導クラブ空洞施設からリングを1/4周ほど時計回りに進んだ先の筑波エリアにある「筑波実験棟」。ここが斜めに傾いた電子と陽電子のバンチ同士が衝突する現場であり、その衝突点を囲む巨大な検出システムBelle測定器がある施設でもある。このBelle測定器を使った「Belle実験」は、世界中の60の大学と研究機関に属する約400名の研究者によって構成されている、国際共同実験だ。
 |  |  |
| 案内図での筑波実験棟の位置 | 航空写真での筑波実験棟の位置 | Bファクトリー模式図での筑波実験棟の位置 |
 | 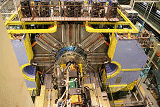 |  |
| 筑波実験棟の外観 | Belle測定器 | Belle測定器の各種検出器の位置 |
陽子と陽電子が衝突すると対消滅が起きるのは、ご存じの通り。SFドラマ「スタートレック」の宇宙船は、この物質・反物質による対消滅を、光速を突破するためのエネルギー源としているわけだ(ダイリチウムとか、架空の物質が関わっていたりはするけど)。対消滅が起こると、全質量が純粋なエネルギーに変換され、まさにアインシュタインの有名な方程式「E=mc2乗」が成り立つようになる。そして、そのエネルギーの中からさまざまな粒子が生まれ、その中にB中間子と反B中間子も含まれているというわけだ。必ずしもB中間子と反B中間子だけが生成されるわけではなく、中には小林・益川理論の先へ進む足がかりとなる可能性のある、これまでにない素粒子も発見されている。
例えば、4つのクォークからなる複合素粒子「Z(4430)+」(最後の「+」は本来乗数と同じように肩につく)などだ。陽子や中性子がクォーク3個からできあがっていることを考えると、クォーク4個の素粒子は、かなり目新しい素粒子なのではないだろうか。
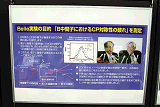 |  |
| CP対称性の破れを扱った小林・益川理論をBelle実験で証明 | Belle実験では、小林・益川理論の先へ進む足がかりとなりそうな、新しい素粒子も見つかっている |
そうした素粒子の検出を行なっているのがBelle測定器だが、地下4~5階分の体育館のような巨大な吹き抜けの空間に設置されている。測定器自体は八角柱を横に寝かせた状態で、幅も奥行きも高さもおよそ8mというサイズだが、その周囲に付属している計算システムや作業用プラットフォームなどの構造物をすべて含めると、幅と奥行きが10m以上、高さはそれよりももう数mあるぐらいの感じとなる。修理や調整を行なえるよう、リングに対して真横方向にレール上を移動できる仕組みで、アップグレード計画が実施されることになれば、来年の一般公開では反対側に移動して作業が行なわれている様子が見られるかもしれない。
Belle測定器の中核をなすのはソレノイド型超電動磁石で、1.5テスラの強磁場を測定器中心付近の直径3.4m、長さ4mほどの空間に作り出す。ニオブ・チタン合金製の超伝導材からなる線材を巻いたコイルを使用しており、液体ヘリウム冷凍機で-268度まで冷やされている。線材の断面は3×33mmで、そこを流れる電流は大きく、4,160アンペア。この磁場が荷電粒子の運動を曲げることになり、その曲線的な軌跡から、B中間子と反B中間子をはじめとする生じた素粒子の運動量を測定できる仕組みになっているというわけだ。
前述したように、Belle測定器はそれぞれ検出対象の異なる7種類の検出器からなる。衝突点に最も近い位置に設置されており、B中間子の壊れた位置を0.08mmの精度で測定しているのが、「シリコンバーテックス(シリコン崩壊点)検出器」だ。シリコン基盤上に集積回路の製造技術を使って微細な検出素子や電極を配置してある、半導体検出器である。数段階に渡って素粒子が通過していくのをとらえられるので、その通過点をつないで飛んできた方向に延長することで、素粒子の発生点を求められるという仕組みだ。
そして、衝突点の電子や陽電子の通り道に近い角度で設置されているのが、一対の電磁熱量計の「超前後方カロリーメーター」である。仕組みとしては、荷電粒子が通過するとシンチレーション光より小さい角度に散乱された電子や陽電子を測定するのに用いる装置だ。実験中にリアルタイムにルミノシティを測定するという機能も有する。ちなみにシンチレーション光とは、荷電粒子が物質を通過した際に物質から発せられる非常に微弱な光のこと。荷電粒子が通過すると、物質中の電子を励起状態と呼ばれる少しエネルギーの高い状態にするのだが、10万分の1秒から10億分の1秒で元に戻り、その時に発せられるのがシンチレーション光というわけである。荷電粒子が通り抜ける物質として、BGO結晶と呼ばれる透明で密度の高い結晶を使用している。
衝突点を覆うようにして配置されているのが、クラブ空洞のところでも少し触れた中央ドリフトチェンバーだ。外半径88cm、内半径7.7cmの金蔵製の筒の内部に3万4,000本の細い電極線が張られていて、さらにヘリウムとエタンの混合ガスを充満させた構造となっている。荷電粒子が通り抜けると、ガスの分子がイオン化するので、それによって飛んだ軌跡がわかるという仕組みだ。電荷の正負と運動量もわかるし、電気信号の大きさ粒子の識別も行なえる機器である。
中央ドリフトチェンバーの外側にあるのが、「シリカエアロジェル(ゲル) チェレンコフカウンター」だ。高速の荷電粒子が透明な物質中を通過するときに発生するのが、チェレンコフ光だ。透明な物質として超純水を用いてチェレンコフ光をとらえ、ニュートリノの通過を観測しているのが、スーパーカミオカンデなのはご存じの方も多いことだろう。透明であれば水のように液体である必要はなく、シリカエアロジェルのような固体でも用いることができる。また、チェレンコフ光は、特定の速さ以上の速度を持った荷電粒子が透明な物体を通過した場合に発生するという特徴を持つ。それに加え、シリカエアロジェルは屈折率が非常に小さいことから、光速に近い速さの粒子の識別を行なえる。
シリカエアロジェル チェレンコフカウンターの外側に位置しているのが「飛行時間(TOF)カウンター」だ。粒子の速度を測定し、そこから粒子の識別を行なうための検出器だ。カウンターの両端に光電子倍増感が備えつけられており、超前後方カロリーメーター同様にシンチレーション光をとらえる仕組みとなっている。衝突点からカウンターに到達するまでの飛行時間をおおよそ100億分の1秒の精度で測定可能だ。荷電粒子が当たった際に傾向を出す物質のことをシンチレータというが、ここでは、ポリビニルトルエンという透明なプラスチックに、2種類の蛍光物質を微量に混ぜた物質を使用している。
飛行時間カウンターの外側に位置しているのが、光子や電子のエネルギーを測定するための「電磁カロリーメーター」だ。ヨウ化セシウムの結晶が発するシンチレーション光を利用し、光子や電子が物質中で起こす電磁シャワーという現象のエネルギーを光の量に変換している。そして、フォトダイオードでその光の量を測定しているという具合だ。
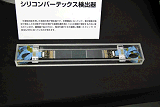 | 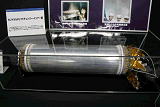 | 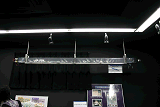 |
| シリコンバーテックス検出器 | 中央ドリフトチェンバーのインナー部 | 飛行時間カウンター |
最も衝突点から遠い位置にあるのが、7つ目の装置である「ミュー粒子およびK0L(0は本来右肩、Lは右下)中間子用高抵抗板検出器」。物質を通り抜けやすい性質を持っているミュー粒子と、電気的に中性で物質と反応するまでは検出できないK0L中間子の検出を目的としている。わずかな伝導性を持っているガラス板の間にアルゴンなどからなる混合ガスが封入された板状の大きな装置だ。超伝導ソレノイド電磁石の鉄製リターンヨークの隙間に配置されている。
またBelle測定器の横には、同程度のサイズの巨大な機器があり、データ収集のための各種高速エレクトロニクス機器が搭載されている。Belle測定器からのデータは、1秒間に最大600回の電子-陽電子衝突反応のデータが送られてくるのだが、それをデジタル信号に高速変換し、コンピュータに直接送り込んでいる。1つの事象のデータ量は約40KBで、多数の大型PCサーバーで構成されたコンピュータ群に送られ、信号はリアルタイム処理される。物理解析に必要なデータだけを取り出して、光ファイバー経由で計算科学センターにある高速磁気テープ装置に記録されるようになっている。
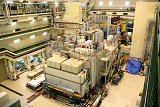 | 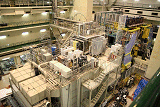 |
| Belle測定器の横の各種高速エレクトロニクス機器 | そのアップ |
そうして記録されたデータの解析も、計算科学センターのコンピュータ群が受け持つ。同センターのシステムは、3.5PB(ペタバイト、3.5PB=3500TB=350万GB)のテープライブラリ、1PBのRAIDディスク、約2,000台のPCで構成されている。1日24時間、常時データ処理が行なわれており、処理されたデータは専用や汎用の計算機ネットワークのラインを通じて、Belle実験に参加している国内外の大学や研究機関に送られ、さらに多くの共同研究者によってより詳しく研究がなされている。Bファクトリーも24時間稼働なら、情報を処理する計算科学センターも休むことなく交代制でフル稼働しているのである。
以上、高エネルギー加速器研究機構の主要施設を紹介してみたが、いかがだっただろうか。この世界の物理的な謎に迫るためには、これだけの技術力が必要であること、そしてこの分野でもこれだけの技術力を日本(海外の研究者の協力も得ているが)が擁していることが、少しはわかっていただけたのではないかと思う。実は、このほかにもまだまだ施設はあり、さすがに1日で回るのは不可能だった。もし可能なら、また次の一般公開で今度は違う施設を訪ねてみたいと思う(それでもまだ全部は回りきれない可能性が高い)。
一般公開の際は、つくばエクスプレスのつくば駅とKEKの間を無料のシャトルバスが何本も運行しているし、KEKへの入場そのものも無料なので、いい科学技術体験が可能だ。さすがに科学ミュージアムではないので、興味のない幼児や小中学生にトンネルの中を歩かせて科学体験というのは難しいかもしれないが、子供向けイベントも実は多数用意されている。今回は、「科学おもちゃであそぼう!」「紙飛行機を作って滞空時間に挑戦しよう!」「ラジオを作ってみよう」などが行なわれ、親子で遊びに来ている人たちも多数見かけた。
そのほか、今回はタイミングが合わなくて(主要施設を回るのでいっぱいいっぱいで、何kmも離れたところにいた)直接拝見することは叶わなかったのだが、小林誠氏の「CP対称性の破れとは」という講演もあり、サイエンス好き(特に物理系)にはたまらない内容になっている。将来は、こうした分野の最先端で働きたい! なんて高校生や大学生たちも、ぜひ見てみよう。LHCの全長27kmに比べればかわいいかもしれないが、日本にもこれだけの施設があるということに感動するはずだ。世界一を誇る日本の技術力を、ぜひチェックしてみてほしい。
2009/9/16 00:00