日本科学未来館、メディアラボをリニューアル
~クワクボリョウタ氏による子供も大人も楽しめるデバイスアート作品個展に
日本科学未来館では20日より、3階の常設展示「情報科学技術と社会」にある「メディアラボ」にて、第4期展示「クワクボリョウタ:微笑みトランジスタ」を公開した。期間は9月28日までの4カ月間。一般公開に先立ち、19日にプレス向け内覧会が実施されたので、その模様をお届けする。
●メディアアーティスト:クワクボリョウタ氏とは?
クワクボリョウタ氏は、現代美術とメディアアートを学んだ後、1998年から主にエレクトロニクスを用いたデバイスアート作品を発表しているアーティスト。それらの作品は遊ぶことができるのと同時に、アナログとデジタル、人間と機械、送り手と受け手といった、境界線上で起きるさまざまな事象に焦点を当てているのが特徴だ。2002年と2003年にはサイバーアートコンテストの世界最高峰であるアルス・エレクトロニカで入選し、2003年には国内でも文化庁メディア芸術祭アート部門で大賞を受賞している。今回は、1999年から2001年までの初期の作品と、今回に新たに制作された2作品が展示されている形だ。
 |  |
| 挨拶をするクワクボリョウタ氏。下は1歳3カ月の息子さん | メディアラボの入口付近 |
●微笑みトランジスタとは?
メディアラボは、未来館3階の常設展示の内、ヴァーチャル・リアリティやインターネットモデル、ライドカム、インタロボットなどを扱う体験型常設展示施設「情報科学技術と社会」の一角にある。昨年4月24日に、同展示施設の一部、150平方mほどのスペースを改修してオープン。汎用性の高い可動型メディアウォール(展示壁)により構成されており、多種多様な展示用途に対応できるフレキシブルな空間となっている。メディアラボは4つの特徴がある。1つ目が「研究室(ラボ)である」ということ。ここから、研究成果が生まれるのだ。2つ目は「ギャラリーである」ということ。技術と創造性が結びついたデバイスアート作品に出会える場だ。3つ目が「メディア」であるということ。来場者と研究者をつなぐ場なのである。そして4つ目が「表現の場である」ということ。来場者自身が表現者になれる場というわけだ。
そんな特徴を持ったメディアラボが、オープン時から扱っているのが、デバイスアートである。デバイスアートとは、日本発のテクノロジーと創造性を融合させたアート作品のことで、従来のアートの枠組みに挑戦する試みでもある。3つの特徴があり、1つ目が「部品や技術、ツールを隠さず、それらも含めてコンテンツとする」こと。2つ目が、「デバイス(装置)やガジェット(小物)の形で日常生活の中に入っていく」こと。そして3つ目が、「発想の背後に、日本的な感性とモノづくりの伝統がある」こととなっている。アートが生活の中に溶け込んでいたかつての日本文化が、先端技術と出会うことで生まれたのが、遊び心あふれるデバイスアートというわけなのだ。ちなみに、デバイスアートの第一人者は、1つ前の第3期展示「博士の異常な創作」の主役であった筑波大学大学院システム情報工学研究科教授の岩田洋夫氏といわれている。クワクボ氏は、岩田氏らとともに「デバイスアートにおける表現系科学技術の創成」プロジェクトメンバーに所属。デバイスアートを通して、前述したように内外で活躍しているというわけだ。
今回の個展に対し、クワクボ氏は、メディアラボの入口にメッセージを用意。それによれば、今日革新的だったものでも明日には時代遅れになってしまうような、現代の情報技術が我々の適応速度よりも速く世の中を変えつつある中で、人と人のコミュニケーションについて、心に引っかかる事柄をもとにエレクトロニクスを駆使してアート作品を作っている、とする。「電子部品は決して微笑まないけれども、人はそのふるまいに微笑みを見出すことができます。これら作品を体験する皆様にイマジネーションを喚起していただければと思います」と結んでおり、それがタイトルの「微笑みトランジスタ」につながるというわけだ。
内覧会にはもちろんクワクボ氏も来場しており、マイクを持って挨拶。小学校1、2年の時に「2SC372」というトランジスタを使って、本を見ながら赤いランプを点滅させるという回路を作り、完成して狂喜乱舞したという子供時代の電子回路初体験エピソード披露からスタート。それを何に応用したかというと、当時の実家の近所にあったクヌギ林で、カブト虫を捕まえるために蜜を塗った木に設置したのだそうだ。インジケータとかビーコンとして活用したつもりだったが、役に立ったのか立たなかったのかよくわからないという微笑ましいオチであった。その当時からデジタル的なものに特別な感情をいだいてきたということで、そのままずっと引きずっているのだそうだ。また、自身による作品の説明では、1999~2001年の初期の作品は、「デジタルって何だろう?」というコンセプトのもとに作ったものが多いという。逆に今回制作された最新作2点は、情報やデジタルということよりも、「人間てなんだろう?」というコンセプトであるとした。そういうものを電子的に作ってみて、実験してみた作品なのだそうだ。
微笑ましかったのが、この日は関係者の方も多く、奥さんとまだ1歳3カ月の息子さんも来場していたこと。この年頃の子は、どんないたずらをするかわからないから目も離せないけど、まさに目に入れても痛くないほど可愛い盛り。そんな息子さんを見て、すっかり何を話そうか忘れてしまったらしく(笑)、その後は招き寄せて抱っこしてのアットホームな挨拶となった。ちなみに息子さん、立っても歩けるようだけど、まだハイハイの方が好きというか得意なようで、未来館の床もペタペタと四つんばいでお父さんのところへ。ちなみに、息子さんを授かって、アーティストとして作品に対する見方や作り方が変わったという。それまでは、ルールがまずあって物が作られていくという風に考えており、それを脱構築するような作品を制作していたのだが、息子さんが生まれてみると真逆に。今では、まずカオスがあるという感覚なのだそうだ。新作2作品の内の「ニコダマ」は、息子さんを抱っこした時に目があって、それでコミュニケーションできたのかどうかはわからないが、その時の感覚がもとになって、作ったのだそうだ。「シリフリン」はとてもオススメなので、ぜひ体験してほしいと語っていた。
●最新作2点はシリフリンとニコダマ
 |
| シリフリン。ヒップバックからしっぽが生えている感じ |
【シリフリン】
クワクボ氏の個展は、実は今回が初めてだという。7作品が展示されており、どれもちびっ子から大人まで、実際に触って楽しめるのが特徴だ。しかし、そんな中で間違いなくちびっ子たちが長蛇の列を作りそうなのが、「シリフリン」。人類が進化する過程で切り捨てた部位の1つであるしっぽを、再び手に入れられるという作品だ。シリフリンはヒップバックからしっぽが生えているような形状で、しっぽは複数のサーボで構成された多関節構造となっている。しっぽを動かすのは、装着者の腰の動き。センサーが装着者の腰の動きをとらえ、それによってクネクネと動作するのである。うまく腰を動かすと、本当に生えているかのように自然な感じで動かせ、気分は「ドラゴンボール」の孫悟空、というわけである。なお、本当の正しい日本語での表記は、「シ'│フ'│ン」だそうで、リを濁点として読ませ、「ジブン」とする二重の意味合いもあるそうだ。ちなみにシリフリンは革製なのだが、その裁縫はクワクボ氏の奥様が行なったそうである。
シリフリンの使い方は、ヒップバックのように腰に装着して行なう。前述したようにセンサーが腰の動きを感じ取り、それで複数のサーボが動く。コツとしては、腰を鋭くキュッと動かすとその方向にしっぽが向くようである。展示スペースで流す映像を撮影するため、未来館のスタッフの方が前日に装着しっぱなしでがんばったそうだが、その甲斐あってだいぶコントロールのコツをつかんだという。そこで、今回はそのスタッフの方にモデルとして絶妙なるしっぽ&腰の動きを披露してもらった。イケメン男性スタッフによる、セクシーな腰の動きは女性読者も必見だ(笑)。見事なシリフリナー(シリフリンを上手に扱う人という意味の勝手な造語)ぶりをご堪能いただきたい。
なお、クワクボ氏に話を聞いたところでは、当初別の作品(2人で動かす二人羽織ロボット)を検討していたそうだが、それを中止。しかし、サーボを使っていろいろと研究していて面白かったことから、直線的につなげてみてどう動くかをチェックしてみたそうである。それが意外に面白かったらしく、結果としてシリフリンが生まれたというわけだ。サーボは近藤科学製を使っているという。オモチャメーカーが製品化すれば、結構売れるような気がするのだが、いかがなものだろうか。
ちなみに、記者も装着できたほどなので、エビス様のようにお腹の突き出た人でない限りは大概の人が装着可能なはず。なので、「オラ、悟空!」とばかりに、ぜひフリフリして楽しんでみてほしい。装着部分の形状が象の顔のようになっているので、一見するとしっぽではなく象の鼻のようにも見える。なので、前につけると孫悟空ではなく、「クレヨンしんちゃん」になってしまうので、注意が必要(笑)。また、土日祝日、夏休みは子供たちで非常に混む未来館だが、この作品は間違いなく人気が出るはず。つけて遊んでみたい! というお子さんをお持ちの方は、その子の学校の創立記念日とか、この後多いはずの春の運動会の振替休日とかをうまく利用して、遊びに行ってみるといいのではないだろうか。
 |  |  |
| このスイッチを押しっぱなしにすると、サーボが駆動してしっぽが動く | 未来館の男性スタッフの方。シリフリンの達人と化していた | 【動画】未来館のイケメン男性スタッフによるシリフリンの動作する様子 |
【ニコダマ】
目玉をモチーフにしたデバイスで、前述したように最新作の1つ。2個でワンセットのデバイスで、壁でも物でもどこでも何でもいいから2つ並べて貼り付けると、しばらくして瞬きを始め、顔に見えてくるという作品だ。瞬きが同期している仕組みは、ニコダマ同士が相互に通信しており、通信が確立されたあとに揃って瞬きをするようになる。瞬きのタイミング自体はランダムなだけに、なおさら生き物っぽい。メディアウォールにノートPCやチリトリなど、さまざまな物がかけられており、そこにペタッと貼り付けられるようになっている。ちなみに、クワクボ氏は子供時代、お母さんが作ってくれた「顔弁」がどうしても食べられなかったのだそうだ。実際、瞬きをするのを見ていると確実に顔に見え、顔に見ればなんか意思疎通できそうな気がしてしまう。とても面白い作品である。
 |  | 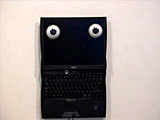 |
| ニコダマ。近くの2個同士が通信を確立させ、瞬きを同期させて行なう | 【動画】弁当箱と水筒のセット。それでもニコダマが瞬きを始めると、顔に見えてくる | 【動画】こちらはノートPCの液晶画面に貼ったところ。完全に顔っぽい |
●初期の作品5作品は1999年から2001年のもの
・PLX
2001年の初期の作品で、対面した2人が別々のゲームを遊んでいるように見えて、実は対戦ゲームとして戦っているという内容。食い違っているのにはずんでいる会話、前提が違ってかみ合わない議論など、すれ違いやズレによるどうにもならないコミュニケーションの壁をモデルにした対戦ゲームである。一度片側で遊んだ後に交代してみるのも面白い。
・デューパールーパー
2001年の作品。ばちでテーブルを叩くと、そのリズムを真似て叩き返す装置だ。人のマネをしている感じで、まるで機械に心や感情といったものがあるような気がしてしまう。でも、叩いたリズムを楽譜で表示すると、真似をしているようには見えないそうで、人が楽しいと感じても、情報化されると、見えなくなったり、つまらなくなってしまったりするのである。
・ヘブンシード
2000年の作品。放ったり転がしたりすると、マンガやアニメのような、不思議な音がするボールだ。どんな音が出るか、放り方や転がし方を工夫してみるといい。PLXもそうだが、これも2人で放り合ったりするといい。意外と2人用が多いのがクワクボ氏の作品の特徴である。
 | 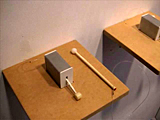 |  |
| PLX。どんなゲームかはぜひご自分の目で | 【動画】デューパールーパーがマネをして叩く様子 | 【動画】ヘブンシード。放ったり転がしたりでいろいろな音がするので楽しめる |
・ヴォモーダ
2000年の作品。テレビ電話型の作品で、これも2人向け。相手が話すと、自分の電話のモニタの顔が動き、ニコニコする。怒っていても泣いていても表情は、そのズレが面白い。
・ビットハイク
1999年の作品。8×8ドットの絵を8パターンでアニメーションさせているというもので、512ビットの情報で作られている。少ない音数で無限の情感を表現する俳句と、最小の電子単位のビットをかけ合わせたネーミングだ。単純な要素のアニメの中にも動きや意味を見出すことができ、人の何かを感じられる能力と、情報量にはどのような関係があるのかと考えたくなる作品である。
 |  |
| 【動画】もう1台のヴォモーダの受話器に向かって話しかけるとこのように表情が変化 | 【動画】ビットハイクの波のアニメーション。アニメーションは複数のパターンがある |
以上、クワクボ氏の個展であるメディアラボ第4期展示「微笑みトランジスタ」を紹介させていただいた。未来館の広報の方に話を伺うと、これまでで最もアート寄りということなので、サイバーアート系に興味がある方もぜひ足を運んでいただきたい。また、お子さんに(自分も)変わった機器で遊ばせてあげたいと考えている保護者の方にも、ぜひともオススメである。まだしばらく先だが、夏休みも挟んでいるので、ぜひ体験させてみてはいかがだろうか。アートでありながら誰もが遊べる、思わずニッコリしてしまいそうな「クワクボリョウタ:微笑みトランジスタ」を楽しんでいただきたい。
2009/5/21 16:41