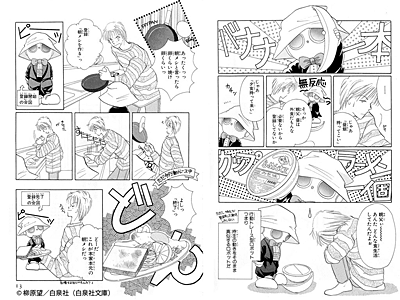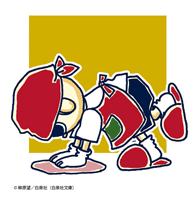|
記事検索 |
バックナンバー |
【 2009/04/17 】 |
||
| ||
【 2009/04/15 】 |
||
| ||
【 2009/04/09 】 |
||
| ||
【 2009/04/06 】 |
||
| ||
【 2009/04/03 】 |
||
| ||
【 2009/03/27 】 |
||
| ||
【 2009/03/24 】 |
||
| ||
【 2009/03/18 】 |
||
| ||
【 2009/03/11 】 |
||
| ||
【 2009/03/06 】 |
||
| ||
【 2009/03/04 】 |
||
| ||
【 2009/02/27 】 |
||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
「しお少々」が伝わるロボットが欲しい |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Reported by
森山和道
|
|||||||||||||||||||||||||||||
「まるいち」とは、架空の大手家電メーカー「KAMATA」が開発・販売する家庭用汎用ヒューマノイドロボットである。大きさは3歳児くらい。頭部には大きな丸いカメラアイと耳、鼻にあたる突起がついている。口はなく、表情はない。言葉も発しない。できることは作中で「行動トレース方式」と呼ばれているユーザーの物まねだ。これで家事をさせる。ただし「まるいち」は登録された動きしかしない。
基本的な運動機能はマンガらしく全て備えたものとして設定されているが、「まるいち」には人工知能や感情はない。「アトム」に代表される他の多くのロボットマンガのように考えたり悩んだりすることはない。「まるいち」そのものは徹底的に機械、モノとして描かれている。主役はあくまで人間だ。作中では、新しい機械、新しい道具としてのロボットが人間社会に投入されたときにどんなことが起こるのか、主として開発チームのメンバーたちの目から描いている。 こういう言い方だとかたい話のように思われるかもしれないが、実際のストーリーは、ほのぼのヒューマンドラマだ。主人公は、KAMATAのまるいち製作室の研究員でこよなく自分が開発した「まるいち」を愛する美月ななこと、折り合いの悪かった父の死がきっかけで「まるいち」と関わることになった童顔の大学生・有里幸太。この2人を中心に、主に「まるいち製作室」の面々が物語を展開する。
繰り返しになるが『まるいち的風景』が執筆されたのは1995年~2001年。ホンダがヒューマノイド「P2」を発表したのが1996年末、ソニーがAIBOを発売したのが1999年である。1995年当時は、まだサービスロボット、パートナーロボットなど、影も形もなかった。にもかかわらず、『まるいち的風景』では、ロボットが家庭内に入ったときにどのようなことが問題になりえるのか、ロボットを社会に溶け込ませるためには何が必要なのか、用途としてどんな可能性があるのか、そして人間がやるべきことと機械がやるべきことの切り分け方のありかたなど、最近になってようやく研究者たちが問題としはじめたことが、かなり深いレベルまで考えられて、身の丈で起こる身近な物語のかたちで描かれている。 「知る人ぞ知る」と述べたのはそのためで、いま読んでもまったく古びていない、いや、今でこそより深く理解できる示唆に富んだ内容は、実際に少なからぬ数の研究者たちが認めている。筆者がこのマンガの存在を知ったのは実際にロボット開発を行なっている、ある研究者からだった。インタビュー取材のなかで書名が研究者側から挙がったこともある。このマンガで描かれていた人間とロボットとの関わり方は、そのくらい示唆的だったのだ。 今も家庭用ロボットは実現していない。『まるいち的風景』はいわば、将来、家庭にロボットが普及したときのシミュレーション、疑似体験としても読むことができるのだ。 人とモノの界面(インターフェイス)、道具を介した人と人との関係についての優れた物語である『まるいち的風景』。作者の柳原望さんに『まるいち的風景』が誕生した経緯や、執筆中に考えていたことを聞いた。
「そのころの『ロボットもの』って、ロボットが気持ちを持って人間そっくりになって生活するというものが多かったんです。それがすごくしんどいなって。自分自身の気持ちでさえ、持てあましているじゃないですか。なのにロボットにまで気持ちを与えたら始末におえないなと思って。 たとえばドラえもんはかわいいじゃないですか。自分のことを心配してくれるし、ちょっと傷ついたりもする。隣にドラえもんがいたら、私はきっと『ジャイアンとはもうつきあわなくていいや』と思っちゃう(笑)。私はなまけものなので、楽なほうへ楽なほうへと流れちゃうと思うんです。でも本来の人間関係は、痛かったりすることもあるけれど、それを乗り越えていくものですよね」 たとえば人間よりも人間らしい心を持ったロボットがそばにいたら、人間よりもロボットのほうを大事にしてしまうかもしれない。それはどうなのか。だがロボットはやがて必ず生活のなかに入ってくるし、実際に便利になるのは嬉しい。では、どんなロボットだったら「なまけものの自分」でも一緒に暮らせるかな……。そう考えたのだという。 「じゃあ、『まるいち』は気持ちはいらないや、そこはきっぱり分けちゃえと。それと、自動販売機に『ありがとう』といわれても、私は嬉しくないんです。機械に何かを言われても嬉しくないんですよね。基本的になまけもので低きに流れちゃうので、機械に「ありがとうございました」といわれることに馴れちゃうと、たとえば駄菓子屋さんや八百屋さんに『ありがとう』と言われても、無視してしまうかもしれない。『ありがとう』という言葉が軽くなって、すぐに反応できなくて、自分がどんどん嫌な人になるなと。それで、これも分けちゃえ、まるいちは喋らなくていいと考えました」 表情も同じだ。表情のアイコンをつけたロボットも、少なからず見かける。「まるいち」には表情がない。口もない。 「表情というのは微妙で、ふだん自分に寄り沿ってくれているものって……。たとえばテディベアは無表情だけど、かわいいじゃないですか。自分が悲しいときに悲しく見えるのは人間の想像力ですよね。そこにうまくフィットするから、テディベアはかわいいわけです。勝手にプログラミングで笑ってくれたら、むしろむかつくんじゃないでしょうか。人間にはせっかく想像力があるのに、それはいらないんじゃないか。無表情でいいだろうと思ったんです」 「あれは私はプログラミングはできないから、真似てねと(笑)。それと、お掃除ってこういうものだよね、というふうに企業から押し付けられるよりは、自分の方法でやってもらいたかったんです。賢い人はプログラミングすると思うんですけど、私は無理だから真似てねと」 普段われわれは実物のロボットを取材しているのだが、そのなかでも、表情や音声発話に関しては疑問を抱くことが少なくない。現在の技術でロボットの状態表現として音声や表情を用いると、逆にロボットが浅く見えることが多いのだ。今も柳原さんの指摘に耳が痛い開発者はいると思う。 実物を見たあとなら想像できることも多いと思うのだが、1995年の時点でここまでリアルに家庭用ロボットの問題、ひいては新しいモノが社会に投じられたときのことを考えることができたのはどうしてなのだろうか。 「私は不安のかたまりなんですよ」と柳原さんは語る。「まるいちを考えたときに、ロボットがあんまりいたれりつくせりになると、自分の中で言葉が軽くなっちゃうなとか、そういったことがすごく嫌だったんです。固まってきたのは描き始めてからですけど、描こうと思ったのは、心って要るのかな、表情って要るのかなという不安からですね」。まるいちはもともと「漠然とした不安」から生まれたのだ。 ● 「ロボット」をかわいいと思えるのは自分を投影しているから 人格や知性を持たない家電製品ロボットである「まるいち」という存在を思いついた経緯については、愛用の古い自転車を捨てろと言われたときに思い出が蘇ってきて捨てられず泣いてしまったことからだ、というエピソードが、単行本1巻のあとがきで書かれている(文庫版には未収録)。「わたし、なんでこの自転車のことを泣けるんだろう。ロボットに気持ちがあるからロボットが好きなわけではないよね、と思ったんです。モノを擬人化するのは人間の特徴なんですけど、モノに対して人格を求めるというのは、ちょっと違うんじゃないかなあと思って。モノのなかに、人格なり『一個の人間』というものを求めちゃうなら怖いなと。漫画のロボットはそういうのが多すぎて。そういうロボットとはお友達になれないなーと。テディベアと同じなんですが、自分のことを投影しているから、ロボットやモノって『かわいい』と思うんですよね。そのへんのわーっとした感情を描きたいなと思ったんです」 多くのマンガのなかでは「ロボット」というキャラクターは一種の擬似人間的存在として扱われている。人間に似てはいるが人間ではない存在、時として不死であったり、人間以上だったりする存在が人間と1:1の関係を作ろうとする話が少なくない。いっぽう、「まるいち」は機械だ。新しい機械である「まるいち」が人間社会のなかに登場することで、登場人物たちが自分でも気がついてなかったことや無意識のうちに自分が考えていたことを明示的に意識化されるというのが普遍的なプロットだ。 「私はコミュニケーションがすごく苦手で……。機械が便利になればなるほど、自分が甘やかされたりするじゃないですか。例えば直接電話しなくてもメールでよくなったりしますね。ただでさえできない自分が、もっとできなくなるんじゃないかと。そういうことが漠然とずっと怖かったんです。怖いと思ったこと、ないですか? 1つ便利になると、1つ不便になると思うんですよ」 どういうことだろうか。 「なくなっていく部分がすごく怖いんです。便利になることは派手だし楽しいから意識される。だけど、なくなっていくものって知らない間にすーっとなくなっちゃっていく。それが不思議で怖かったんです。書き下ろしした最終話でも似たようなことを言ってるんですけど、なくさずに上手につきあっていこうと思ったら、いままで自然にやってたことを意識化して『こういう価値があったよね』と価値付けしてフォローしないと、どこかで壊れていっちゃうと思うんです」 たとえば単純なことだがテレビがリモコンになってから「忍耐力」が減ったと冗談交じりに語る。 「ちょっと立ってテレビのところに行ってチャンネルを変えてくる、そんな小さな操作の毎日の繰り返しがピッととやるだけですむ。だから毎日の訓練がなくなっちゃうんだよねと友達と話しているんです。テレビだけではなく、日常のちょっとした小さなルーチンワークにイラッとするんですよ。たとえば洗濯物たたむのめんどくさいなとか、どうしてラジオにはリモコンがないの、とか」 リモコンで便利になることと引き換えに、ちょっとしたことでイラッとすることを考え合わせると、QOL(Quality of Life)はゼロサム、むしろ減っているかもしれない、と笑う。 だが、便利になったものはすごく意識的に獲得しているが、なくなっていくものは自然になくなっていく。 「だから、『ちょっと待って待って』と。機械が便利になったぶん、生活の質を上げようと思ったら、流れ去っていくものを意識的にして、どこかでグッと留めておかないと、けっきょくいっしょかもと。『まるいち』の中では、そういうことばっかり言ってる気がするんですけど(笑)」 「まるいち」のような物語を描くことができた理由は、「ずっと、ヘタレで怖がりだったから」だという。 「人間関係を雑にしちゃうとか、不親切にしちゃうなとか、そういうことを社会や道具のせいにして、こういうシステムだったらいいよねと持っていくあたりは、漫画を描く人間の現実逃避的なところがあるんじゃないでしょうか(笑)。こういうシステムがあったら、わたしはいやな人間にならないよねとか、まるいち君みたいなシステムがあったら、社会のシステムが節度をもってくれたら、もうちょっと鍛えられるのにねと。 とりあえず、自堕落になるのが怖いと同時に『なくしていくものがもったいない』と思うんです。それはちゃんと意識してたい。インフォームドコンセントみたいな感じで『この機械が出たら、ここは便利ですけど、ここは駄目になる』とメーカーの人が教えてくれたらいいんですけれど。でも、それこそ自堕落ですよね(笑)。自分で考えろ、体験して考えろということですね」 だから繰り返し頭のなかで想像し、シミュレーションした。ストーリーも、モノや社会に対して自分が「ヘタレ」なところを中心に描いていったという。 「だから逆にキャラがちょっと薄かったかなあと。そこが反省点です。反省漫画です。これはだめだめかなあとか、ここは欠落していった部分だとか、ここは補ったほうがいいよなあとか。そういうふうに考えるとネガティブな漫画ですね(笑)」 ちなみにキャラクターは、それぞれ柳原さんの一部を反映しているのだという。自分の中に全くないものは絶対に描けないそうだ。では「まるいち」も一部ということになる。 「まるいち君は、機械に対する要望のかたまりです。そばに置くなら、かわいいもので、3歳児くらいの大きさで、膝にのっけられるくらいの軽さで、手触りもきっとそんなに悪くないんだろうなと思う」 たとえばステンレスは冷たいが、檜はあたたかい素材だという感覚がある。表面素材はそんなイメージだという。また、少女マンガのなかのキャラクターなので、着せ替えができることも重要だったという。「お仕着せではなく、自分の好きな服を着せたいよねと思うじゃないですか。女の子が欲しくなるものを目指すなら、着せ替えはとても重要だと思います」。だから「まるいち」は、3歳児程度の既製品が着せられるという設定になっている。靴だけは足が大きいので成人用のものを履いているのだそうだ。ちなみに、まるいちの価格は「ファミリーカー1台分くらい」と設定されている。頑張れば買えるかな、というくらいの価格帯にしたかったのだそうだ。 ● 『こしょう少々』がわかるやさしいロボットとは?
「人間に近づけて表情をつくるのはやっぱり怖いなと思いました(笑)。でもやっぱり、出てきてみないとわからない。あれだけ怖い怖いと思っていたのに、出てきてみたら楽しいな、かわいいな、乗ってみたいな、使ってみたいなと思いました。日本のロボットはエンターテイメントとか明るいほうを志向している感じ。いきなり実務に入ると怖いものがありますけど、そこからちょっとずつちょっとずつ、馴れていこうとしているところがすごく好きです」 特に興味があるのは介護ロボットだという。 「でも介護とロボットはやっぱり怖いなというところがありまして。ベストセラーになった『おひとりさまの老後』(上野千鶴子/法研)。あの本に、介護するほうのノウハウはたまっているけど介護されるほうのお作法がまだ全然できてないじゃないかという話があります。ロボットは人間から意思を伝えないといけないのに、介護されるほう、意思を伝えるほうのノウハウがたまってない。それは、怖い状態になるなと。そこはどきどきしているんです」 なお介護ロボットのネタは、文庫本2巻に書き下ろされた最終話「Living life with a MARUICHI」に少しだけ使われている。機械に対してどう指令するかという問題はまさにインターフェイスの問題そのものだが、『まるいち的風景』では架空の「行動トレース方式」という技術が使われている。描いているうちにだんだん、いいなと思うようになったそうだ。
わたし、落ち込んだらガラス拭きをするんです。きれいになると透明になるし、目に見えて自分が役に立つことがわかるじゃないですか。でも、本格的なお掃除ロボットが家庭に入ったら、ガラス拭きって、たぶん一番最初にロボットがやることですよね。そうすると落ち込んだときに散財するとか、お酒のむとか、なにかとんでもない方向に行って、しかも気持ちも解消できないとか、そういう状態になるんじゃないかと。あんたはガラス拭きをすると凹んでも復活するんだよ、すごくシンプルなところに正解があるんだよということが、やったことがないとわからない。 でも、忙しいときには掃除は誰かにやってほしいですよね。だから一度は自分でやるということがすごく重要だなと、思うんです。自分が好きなやり方とか、コツとか、ふだん見てないことも見えてくるし。ロボットにまかせるにしても一度は自分でやろうよ、と。そういうことを自分のなかに組み込むという意味で、行動トレース方式はお気に入りになってきました」 でも実際にこのような仕組みができたら、たぶん「まるいち君行動インプット代行業」ができるだろう。でも、それでもいいかなという。なぜかというと、大事なことは、一度は人間の目や体を通していることだから、という。 「問題は、大きな企業が、お掃除はこういうもんだ、たとえば椅子は窓側におけとか、お仕着せになるのが嫌なんです。でも、誰か人間の体を通した情報ならば、それほど歪まないと思う。全部人間から離れてしまうのは、すごく怖い。『あんたはこれでいいでしょ、機械にあわせてね』といわれるのがすごくいやなんです。それでいいやと思ってしまう自分も怖い。自分の中から判断材料を奪わないで、って」 柳原さんは、持っていて嬉しいもの、心地いいモノとは「作った人の思想や哲学」が感じられる「普遍的なモノ」で、「ずっとそこにあるよという安心感」を与えてくれる存在だという。実際に欲しいロボットは、当然ながら「まるいち君みたいなロボット」だ。 「寄り添ってくれて、しゃべらなくて。すごく器用で、いざというときには力も出せる。普段は、できるけどしない。引き算です。工学系の人に『引き算』というと嫌がるだろうけど、引き算のロボットというのもいいなあと思うんです。でも、今のロボット工学では難しいですよね。コップ1つとっても認識して持つのは難しいですし。棚の上の調味料の順番が変わっていても、『こしょう取って』と言ったらとってくれて、『こしょう少々』の感覚をわかってくれるロボットだといいんですけど。それと、いろいろな方言でも理解してくれて、お年寄りも使えるロボット。人間にはとことんやさしいけど、ちょっと不便なロボットが欲しい。ただ、やさしくしてほしいなと思います」 「やさしい」とはどういうことだろうか。方言を理解してくれたり、「塩少々」を理解してくれること。どんなコップであってもコップはコップだと認識してくれることが、柳原さんの考える「人にやさしい」ということだという。「やさしさ」を明示的に表現するのは難しい。だが、ストーリー、物語の形式で表現されると、たぶんこういうことなんだろうなということは分かる。 『まるいち的風景』の物語中では、「まるいち」という新しい機械が登場することで人間関係に変化が起きる。いやむしろ、命令に従う大量生産の道具でありながら、単なる道具を超えた意味を使用者が見出すことができる機械として「まるいち」は描かれている。人は将来、ロボットに人間関係の変化の触媒のような役割を望むのだろうか。それともお茶を出したり下げたりしてくれる単なる道具のほうがいいと考えるだろうか。柳原さんはこう語る。 「外国では昔からロボットは使役物ですよね。でも日本では無生物にものすごく愛情をかける。置物にしても、記憶が重なれば重なるほど擬人化するし大事にする。ロボットみたいに動くものだったら、単にお茶を下げるだけの道具であっても必ず感情は込めると思います。ロボットの感情ではなく、こちらからの感情のことです。それによって人間関係が変わるというより、ロボットがいる状態を基本として、それをコミュニケーションツールにした人間関係はできてくると思います。変わる変わらないじゃなくて。そういうふうになるだろうなと思います」 ● 哲学のあるロボットを
「無個性というよりは『こうであるべきだ』というお仕着せはいらない。でも哲学は欲しいです。それに賛同したら買います。あとはこっちの自由にさせて欲しい。全部メーカーが作りあげてしまうのではなくて、ユーザーの人がアレンジできる余地があるもの。いわば政府の政策みたいなものですね。哲学はガンとあって、あとは現場現場でうまくやってねと。それがうまい政策でしょう。でないとファシズムになっちゃう。そういうのはだめだなあと思います」 プロダクトデザインは、それ自体が選択、制限のなかの選択だ。そして、どんなものを選択していくかはメーカーや研究者だけではなく、我々消費者側にもゆだねられている。 「ロボット技術は、すぐ近くまで来ているけど、まだ遠い。完全な人型ロボットで、という時代はまだまだ遠いと思います。ですけれど、ユビキタス技術なんかは、ものすごく近いなと思います。いつでもどこでもは便利だけど、いつでもどこでも色々なことができるようになると、自分の能力がこそぎとられる。ミヒャエル・エンデの『モモ』(岩波書店)に出てくる時間泥棒みたいな灰色の人たちが出てきて自分の能力を削ぎ落としていくようなイメージがあります。不便な感覚を感じてないと、当たり前になって馴れちゃうのが怖いんですよ。馴れちゃうと文句を言えないじゃないですか。そうするとネタもなくなるし(笑)」
「新しく暮らしの中に入ってくるモノに対して『怖い』という感覚を持っている人は大勢いると思うんです。『怖いよね、そうだよね、どこでストッパーをかけてる?』とか、そういう話ができると嬉しいですね。怖いところがはっきりわかれば、新しい技術が入ってきたときにも『ここは受け入れるけど、ここはストッパーをかけておく』というところがはっきり分けられて、逆に受け入れられると思うんです。価値観を鉋で削ぎおとされるような、知らない間にかすめとられている感覚がすごく怖いんです。自分の能力や肉体感覚が、削ぎ落とされるようになくなっていく感じ。ないですか?」 インタビュー中、なんども「怖い」という言葉を柳原さんは使った。「怖がりなんです」と笑う。だが、普段はMacを使いこなし、マンガ執筆もデザイン作業も行なっている柳原さんはテクノフォビアではない。新しいモノが登場したときに感じる何となくの座りの悪さ、違和感を含め、自分自身の状態を絶えず意識化しておく、そのためには自分自身の身の回りに置くモノも絶えず選択し続けなければならない。そして違和感や葛藤を物語として描いておきたい――。そんな気持ちにかられているように見えた。 ただ最近、地理学の研究者と一緒に海外のさまざまな場所に取材を兼ねて出かけるようになり、そこで現地の人々と接し、色々な文化に触れることで、考え方もすこし変わってきたそうだ。 「外に出れば価値観はいくらでも仕入れられる、獲得できるなと思いました。だから、もし『まるいち』のネクストジェネレーションを描いたら、ロボットやネットワーク技術が当たり前にある世の中に暮らしている子たちが、価値観を新しく獲得していく話が描けるだろうなあと思います。価値観を獲得していくのは楽しいじゃないですか。『こういう価値観があるよ、こういう世界もあるよ』と見せられるんじゃないかなと。ちょっと、昔よりはポジティブになりました(笑)」 そう遠くない将来、人間にずっと寄り添い、自分の人生を一緒に全部記録するデバイスが登場する時代も来るだろう。 「わたし、『大きなのっぽの古時計』が、すごく好きなんです。生まれたときに『まるいち』をプレゼントされて、それがずっと人生を一緒に覚えていてくれたら、どういう生活になるのかな。どういうコミュニケーションができるのかな、恋人ができたら『まるいち』が持っている記憶を交換したりできるのかなとか、いろいろ妄想しています(笑)」 なお、執筆媒体は絶賛募集中とのことだ。 ● 便利になることで失われるものの怖さ
ロボットに至っては、まだ世の中に出ていない。仮に役に立つ機能が開発され世の中に出て行っても、どのように使われるのかメーカーの人たちや研究者たちも想定仕切れていない。そもそもロボットという存在そのものが、どんなものかみんなよく分かってない。たとえば「単なる道具ではない」というように「~ではない機械」という否定形で言われることはあるが、「○○な機械だ」という断定的でピタリとくる形容がない。 「まるいち」とは「01」、つまりデジタルを意味する。柳原さんは登場人物の1人・まるいち制作室室長の牧内千船にこう言わせている。「我々の世界も複雑に見えて、実は0と1で割り切れる程単純なものであり、また、0と1の交わらない永遠の平行線の間を埋める作業ではないでしょうか」(文庫本2巻「まるいち友の会通信」扉)。もの言わぬ「まるいち」は、ユーザーの行動をそのまま再生することで、言葉にならない人の思いを、距離や時を超えて伝える。本物の家庭用ロボットは、果たしてどんな機械になるのだろうか。
「やっぱり、工夫だったり、発見だったり、臨機応変さ、あとは感情ですよね。コミュニケーションを円滑化するために気を使うとか……。そういう部分が、もっともっと要求されてくるのに、機械や道具で便利になると気を遣う部分がそぎ落とされていく。私、どうなっちゃうのということが怖かったんですよ。すごい要求されてるなあと思っていたんです。だって機械で補ったら、私、用なしになっちゃうじゃない。機械がそういう訓練する機会をそぎおとしているのに高度なコミュニケーション能力を要求される世の中になったらどうなっちゃうの、と思って、怖かったんです」 人と機械、人と自然。その間の関係は多種多様だし、スケールを変えれば見える風景も変わる。短い人生で獲得してきた自分一人の価値観だけが全てではない。柳原さんのマンガには「壮大にふっておいて、小さくまとめる」傾向がある。そういうストーリー展開が大好きだそうだ。 「本当に大事なことは日常の些細なことなんです」 ■ 関連記事 ・ 白泉社、柳原望「まるいち的風景」の文庫版を15日に発売 ~家庭用ロボットが実在する世界を描いたハートフルROBOストーリー(2008/07/11) 2008/08/22 11:39 - ページの先頭へ-
|